ひまわりの育て方

ひまわりの栽培条件
ひまわりの栽培方法についてお話しします。ひまわりは豊かな日照と水分を補給して育つため、日照条件において良いところで栽培しましょう。建物や障害物が日照を遮るような条件下ではひまわりが元気にすくすくと育ちません。日が当たらない条件下で、栽培しても成長が十分ではなく、色も悪くなり、弱々しく育ちます。
国内で未曾有の事故となった東日本大震災が及ぼした津波被害で、福島原子力発電所の爆発による大惨事で、放射能汚染が懸念されると、太陽から発せられる放射線を自身の栄養素として育つという都市伝説的なことが広がり、ひまわりが放射能の除染を行うということがにわかに広がりましたが、これは全く根拠がないことです。
日照には強く寒さに強くない側面を持ち、霜などが下りれば枯れる原因となります。自然な状況で咲く場合、全長はそれほど伸びませんが、人工栽培では茎を太くし、太陽の方向へと次第に大きくなり3メートルもの長身になると、折れた茎でけがをすることもあると言われています。また夏の終わりごろに成長を止めた花に種が付き、重みを増すと、首から折れて落下することがあり、とてつもなく大きな成長を遂げたものは危険であると言われます。
ひまわりの種付けと苗付け、育て方
ひまわりの種付けは意外に簡単です。種付けは一番適したシーズンは、4月下旬から5月上旬となります。このころに、発芽に最も必要な20度の温度となります。
家庭で簡単に栽培できるミニひまわりも人工化が可能となり、プランターや植木鉢などでも栽培でき、種子を扱う花店で販売されています。種付けをするために、プランターや植木鉢の土に割りばしなどで、1センチほど穴を開け、穴に種を落とし土をかぶせます。
穴に入れる種は2つほど入れると良いでしょう。その後水やりをして発芽を待ちます。大抵、1週間以内に発芽します。双葉が開いた時点で1本に間引きします。苗として種子を販売する花店で購入した場合、しっかりと根が入り込むために必要な深さに穴を掘り、植え替えをします。
植え替えの際は必ず、値を切らないように気を付けましょう。植え替え後はしっかりと水やりを行い、とくに土の表面が乾燥しないように水をたっぷりと掛けると良いでしょう。夏場はとくに水を吸い、また蒸発が早いことから朝夕の水やりを欠かしてはいけません。
ひまわりを土中の養分や水分を吸い上げ、太陽の日射で花弁の栄養や鼻の成長へと変換させるため、土からの養分が非常に大切で、庭や畑のように十分な土があれば、肥料をやる必要がないのですが、植木鉢やプランターなどの限られた土の状態では、土中から十分な養分が吸い上げられないため、肥料をまくことが良いでしょう。
栄養不足となると葉や花弁の色が黒ずんだり悪くなったりします。家庭での栽培の場合、ホームセンターなどで売られている液体肥料で十分です。10日に1度程度のペースで液体肥料を与えると良いでしょう。
ひまわりは直根性と言い、茎から下に一本の根が深く生え、蛇のように根尾へと細くなります。直植えで太く長く成長した根はとくに水分や養分を吸収し、花弁へと水分や栄養を到達させます。
プランターや鉢植えでの育て方となれば、根が太く長く伸びることは無く、株が小さなものとなりますが、過密に植えると沢山の小さな花を咲かせるため、見栄えにおいてきれいになるでしょう。
ひまわりの育て方に関する工夫・雑学
自宅でひまわりを育てる場合観賞用としてが多く、お庭の広いお宅や畑があるお宅では、再び花を咲かせるために種を摂るということもありますが、プランターや植木鉢で育てる場合、1年草として育てられ、種を採取する人は少ないでしょう。
直植えで背を伸ばし、1本あたりを大きくしたい場合、間隔を開けて直植でも栄養を与えるなどすると力強く大きく成長します。一方で、プランターや植木鉢の場合、株間を過密にすることで、短く小さい花を沢山咲かせることが出来ます。
小さなひまわりから取れた種では小さなものしかできず、大きなひまわりから取った種では大きなものが出来ます。ひまわりの育て方で難しいのが、水のやり、栄養、害虫駆除です。栄養や水分を多く含むため、害虫にとっても好条件です。スプレー式の害虫駆除剤や希釈式の害虫駆除剤を噴霧すると害虫被害に会いません。
国内外で人工生産されるひまわりは、主に食用油の生産や植物園などの観賞用として多いです。種子生産量はロシアがもっとも多く、6,430千トン、ウクライナが5,230千トン、アルゼンチンが3,440千トンとこれらの国が上位3位を占めます。
種を絞って食用油としますが、不飽和脂肪酸が多く含まれることで、油の使用により発癌や高血圧、脂質異常などの様々な点についてこれを抑制し、健康的側面でのメリットも高いと言われています。食用油として使えるものは、専用の食用主であり、観賞用としては種の色が黒と白っぽい色の2色のバイカラーとなっています。
ひまわりの歴史
ひまわりは、漢字で向日葵と書くことから、向日葵=ヒュウガアオイとも言われることもあります。この花は、現在では観賞用として飼育されるほか、食用としてヒマワリ油の採取や、リスやハムスターなどのペットのえさとして利用されます。
現在日本全国各地で栽培が進められているひまわりも元々は、北アメリカが原産と言われており、紀元前から栽培されていたと言われています。この花はキク科でありながら元々雑草として生えていたものを、紀元前に北アメリカ大陸西部で狩猟生活をしていたインデアンにより、食用とされ、栽培が進んだと言われています。
その後北アメリカ南部でも生息地が見つかり、1500年以降メキシコに広がり、当時メキシコがスペインの植民地となったことから、スペインに渡り、首都マドリードの植物園に栽培されることになりました。現在では、世界中に広がっていますが、太陽の光と大量の水を必要として育ちますので水の乏しい国では育ちません。
ひまわりの特徴
ひまわりの特徴は大きな丸い中心部分に大輪の花弁を広げ、中心部分はキク科の特徴でもある多数の小さな花弁が集まって外に行くにつれて大きな花弁を広げ、大輪の花として成長しています。
これは、キク科の植物全体に見られることで、道端や野に咲くタンポポ(蒲公英)などでも同様であり、頭状花序と言い、中心から無数の花弁が集まって大きな1つの花を形成するものです。
タンポポやひまわりは小花(しょうか)と言われる小さな花が集まることで頭状花と言う中心部分を形成します。日本には1700年代になって持ち込まれ、栽培が進んだのですが、当時は和名で向日葵(ヒュウガアオイ)、日輪草(ニチリンソウ)と言われていました。
この花は、太陽の日差しを真っ向から受け、光合成と地中からの十分な水分を得て背を伸ばし、もっとも高くなるとその全長は3メートル以上となることもあります。
日の出には太陽の上る東に頭を向け、日に入りには西を向く1日に180度頭を回転させながら成長が進み、成長を終えると、頭を下げ、日照に応じて頭を振ることがなくなるという特徴を持ちます。蕾が付くまでは成長を続け、蕾が完全に開き切ると花は東を向いたまま動かなくなり花弁が次第に落ちます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アスクレピアスの育て方
タイトル:ヒマワリの育て方
タイトル:ルドベキアの育て方
-

-
一重咲きストック(アラセイトウ)の育て方
一重咲きストック、アラセイトウはアブラナ科の植物です。原産地は南ヨーロッパで、草丈は20センチから80センチくらいです。...
-

-
ラグラスの育て方
ラグラスは、ふさふさした穂がかわいらしく、野兎のしっぽの意味を持つ名前で、イネ科の植物です。原産地は地中海沿岸で、秋まき...
-

-
ウェデリア(アメリカハマグルマ)の育て方
ウェデリアは地面を這いながら成長が特徴の這い性のキク科の植物であり、常緑の多年草になります。原産地は中央アメリカから南ア...
-

-
ヤグルマギクの育て方
この花の特徴としてはまずは菊の種類であることです。キク目キク科の花になります。野生の状態で青色の状態になっています。です...
-

-
クロッサンドラの育て方
クロッサンドラは、促音を抜いたクロサンドラとしても呼ばれ、その名前の由来はギリシャ語で房飾りを意味する「Krossos」...
-

-
黄花セツブンソウの育て方
キバナセツブンソウはキンポウゲ科セツブンソウ属ということで、名前の通り黄色い花が咲きます。この植物はエランシスとも呼ばれ...
-

-
ヒヨドリジョウゴの育て方
ヒヨドリジョウゴの特徴は外観と有毒性が挙げられます。外観に関して、白い毛が生えています。現物を見た人や写真を見た人の中に...
-

-
グアバの育て方
皆さんはグアバという果実をご存知ですか。あまり聞きなれない人も中にはいるかもしれませんが、最近では健康食品や女性の美容健...
-

-
ディモルフォセカの育て方
ディモルフォセカは、南アフリカ原産のキク科の一年草で、日本名ではアフリカキンセンカと呼ばれています。よく似た花に、多年草...
-

-
アーモンドの育て方
アーモンドの主要である、カリフォルニアでは、どのようにして身の収穫をしているのでしょうか。また、特徴とは一体なんなのでし...




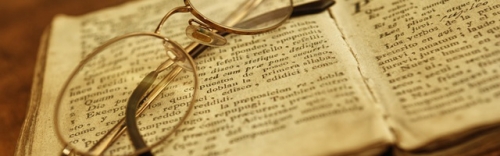





ひまわりはきく科に属し、日輪草(ニチリンソウ)や日車(ヒグルマ)と言う別名を持ちこれは、ひまわりが日輪のように見えることや、車の車輪のように見えることなどからつけられたという説があります。