ツワブキの育て方

ツワブキの育てる環境について
育て方に難しい点は少なく、付き合いやすい植物です。用土は腐葉土などの有機質をたっぷりと含んだ水はけの良い、少し湿った土が適しています。とはいえ余程水はけが良くない場合を除いて、土質をあまり選ばずに育ちます。市販されている土で構いません。
有機質が少ないと育ちが良くないので、植え付けの際には堆肥や腐葉土をたっぷりと混ぜ込んでおくと良いでしょう。日陰に強く午前中に2〜3時間日光にあたることができれば充分です。半日陰の場所、明るい日陰の場所を好みます。極端に暗い場所だと、
葉が大きくなりすぎたり色が悪くなったり、ヒョロヒョロとしたのび方になってしまいます。葉に斑が入るものは人気がありますが、この種類のものは日光が不足すると斑がボヤけてしまいます。真夏の直射日光には気をつけて、西日のあたる場所は避けたほうが良いでしょう。
枯れたりはしませんが葉が焼けてしまい、観賞用には向かなくなってしまいます。斑入りの葉は、斑の部分が周りの緑色の部分より強い光線に弱く、強烈な日光にあたることで茶色く枯れて穴があいたようになってしまうことがあるので注意が必要です。
ベランダなどで鉢植えをする場合、日のあたり方にムラがあると良く育つ部分とそうでない部分ができてアンバランスな形になってしまうことがあります。様子を見ながら時々鉢をまわして、満遍なく日があたるようにしましょう。寒さには強いほうです。特に防寒対策を行うことはありません。
ツワブキの種付けや水やり、肥料について
地植えをする時は、10〜20センチほど土を盛ってから植え付けるとよく育ちます。一度植え付けて根付いた後は、特に植え替えをする必要はありません。鉢植えの場合は、鉢が根でいっぱいになったら植え替えを行います。適期は4〜5月、9〜10月頃です。
鉢から地面に植え替える場合は、真冬を除いていつ行っても問題ありません。鉢植えは深さの浅い平鉢を使うと全体的にバランス良くまとまり見た目が良いでしょう。株は鉢の大きさにあったように育ちます。小さめの鉢で育てるとコンパクトな姿になります。
植えた後、次々に出てくる葉や軸がだんだん小さいものになり、2〜3年ほどで収まりの良い株になるので、気長に楽しみながら自分好みのミニ観葉植物、ミニ盆栽風の鉢に仕立てていくことができます。水やりは、適地に地植えした場合はよほどの干ばつでない限り必要ありません。
鉢植えは土の表面が乾いたらたっぷりと与えるようにします。肥料もそれほど必要ありません。地植えの際用土に堆肥や腐葉土を混ぜ込んだなら追肥の必要はほとんどありません。与えるなら6月頃か花の咲く頃に化成肥料を少しだけ株元に施します。
肥料を与えると葉が大きく立派になるので、それを好まないのであれば控えめにしましょう。日常の手入れは見た目を保つために枯れた葉を地面の際から軸ごと取り除きます。日本の気候にあった植物なので、適した環境や土壌であればそれほど手間をかけずに育てることができます。
ツワブキの増やし方や害虫について
ツワブキは株分けで増やすことができます。適期は植え付け・植え替え時期と同じで、葉を2〜3枚以上つけて根茎を切り取って植え付けます。それぞれの葉に充分に根がついていれば大丈夫です。葉のない古い根茎でも植えておくと、生きていれば芽を出して新しい株ができます。
また、花が咲いた後にタンポポの綿毛のような種ができるので2〜3月頃に種まきをすることもあります。自然に実った種からは、親と同等か少し劣るものしか育たないので好みの親を選んで交配しましょう。種を採取する必要がなければ花が咲き終わった花茎は切っておきます。
害虫にはキクスイカミキリがおり、成虫が4〜7月に葉柄に卵を産みつけます。孵化した幼虫は根茎に向かって葉柄の中を食い進み、やがて根茎の内部を食い尽くしてしまいます。春から夏にかけて疑われる株があれば掘り上げて捕殺しますが完全に防ぐのは難しく、
周囲にキク科の雑草を生やさないようにすることである程度避けることができます。5〜8月頃に葉の表面に白い粉状のカビが生えていたらうどんこ病です。また、斑葉病・褐斑病にかかると葉に灰白色のまるい斑点が現れ、後に黒い点が現れます。
どちらも大発生したり重症化することは少ないですが気になるようであれば葉を切り取って再生させます。ほかに黒や灰色のポツポツとした変色が見られることがありますが、これは葉についた水滴が強い日差しにあたり、レンズのように光を集めることによって起こる葉やけです。
ツワブキの歴史
ツワブキは海沿いの草原や崖、林の縁などを生息地としている常緑の多年草です。原産は日本・中国・台湾・朝鮮半島で、日本国内では福島県・石川県以西から四国、九州、琉球諸島にと広く分布しています。日陰でもよく育ち乾燥や塩害にも強い植物で、
艶のある美しい葉は季節によって色や形を変えながら一年中鑑賞することができます。そのため古くから庭の下草や木の根元、石組みなどに好んで植栽されてきました。「庭に干す土人形や石蕗(ツワブキ)の花」と正岡子規も詠んでいます。
ツワブキの名は、艶のある葉のフキという意味の「艶葉蕗(つやばぶき)」から転じたという説のほか、フキのように見える厚い葉をしているという意味の「厚葉蕗(あつはぶき)」からきたという説、あるいは海岸などに自生していることから「津葉蕗」と呼ばれたという説など諸説あります。
因みに津和野町の地名は「石蕗の野」に由来するといいます。生薬名を「たくご」と言って民間薬にも用いられてきました。葉や茎に含まれる薬効成分ヘキセナールには抗菌作用があり、生葉を炙ったり揉み込んで柔らかくし、打撲・できもの・切り傷・湿疹・筋肉痛・しもやけや虫刺されに湿布します。
また、煎じて飲めば食あたりや下痢にも効果を発揮します。フキと同じように茎を食用にすることもあり「キャラブキ」と呼ばれることもあります。フキとはよく似た姿をしていますが、フキはフキ属、ツワブキはツワブキ属で別属です。
ツワブキの特徴
ツワブキの葉はワックスを塗ったようにツヤツヤしており、裏側や軸は茶色い毛で覆われています。このツヤや毛が潮風や乾燥した風から本体を守っているとも言われています。地下には短いワサビ状の根茎が連なって大きな株になります。
花は株の中心から出て先端にキクに似た黄色い花を10〜30輪ほど咲かせます。草丈は20〜50センチ、花の開花期は10〜12月です。鉢が市場に出回るのは5〜6月、9〜11月頃になります。鉢植えは海外にも輸出され人気があります。さまざまな園芸品種が栽培されており、
花の色も黄色のほかにクリームホワイト、朱色、レモン色などがあります。葉の色形もバラエティーに富んでいます。キンモン(金紋)は星斑とも呼ばれ葉全体に大小の黄色い斑点が散りばめられています。キンカン(金環)は葉に黄色い縁取りが見られます。
また、葉の縁が大きく波打つシシバ(獅子葉)や、葉の表面に細かい凹凸があるチリメンなどがあります。茎を食用にすることがありますがアクが強い植物です。肝臓に有毒なピロリジジンアルカロイドを含むのでアク抜きをしてから調理する必要があります。
フキと同様に葉柄のスジを取り、重曹や灰汁でアク抜きし、煮物や炒め物に広く利用されます。また、保存用に塩漬けにしたり冷凍保存しておくことも可能です。若い茎を佃煮にしたものをキャラブキと呼びます。ツワブキの花言葉は、愛よよみがえれ・謙譲・謙遜・困難に負けない・先見の明などです。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ニューギニア・インパチエンスの育て方
-

-
フォックスフェイスの育て方
フォックスフェイスはブラジル原産のナス属の植物とされ、ナス属は世界の熱帯から温帯にかけて1700種ほどが分布しています。...
-

-
梅(ハクバイ)の育て方
梅は非常に色が豊富です。濃いピンクがありますがそれ以外には桜のような薄いピンクがあります。白っぽいピンクから真っ白のもの...
-

-
ツルハナナスの育て方
ツルハナナスの名前の由来は、つる性の植物であるために「ツル」と、またナス科の仲間であるためその花は紫の綺麗な色をしている...
-

-
ブライダルベールの育て方
ブライダルベールは吊り下げるタイプの観葉植物が流行した昭和50年代に日本に登場しました。英語での名称は「タヒチアンブライ...
-

-
アカネスミレの育て方
特徴としてはバラ類、真正バラ類に該当します。キントラノオ目、スミレ科、スミレ属でその中の1種類になります。スミレの中にお...
-

-
植物の上手な育て方を知る
生活の中に植物を取り入れることで、とても豊な気持ちになれます。また、癒しの効果もあって、育てていく過程も楽しめます。キレ...
-

-
コバイケイソウの育て方
この植物は日本の固有種ということですので、原産地も生息地も日本ということになります。わたぼうしのような、まとまった小さな...
-

-
アンスリウムの育て方
アンスリウムは、熱帯アメリカ・西インド諸島原産で、日本には明治の中頃に渡来してきた歴史ある植物です。木の枝などに着生する...
-

-
タンチョウソウの育て方
タンチョウソウは別名で岩八手といいます。中国東部から朝鮮半島が原産地です。生息地は低山から山地で、川岸の岩の上や川沿いの...
-

-
デュランタの育て方
クマツヅラ科ハリマツリ族(デュランタ属)の熱帯植物です。形態は低木です。和名には、ハリマツリ、タイワンレンギョウ、などの...




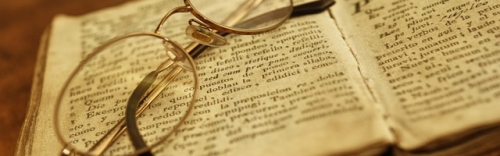





ツワブキは海沿いの草原や崖、林の縁などを生息地としている常緑の多年草です。原産は日本・中国・台湾・朝鮮半島で、日本国内では福島県・石川県以西から四国、九州、琉球諸島にと広く分布しています。