ゴメザの育て方

ゴメザの育てる環境について
ゴメザはオンシジウムに近い仲間なので、栽培環境はほぼオンシジウムと同じように考えて構いません。園芸品種はほとんどが鉢物なので、鉢で育てるのが基本です。日当たりの良い場所を好むので、一年を通して日向管理するようにします。冬は鉢を取り込んで、室内の日が当たる窓辺で管理します。
春〜秋にかけては戸外の風通しの良い場所を選んで置きます。あまり日が当たり過ぎると葉が焼けてしまうので、30%遮光下で育てると良いでしょう。風通しを良くする理由は、熱が溜まって根が弱るのを防ぐためです。鉢の下に照り返しを防ぐために簀(すのこ)を敷くのも良い方法です。適度に風が通るようになります。
冬場は休眠期に入るので、冬越しの温度に注意して管理します。だいたい5〜10℃を目安として、それ以下に下がり過ぎないようにして室温を保ちます。秋に入り、気温が下がってきたら室内に取り込むようにしましょう。室内に置くときの注意点として、乾燥しやすい場所は避けましょう。
特に暖房の温風が直接当たるような場所は避けます。乾燥させてしまうと、蕾がついても花が咲かずにそのまま落ちてしまうこともあります。用土には、素焼きの鉢にミズゴケを使うか、もしくはプラスチック製の鉢や化粧鉢に細かめのバーク(樹皮)を使って植え込みます。
成長期は水をたっぷり吸うので、水持ちの良い用土を用意してあげると、水やりの負担が減ります。植えるときには大きめの鉢に植えないとバランスを崩して倒れてしまうことがあるので、鉢のサイズには気を付けましょう。
ゴメザの種付けや水やり、肥料について
ゴメザはランの仲間なので、種付けで増やすことは出来ません。植え付けでは、2年に1回の割合で、4〜5月下旬に植え替え作業を行うようにします。株が大きくなっているものは、植え替えと同時に株分けをしても良いですが、細かく分け過ぎないように注意しましょう。小さ過ぎると生育が悪くなります。
水やりは、生育期の春〜秋にかけてはたっぷり目に与えるようにします。冬はそれほど水を吸わないので、やや乾燥気味で管理します。ただし、12月頃になって花芽が伸びてきたら、芽を乾かさないように水やりするようにします。肥料は、春に規定量の有機質固定肥料を置き肥にします。
初夏までに2〜3回新しいものに取り替えれば良いです。さらに追肥として、規定倍率に薄めた液体肥料を5〜9月終わりごろまで週1回施すようにします。冬の間は生育がストップしているので、肥料は与えないようにします。肥料についての注意点です。花の栄養素はチッ素・リン酸・カリですが、
このうちチッ素分が多い肥料をあげてしまうと、葉ばかりが大きくなり過ぎるだけではなく、花が緑色がかってしまうことがあります。なので、開花期にはできるだけ肥料は控えて管理するようにします。肥料を与えれば与えるほど良いというのではなく、必要に応じて与えることが大切ということです。あげ過ぎは根腐れの原因にも繋がります。基本的には用土にはミズゴケを使ったほうが管理が楽で、失敗する確率が低くて済みます。
ゴメザの増やし方や害虫について
株分けで増やすことが出来ます。ラン科の植物なので、種では増やすことが出来ません。バルブ(球根)をカットして増やします。つまり、このバルブを増やすことが種付けの代わりになるということです。鉢に対してゴメザが大きくなってきたら植え替えのタイミングなので、そのときにまとめて株分けすると楽です。
植え替えの時期は4〜5月です。ちょうど成長期に当たるため、他の株と一緒に管理すると良いでしょう。株が大きくなってバルブの数が増えてきたら、新芽の出たバルブごとに切り分けて株分けします。この時、あまり細かく分け過ぎてしまうと、作落ちといって翌年花が咲かなくなります。なるべく大きく切り分けて、新芽が伸びるようにしてあげましょう。
植え替えの鉢には、株よりひとまわり大きいサイズのものを使います。鉢の大きさが大きすぎると加湿状態になりやすく、小さすぎるとバランスを崩してしまう原因になります。なので、ひとまわり大きい鉢に入れて、さらにその上から二重鉢にしてもう一つ鉢を被せてあげると良いでしょう。新芽の出る方向は十分にスペースを開けてあげるのがコツです。
病気は特にありませんが、カイガラムシがつくことがあります。カイガラムシがついてしまうと排泄物で葉が汚れてしまうことがあるので、見つけ次第駆除するようにします。専用の駆除剤を使っても良いですが、薬を使いたくないのであれば、牛乳と水を等量の割合で混ぜて、それを霧吹きでかけてあげるとカイガラムシが呼吸できなくなって撃退することが出来ます。
ゴメザの歴史
ブラジル原産のラン科の植物です。属名がなんども変えられた歴史を持っています。最初はSigmatostalix(シグマトスタリックス)、次にOrnithophora(オーニソファラ)、そして現在ではGomesa(ゴメザ)となっています。元は1属1種でしたが、ゴメザ属に変更されたということです。
オンシジウムという植物の原種で、栽培方法も性質もよく似ています。オンシジウムの系統のラン科の植物は、熱帯地域で種類も多く、様々な形のものを見ることが出来ます。それらを総称して洋ランと呼んでいます。洋ランの人気が始まったのは、ヨーロッパからです。
特にイギリスでは古くから品種改良や栽培が盛んで、世界各国から植物が持ち込まれ、園芸用に栽培されてきました。オンシジウムは1820年頃にはイギリスに紹介されていたと言われています。この時代はまだ温室の設備が不完全であったため、栽培方法も手探りの状態でした。
しかし、19世紀に入ると暖房設備が整い始め、オンシジウムの栽培方法も確立してきました。そして、19世紀の半ばには、ラン栽培に関する書籍なども出版されるまでになりました。この時代になると植物学者など特別な人だけではなく、
一般の人たちにまでラン栽培が広まっていき、親しまれるようになりました。この時代には、現代でもラン栽培によく用いられるミズゴケの利用も盛んになりました。日本では現在、ほとんどが鉢植えで出回っています。
ゴメザの特徴
ラン科ゴメザ属の常緑性の植物で、大きく育てるとわずかですが香りがあります。バルブ(球根)の脇から穂のように花を伸ばし、それがまるで人形が万歳をした形に見えることから、人形蘭(ニンギョウラン)という和名がつけられています。
その他の別称では、花の形が妖精が手足を広げた格好に似ていることから、「小人ラン」という愛称もあります。株を囲むように花をつけるので、見応えがあります。オンシジウム(ラン科オンシジウム属)の仲間の原種なので、基本的には同じように育てることが出来ます。
性質もよく似ています。多少の違いとしては、ゴメザは冬の間はやや暖かい場所に置いた方が良いくらいで、あとはほとんどオンシジウムと同じ育て方で栽培することが可能です。あまり園芸用には出回っていない品種なので、入手するには洋ラン専門店などで探すと良いでしょう。
オンシジウムは洋ランとして用いられ、お祝いの時など華やかな演出をする時に使われることが多いです。花持ちも良く、一度花をつけると数ヶ月はそのまま咲いてくれるため、縁起がよい花です。日本でもラン科の植物としてオンシジウムは人気があります。
ゴメザの生育方法のポイントは、日光と風通しです。元の生息地であったブラジルではジャングルに育っていたので、直射日光が苦手です。当てると葉焼けして枯れてしまうこともあります。風通しが悪いと根が弱ってしまうので、風通しを良くして熱を溜めないようにすることも大切です。
-

-
イトスギの仲間の育て方
イトスギはヒノキ科イトスギ属に属するイトスギの仲間を総称しています。サイプレスやセイヨウヒノキと呼ばれることもあり、主に...
-

-
オウコチョウ(オオゴチョウ)の育て方
オウコチョウの特徴を記載すると、次のようになります。植物の分類上はマメ科のカエサルピニア属に属します。原産地としては熱帯...
-

-
パンジーの育てかたについて
スミレ科のパンジーは、寒さには強いのですが、暑さに弱く、5月前後に枯れてしまいます。ガーデニング初心者の方には、向いてい...
-

-
クルミの育て方
クルミは美味しい半面高カロリーである食材としても知られています。しかし一日の摂取量にさえ注意すれば決して悪いものではなく...
-

-
スズランの育て方
春を訪れを知らせる代表的な花です。日本原産のスズランとヨーロッパ原産のドイツスズランがあります。ドイツスズランは、草姿お...
-

-
マツの育て方
マツ属はマツ科の属の一つで、原産はインドネシアから北側はロシアやカナダなどが挙げられます。大部分が生息地として北半球にあ...
-

-
ミニトマトのプランターの栽培方法
ミニトマトの栽培は初心者でも簡単に育てられ庭がなくても、プランターで栽培出来きるので、プランターでミニトマトの育て方はと...
-

-
ヤナギランの育て方
花の特徴としては、まずはフトモモ目、アカバナ科、ヤナギラン属の種類となっています。多年草なので1年を通して葉などをつけて...
-

-
エロディウムの仲間の育て方
フウロソウ科エロディウム属に属する品種なので、厳密には異なります。和名ではヒメフウロソウと呼ばれており、良く似た名前のヒ...
-

-
アリウムの育て方
原産地は北アフリカやアメリカ北部、ヨーロッパ、アジアなど世界中です。アリウムは聞きなれない植物かもしれません。しかし、野...




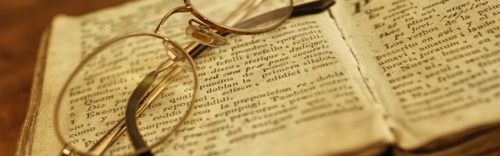





ブラジル原産のラン科の植物です。属名がなんども変えられた歴史を持っています。最初はSigmatostalix(シグマトスタリックス)、次にOrnithophora(オーニソファラ)、そして現在ではGomesa(ゴメザ)となっています。元は1属1種でしたが、ゴメザ属に変更されたということです。