ヒナゲシの育て方

ヒナゲシの育てる環境について
育てる環境としては日当たりの良い場所を好みます。また、風通しの良い場所を好み、多湿の場所を嫌います。じめじめしている場所に植えると弱ることがありますから注意が必要です。土壌については、酸性土壌を嫌う傾向があります。ですから、植え付ける前に苦土石灰を混ぜ込んで中和しておくのが良いです。
他には移植を嫌う傾向がありますから、直まきをするのが普通です。育て方は難しくはありませんが、このあたりが一般的な観賞植物とは少し異なりますから注意が必要です。なお、一般的に石灰と言われるものが消石灰なのか苦土石灰七日の違いを把握しておかなければなりません。
消石灰は水酸化カルシウムを指します。これに対して苦土石灰は炭酸軽し言う無にマグネシウムを加えたものを指します。苦土石灰はカルシウムを補給することはpHを上昇させること、マグネシウムを補給するなどの目的があります。消石灰はpHを上昇させる効果はありますが、
マグネシウムは含んでいませんから、この点では違いはあります。「苦土」とはマグネシウムのことを指します。マグネシウムも必要なものですから、苦土石灰を利用して酸性度の土壌を中和する方が良いですが、ヒナゲシを育てる場合には消石灰でも問題はありません。
その後も肥料を与えることになるでしょうから、最初の土壌は消石灰で中和しても良いですが、苦土も栄養としては必要です。土壌に関しては、水はけの良いものを好み、保水性が高すぎると弱ることがあります。
ヒナゲシの種付けや水やり、肥料について
種を蒔くときには直まきができてしています。ポットに蒔いてから育てることもできます。ポットに蒔いて少し大きくなってから植え付けるのが良いです。種はあまり大きくはありませんから、厚まきになってしまわないように注意が必要です。
適した季節は9月から10月中旬くらいです。光発芽種子ですから、土をかぶせる必要はありません。ある程度種が発芽すると、間引くことが必要です。密生すると混み合うことによって蒸れ、それが原因で弱って枯れてしまう可能性が高くなりますから注意が必要です。
適当に間引いて葉が6枚から7枚くらいになったときに植え付けるのが良いです。肥料については、まず植え付けのときに混ぜ込んでおくのが良いです。このときには緩効性肥料を混ぜ込んでおきましょう。追肥も必要です。花の茎が伸びるころには追肥があるほうが良いです。
春頃には茎が伸びてきますから、このときには液体肥料を与えると良いです。肥料は必要ですが、やり過ぎると逆に弱ることもあります。肥料が多すぎると草丈が大きくなりすぎて倒れやすくなったり、あるいは花付きが悪くなったりします。肥料が全くない状態だと育ちが悪くなりますが、
肥料を与えすぎるのは良くありません。様子を見ながら肥料をやっていくのが良いです。水やりは、湿気が多くなりすぎないように注意しながらやります。根腐れを起こすことがありますから、鉢植えの時には土が乾いてから水を与えるようにします。
ヒナゲシの増やし方や害虫について
基本的には種で増やします。種を膜のは9月から10月くらいが普通ですが、寒い地域ではこの時期に蒔くと育たないこともありますから、寒さが厳しい地域であれば春に蒔く方が良いです。ケシの一種で、「ケシ粒」という言葉があるように、非常に小さい種です。
小さすぎますから、一つの場所にたくさん蒔いてしまわないように注意が必要です。種の取り方は簡単です。花をそのまま残しておくと種子が熟してきます。この状態になれば花ごと切り取れば良いです。花を乾燥させると種子をとることができますから、
この種子はさらに十分乾燥させた上で紙袋に入れて涼しい場所で保管すると良いです。冷蔵庫に入れておくと発芽してしまうことはありませんから安心です。品種によっては、株分けのできるものがありますが、基本的には株分けで増やすことはないと思っておいた方が良いでしょう。
というよりも、種で簡単に増やすことができるために、株分けをする必要はありません。害虫としてはアブラムシがつくことがあります。つぼみや新しくできた葉にはアブラムシが群生することがあります。アブラムシが群生して汁を吸うと、その部分の生育が悪くなります。
風通しの悪い場所で育てるとアブラムシが尽きやすくなります。見つけたのなら、できるだけ早めに殺虫剤で駆除するのが良いです。病気としては苗立枯病や灰色カビ病などにかかることがあります。日当たりの良い場所で適度な水をやっていると予防できます。
ヒナゲシの歴史
ヒナゲシはヨーロッパ原産のケシの一種で、虞美人草という別名を持ちます。虞美人草という名前は中国の伝説に由来しています。秦の時代の武将として項羽は有名でしょう。項羽には虞という名前の愛人がいました。項羽が劉邦に敗れ、追い詰められたときに、
項羽が一つの歌を詠みます。虞はこの歌に合わせて踊り、その後に自害するのです。虞を葬った墓には、翌年に赤く花が咲いた花がヒナゲシで、そのために虞美人草と言われるようになったという伝承があります。ヒナゲシは、もともとは西南アジアを原産とする植物です。
ケシが日本へもたらされたのは室町時代で、アヘンを「津軽」と呼ぶことなどからも分かるように、青森から日本へ入ってきました。観賞用のものはその後の明治時代に日本へ再び入ってきます。現在、観賞用として用いられているヒナゲシはこの時代に日本へ入ってきたものです。
歴史として見れば、フランスの国旗の色であると言うことも象徴的なことでしょう。フランスの国旗は青と白と赤からなります。白は平等、青は自由、赤は博愛を指します。この色はそれぞれ花の色によって現わされていますが、この赤を現わしているのがヒナゲシです。
中国でもヨーロッパでもこのように古くから文化に根ざした花として多くの人に愛されてきました。園芸品種としての歴史も古く、色々な品種が開発されています。赤い花というイメージが強いと思いますが、それ以外にも白い花のものや、一部だけが赤いものなどがあります。
ヒナゲシの特徴
草丈は50センチから80センチほどになりますから、それほど大きな植物ではありません。花の大きさは5センチから8センチくらいです。元々の生息地では一重の花でしたが、栽培品種のものには八重咲きのものもあります。原種の色は赤ですが、白いものやオレンジ、
ピンク、紫など様々なものが品種改良によって作り出されています。耐寒性は比較的強いです。日本では暖かい地域で普通に育てることができますが、霜には弱い傾向がありますから、霜のつく地域では霜よけをした方が良いです。花びらは非常に薄く、透けるくらいの薄さになっています。
このか弱さが人気を集めているようです。つぼみができはじめたときには下を向いているのですが、花が咲き始めるときには徐々に上を向きます。生命力は旺盛で、ヨーロッパでは雑草として扱われることもあるくらいです。日本でも種で勝手に増えることもあります。
日本ではケシというとアヘンの材料だというイメージが強いと思いますが、 アヘンをとるケシは特殊なものです。この点はあまり心配する必要はありません。栽培していたことが原因で、麻薬取締法違反で逮捕されると言ったことはありませんから安心して下さい。
ヒナゲシから薬物はとることはできませんから、日本で栽培することには問題がありません。花の特徴として開花期が長いことが上げられます。長い間に渡って花が咲くことから、ガーデニングをしている人にとっては非常に魅力的な植物です。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ウチョウランの育て方
タイトル:アヤメの育て方
-

-
コバイモの育て方
コバイモは本州中部から近畿地方の山地に多く自生している植物で、原産国としては日本であるとされているのですが、その生息地は...
-

-
マサキの育て方
マサキは日本、中国を原産とする常緑の広葉樹で、ニシキギ科ニシキギ属の常緑低木です。学名はEuonymusjaponicu...
-

-
ボリジの育て方
この花については、シソ目、ムラサキ科、ルリジサ科に属するとされています。一年草なので1年で枯れてしまいます。高さとしては...
-

-
ニガナの育て方
ニガナはキク科の多年草で、原産地及び生息地は日本や東アジア一帯ということで、広く分布している植物でもあります。日本でも道...
-

-
オキナワスズメウリの育て方
この植物は被子植物に該当します。バラ類、真正バラ類のウリ目、ウリ科になります。注意しないといけないのはスズメウリ属ではな...
-

-
フジバカマの育て方
フジバカマはキク科の植物で、キク科の祖先は3,500万年前に南米に現れたと考えられています。人類が地上に現れるよりもずっ...
-

-
ユーフォルビア(‘ダイアモンド・フロスト’など)の育て方
ユーフォルビア‘ダイアモンド・フロスト’などは小さな白い花のようなものが沢山付きます。だからきれいで寄せ植えなどに最適な...
-

-
エマルギナダ(ヒムネまたはベニゴウカン)の育て方
この花についてはマメ科、カリアンドラ属となっています。和名においてネムが入っていますが、基本的にはネムは全く関係ありませ...
-

-
ヒョウタンの育て方
ひょうたんの歴史について、ご紹介したいと思います。ヒョウタンは本来中国原産の植物で、日本に入ってきたのは、奈良時代前期だ...
-

-
ミニバラの育て方
バラと人間との関わりは古く、およそ7000年前のエジプトの古墳にバラが埋葬されたとも言われています。またメソポタミア文系...




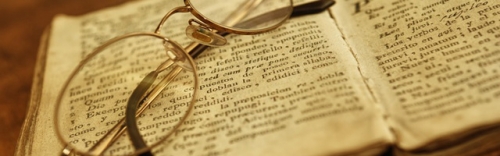





ヒナゲシはヨーロッパ原産のケシの一種で、虞美人草という別名を持ちます。虞美人草という名前は中国の伝説に由来しています。秦の時代の武将として項羽は有名でしょう。項羽には虞という名前の愛人がいました。