ジョウロウホトトギスの育て方

育てる環境について
ジョウロウホトトギスは山奥の渓谷にある岩場や崖などに自生する多年草植物であり、寒さはそれ程弱くは有りませんが、高温を嫌うため育てる環境は温度変化が少ない場所を選ぶ事がポイントとなります。鉢植えと庭植えのどちらでも栽培は可能になりますが、
鉢植えで行う場合は、秋から春までの季節においては日向で育ててあげて、晩春になった時には日陰に移動させてあげます。また、夏時期は極力温度変化が少ない場所を選び、7割ほどの遮光が可能な涼しい日陰で育て、鉢の周りには人工芝などを敷いてあげて、打ち水を行って湿度を作り出すのがコツです。
庭植えの場合は、鉢植えのように移動する事は出来ませんので、育てる環境をしっかりと把握して決める必要が有ります。まず、暑さを嫌いますので夏時期に日陰になる場所を選び、鉢植と同じ用土を入れ替えてあげてから、周囲より50㎝から60㎝程の高さの花壇をつくり、そこに植え付けます。
また、自生している場所と似たような環境を作ることで成長も良くなるため、周りにはシダなどの植物を植えてあげるなどして、湿度を一定に保つことが出来る環境づくりを行う事が庭植えでの栽培のコツです。尚、種まきは2月から3月にかけて行い、
肥料につては鉢植えや庭植えどちらの場合も3月から10月の中で程してあげます。また、植え付けや植え替えなどは種まきと同時期の2月から3月頃に行うのが良く、鉢植えから庭植えに切り替える時などは2月から3月頃が適している季節となります。
種付けや水やり、肥料について
鉢植えで育てる場合は、乾燥し難い鉢を選ぶ事がポイントで、直径15センチ以上の、深めの山草鉢などを選ぶと良いでしょう。ジョウロウホトトギスは水はけが良い事、そして湿気を好みますので、桐生砂や富士砂、赤玉土、軽石砂と言った多孔質の砂を何種類選び、
それと腐葉土を混ぜ合わせて培養土を作りだします。また、栽培を行う人の中にはミズゴケを使って湿気を作り出す人も多いと言われており、ミズゴケにより湿気と水はけを良くしてくれる効果を期待出来ます。また、栽培する環境は空中湿度を保てる、半日陰の場所を選ぶ事が大切で、
5月上旬頃までは日当たりが良い場所において太陽の光を当ててあげますが、これ以降は直射日光は厳禁であり、日陰になる場所を選びます。鉢植えの場合は、鉢を移動させてあげれば良いわけですが、庭植えの場合は簡単には移動が出来ませんので、
5月以降に日陰になりやすい場所を選ぶ事が栽培における最大の課題となります。尚、鉢植えで行う場合は、真冬の時期は出来る限り凍ることが無いようにし、霜よけ下に置いておく必要があります。水やりは適度な湿気を好みますので、適度に行う事が大切ですが、
あまり多くの水を与えてしまうと根を腐らせてしまう事になるため、過湿は禁物となります。目安としては春時期から秋時期にかけては1日1回、冬場の休眠期においては2~3日に1度の割合で水やりを行い、表土が乾いたら十分に与えることと、葉の裏側を乾燥させないように霧吹きなどを利用して水やりを行って管理をしていきます。
増やし方や害虫について
植え替えを行う時などは元肥としてリン酸の成分が多い緩効性化成肥料を施します。目安としては3~4号鉢で一掴み程度であり、3月から5月にかけては親指大の固形の油かすを、3~4号のサイズの鉢で月に1個を目安にし、更に、チッ素が多く含まれている液体肥料を選んで、
週に1度の割合で2000倍に薄めて与えてあげます。6月から10月頃は、リン酸が多く含まれている液体肥料を週に1度の割合で、2000倍に薄めて与えてあげると良いでしょう。尚、葉の色が悪い場合などでは、葉面散布肥料を3倍以上に薄めて与えてあげると葉色を良くさせることが出来ます。
また、庭植えで行う場合もこれらと同じ要領で与えてあげると成長を良くさせることが出来ます。5月から9月にかけて白絹病になる事も有りますが、これをそのままにしておくと毎年発生するようになるので早目の対処が大切です。また、害虫についてはナメクジやカタツムリ、ハダニと言ったものが発生します。
ナメクジやカタツムリは若葉や新芽などの柔らかいものを食害してしまいますので、見つけ次第退治をする事が大切で、鉢植えなどの場合は鉢の裏側もチェックをしておきます。また、ハダニは温暖な時には一年中発生し易いと言われているのですが、ハダニが発生する要因の一つとして湿度不足が有り、
栽培を行う環境の見直しが大切だと言われているのです。尚、増やし方としては挿し木や種まきが有りますが、挿し木の場合は5月から6月にかけて、茎を3から5節ほど付けてカットし、、川砂、赤玉土、鹿沼土などの用土にさします。種は秋口に出来るので、2月から3月に種をまくことで増やす事が出来ます。
ジョウロウホトトギスの歴史
ジョウロウホトトギスはユリ科の植物でホトトギス属に分類されており、別名をトサジョウロウホトトギスと言います。尚、ジョウロウホトトギスには幾つかの種類が有りますが、サガミジョウロウホトトギスやスルガジョウロウホトトギスと言うのは、日照や湿度、
温度の変化に対して弱くいため、育て方が難しい事からも栽培には向いていないと言われています。日本国内には10種類ほどが生息していますが、ジョウロウホトトギスの生息地は四国地方の太平洋側であり、山奥の渓谷などにある湿った岩場や崖に生息していると言われており、原産地についても四国地方になります。
因みに、ホトドギス属と言うのは、植物のホトトギスであり、多年生草本植物になります。ホトドキスは日本を初め、台湾やフィリピンなどを原産とする植物でもあり、山野の林の下、林縁や崖、傾斜地と言った場所に生息しており、特に日当たりの弱い場所を好みます。
日本、台湾、朝鮮半島などの東アジア圏の中では19種類が生息していると言われており、その内13種類が日本が生息地もしくは原産であり、日本の中には様々なホトトギスの仲間が存在している事になります。尚、ホトトギスは地域的な固有種も存在しているのが特徴で、
ジョウロウホトトギスにおいても四国などに生息する固有種です。中には園芸用の盗掘が多く行われてしまったり、鉱物採取、ダム建設、開発事業を目的とした道路建設のために山を切り開いたりしたことになり、絶滅が叫ばれている種類も有ると言います。
ジョウロウホトトギスの特徴
日本に生息しているホトトギスの仲間は13種類ほどだと言いますが、その内ジョウロウホトトギスについては四国地方を原産としています。釣り鐘状の黄色い色をした花が特徴で、花の長さは約5㎝程の大きさになります。山地の渓谷と言った湿気が多い場所、岩場や崖などの生息しており、
日当たりがそれほど強くない湿気を持つ場所を好むのが特徴です。葉のわき部分から1つから2つの花を咲かせるのが特徴で、花の内側には赤紫色の斑点が有るのも、この花の最大の特徴と言えます。因みに、ホトトギスの種類と言うのは色々な模様が特徴でもあり、
この模様や色に魅力を感じて栽培を行う人が多いのです。また、葉の部分は幅が広くなっており、葉自体には光沢は少なく、産毛の様な毛が生えているのも特徴です。茎の長さは40センチから1メートルほどで、花を多く付けることで弓なり状に伸びて垂れ下がって来るため、
茎が垂れても平気な場所に栽培を行ったり、鉢を置くようにします。ジョウロウホトトギスは園芸分類においては草花や山野草に分類される植物ですが、落葉性を持ち日陰でも栽培が出来るなど、ホトトギスの仲間の中では比較的育てやすい種類だと言われており、
10月頃に黄色い花を開花させてくれます。尚、自然に自生している環境と同じような場所を好むため、耐暑性は弱いのが特徴でも有り、夏時期の暑い時などは極力温度変化が少ない環境の場所を選んで栽培をする事が大切だと言います。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:カマッシアの育て方
タイトル:ゼフィランサスの育て方
-

-
ビギナー向けの育てやすい植物
カラフルな花を観賞するだけではなく、現在では多くの方が育て方・栽培法を専門誌やサイトなどから得て植物を育てていらっしゃい...
-

-
カルミアの育て方
カルミアはツツジ科に属している植物のことで約7種類が世界で認められています。北アメリカやキューバが原産とされていて、主に...
-

-
デージーの育て方
ヨーロッパおよび地中海原産の草花です。自生の生息地であるヨーロッパでは野草として、ごく自然に芝生に生えています。デージー...
-

-
プチアスターの育て方
キク科カリステフ属のプチアスターというこの花は、中国北部やシベリアを原産国とし1731年頃に世界に渡ったと言われておりま...
-

-
トキワサンザシの育て方
真赤な赤い実と濃い緑の葉を豊かに実らせるトキワサンザシは、バラ科の植物で、トキワサンザシ属です。学名をPyracanth...
-

-
ヒヨドリジョウゴの育て方
ヒヨドリジョウゴの特徴は外観と有毒性が挙げられます。外観に関して、白い毛が生えています。現物を見た人や写真を見た人の中に...
-

-
メセンの仲間(夏型)の育て方
この植物の特徴としては、まずはハマミズナ科に属する植物で多肉植物であることです。ですから茎などがかなり太くなっています。...
-

-
サボテンの育て方のコツとは
生活の中に緑があるのは目に優しいですし、空気を綺麗にしてくれるので健康にも良いものなのです。空気清浄機のように電気代がか...
-

-
緑のカーテンに最適な朝顔の育て方
ここ数年毎年猛暑が続き、今や日本は熱帯よりも熱いと言われています。コンクリートやアスファルトに覆われた環境では、思うよう...
-

-
金のなる木の育て方
金のなる木は和名をフチベニベンケイ(縁紅弁慶)といいますが、一般にはカネノナルキ、カゲツ(花月)、成金草、クラッスラなど...




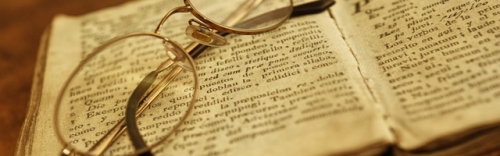





ジョウロウホトトギスはユリ科の植物でホトトギス属に分類されており、別名をトサジョウロウホトトギスと言います。