インゲンの育て方

インゲンの育てる環境について
種まきの時期は4月中旬から6月中旬頃ぐらいの気候が穏やかな時期にするのが最適です。高温多湿、乾燥に弱いため真夏は実付きが悪くなりますので、地域ごとの収穫時期の気温を考えて植える時期を決定します。短期間で何度も収穫できるので時期をずらして種植えすると無駄がありません。
つるありの場合は支柱立てを早めに行うようにしなければ隣同士のツルが絡んで上手く巻き付かなくなります。基本的に日当たりの良い場所で育てますが、花が咲いてから雨に当たると花粉の付きが悪くなってしまうので、直接雨に当たらない場所で育てるほうがいいでしょう。
プランターで植える場合は株間を約20センチほど空けて、つるありの場合は二粒、つるなしの場合は3、4粒が最適です。盛土の量が多すぎると光量不足で発芽率が下がるので気をつけます。種を植えた後は乾燥に注意して発芽までたっぷりの水を与えて土が乾かないようにすることが必要です。
それでも多雨などによる湿害を防ぐために、梅雨時期までにできるだけ成長を進めるか、梅雨明けに種まきをするかのどちらかがいいでしょう。基本的に栽培場所や土質は選ばなくても構いませんが、極端に水はけや日当たりの悪いところ、粘土質の場所は避けましょう。
つるありの場合はツルが左巻きなので必ず上から見て反時計回り、横から見ると右上がりになるように市中などに巻きつけるのがいいでしょう。雑草が生えてくると支柱に邪魔をされて取りにくいので生育初期に除草を行うようにします。
インゲンの種付けや水やり、肥料について
インゲンの育て方としては株間を30センチほど取って点播きします。プランターの場合は二株を目安に種付けします。指先などで軽くくぼみをつくってひと穴に2、3粒ずつ種付けします。覆土は種の厚さの倍、1センチ程度を手や足でしっかり押さえましょう。
鳥害がある場所では栽培時に蒔き条の上に10』センチぐらいの高さで糸を張っておくといいでしょう。あるいは寒冷紗をかけて、隙間から鳥が入り込まないように周囲に土をかけておきます。つるありインゲンは種付け後、約5、6日で発芽します。
一ヶ月頃になったら苗が混み合うので丈夫な苗を残して間引きします。水やりは土の乾燥を防ぐためにたっぷりの水をやります。開花着莢時期に水分が不足すると落花や曲がりさやが多くなるので十分に水まきをすることが大事です。追肥は草丈が20センチほどになれば与えます。
その後は2週間おきに様子を見ながら適量与えるといいでしょう。一般にマメ科植物は肥料分が多すぎると「つるボケ」を起こして実付きが悪くなります。開花時と収穫が始まった時期に追肥することをおすすめします。生育期間が長いので元肥はあるといいでしょう。
しかしマメ科植物は根に窒素を固定できるので必ずしも元肥が必要というわけではありません。追肥は花が咲く頃に一回、収穫が始まった頃に2週間ずつ追肥します。窒素成分が多いと花が落ちたり、実が成らなかったりします。窒素成分はほとんど必要ありませんのでリン酸やカリが多い肥料を選ぶようにします。
インゲンの増やし方や害虫について
つるありインゲンは初期のうちからアブラムシがつきやすいので葉の裏まで丁寧に観察して駆除することが大切です。アブラムシは汁を吸って株を弱らせるだけでなく、ウイルスによる病気を媒介します。光を嫌うので発生前にアルミホイルなどを置いておくと多少効果があります。
また、牛乳を噴霧することで窒息させる方法もあります。それ以外にもハダニに気をつけなければなりません。成虫、幼虫ともに葉裏に集まり吸汁して加害します。食害された跡は、葉に小さな白い斑点やかすり傷模様ができるのが特徴です。
ハダニは集団で葉の裏に帰省するため、セロテープやガムテープなどを貼り付けて一気に駆除することができます。収穫量を増やす場合は下から2節から3節までは成長の妨げにならないようにわき芽を取ります。本葉5、6枚の頃には成長点を詰心します。
横からわき芽が出てきて収穫量が増え、収穫期間も長くなります。摘心しなくてもそこそこ収穫できますが、実が小さくなったりすることもあります。品種によっても変わってきますが、小さな品種ほど実がたくさんなり、大きな品種は数が少なくなります。
たくさん収穫したい場合は小さな品種を選ぶことをおすすめします。つるありは栽培期間が長く、たくさん収穫でき、つるなしは栽培期間が短く収穫量も少なめになります。マメ科は同じ場所に連続して植えると病害や虫害が発生しやすくなります。どうしても連続して育てたい場合は土を消毒、または総入れ替えをすると収穫量は増えるでしょう。
インゲンの歴史
豆の栽培は農耕文化が誕生したときから穀類と並んで始まったと言われています。乾燥豆は品質を低下させずに長い期間貯蔵できることや、肉や野菜に劣らないタンパク質を含み、豊かな栄養分が有ることや豆の栽培すると根粒菌の働きにより地力の維持・向上に役立つことから世界中のいたるところで生産されているのです。
インゲンは中南米が原産で16世紀末にヨーロッパを経由して中国に伝わり、その後17世紀頃日本に伝わったとされています。明からの帰化僧である隠元隆琦が伝えたことからこの名がついたとされているが、真偽のほどは不明です。
元々生息地はメキシコ南部、中央アメリカで、先住民たちの重要な作物の一つとされ、多くの種類が栽培されていました。コロンブスによる新大陸発見にともない、16世紀初頭にスペイン人によりヨーロッパに持ち帰られたことからヨーロッパ全域に広がり、その後江戸時代に日本に伝えられたものです。
北海道開拓が始まった明治時代初期に、アメリカから品種を導入して広大な土地での本格的な栽培が始まったのです。導入された当初は豆のみを主に食べていたようですが、江戸時代後期に入ると豆を取る前の未成熟「インゲン」のさやを食べるようになり、
「サヤインゲン」と呼称されるようになりました。現在栽培されているものは明治時代初頭に行われた勧業政策によって欧米から日本へもたらされたものが元になっていて、様々な品種改良や栽培方法の工夫で一年中流通しています。
インゲンの特徴
インゲンとは完熟した豆を乾燥させて調理などに使用される豆自体を主に指し、全世界に約1000種類以上があるといわれています。国内であれば約200種類以上、その中でも「つるあり」と「つるなし」に分類することができます。
「つるあり」の仲間には「つる性」と「半つる性」に分類されており、「つる性」のものはツルの長さが3から5メートル以上で収穫量が多いものがほとんどです。「半つる性」はツルが「つる性」よりも長く成長しませんが、比較的収穫作業が楽に行うことができます。
「つるなし」のものは数10センチから1メートル以内で成長が止まり、収穫量はそれほど多くありません。また、品種改良によって最近の流通品種の8、9割すじのない、もしくは少ないストリングレス品種になっています。栄養価としてカロチンやビタミンA・B郡・C、カルシウム、リン、食物繊維などが多く含まれています。
カロチンは細胞の老化防止や抵抗力をつける効果があり、ビタミンB郡は疲労回復、食物繊維には腸を整える働きなどがあります。カルシウムは骨の強化やイライラ防止、カリウムは体内の水分量を調節してむくみなどを解消してくれる効果があります。
さやの緑色が濃く、細めで表面がみずみずしくハリのあるものが良品とされています。また、表面が非常に乾燥しやすいので収穫してから半日も経たないうちに食味や味が変化してしまうのでなるべく早く食べることが望ましい野菜になっています。
野菜の育て方なぢ色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:三尺ササゲの育て方
タイトル:ケールの育て方
-

-
スパラキシスの育て方
スパラキシスはアヤメ科の秋植えの球根草として知られています。純粋に和名であるスイセンアヤメとも言います。和名が付いている...
-

-
レウイシア・コチレドンの育て方
この植物の特徴は、スベリヒユ科、レウイシア属になります。園芸上の分類としては山野草、草花となることが多くなります。花の咲...
-

-
ヒトツバタゴの育て方
20万年前の近畿地方の地層から、泥炭化されたヒトツバタゴがみつかっています。しかし、現在の日本でヒトツバタゴが自生するの...
-

-
フランネルフラワーの育て方
フランネルフラワーは、セリ科の常緑多年草で原産地はオーストラリアとなっています。生息地は、オーストラリアのような乾燥して...
-

-
レタスの栽培に挑戦してみませんか。今回はレタスの育て方につい...
今回はレタスの育て方について学んでいきます。レタスの栽培は暑さに弱いので秋蒔きが作りやすいのですが、春蒔きでも可能です。...
-

-
アオマムシグサの育て方
アオマムシグサという植物はマムシグサの一種です。マムシグサというのはサトイモ科テンナンショウ属の多年草です。「蛇の杓子」...
-

-
ランタナ・カマラの育て方
ランタナ・カマラは通称ランタナで、別名をシチヘンゲやコウオウカ、コモン・ランタナといいます。クマツヅラ科ランタナ属の常緑...
-

-
ハクサイの育て方
ハクサイは漬物や鍋の中に入れる野菜、中華料理の食材や野菜炒めなどでもお馴染みの野菜です。色々な料理に利用出来る万能野菜と...
-

-
マツの育て方
マツ属はマツ科の属の一つで、原産はインドネシアから北側はロシアやカナダなどが挙げられます。大部分が生息地として北半球にあ...
-

-
フシグロの育て方
フシグロは、ナデシコ科の野草で、葉のつく節が黒っぽいので、このように呼ばれるようになりました。丘陵や山地、人里でも日当た...




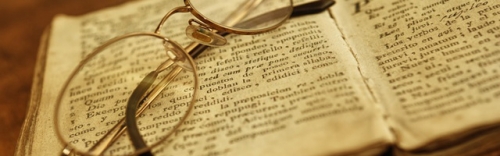





豆の栽培は農耕文化が誕生したときから穀類と並んで始まったと言われています。乾燥豆は品質を低下させずに長い期間貯蔵できることや、肉や野菜に劣らないタンパク質を含み、豊かな栄養分が有ることや豆の栽培すると根粒菌の働きにより地力の維持・向上に役立つことから世界中のいたるところで生産されているのです。