チューリップの育て方

球根の選び方
チューリップの育て方について紹介します。チューリップは育てやすく種類も豊富なので人気の高い花です。ですが、育てやすいといってもやはり注意点はあります。まずは、球根の選び方です。
チューリップには球根だけではなく種もあるのですが、こちらは手に入れるのは困難ですし、花が咲くまでに数年要します。なので、入手しやすい球根での育成が種付け・栽培ともに手軽です。球根は、秋ごろにホームセンターや園芸店で入手することができます。
選ぶ際の注意点ですが、まず、大きくふっくらとしたものを選びましょう。次に、手に持った時にずっしりと重みのあるものを選びましょう。そして、見た目に傷やカビのないツヤのあるものを選んでください。
傷は、小さなものなら大丈夫ですが、大きい傷のものはまず避けるようにしてください。また、分球しているものも避けたほうがきれいな花が咲きます。球根の種付けの前には、球根用の消毒剤に15分ほど漬け込んでから種付けしましょう。
チューリップの栽培方法
プランターに植えるか、花壇に植えるかで球根の深さが変わってきます。プランターに植える場合は、浅く植えるようにしましょう。根の伸びるスペースが限られているので、あまり深く植えることはおすすめできません。
65センチのプランターの場合は1つに10~20個の球根を植えるようにして栽培してください。花壇への植え付けの場合は、深植えが基本なので、チューリップの場合は、5センチほどの深さに植えましょう。
植えるときに、球根の向きに気をつけると、花が咲いたときに、見た目がきれいに整います。球根には、葉が出る方向と花が咲く場所があります。それらの位置を正しく理解していると、開花時に均整のとれた花壇・プランターになります。
見た目の問題だけではなく、適当に植えてしまうと、日当たりの良し悪しから成長しないおそれがあるので、球根の向きは揃えるように注意して種付けし栽培してください。肝心の球根の向きですが、葉が出る向きは、上から見たときに尖っている方です。
球根は楕円形をしており、カーブの緩やかな面ではなく、やや尖った面の方から葉がでます。花の出る場所は、横から見た時に出っ張っている部分です。これらの向きに注意して、葉が出る方向を揃え、花が出る面を上にして植えてください。植え付けは、9月~11月です。そして、開花時期は3月~5月です。覚えておくと、育てるときに役立ちます。
植え付け後の管理の仕方・育て方
基本的には、そこまで難しい育て方ではありません。ある程度できていればしっかりと花は咲いてくれるので、間違った育て方をしないように気をつけるだけで大丈夫です。水やりは、花壇の場合は自然の雨に任せて大丈夫です。
ですが、あまりにも晴れが続くようなら、水撒きをしてください。プランターの場合は、土の表面が乾いたら与えてください。ですが、あまり与えすぎると根が腐ってしまうので与え過ぎに注意してください。土の表面を確認してから水をあげるように心がけてください。
乾燥に弱いので、土の状態は小まめに確認しましょう。乾燥が激しいのであれば、腐葉土などを敷き詰めて乾燥を防ぐように対策して下さい。植え付け時期が秋から冬ですが、寒さには強いので特に防寒対策をする必要はありません。ですが、乾燥する季節なので、乾燥には注意しましょう。
きちんと土を作った場所で育てるのであれば、肥料は必要ありません。ですが、寄せ植えをするのであれば、薄めた液体肥料を与えてください。花が終わった後の球根にも注意が必要です。また、次の年も楽しみたいのであれば葉は1つたりとも切り落としてはいけません。
花を切ったあとに、土をかけて、球根を育成してください。葉が全て枯れた後に掘り上げをして乾燥させてください。そうすることで、次の植え付けのときまでに、球根が育ち、大きい球根からまた花が咲くことができます。
チューリップによく見られる病気として、モザイク病・白絹病・軟腐病があります。モザイク病とは、花弁に本来あるはずのない縞模様が出る病気のことです。白絹病とは、株元に白い菌糸が現れて、立ち枯れる病気のことです。
軟腐病とは地際や球根が腐る病気です。病気の株を発見したら、すぐに抜き取って処分しましょう。先程も紹介しましたが、虫害としては、アブラムシやネダニが発生することがあります。特にアブラムシはモザイク病などを媒介するので、注意してください。
発見した際には、先に紹介した薬品などで迅速に駆除しましょう。簡単なようで、極めようとすれば奥が深いのがチューリップです。まずは、育てやすい品種から取り組んでみましょう。
色々育てることで、様々な種類のものを育てられるようになるので、春には色とりどりの花壇を楽しむことができるようになります。また、球根も育てることで、次の年にも利用できるので、何度でも花を咲かせることができます。
チューリップの歴史
チューリップといえば、オランダというイメージがありますが、実はオランダが原産国ではありません。チューリップは、トルコから中央アジアにかけてが原産だとされています。思ったよりも広い範囲なのは、トルコ民族の移住によって、中央アジアまで分布したからだといわれています。
トルコ民族は、ターバンやアクセサリーにその花を使っていました。それが1554年に、当時オーストリア大使としてトルコにいたブズベックの目に止まります。これが、きっかけとなりヨーロッパにチューリップが広まることになります。
ヨーロッパに持ち込まれたチューリップは、当初、上流階級の人々にしか楽しめないほど高貴な存在でした。17世紀に入ると、その熱が爆発しチューリップ狂時代とよばれるようになります。生育環境が適していたオランダでは人々はこぞってその花を求めました。
特に、斑入りのものが好まれ爆発的に売れました。ですが、それも長くは続かず、バブルが弾けます。価格が一気に下落し、人々は混乱の渦に巻き込まれることになりました。しかし、その後、オランダ以外のヨーロッパの地域でも要望が高まり、いち早く生育に取り組んでいたオランダから多くの品種が広まっていきました。
チューリップの特徴
生息地のものは、私達の知っているものよりも、草丈の低い可憐な花が特徴です。また、この花は、非常に品種が多いことも特徴のひとつです。品種改良をされてどんどん増えた結果、正確な数が把握できていません。8000種以上あるといわれています。
また、ほとんどのものに毒性があることも特徴です。中には、球根を食べられる品種もありますが、品種によっては、球根にも含まれています。傷をつけると生成され人によっては触れるだけで炎症をおこす場合があります。身近な花ですが、危険性もあるので扱う際には注意が必要です。
また、あまり香りが強くないことも特徴です。中には品種改良によって香るものもありますが、多くは香りが弱いので、大量に植えても不快感を覚えることはありません。ですが、そう思って安易に植えるのではなく植える際には、品種を確認し、どの程度の数咲かせるのかで、香りのある品種とない品種を使い分けるといいでしょう。
香りの強い品種は、植えすぎると強い香りに不快感を抱く人が出てくる可能性があるので、住宅密集地での栽培を考えている方は、特に注意して品種選びをするようにしてください。
花の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アンスリウムの育て方
タイトル:ハナニラの育て方
-

-
ヤマジノホトトギスの育て方
ヤマジノホトトギスはユリ科の植物です。そのため、ユリのように花被片があり、ヤマジノホトトギスの場合は6つの花被片がありま...
-

-
ラカンマキ(実)の育て方
特徴としてはマキ科、マキ属になります。シンボルツリーとしても使われる木で、高くなると8メートルから10メートルくらいの高...
-

-
ほうれん草の育て方について
ほうれん草は日常の食卓にもよく出てくる食材なので、家庭菜園などで自家製のほうれん草作りを楽しんでいる人も少なくありません...
-

-
ホワイトレースフラワーの育て方
この植物においてはセリ科になります。ドクゼリモドキ属となっています。宿根草ですから何年も花をつけることができますが、あま...
-

-
シランの育て方
シランという植物は、ラン科シラン属の宿根草のことを言います。宿根草は多年生の中でも生育に適していないシーズンには地上部分...
-

-
ヒマラヤユキノシタの育て方
ヒマラヤユキノシタとは原産がヒマラヤになります。おもにヒマラヤ山脈付近が生息地のため、周辺のパキスタンや中国やチベットな...
-

-
アルケミラ・モリスの育て方
アルケミラ・モリスは、ハゴロモグサ属でバラ科の植物です。アラビア語のAlkemelych、錬金術に由来しています。アルケ...
-

-
ボケの育て方
ボケはもともと中国原産の落葉低木です。梅と比べてもかなり木の丈が低く、コンパクトな印象で春の花木として人気があります。 ...
-

-
オオイヌノフグリの育て方
気温が下がりつつある秋に芽を出して、冬に生長し春の早いシーズンに小さな花を咲かせるプラントです。また寒い冬でも過ごせるよ...
-

-
ウラシマソウの育て方
ウラシマソウ(浦島草)は、サトイモ科テンナンショウ属の多年草で、日本原産の植物です。苞の中に伸びた付属体の先端部が細く糸...




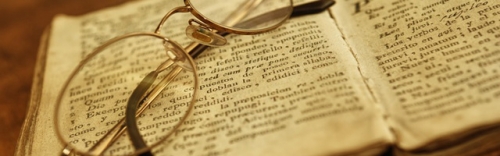





チューリップといえば、オランダというイメージがありますが、実はオランダが原産国ではありません。チューリップは、トルコから中央アジアにかけてが原産だとされています。思ったよりも広い範囲なのは、トルコ民族の移住によって、中央アジアまで分布したからだといわれています。