ブバルディアの育て方

育てる環境について
育て方・適切な環境に関しては、温暖な気候を好み、15℃以上で生育し、冬越しには最低温度7~8℃くらいを保つようにします。日照を必要とするので、真夏以外は日がよく当たる場所で栽培します。春から秋のあいだは、風通しが良好で日あたりのよい、戸外で育てます。花が咲いたら、
日光のさす窓辺に置いてもよいです。夜間はガラス越しの冷気で気温が下がるので、部屋の中央付近に移動させてください。寒さと暑さが苦手なので、季節に応じて、管理する場所を工夫しましょう。霜に当たると枯れてしまうので11月を過ぎれば室内に入れると安心です。
短日性の花ですので、適温と日照時間を調整出来れば、ほぼ周年花がたのしめます。南関東から西日本では、庭植えでも、育てることができます。剪定は咲き終わった枝を、短めに切ります。冬越し直前に、強めに剪定をしましょう。冬越しの対策として、
11月初旬から室内におき、水やりの頻度を減らします。最低気温を5℃以上になるようにしながら、春まで管理をしましょう。冬越し中に葉が枯れ落ちても、春を迎えるころには新芽が出てきます。枯れた訳ではないので、そのまま育ててください。
室内温度を7℃〜10℃くらいに保つことができれば、休眠しないまま冬を越すことができます。鉢植えにする場合、用土は水はけのよいものがよく、一般の草花用培養土やバラなどの培養土と同様のものが利用できます(例:赤玉土5、鹿沼土2、腐葉土3の配合用土など)。
種付けや水やり、肥料について
種付けに関して、温暖な時期であれば、いつでも植えつけできます。4月から6月、または9月から10月ごろに植えつけると生育が良好です。また、植え替えに関しては、木本なので頻繁に植え替える必要はありません。6号鉢以上で大株に育ったものは2~3年ごとに植え直します。
小さい苗のうちは、成長にしたがって毎年少しずつ大きな鉢に植え替えます。適期は植えつけ時期と同じです。水やりに関しては、水切れに注意して、鉢の底から水が出るぐらいたっぷりとやってください。乾燥させると生育が止まり、ひどい場合は落葉することもあるので、
生育中は用土が乾燥しないよう十分に水を与えるようにします。水はけをよくしておくことも大切です。いつも湿った状態、過湿にしてしまうと根腐れを起こすので、水のやりすぎにも気を付けてましょう。また、受け皿に溜まった水はそのままにせず捨てましょう。
冬は乾かし気味にします。表面の土が十分に乾いてから、その2~3日後に水を与えるようにしてください。生育が旺盛な期間は水を欲しがりますので、タイミングをみて水をあたえます。肥料に関しては、真夏と冬を除き、肥料切れしないよう、定期的に施します。
肥料をやると花を長く咲かせるので、月1回の置き肥、または月3回(10日に1回)くらい液体肥料を施します。春と秋に置き肥を使う場合は緩効性のものを与えましょう。真夏と冬は花を咲かせていないので、肥料をやる必要はありません。
増やし方や害虫について
ブバルディアの増やし方は、さし木が一般的です。さし木のタイミングは高温長日期の6月から7月がよく、枝の先端を切り取ってさします。10cmほど枝を切り、じゅうぶんに水揚げをしてから、清潔な用土に挿しておきます。明るめの日陰におき、乾燥しないように霧吹きなどを利用して、発根を促すのがコツです。
また、他にブバルディアの栽培・生育に必要な作業としては「切り戻し」があります。花の終わった枝は、枝の途中で切り戻しをしましょう。全体の草姿を見ながら、形を整えていきます。ただし、秋には花芽ができるので、8月以降は切らないように注意してください。
日当たりと風通しがよければ病気はあまり見られませんが、灰色かび病やうどんこ病は根が傷むと発症します。これらの病気は日光によく当て風通しをよくしていれば防げます。また多肥多湿の状態が続くと根が傷むので、乾燥させないようにしながらも、水はけよくしておき、
低温期、高温期は肥料を施さないようにします。これで同時に病気の発症も防ぐことができます。被害を受けやすい害虫としては、アブラムシ・ハダニ・オンシツコナジラミなどが主な害虫として挙げられます。まず、アブラムシが発生したら、
早めに殺虫剤を散布して駆除してください。ハダニが発生するときは、葉水で対処しましょう。オンシツコナジラミについてもアブラムシやハダニと同様に殺虫剤や薬剤を用いて早めに駆除することが必要となります。
ブバルディアの歴史
ブバルディアは、学名「Bouvardia hybrida Bouvardia」、アカネ科ブバルディア属の半耐寒性の低木、または多年草で、数種の植物を交配して作りだされた人工の植物です。属名のブバルディアは、17世紀に活躍したフランスのルイ13世の侍医で、パリの王室庭園の園長でもあったシャルル・ブヴァールの名前にちなんでいます。
原産・生息地はメキシコ~中南米の熱帯高地で、日本へは昭和のはじめごろに輸入されました。別名「ブバリア」と呼ばれ、9月10日、10月18日、11月4日、12月26日の誕生花で、花言葉は「愛の誠実」「空想」「夢」「情熱」「幸福な愛」などの意味があります。
園芸用として一般に広く出回っているのは、秋から冬にかけて強い芳香のある、赤やピンクの交雑種「B・ヒブリダ」や、白花種の「B・ロンギフロラ」とその園芸種です。現在も品種改良が盛んに行われており、その結果、一重咲きや八重咲きのほか、半八重咲き、大輪系など数々の種類の花が生み出されています。
鉢花としてよく出回っており、また短日植物で周年栽培が可能なので、花束やアレンジなどにも頻繁に使用されています。甘い香りの白花種は白い十字架を思わせるため、ウェディングブーケなどによく利用されます。ブバルディアの樹高は20~40cmで、主な開花期は5~6月と9~11月ごろの2回です。鉢の市販期は6~10月頃で、切り花は時季に関わらず販売されています。
ブバルディアの特徴
ブバルディアはカンチョウジ(管丁字)とも呼ばれ、花は細長い筒状で、先端が4つに裂けて十文字のように開きます。これが茎の先に何輪も固まって咲き、多いものでは30輪くらいつきます。濃緑の葉先は尖り、披針形または卵形で対生します。春から秋にかけて、
この葉に抱えられるように約1.5~2cmの細長い筒状の小花が枝先に集まり、群がったように十字に開きます。花の先が4裂しているのが特徴で、花色は白が基調ですが、朱赤・ピンク・オレンジなど色の種類は豊富です。切り花として花束やフラワーアレンジメントに利用されることが多く、
鉢植えも流通しますが、耐寒性が弱いので、一般家庭での栽培は比較的少ないほうです。短日開花性のものがほとんどで、通常は10月下旬以降に開花します。わが国では、伊豆大島などの温暖な地域での栽培が多く、シェード栽培(短日処理)により、ほぼ周年切り花が楽しめます。
ブバルディア属には30種もの品種があり、半常緑性の低木灌木で、葉は対生または3~5枚で輪生します。そのなかで、ブバルディア・ロンギフローラは、白色大輪で強い芳香があり、比較的古くから栽培されていました。
その後、ブバルディア・テルニフォリアやブバルディア・レイアンタなど、いくつかの原種をもとに品種が育成され、赤や桃色など、小輪多花性のものが栽培されるようになりました。現在も新しい品種が育成され、これらはハイブリッド系と呼ばれています。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ケショウボクの育て方
-

-
コリアンダーの育て方
地中海東部原産で、各地で古くから食用とされてきました。その歴史は古く、古代ローマの博物学者プリニウスの博物誌には、最も良...
-

-
ルバーブの育て方
ルバーブはタデ科カラダイオウ属に分類されている、シベリア南部が原産のハーブです。ボルガ河の辺りは、野生種の生息地でもあり...
-

-
ルコウソウの育て方
ルコウソウの原産地は熱帯のアメリカで、暖かい気候の土地に定着しやすいです。日本では本州中部以南に生息しており、1848年...
-

-
シラタマノキの育て方
シラタマノキは学名をGaultheriamiquelianaといい、ツツジ科のシラタマノキ属になります。漢字にすると「白...
-

-
アゲラタムの育て方
アゲラタムは熱帯アメリカ原産で、生息地には約40種ほどがあるといわれています。丈夫な植物で、日本でも沖縄などでは野生化し...
-

-
フォックスフェイスの育て方
フォックスフェイスはブラジル原産のナス属の植物とされ、ナス属は世界の熱帯から温帯にかけて1700種ほどが分布しています。...
-

-
ヘンリーヅタの育て方
特徴として、まずブドウ科、ツタ属であることです。つまりはぶどうの仲間で実もぶどうに似たものをつけます。しかし残念ながら食...
-

-
サボテンの育て方のコツとは
生活の中に緑があるのは目に優しいですし、空気を綺麗にしてくれるので健康にも良いものなのです。空気清浄機のように電気代がか...
-

-
シェフレラ・アルボリコラ(Scefflera arboric...
台湾や中国南部が原産地のウコギ科セイバ属の植物です。生息地は主に熱帯アジアやオセアニアで、およそ150種類ほど存在する低...
-

-
ゴーヤの栽培こでまりの育て方あさがおのの種まき
種物屋さんに行くといろいろ知識の豊富な方がいらっしゃいますのでわからない時はまずはそういう専門家に相談してみます。そうし...




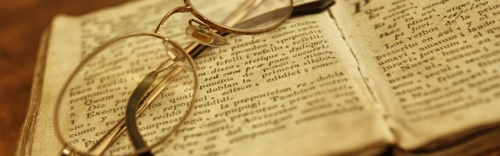





ブバルディアは、学名「Bouvardia hybrida Bouvardia」、アカネ科ブバルディア属の半耐寒性の低木、または多年草で、数種の植物を交配して作りだされた人工の植物です。属名のブバルディアは、17世紀に活躍したフランスのルイ13世の侍医で、パリの王室庭園の園長でもあったシャルル・ブヴァールの名前にちなんでいます。