オンシジウムの育て方について

育てる環境について
5月から10月頃までは、戸外の風通しの良い所に置き、できるだけ長く日が当たる場所を選んで置きます。葉焼けを起こすことがあるので、50%の寒冷紗(遮光ネット)をかけて強い直射日光を避けましょう。冬は室内の日光が良く当たる窓辺などに置くのがよいでしょう。
10月下旬になると急激に温度が下がるので、室内の日当たりの良い場所に移動させ、夜間など窓の近くは大変冷えるので、部屋の中央などに鉢を動かすなど、こまめな温度管理が必要です。用土は保水力があり、比較的早く乾く植込み材料を使用します。
乾燥には強いのですが、多湿には弱いために水ゴケで植え付けを行うのが一般的です。その場合小さめの素焼の鉢を使用し、水やり後はできるだけ早く株元が乾くようにします。最低気温が15℃以上になれば戸外で管理できるようになります。冬に売られているオンシジウムは、
冬から春に咲くタイプのものです。寒さには強くないので室内の暖かい明るい窓辺に置き、暖房の温風が当たらない場所で管理します。水やりは鉢土の表面が乾いて翌日に与えるくらいやや控えめでかまいません。冬の暖房が利いた室内では、
霧吹きで花と葉に水を与えると花もちがよくなります。夏から秋咲きのタイプは、冬の最低気温が7℃以上で管理します。冬から春先のタイプは、15℃以上であれば冬でも開花し、最低気温が10℃くらいなら冬の終わり頃に開花、最低気温が7℃くらいなら春の開花となります。
種付けや水やり、肥料について
オンシジウムの植え付けは、しばらくは購入した時の鉢のままで育て、株が鉢からはみ出したり、植え込み材料が傷んだ場合には、春になってから植え替えを行うとよいでしょう。植え替えるときの鉢は、1まわりから2まわり大きなものを選びます。乾燥を防ぐために水ゴケを使用します。
季節を問わず、土が乾きはじめたらたっぷりと水を与えましょう。特に夏はすぐに乾くので毎日の水やりはかかせません。からからに乾く前にこまめにチェックして水をあげましょう。水ゴケは1回乾くと水をはじいて吸収しにくくなりますので、乾ききった場合は、
バケツを入れた水に鉢ごと一晩つけ、水ゴケにしっかり吸収させる必要があります。冬は部屋を暖房している場合、空気がとても乾燥するので、霧吹きで葉水を与えます。開花中でも霧吹きで花を保湿してあげますが、この場合暖房の効いている暖かい時間帯に行うのがポイントです。
また暖房の熱風が直接あたらないよう注意しましょう。水やりの基本は植え込み材が乾いたら水を与えること。晴れた日の午前中に与えるのがポイントです。肥料は4月中旬頃から施し始め、9月いっぱいまで続けます。このころはラン用の液体肥料を1000倍に薄めて使用し、
10日に1回程度行います。冬は室内に取り込み、10~15℃になるように保ちます。晴れた日には戸外に出して日に当てることも大切です。温室が必要ない品種ですが、温度管理はこまめにチェックすることが必要です。
増やし方や害虫について
根が鉢からたくさんはみ出して根づまり気味になったら、植え替えを行いましょう。植え替えは春の新芽が出てくる頃が適期で、2~3年を目安に行います。用土は水ゴケかバークを使用し、古いバルブは養分になるのですべてを取り除かないように一株に2つはつけておきましょう。
またオンシジウムは株分けで増やすことができます。バルブが4つ以上になったら、親株から2つのバルブをつけたまま、根を傷めないようにゆっくりと根をほぐし切り離して株を分けます。根が詰まっている場合には、清潔なハサミで切り分けを行います。
このときに根元に水ゴケを巻きつけたり、洋ラン用のバークを使用するのがよいでしょう。古いバルブは養分になるので、子株につけたままにしておくとよいでしょう。一番害虫が多いのが、外に出して室内に移動する秋です。ナメクジ、ダニ、カイガラムシなどの害虫に注意し、駆除しましょう。
特にナメクジは柔らかい花茎をたべてしまいます。食べられてしまったら花茎が駄目になってしまうので、ナメクジ専用の薬を使うなどして駆除しましょう。またダニやカイガラムシは見つけたら殺虫剤で駆除しましょう。また新芽や花芽が伸び始めると、アブラムシが発生しやすくなるので注意が必要です。
葉が茶色くなり、水気を帯びた状態になったら、軟腐病かもしれません。そのまま放っておくと枯れてしまう可能性があるので、早めに対処しましょう。また根腐れにも注意し、早めに根込み材料を取って根をきれいに洗ってから、元の鉢に根だけになった株をいれます。たっぷりと水をかけてあげると、新しい芽が出てきます。
オンシジウムの歴史
オンシジウムは約400種が中南米の熱帯・亜熱帯地域に分布する蘭の仲間で、原産地は中央アメリカ・南アメリカです。生息地は低地~標高3500mの高地と種類によって様々です。また姿形も変化にとんだユニークな花の一種です。オンシジウムと言う名前は、
ギリシア語のオンキディオン(小さなこぶ)に由来し、花の一部にある小さな突起があることに因んでつけられました。日本には明治時代に渡来してきましたが、当時は華やかな雰囲気の花ではなかったため、あまり普及はしませんでした。その後品種改良などもあり、
切り花として輸入されることで注目を集めるようになった花です。もともとは黄色の花しかありませんでしたが、ピンクや白、褐色、赤、オレンジなどカラフルな品種も生まれ、パーティーなどの飾りとしてよく用いられています。洋ランの中では耐寒性があるので、温室がなくても花を楽しむことができます。
贈り物などでよく売られているオンシジウムですが、この場合数個のポット苗が寄せて植えられていることがほとんどです。そのまま管理してしまうと根が腐ってしまうことがあるので、花が終わったら人株ずつ育てるようにしましょう。オンシジウムは洋ランの中では栽培しやすく、
温室がなくても育てることができる扱いやすい品種です。花期は種類によってまちまちで、夏から秋頃に咲くものもあれば、冬から春に咲くものまでいろいろです。開花してから長く楽しむこともでき、切り花としても花もちがよいのも人気の理由です。
オンシジウムの特徴
華やかな黄色い花として広く知られているオンシジウムですが、その種類は多く、小型で香りの強いものから大型でボリュームがたっぷりなものまでさまざまな品種があります。基本的に育て方は簡単な花なので、とてもポピュラーな花として人気があります。
花は比較的長く楽しめるので、切り花としてもよく利用されています。枝別れをした先に総状花序を出し、花の径は1㎝から2㎝くらいの黄色に褐色の斑点のある花をたくさん垂れ下げるのが特徴です。さまざまな種類がありますが、大きく分けると
「薄い革質葉」、「棒状葉」、「針状葉」、「肉厚葉」の4種に分類することができます。この中でもよく知られているのが「薄い革質葉」の種類だと思います。この種類のものはたまご形のバルブを持っていて、蝶の群れが飛んでいるように花が咲きます。
花弁の基部がこぶ状に隆起っしていることで蝶のように見え、オンシジウムといえばこの種を想像する方も多いもっともポピュラーな品種です。オンシジウムの花もちはとてもよく、1か月から2か月くらいは花を咲かせ続けます。全体の3分の1くらいが咲き終わったら、
花茎を元から切り取り、切った花は切り花にすると2週間ほど楽しむことができます。オンシジウムはもともと樹木の幹や枝に養生するランで、乾燥に強いのが特徴です。オリジナルの黄色の他にも、ピンクや紫などの品種も改良されていて、種類がおおく年間を通じて花が咲くのも魅力のひとつです。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:カランセの育て方
-

-
シェフレラ・アルボリコラ(Scefflera arboric...
台湾や中国南部が原産地のウコギ科セイバ属の植物です。生息地は主に熱帯アジアやオセアニアで、およそ150種類ほど存在する低...
-

-
ヤシ類の育て方
ヤシ類の特徴としては、まずはヤシ目ヤシ科の植物であることです。広く知られているものとしてはココヤシ、アレカヤシ、テーブル...
-

-
サンギナリア・カナデンシスの育て方
サンギナリア・カナデンシスとはケシ科サンギナリア属の多年草の植物です。カナデンシスという名の由来はカナダで発見されたこと...
-

-
カトレアの育て方について
カトレアと言えば、バラと並んで花のクイーンとも言える存在になっています。ただし、カトレアとバラには大きな違いがあります。...
-

-
すなごけの育て方
特徴は、何と言っても土壌を必要とせず、乾燥しても仮死状態になりそこに水を与えると再生するという不思議な植物です。自重の2...
-

-
ヒメノカリスの育て方
ヒメノカリスはヒガンバナ科の植物で原産地は北アメリカ南部や南アメリカで、日本では一般的には球根を春に植えると夏には白く美...
-

-
木立ち性ベゴニアの育て方
木立ち性ベゴニアの科名は、シュウカイドウ科で属名は、シュウカイドウ属(ベゴニア属)になります。その他の名前は、キダチベゴ...
-

-
アボカドの栽培について
栄養価が高く、サラダやサンドウィッチの具材としても人気の高いアボカドですが、実はご家庭で観葉植物として栽培することができ...
-

-
リコリスの育て方
種類としては、クサスギカズラ目、ヒガンバナ科、ヒガンバナ亜科、ヒガンバナ連、ヒガンバナ属になります。園芸上の分類としては...
-

-
アスコセントラムの育て方
古来より植物と人間の生活は密接に繋がっている。食料として利用されるだけでなく、住居の材料にもなりますし、現在では観賞用と...




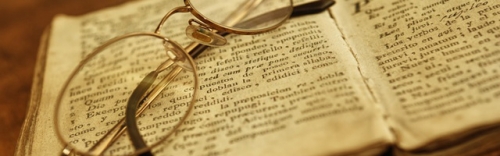





オンシジウムはラン科、オンシジウム属になります。その他の名前は、オンシジューム、群雀蘭(むれすずめらん)と呼ばれます。