ハツユキカズラの育て方

育てる環境について
ハツユキカズラは日陰でも育てられますが、葉の斑や新芽の発色を良くするときには、日当たりの良い場所で栽培するようにします。育て方として注意したいのは、真夏の直射日光に当ててしまうと葉が焼けてしまい茶色く枯れることがあるので、
日差しが強くなる時間帯は光を遮ったり置き場所を変えるなどの対策をします。購入してきた時と比べて葉のピンク色が薄くなってきた場合は、日照不足または水分や肥料の不足などが考えられます。ハツユキカズラは寒さにも強いので、冬でも屋外で育てられます。
生育に適した温度は10~25度になりますが、マイナス5度くらいの環境まで耐えられます。ただし冷たい風に頻繁にさらされるような場所では葉が傷んでしまう恐れがあるので、庭木として育てる場合は植える場所に注意してください。鉢植えの場合は風が避けられるような場所に移動して管理します。
温暖な地域では防寒対策を行わなくても越冬できますが、寒冷地で栽培する際には、藁などを敷いて霜対策をしておくと安心です。比較的丈夫な植物なのですぐに枯れてしまうことは少なく、環境や温度管理については、それほで厳密に行わなくても十分に育っていきます。
鑑賞用として葉の色や斑をきれいに出す際のポイントは、日光によく当てるようにして、こまめに刈り込んで新芽を育てることです。繁殖しやすい植物なので、思い切って刈り込みを行っても問題なく育ちます。また斑がなく単色になってしまった場合は、その部分を枝ごと剪定します。
種付けや水やり、肥料について
ハツユキカズラを種から育てることはほとんどなく、苗や植木を購入して育てます。植付けに適した時期は3月下旬から6月下旬、または9月中旬から10月下旬頃です。水はけが良い土壌に植付けするようにして、庭の水はけが心配な時は腐葉土や川砂などを混ぜておき、
鉢で育てるときは赤玉土、腐葉土、バーミキュライトなどの通気性のあるものを混ぜて使います。植付けの時に緩効性の肥料を混ぜ込んでおき、根をくずしてから植え付けます。庭木の場合は定期的に植え替える必要はありませんが、鉢植えは根が伸びて底の鉢穴から見えるようになってきたら、植え替えを行います。
植え替え時期は植付けと同じ時期が最適です。乾燥には強い性質がありますが水分を好み、与える水が少ないと斑や新芽の発色に影響が出てくるので、水は切らさないようにしてください。水切れを起こすと下葉が落ちてしまうこともあるので、
表面の土が乾いてきたらたっぷりと水を与えるようにして、適度に湿り気を帯びた状態にしておきます。庭木では水やりを行う必要はありませんが雨が降らない日が続くなど、降水量が不足しているような時には水を与えるようにします。生長が著しい植物になり、
肥料が切れてしまうと葉の発色が悪くなることがあるので、肥料は定期的に与えるようにします。春から秋にかけて月1回程度緩効性の置き肥または液体肥料を与えてください。窒素分が多い肥料をたくさん与えてしまうと緑が強くなってしまい、ピンクや白が薄くなってしまうことがあります。
増やし方や害虫について
ハツユキカズラを増やす時は挿し木をします。5月から8月くらいが適していて、3節から4節くらいの長さに枝を切って、下部分に生えている葉を取り除きます。それを水はけが良く保水性のある赤玉土や挿し木用の土などに挿して、明るい日陰で管理して発根させます。
土に挿す時には割りばしなどで穴を空けてから挿し込むようにすると、茎を傷めずに済みます。またハツユキカズラは節から自然に根が生えてきて増えてくるので、その部分に土をかぶせて植え込んで増やすこともできます。ハツユキカズラで注意したい害虫には、
アブラムシとカイガラムシがあります。アブラムシが大量に発生すると見た目を損ない、葉の汁を吸うことで形が悪くなったり株が弱って病気にかかりやすくなります。ウイルスの媒介となることもあるので、見つけた時には早めに駆除するようにします。
カイガラムシはさまざまな種類が存在していて、草木の汁を吸って生育を悪くします。被害が進んでくると新芽が出にくくなったり枝枯れなどを起こすことがあります。また、アブラムシやカイガラムシの排せつ物が原因で、すす病が発生することもあります。
すす病になると葉の表面が黒くなってしまため、日光が阻害されて生長が緩やかになってしまいます。これらの害虫は、ハツユキカズラの枝葉が密集してくると発生しやすくなるので、こまめに剪定を行って葉の間の風通しを良くすることが予防になります。被害がひどくなってきた場合は殺虫剤などの薬剤を散布して害虫を駆除します。
ハツユキカズラの歴史
ハツユキカズラはキョウチクトウ科テイカズラ属で、日本の本州以南と朝鮮半島が原産の植物になります。名前の由来は、葉に入った白い斑が初雪が降ったように見えることから付けられました。ハツユキカズラはテイカカズラの園芸用品種になり、テイカカズラは日本の山に自生している品種で、漢字では定家葛と書きます。
平安時代末期から鎌倉時代にかけて活躍した歌人の藤原定家が名前の由来となっていて、古事記や古今集などにも記載されているほど日本では古くから親しまれている植物です。ハツユキカズラはこのテイカカズラの葉に斑が入った品種になります。
ハツユキカズラと良く似ている品種に、同じテイカカズラ属のゴシキカズラがあります。新芽が白色とピンク色になり葉には白い斑が入っているので、見た目はほとんど同じになり区別が付きにくいのですが、比べてみるとハツユキカズラの方が葉が小さく、斑の入り方が微妙に異なります。
ハツユキカズラが属するキョウチクトウ科の植物は毒があることでも知られていて、毒と言ってもその成分は医薬品として用いられることもありますが、経口摂取してしまうと嘔吐や下痢、めまいなどの中毒症状を起こす可能性が高いので、ペットを飼育している場合などは、
誤って食べてしまわないように気をつけて管理してください。樹液がついてしまうと皮膚が炎症を起こしてかぶれることもあるので、剪定時にも注意するようにします。ハツユキカズラは下葉の落ち着いた濃い緑色や先端の明るい白やピンクの葉は和風にも洋風にも合うので、さまざまなテイストのガーデニングで用いられています。
ハツユキカズラの特徴
ハツユキカズラは常緑蔓性品種の多年草で、草丈は5cm~15cmほど、つるの長さは10cm~30cmほどに育ちます。濃緑色の葉には白い斑が入り、先端の新芽は濃いピンク色をしていて葉が生長するにつれて白っぽくなり、次第に緑がまじって斑になって、やがて単色の濃い緑色に変わります。
とてもカラフルなので葉が鑑賞のメインとなり、こまめに剪定していると花はほとんど見られないのですが、まれに直径2~3cmくらいの白い小さな花を咲かせることがあります。開花時期は春になり、前年の夏に芽を付けます。5枚の花弁はスクリューのように少しねじれていて、
ほのかに甘い良い香りがします。開花前に剪定をすると花芽を切ってしまうことになるので、花を楽しみたい時は剪定は花が終わった後に行うようにします。特に花を意識しないのであれば、伸びた枝はこまめに刈り込むようにします。白やピンクの葉は新芽なので、
カラフルな葉を楽しみたい時には刈り込みを行いますが、主に春から夏にかけて行うようにして、冬場の生長が鈍くなる時期には刈り込みは控えるようにしてください。耐寒性があり日陰でも育つ植物になり、もともと生息地が日本なので環境には適応しやすく、
栽培しやすい品種です。気温が低くなってくると紅葉するため、一年を通じてさまざまな姿が楽しめます。つるが伸びるのでグランドカバーとして庭に植えたり、ハンギングバスケットなどで吊るして鑑賞したり、寄せ植えの利用にも適しています。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:アラマンダの育て方
タイトル:ヒトツバタゴの育て方
タイトル:ハナカイドウの育て方
-

-
ヒメヒオウギの育て方
現在の日本国内で「ヒメヒオウギ」と呼ばれる植物は、正式名称を「ヒメヒオウギズイセン」と言います。漢字では姫の檜の扇と書き...
-

-
ルエリアの育て方
ルエリアはルエリア属キツネノマゴ科の多年草で生息地はアメリカ、アジア、南アフリカの熱帯地域などです。その名前は、フランス...
-

-
ゆり(アジアティックハイブリッド系)の育て方
ゆり(アジアティックハイブリッド系)の歴史は古く日本では最も古い文献古事記に桓武天皇が、ユリを摘んでいた若い女性に心を奪...
-

-
シャリンバイの育て方
常緑の植物で、低木となるものが多いです。日本では暖かい地域ではもちろん育ちますが、宮城県や山形県くらいまでなら育つことが...
-

-
長ねぎの育て方
長ねぎの他、一般的なねぎの原産地は中国西部あるいはシベリア南部のアルタイル地方を生息地にしていたのではないかといわれてい...
-

-
大根の栽培方法を教えます。
日本人の食卓に欠かせない大根は、酢漬けや煮物などで美味しく食べる事が出来ます。特に大根の漬漬けには数多くのバリエーション...
-

-
カスミソウの育て方
カスミソウの原産地は地中海沿岸から中央アジア、シベリアなどで、生息地は夏季冷涼なところです。カスミソウの属名ギプソフィラ...
-

-
スタペリアンサスの育て方
サボテン系での育て方の注意点ということでは、他の植物と同じで、日当たりの良い風通しの良い所を好みます。ですので反対に風通...
-

-
フイリゲットウ(Alpinia sanderae)の育て方
ニューギニアが原産や生息地です。フイリゲットウとはフイリとは斑入りという意味ですが、ゲットウという名前がついていてもゲッ...
-

-
エダマメの育て方
エダマメは「枝豆」と書きますが、ビールには欠かせないおつまみとして人気が高い野菜です。そもそもエダマメと言うのは未成熟の...




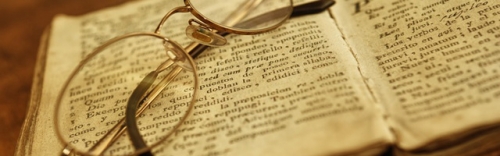





ハツユキカズラはキョウチクトウ科テイカズラ属で、日本の本州以南と朝鮮半島が原産の植物になります。名前の由来は、葉に入った白い斑が初雪が降ったように見えることから付けられました。