イワチドリの育て方

育てる環境について
イワチドリは日光を好む植物ですので、できるだけ日当たりの良い場所で育てます。しかしあまりに強烈な日差しは苦手ですので、可能なら半日陰の場所で育ててあげるといいでしょう。夏の日差しを避けるためにすだれや寒冷紗などを用いるのもいい方法です。
風通しが良いことも生育環境を良くするためには必要です。イワチドリによく用いられる育て方では、腰水栽培という方法があります。腰水栽培とはイワチドリを植えた鉢の底を1センチ程度水につけたままで栽培する方法のことで、水を好むこの植物には適している栽培方法です。
イワチドリの園芸愛好者の中でも、特に大量に栽培することを楽しみとしている人には適している方法といえるでしょう。ただしこの方法で育てる場合は、芽出しの時期から秋にかけてです。冬場は湿り気を切らさない程度に水やりを控えるようにします。
関東から北の、もともとこの植物が自生していないような寒い地域では、冬場の生育環境にも注意を払う必要があります。ある程度の温度を必要とする植物ですので、凍結や急激な温度変化の起きない場所に移動させなければいけません。ただあまりに暖かい場所、たとえば室内で保管した場合などは、
1月や2月のまだ気温の上がらない時期に発芽してしまうことがあり、そうなるとその後の生育スケジュールにも影響がでてしまいますので注意が必要です。用土に関しては鹿沼土や日向土を用いて配合してもいいのですが、初心者の場合はホームセンターなどで販売されている山野草専用の土などを利用するといいでしょう。
種付けや水やり、肥料について
植え付けのタイミングは2月から3月にかけて、徐々に暖かくなってきた頃におこないます。鉢植えで育てる場合は2.5号から3.5号のポリポットの鉢などを用います。浅目の鉢や大鉢などで育てたい場合は、通気性と排水性をしっかりと確保することが必要になるので、
初心者には難しい可能性があります。このような鉢で育てる場合は、用土を盛り上げる高植えをおこなうなどの対策が必要になるでしょう。ポリポットの鉢に植え付ける場合は、底石として8ミリから10ミリ程度の鹿沼土や日向土などの吸水性のいいものを用います。
この際に根腐れを防ぐため、ゼオライトを2割から3割の割合で混入するといいでしょう。中層土は底石よりも小さい4、5ミリ程度の鹿沼土、日向土などの混合用土を用い、上層土にはさらに細かな鹿沼土や日向土、あるいは川砂などの混合土を用います。
もちろん市販の山野草専用の土を用いるという方法でもかまいません。水やりについては上記に表したように、腰水栽培を用いる場合は芽出しから秋にかけては水を切らさないようにします。通常の栽培方法で育てる場合は、芽がでてからは1日に1回、夕方に十分な水を与えるようにします。
冬場に関しては、表面の土が乾かない程度に水やりを控えてもかまいません。肥料は真夏と冬の間を除く期間に液体肥料などを与えます。腰水栽培の場合は受け皿から肥料を吸わせるように与えます。ただし肥料の与え過ぎは良くありませんので、規定の倍率より1000倍から2000倍薄めたものを用います。
増やし方や害虫について
イワチドリは球根植物ですので、数を増やしたい場合は分球によりおこないます。分球とは球根を増やすことです。球根植物のなかには、栄養をたくさん内部に貯蔵しているため親球の周りに子球が増えるものがあります。品種によっても異なりますが、
子球をそのままにしておくと生育が十分に進まないこともあるため、分球して生育スペースを確保することが必要になる場合があるのです。イワチドリはこの分球によって数を増やすことができます。分球は植え替えのタイミングでおこないます。植え替えは2年から3年に1回程度おこないますが、
植え付けた時期と同じ頃におこなうのが適しています。用土をリフレッシュし、痛んだ根を取り除くことが目的の植え替えですが、数を増やしたいのであればこの際に分球して新たに植え付けるといいでしょう。病害虫に関しては、花が終わる3月から6月頃にかけて特に注意が必要です。
灰色かび病などの病気にかかることが多いため、殺菌剤の散布が必要になります。殺菌剤をなるべく使いたくない人は、液を希釈して散布してもいいでしょう。また病気に侵されている部分を早めに取り除くことも、被害を拡大させないためには重要です。
害虫はアブラムシやアザミウマなどが発生することがあり、これらは見つけ次第に駆除しなければいけません。またナメクジやネズミなどもイワチドリに被害を及ぼすことがあり、環境次第ではこれらに対しても何らかの対策を講じる必要があるでしょう。
イワチドリの歴史
イワチドリは、ラン科ヒナラン属の球根の多年草です。本州では中部地方より西の範囲に生息地としており、さらに四国地方にも自生していることが確認されています。春になると唇弁が裂けた形の薄いピンクの花を咲かせ、渓流沿いの岸壁や岩の割れ目などで育ちます。
またこの花にはヤチヨという別名もあります。日本原産の山野草であるため、昔は渓流沿いなどでよく見かける植物でしたが、都市化や開発の影響で日本各地の生息地の生育環境が悪化したこともあり、個体数は大幅に減少してしまいました。さらに追い打ちをかけるように、
園芸愛好者らの間でイワチドリを含む山野草ブームが巻き起こり、各地で過剰な採取がおこなわれてしまった結果、現在では一般人の立ち入ることのできる領域でイワチドリを発見することが困難な状況になってしまっています。個体数の激減を受けて、環境省にも近い将来における
絶滅の危険性が高い種として登録されており、自生が確認されている各自治体においても、保全対策がとられるようになりました。。したがって今では自然界での生息が確認された場合でも、イワチドリが採取されることを防ぐために生息地が特定できないような
配慮がされるなどの措置が取られています。ただ現在でもイワチドリは多くの園芸愛好家の間で人気があり、さまざまな園芸品種の開発が進んでいます。それぞれに花の形や色に特徴があり、庭の彩りに適した品種を自らの好みに合わせて選ぶことができます。
イワチドリの特徴
イワチドリは草丈が5センチから15センチほどの小さな山野草です。4月から5月頃になると咲く小さな花の唇弁は大きく3つに裂け、中裂片がさらに2つに裂けています。花の色は薄いピンクですが、園芸品種により白や紫がかったものも販売されています。
花茎は1本しかなく、葉も1、2枚しかついていません。イワチドリという名前の由来はこの花の姿にあります。岩場に咲く花の姿が千鳥に似ているということからこの和名がつけられているのです。漢字では岩千鳥と表記します。イワチドリは多年草ですので、
晩秋頃になると葉が黄変して落葉し、地上からはその姿を消してしまいます。もっとも、花が終わったからといってもすぐに枯れてしまうわけではありません。花が咲かなくなった春以降も、その他の部分に関しては晩秋に至るまでその姿を残したままです。
冬の期間に休眠した後、春になれば再び成長をはじめます。またイワチドリは水分を非常に必要とする植物でもあります。もともと渓流沿いの岩場に生息している植物ですので、人工的に栽培する場合でも水には非常に注意しなければいけません。山野草の園芸品種の中では比較的丈夫な部類とされていることもありますが、
それでも放置していても育つというほど難易度の低い品種ではありません。園芸品種として品気の高い植物ですが、株そのものが小さいため庭植えよりも鉢植えにするほうが一般的かもしれません。もちろんレイアウト次第では庭植えでも十分楽しむことはできます。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:エピデンドラムの育て方
タイトル:イオノプシスの育て方
タイトル:プレウロタリスの育て方
タイトル:オドントグロッサムの育て方
タイトル:エリデスの育て方
タイトル:ウスユキソウの育て方
タイトル:ウェデリア(アメリカハマグルマ)の育て方
-

-
イオノプシスの育て方
イオノプシスとはメキシコ〜南アメリカなどを原産地とする多年性草本です。ブラジルから西インド諸島へと分布し、ガラパゴス諸島...
-

-
ウェストリンギアの育て方
シソ科・ウエストリンギア属に分類され、別名にオーストラリアンローズマリーの名前を持つ低木がウェストリンギアです。別名にあ...
-

-
ソレイロリアの育て方
特徴としては、イラクサ科の植物とされています。常緑多年性の草になります。草の高さとしてはそれ程高くなりません。5センチぐ...
-

-
フィクス・ウンベラタ(フィカス・ウンベラータ)(Ficus ...
フィクス・ウンベラタとは、フィカス・ウンベラータとも言われていますが、葉がとても美しいだけでなく、かわいいハートの形をし...
-

-
タッカ・シャントリエリの育て方
原産地はインドや東南アジアで、タシロイモ科タシロイモ属の植物です。和名はクロバナタシロイモで漢字では黒花田代芋と書きます...
-

-
コルムネアの育て方
コルムネア属の植物は熱帯アメリカに自生していて、熱帯雨林に生えている樹木の幹の部分や露出している岩の部分などに付着しなが...
-

-
アニスヒソップの育て方
アニスヒソップはシソ科 カワミドリ属の常緑多年草です。原産は北アメリカから中央アメリカで、森林や比較的降水量の多い高原な...
-

-
ブライダルベールの育て方
ブライダルベールは吊り下げるタイプの観葉植物が流行した昭和50年代に日本に登場しました。英語での名称は「タヒチアンブライ...
-

-
ホリホックの育て方
この花については、アオイ木、アオイ科、ビロードアオイ属になります。見た目からも一般的な葵の花と非常に似ているのがわかりま...
-

-
ブリメウラ・アメシスティナの育て方
「ブリメウラ・アメシスティナ」は、南ヨーロッパを原産とした鉱山植物です。花の宝庫と呼ばれ大自然あふれる山脈、ピレネー山脈...




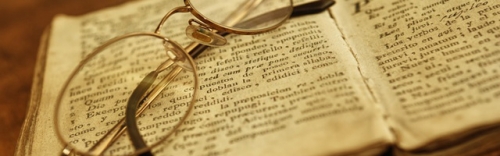





イワチドリは、ラン科ヒナラン属の球根の多年草です。本州では中部地方より西の範囲に生息地としており、さらに四国地方にも自生していることが確認されています。春になると唇弁が裂けた形の薄いピンクの花を咲かせ、渓流沿いの岸壁や岩の割れ目などで育ちます。