アメリカテマリシモツケの育て方

アメリカテマリシモツケの育て方
植えつけや種付けをする場合では、極端に乾かない、水はけの良い日なたで育てることが良いと言われています。因みに、日当たりが悪いと花が減ることがありますが、それでも枯れることは無いと言われています。
また、土質は選びませんが、アルカリ性の土壌で栽培する場合では、葉が黄色くなり、成育が悪くなる可能性があると考えられています。ただし、雨が弱酸性なので、雨が多い地域では土がアルカリ性であることは少ないと言われています。
植えつけの時期としては、3~4月の葉が出る前や、成長が止まって気温が下がってきている10~11月に行うのが良いです。やり方としては、根鉢の表面を3分の1ほど崩してから、根鉢の2~3倍の大きさの植え穴を掘り、
掘り上げた土の量の3分の1程度の腐葉土と元肥として粒状肥料を1平方メートル当たり150gを混合して植えつけていきます。そして、植えつけた後には、たっぷりと水やりをすることが大切です。さらに、枝が多く、倒れやすい場合には、支柱をして倒れないようにします。
剪定の仕方について
アメリカテマリシモツケは、放置していても自然と整った樹形になります。このことから、剪定をする場合には、枯れた枝を落としたり、邪魔な枝を落とす程度で大丈夫です。また、何年かに1回は、2月の落葉時期に勢いがない枝や花が咲きにくい枝を刈りこむことで花が増えることがあります。
剪定する際に気を付けることは特にありませんが、邪魔な幹や重なっている幹を落とすことにより、花が咲きやすくなると言われています。そして、花後に剪定する場合は夏までにすると良いです。
栽培時の注意点
自然雨だけで育ちますが、真夏の乾燥時期には、乾燥を嫌うので土が乾いていた場合には水やりをする必要があります。また、真夏に水をやる場合には、朝または夕方に水をやることが大切です。なぜなら、昼に水をやってしまうと、水が沸騰してしまい、根が傷んでしまうからです。
肥料は、寒肥として2月に油かすなどの肥料をやります。開花後にも同様に、油かすや化成肥料などをやります。因みに、肥料をやる際に注意する点については、株の近くにやるのではなく、周囲に穴を掘り、そこに混ぜ込む形でやります。
なぜかというと、株元近くに肥料をやってしまうと、根が肥料焼けを起こしてしまうことがあるからだと言われています。そして、肥料を与えすぎると、品種によっては、葉が緑に近くなる場合があると報告されています。
アメリカテマリシモツケは、さし木で増やすことが可能となっています。新梢が硬くなる6~7月に枝を2、3節で切り取り、節の下1センチの場所をカッターやナイフなどで斜めに切断します。この時に、枝の長さが7~8全治になるように調整します。
次に、切り口に植物成長調整剤を薄くまぶし、育苗箱や平鉢に入れた赤玉土小粒や、さし木用の土に2~3センチほどの深さにさして、日陰に置いて土が乾かないように管理します。この方法の他にも、
地下で伸びる枝でも簡単に増やすことが可能となっています。方法としては、春から秋に株元の地面から新しい枝が出てきたときに、親株との間の地面にスコップをさして切断し、掘り起こして植えたい場所に植えつけます。
アメリカテマリシモツケは、四季によって葉の色などが変化する特徴があります。ルテウスという品種の場合、5月の中旬から下旬にかけては、春の葉が開く時期となっており、若葉は同じ低木のレンギョウを思わせるような鮮やかな黄色になり、
この色を保つ期間がレンギョウの開花期間よりも長いことが特徴となっています。6月の中旬から下旬にかけては、直径約6~7センチの球状の花を咲かせます。初夏から初秋である7月から9月にかけては、葉が開く時期の黄金色は徐々に緑色に変化してきますが、
真夏でも黄緑色に近い色調を保つので、柔らかい印象を与えてくれます。一般的な樹木の植栽ではこの時期になると、濃緑色だけの変化が少ない色調構成になってしまいますが、アメリカテマリシモツケを庭などに取り入れることによって、夏の庭の景色に変化をもたらすことができます。
また、雨天時や曇天の場合でも庭が明るい印象を受け、周囲の環境とも調和することができます。秋から初冬の10月から12月にかけては、寒さに強い木々もほぼ葉を落としてしまうのに対して、アメリカテマリシモツケのルテウスという品種の場合は、気温がマイナス5度になっていたとしても、葉が落ちることが少なく、葉の色も保つことができます。
ルテウスの場合は、新葉は常に黄色や黄緑色ですが、初霜のある時期になると、葉が赤味を帯びた橙色に変化する場合があります。強い霜があったとしても、葉がしおれたり色褪せたりすることが少ないのが特徴なので、雪が降ったとしても、葉が落ちにくく、銀世界の中でも存在感を示すことができると言われています。
アメリカテマリシモツケの歴史
アメリカテマリシモツケは、北アメリカが原産だと考えられており、現在テマリシモツケ属の生息地はアジア東部や北アメリカ、メキシコに約10種が分布していると言われています。因みに、アメリカテマリシモツケの耐寒性は、20年ほど前に日本で黄金葉の品種であるルテウスの試験栽培を繰り返すうちに発見されたのではないかと言われています。
日本では現在、育てやすいという理由でガーデニング花木として普及しており、花屋だけではなく、インターネット通販でも購入することが可能となっています。育てやすい理由としては、全体的に大型で花もよく咲き、独特の趣がある点や、
日当たりのよい場所であれば土壌を選ばずに簡単に栽培できる点などが人気の理由だと言われています。現在インターネット通販などで購入可能な主な品種としては、新芽は黄色で、徐々に黄緑に変化し、最後には緑色になるルテウス、ルテウスよりもコンパクトな樹形が特徴で、
新芽は鮮やかな黄色で、初夏まで残るダーツ・ゴールド、葉はシソのような茶色で、新芽の時期から落葉まで観賞することができ、飽きの紅葉期には赤味を増して濃いワインレッドに変化するディアボロの3種類があります。
アメリカテマリシモツケの特徴
アメリカテマリシモツケは、全て亜熱帯地域に分布していると考えられています。中でもルテウスという品種は、北海道全域で成育できることが確認されており、積雪の少ない冬期間の最低気温がマイナス30度で、最大積雪量が40センチ以下、最大凍結深度が1メートルの地域であっても、
10年間生育試験を行った結果、耐寒性には全く問題がなかったと言われています。また、病虫害の発生は極めて少なく、道路沿線の植栽などにも適しており、排気ガスなどの公害に強い耐性があると言われています。これらのほかにも、沿岸地域の植栽などにも適していると考えられており、
移植および干害にも強いと言われています。さらに、若木のうちには多数の枝が伸びることから樹形が整いませんが、大きくなるにしたがって、丸い樹形となり、樹高は大きくても2メートル程度なので、手入れがしやすい樹木だと考えられており、
最近では一般家庭でも庭に植えている人が増えてきていると言われています。因みに、開花期は大体5月中旬から6月くらいで、耐寒性と耐暑性は共に強く、一度地面に根をはってしまえば、自然雨だけで十分生育可能だと言われています。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:コトネアスターの育て方
タイトル:ピラカンサの育て方
タイトル:セイヨウイワナンテンの育て方
-

-
サイネリアの育て方
サイネリアはキク科植物の一つで、カナリア諸島が原産のものだと考えられています。かつては「シネラリア」とも言われていたそう...
-

-
ユキヤナギの育て方について
広い公園や河沿いの遊歩道にユキヤナギが植えられているケースが多いです。ユキヤナギの開花期はだいたい4月頃です。
-

-
カッコウアザミ(アゲラータム)の育て方
アゲラータムは別名カッコウアザミという和名を持っています。アザミに花はとても似ていて、その関係からカッコウアザミという名...
-

-
セロジネの育て方
セロジネはラン科の植物でほとんどの品種が白っぽい花を穂のような形につけていきます。古くから栽培されている品種で、原産地は...
-

-
コチレドンの育て方
コチレドンはベンケイソウ科コチレドン属で、学名をCrassulaceae Ctyledonといいます。多肉植物の仲間の植...
-

-
グラプトペタラムの育て方
グラプトペタラムは様々な品種があり日本ではアロエやサボテンの仲間として扱われることが多く、多肉植物の愛好家の間でとても人...
-

-
パキラ(Pachira glabra)の育て方
パキラはアオイ科で、原産や生息地は中南米です。現在は観葉植物としての人気が非常に高いです。原種は約77種ほどあって、中に...
-

-
小松菜の育て方
小松菜の原産地は、南ヨーロッパ地中海沿岸と言われています。中国などを経て江戸時代の頃から小松川周辺から栽培が始まり、以降...
-

-
葉ネギの育て方
ネギの原産地はアジアの北部だとされています。元々の生息地はこのあたりで、中国の西部、あるいはシベリアあたりのものが栽培さ...
-

-
ツピダンサス(Schefflera pueckleri)の育...
ツピダンサスの原産地はインド、マレー半島などの熱帯アジア地域になります。「ツピダンサス・カリプトラツス(Tupidant...




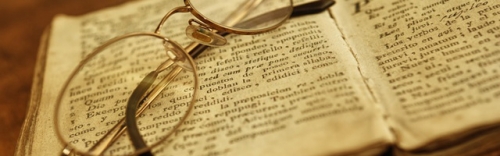





アメリカテマリシモツケは、北アメリカが原産だと考えられており、現在テマリシモツケ属の生息地はアジア東部や北アメリカ、メキシコに約10種が分布していると言われています。