オオチョウジガマズミの育て方

育てる環境について
園芸ショップでは小さくまとめられた、鉢植えの状態で出回っていますので、そのまま育てる人もいるでしょうが、最も適した栽培環境は庭植えです。オオチョウジガマズミは成長スピードが速いという特徴を持っています。そのため、鉢植えでの育て方だと、
根を張るスペースが狭すぎる可能性があります。また、1メートルから2メートルと、人の背丈ほどまで成長を遂げますので、鉢植えでは不安定になり、倒れることで花や枝を傷めてしまったり、付近のものや植物にぶつけてしまう恐れがあります。
台風や強風時にも危険ですので、育てるならできるだけ庭植えに努めてください。自然環境で育った野生種は山の他にも、崖に生えるという特徴を持つことから、日陰った場所よりも、太陽の日差しがよく注がれる、風通しのよい場所を好む性質を持っています。
この性質を踏まえて、日当たりがよく、水はけがよい場所に植えることをおすすめします。土は腐植質であると、よりよい環境を構築できます。乾燥に強い植物です。乾燥する5月頃、冬でも力強く生えてくれますが、水分が多すぎると成長が鈍ってしまいます。ガーデニングなどを楽しむときに、
まずは植えようとしている場所の土の状態や、周辺環境をチェックしましょう。じめじめとした環境であったなら、工夫して土壌改良をする必要が出てきます。土壌改良の方法はネットで調べることができますが、より本格的に行うなら、園芸ショップやガーデニング業者などの専門家に相談してみましょう。
種付けや水やり、肥料について
元々乾燥に強い植物であるため、水やりに気を使うことはありません。室内ではなく、庭植えできちんと育てていれば、雨が降った時に自然に水分補給がなされますので、自然と雨が降るのを待っていれば、そのまま放置しておいても基本的には大丈夫です。
但し、乾燥に強いといってもそれには限度があり、気温が高く、日差しが強力に照りつける、真夏の時期には管理を行いたいところです。この時期に土が速いペースで乾燥をしているようなら、まだ日差しがそれほど強くない、朝や夕方のタイミングで程よく水を与えてやるようにしてください。
肥料に関しては、花が咲いた後の5月の終わり頃から6月に、チッ素N-リン酸P-カリK=10-10-10といった緩効性化成肥料を与えてあげましょう。葉が枯れ、落ちた後の11月から12月頃には、N-P-K=10-10-10などの緩効性化成肥料を与えたり、固形タイプの油かすを与えるようにします。
植えつけ時期は寒さが厳しくなる時期に入る前、葉が落ちた時期を狙いたいところです。11月から12月が適していますが、厳しい寒さが一段落した頃の、2月下旬から3月の上旬頃でも構いません。園芸ショップで購入した時についている鉢から取り出し、
その鉢よりも一回りほど大きい穴を掘って植えるようにします。植える場所の土には腐葉土を混ぜるようにすると、よく育ちます。量は土と同じ分量にしてください。植えた後には支柱を立ててあげ、水を与えましょう。
増やし方や害虫について
増やし方には「さし木」と「種まき」があります。さし木をするには、花が開花した後の6月から7月の中旬頃が最も適しています。1年間で伸びた枝を5センチくらいに切り、さし穂というものを作ります。葉っぱの部分を2分の1の大きさにした後で、鹿沼土小粒単用、
もしくは一般で売られているさし木用土を使ってさすようにします。乾かさないように見守るのがコツですが、日差しが照りつけない明るい場所で行うと上手くいくでしょう。種まきに関しては、秋を迎えた頃に実がなりますが、黒く熟した頃に摘み取って、果肉部分を水でよく洗い落とします。
その種を鹿沼土小粒単用などにまけば完了です。翌年の春には芽が出て、3年から4年程度で花を咲かせてくれます。オオチョウジガマズミの害虫として知られているのは、「カイガラムシ」と「サンゴジュハムシ」です。カイガラムシは1年を通じて植物に発生する害虫で、
オオチョウジガマズミの汁を吸い取ってしまいます。サイズは大きくて1センチほどですが、その殆どが2~3ミリと小さく、見逃しやすいです。被害を防ぐには、風通しのよい場所に植えるのが一番です。サンゴジュハムシは、小さなカナブンのような見た目をした昆虫です。
葉っぱの部分を栄養分としますので、葉っぱに穴がたくさん開いていたらこの虫の被害を疑いましょう。幼虫の駆除が効きますので、幼虫がつく4月頃に捕まえてしまいましょう。葉っぱが展開した後で、専用の殺虫剤をまくと駆除できます。
オオチョウジガマズミの歴史
原産地である日本では、長崎県の対馬市のみに自生する植物になります。海外では、朝鮮半島の南部付近にも存在が確認されています。香りの強さが知られるようになり、最近になって人気が広がってきています。自宅の庭に草花を植えて楽しむ、
ガーデニングなどで、よく利用されるようになり、園芸ショップでの取り扱いが増えています。オオチョウジガマズミが元となった、変種のチョウジガマズミという植物も存在します。チョウジガマズミの方は生息範囲が広く、日本国内では中国地方全域、
香川県や愛媛県、福岡県などに分布しています。オオチョウジガマズミが自生している近隣の地域に広がりを見せているのが分かります。生息地の朝鮮半島でも同様のことが起こっており、標高20~500メートル付近にたまに見られることがあります。この他に、斜面や海岸の絶壁付近でも、存在が確認されています。
生息地の範囲が狭いことから、2007年頃より、環境省のレッドリストに絶滅危惧種として登録されています。正確には絶滅危惧IB類となります。これは今すぐにではないものの、近い将来、絶滅をする恐れがあるというものです。絶滅とは園芸ショップに販売されているものではなく、
対馬市に自生しているものがいなくなるということです。漢字を交えて表記する時には「大丁子がまずみ」になります。学名は「Viburnum carlesii」であり、Viburnumはラテン古名、carlesiiは人の名前が由来になっているとされています。
オオチョウジガマズミの特徴
白い小さな花を、先端にたくさんつけて咲くのが特徴です。花弁の部分が白くなっており、雌しべや雄しべの部分は山吹色、橙色のような黄色系です。花弁からがくの部分に近づくにつれ、ピンク色に変化していきます。花が集まった様子は、まるでアジサイのように半球型です。
花は一つの塊で20個くらいついています。花弁は普通の花のように広がっていますが、がくの付近は細長い筒状になっています。花が開く前のつぼみの時には、色が紅に染まっています。がくの部分は5つに分かれています。花が咲くと、外側に自然に開いていくようになります。
葉っぱの部分は、楕円型をしています。色は濃い緑をしており、ややアジサイの葉っぱに似ています。向かい合って伸びる、対生の習性を持っています。毎年春から初夏、4~5月あたりに開花します。地上よりも標高の高い、山に主に咲きます。
花が咲き、花弁が枯れる頃に、1センチ程度のやや大きな実をつけます。果実に近い核果を実らせ、その形は楕円状をしています。核果の中には1つの種が入っています。実をつけた時には赤い色をしていますが、時間が経過するにつれて、黒く染まっていき熟します。
植物のタイプは草ではなく、樹木に該当します。1メートルから2メートルくらいの高さまで成長し、人の背丈よりもやや小さいか、大きい程度です。花の香りはとてもよいと評判です。花が咲くシーズンには香りを楽しみ、実がつく頃には紅葉を楽しむことができ、観賞用として適しています。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:オドントグロッサムの育て方
-

-
オーリキュラの育て方
オーリキュラは、本来はヨーロッパのアルプスに自生する植物です。高山植物として扱われていて、日本でも栽培されています。原産...
-

-
カレンデュラの育て方
カレンデュラは、キク科カレンデュラ属またはキンセンカ属の植物で世界中で栽培されています。和名はキンセンカ、別名はポットマ...
-

-
ムラサキカタバミの育て方
この植物は、カタバミ科カタバミ属の植物で、日本にもカタバミという植物がありますが180種以上あるということです。また広く...
-

-
コヨバ(エバーフレッシュ)の育て方
マメ科コヨバ属の植物である、コヨバ(エバーフレッシュ)は日本においては、原産地である南アメリカのボリビアから沖縄の生産者...
-

-
グラプトペタラムの育て方
グラプトペタラムは様々な品種があり日本ではアロエやサボテンの仲間として扱われることが多く、多肉植物の愛好家の間でとても人...
-

-
ラッカセイの育て方
ラッカセイは、マメ科になります。和名は、ラッカセイ(落花生)、その他の名前は、ピーナッツと呼ばれています。ラッカセイは植...
-

-
アンズの育て方
アンズはヒマラヤ西部からフェルガナ盆地にかけてを生息地としている、バラ科サクラ属の落葉小高木です。英名ではアプリコットと...
-

-
フウランの育て方
原産地は日本(関東南部・以西)、朝鮮半島、中国南部です。ラン科のフウラン属に分類され、日本では江戸時代から園芸植物として...
-

-
ソテツの育て方
この植物に関してはソテツ目の植物になります。裸子植物の種類に当たり、常緑低木になります。日本においてはこの種類に関しては...
-

-
クルミの育て方
クルミは美味しい半面高カロリーである食材としても知られています。しかし一日の摂取量にさえ注意すれば決して悪いものではなく...




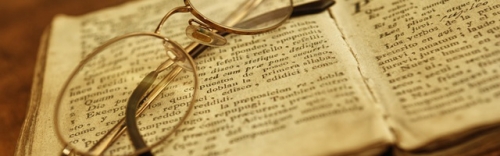





原産地である日本では、長崎県の対馬市のみに自生する植物になります。海外では、朝鮮半島の南部付近にも存在が確認されています。香りの強さが知られるようになり、最近になって人気が広がってきています。自宅の庭に草花を植えて楽しむ、ガーデニングなどで、よく利用されるようになり、園芸ショップでの取り扱いが増えています。