カラミンサの育て方

育てる環境について
南ヨーロッパや地中海沿岸が原産地なので寒さや乾いた風には非常に強いので乾燥にも負けない強さを持っています。しかし耐暑性に関しては日本の夏の直射日光に耐えられるほどはないので、直射日光があまり当たらない場所に植える必要があります。
日向でも半日陰でもどちらでも生育が良いとされているカラミンサは花つきが非常に多いので、株の形を整えるためには日当たりの良い場所で生育しないと強い株にならないので、整えられません。またある程度の乾燥には強い植物なのですが、あまりに乾燥しすぎてしまうと栄養不足になって
株全体が枯れてしまうことがあるので、庭植えをする場合には栄養不足を補うために有機質の肥料を沢山混ぜて耕した土地で育てることが良いとされています。基本的には自然に降る雨の水分で十分生育する植物なのですが、日本の夏は非常に気温が高いので、
雨が少ない時期にはホースの先端にシャワーなどをつけて全体的に水やりを行います。強い植物なのですが、葉の状態をこまめに観察をしてしおれている場合には水やりを行って、良い状態を保つようにします。また鉢植えをしている場合には土が乾き始めたら十分に
水をやる必要があります。この植物はハーブとして利用されるものなので、本体も病気には非常に強い耐性を持っているので、ハーブを目的として栽培することも簡単にできるので、ベランダなどで他のハーブと一緒に寄せ植えにして育てることができる植物です。
種付けや水やり、肥料について
肥料は元肥として緩効性の化成肥料を適度に土壌に混ぜておくと庭植えをした場合でも生育が良くなるので、ハーブを栽培して収穫をする場合には生育を良くするために株の周囲に緩効性加工肥料や液体肥料を追加することで育ちが早くなるので何度も収穫をすることができます。
環境が良い場合には何年間も収穫することができるので、このハーブをお茶などにして日常的に飲んでいる場合には庭やベランダに大量に植えて栽培をすることもできます。水やりに関しては水切れを起こさないように一定の配慮が必要になるのですが、基本的には体力のある植物なので、
病気になる心配もなく十分な水分があるだけで半年以上も開花を続けます。用土としては水はけと通気性の良い土が適しているので、市販されている草花用の培養土を用いることもできますが、自分で作る場合には赤玉土小粒と腐葉土と軽石を配合したものを使うと生育が良くなります。
必要な作業としては切り戻しがあるのですが、このカラミンサという品種は花がら摘みの必要性がないので梅雨の時期に切り戻しを兼ねて、花がらを切っておく必要があります。そうすることによって生長後の姿を美しく整えたり、
ハーブなどの場合には花の数を増やすことができるので、必要以上の茎の生長を抑制して強い芽を出すためには必要な作業です。特に植えこむ直後は枝先をしっかりと切り戻しておくと花の数が増えてボリュームがでるので、たくさんの葉を収穫できるようになります。
増やし方や害虫について
増やし方に関しては株分けや挿し芽が一般的に行われているのですが、繁殖力の強いハーブなので、こぼれ種でも十分に増やすことができます。庭に植えている場合には自生している場所で種が自然に落ちることで自生を始めるので、とくに支障がない場合には自然のままにしておくこともできます。
株分けの方法は大きくなった株を選んで植え付けをしたり、植え替えをするときに分けることができるのですが、時期としては芽が出始める早春の時期がもっとも良いとされています。挿し芽は6月ごろと9月の中旬から10月の上旬に行うことができるので、
しっかりとしている茎を見つけて、7センチほどの長さに切って清潔な用土に挿しておくと2週間ほどで根が張るので水やりなどをしているとそのまま定着をします。害虫に関したはこのカラミンサという品種は虫を駆除するハーブとしても利用されるものなので、
基本的には虫が寄り付いてきません。また殺菌成分などが含まれているので病気にもなりにくいので、外で育てていてもとくに病気になることもないので、初心者でも安心して栽培をすることができます。しかし乾燥には弱いので水やりは欠かさずにするようにしないと、
全体的に体力が落ちてしまって葉が枯れたり、花がしおれる原因にもなります。また直射日光を受け続けると花と葉がしおれてしまうので太陽の光をある程度遮るような工夫が必要となります。場所などをしっかりと考慮することで次の年も楽しむことができます。
カラミンサの歴史
カラミンサはシソ科のハーブで白やピンク、淡い紫色の小さな花をたくさんつけることで人気となっている宿根植物で葉の部分はハーブティーなどにも使われています。昔から南ヨーロッパや地中海の沿岸などで栽培がされてきたハーブですが、栽培が比較的簡単なので日本でも人気となっています。
原産国は地中海の沿岸地域が殆どで、日本で最も人気があるのがカラミンサ・ネペタです。この植物の葉はミント系のさわやかな芳香があるので、花壇や鉢植えなどの様々な育て方がされている植物です。ハーブはヨーロッパなどの地域で古くから民間療法で使われてきたもので、
キャットミントとも呼ばれているカラミンサ・ネペタは古くから風邪の治療や不眠症などに用いられていたもので、現在でもオイル等として人気の商品になっています。ヨーロッパ各地ではハーブティーとしても飲まれていて、心が落ち着くという効果があるので寝る前に飲むのが一般的となっています。
また防腐剤や殺虫剤となる成分が含まれているので、害虫や病気などにも強いので、初心者でも栽培することができます。生息地としてはヨーロッパなのですが、日本でもハーブが人気となっているので、カラミンサという品種がかなり多く販売されています。
基本的に店の外で販売されていて、様々なハーブと組み合わせるようにして育てられるのが一般的となっています。このハーブはシソ科の植物なので葉の部分を利用して健康効果を得ることになります。
カラミンサの特徴
カラミンサの特徴は小さな花が柔らかい茎の部分に群らがるように咲くことで、もともとハーブとして育てられてきた花なので、ミントの香りがとても爽やかなのが特徴です。シソ科の植物で葉の部分は昔からハーブティーとして飲まれてきたもので、
ヨーロッパなどでは風邪の時や胃腸の調子が悪い時にカラミンサから作られたハーブティーを飲んで体長を整えてきました。またこの植物の香りにはアロマ成分が含まれているので、不眠症にも効果があるとされているので、ヨーロッパなどでは日本のジャスミンティーのように寝る前に飲む愛好家が数多くいます。
この植物は葉と花の両方共が小さい作りなので切り花などをした時のカスミソウなどのような役割を立たすことがあり、花壇やベランダなどの寄せ植えなどにも非常に多く使われています。多年草なので栽培を適切に行うことで、数年間楽しむことができる植物で開花をする時期は
5月の中旬から11月上旬とされていますが、カラミンサには多くの品種が販売されているので、品種によっては開花時期が違っている場合もあります。耐寒性が非常に強く夏の暑い気候にもある程度耐えることができることから、初心者向けの植物とされています。
また開花時期が非常に長いのも特徴となっていて、そのままで放置していても次から次へと花が咲き続けるので、特別な管理などを必要としない点も人気の理由となっています。またハーブを採取を目的としている場合に大きめの葉を切り取ってハーブとして利用します。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:グレコマの育て方
タイトル:カランセの育て方
-

-
ネフロレピスの育て方
ネフロレピスはシダの仲間に属する植物で、亜熱帯地方や熱帯地域を主な生息地として世界中に分布しています。中米を原産とし、現...
-

-
ウツボカズラの育て方
ウツボカズラとは、ウツボカズラ科の植物で、食虫植物として広く知られているものの一つです。原産国は東南アジアを中心とした熱...
-

-
ラッセリアの育て方
この花については、オオバコ科、ハナチョウジ属とされています。科としてはゴマノハグサ科に分類されることもあるようです。原産...
-

-
ピーマンの栽培やピーマンの育て方やその種まきについて
家庭菜園を行う人が多くなっていますが、それは比較的簡単に育てることができる野菜がたくさんあるということが背景にあります。...
-

-
クロガネモチの育て方
クロガネモチの原産地は、日本の本州中部から沖縄、朝鮮半島南部、台湾、中国中南部、ベトナムなどです。もともと日本に自生して...
-

-
サトウキビの育て方
サトウキビはイネ科の多年草で、東南アジアや、インド、ニューギニア島などが原産と言います。また、インドの中でもガンジス川流...
-

-
マロウの育て方
マロウは、アオイ科のゼニアオイ属になります。マロウはヨーロッパが原産地だと言われています。生息地としては、南ヨーロッパが...
-

-
アヤメの育て方
アヤメは日本国内でも非常にポピュラーな植物として知られており、歴史的に見ても日本とは非常に深い関係があります。日本人とア...
-

-
ゴーヤーともよばれている健康野菜ニガウリの育て方
ゴーヤーは東南アジア原産の、特有の苦味があるつる性の野菜です。沖縄では古くから利用されており郷土料理”ゴーヤーチャンプル...
-

-
ミニゴボウの育て方
ミニゴボウにかぎらず、野菜の中で形の小さい種類のものは昔からあったのですが、あまり受け入れられてきませんでした。育ちが悪...




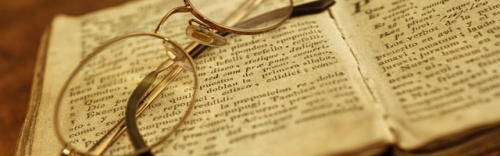





カラミンサはシソ科のハーブで白やピンク、淡い紫色の小さな花をたくさんつけることで人気となっている宿根植物で葉の部分はハーブティーなどにも使われています。昔から南ヨーロッパや地中海の沿岸などで栽培がされてきたハーブですが、栽培が比較的簡単なので日本でも人気となっています。