タイリンエイザンスミレの育て方

育てる環境について
育て方についてですが、地植えで育てることもできますが、鉢植えのほうが好ましいでしょう。動かしやすく、植え替えもしやすいので、花の成長に合わせて、臨機応変に対処することができます。初心者にとっては、種から育てるのはなかなか難しいので、できれば成長した株から育ててみましょう。
日陰、日向どちらで育てても良いですが、あまり乾燥しないよう注意を払いましょう。1番好ましいのは半日陰です。夏の日差しは強いので、葉が日焼けしたり黄ばんだりすることがあり得ます。あまりにも日が強い場合には、明るい日陰へ移して育てることができます。また、同じ種類だからと、他のスミレと一緒に育ててしまいそうですが、良くありません。
他のスミレが負けてしまうからです。ひとつの種類だけで育てるようにしましょう。また、深い鉢を選ぶことで、根を深く伸ばすことができます。この深い根によって、強くて元気な株が成長しますので、根を張れない浅い鉢屋、小さい鉢は避けましょう。撒き床を整え、水持ちの良い環境を作りましょう。野生の花は、林の中に咲いています。
非常に通胃が良い場所です。同じように風通しの良い環境を整えることも大切です。一方、地植えの場合は、あまり手がかからないという利点があります。栄養素や水は地面から吸い上げますし、阻むものがないので、必然的に風がよく通ります。細やかな配慮ができないため、その分リスクも大きいですが、いろんな方法を試してみるのも良いですね。
種付けや水やり、肥料について
繁殖は株分けか種蒔きで行いましょう。先に述べたように、秋に種を蒔けば、つぼみをつけて種を採取することができます。もともと山の中にある植物なので、あまり乾燥を好みません。表土が乾いたら水を十分に与え、土を適度に湿らせておきましょう。庭植えのものは、土の中から水を取り入れるため、頻繁な水やりは必要ありません。
日照りが続いた時など、乾燥がひどければ、水をあげましょう。鉢植えでは、元肥として、リン酸とカリウムが多めの緩効性肥料を用います。3号鉢で二つまみ程度入れましょう。月2~3回、栄養を補給させる必要があります。三要素等量、またはリン酸とカリウムが多めの液体肥料を規定量に従って薄め、入れましょう。
庭植えの場合は、こうした肥料がほとんど必要ないので楽ちんです。強い花なので、多少過酷な環境でも根は伸びます。もしも気になるようであれば、リン酸とカリウムが多めの緩効性肥料を、株の量に応じて、周囲にばらまいておきます。根は長く伸びます。鉢植えの場合は、底の深いものを選ぶのが好ましいです。あまり小さい鉢は避け、根をのびのびと伸ばせるようにしてあげましょう。
土質を選びませんので、草花用培養土でも野菜用培養土でも大丈夫です。細やかな世話を必要とするタイプの花ではありませんが、乾燥には弱いので、土の湿度の状態は小まめに確かめましょう。土が乾きやすいと感じる時には、軽石の量を減らすなどして、水持ちの良い環境を整えましょう。
増やし方や害虫について
気をつけるべき病は、そうか病、うどんこ病などです。そうか病は主に春の終わりから秋にかけて発症する可能性があります。茎や葉を中心に、白いかさぶたのようなものができ、蝕んでいきます。茎がもろくなり、折れてしまう場合もあります。対処法としては、雨を避けることが最も大切です。
外に出した鉢植えは、雨が降る時には玄関に入れておいたり、ビニールをかけるなどして守ってあげましょう。うどんこ病は5月から8月に発生します。葉の表面に、白っぽい粉のようなカビが生えてしまいます。葉や根を枯らしたりする、深刻なものではありませんが、見た目は良くありません。
せっかく綺麗な花をつけても、もったえない感じになってしまいますので注意しましょう。また、主に警戒すべき害虫は、アブラムシ、ハダニ、ヨトウムシ、ツマグロヒョウモン、ネコブセンチュウなどです。春から秋に発生しますが、温暖な気候のところでは一年中警戒が必要です。ネコブセンチュウは土中に住んでいます。
この害虫の発生により、根が傷んでしまい、株の成長が悪くなります。鉢植えの場合は、棚の上に置くなどして、地面から離すことが大切です。株を増やすこともできます。育てた苗を、一回り大きな鉢に植え替えて、株を増やしていきましょう。また、毎年の実ったタネを集めておいて、冷蔵庫に保管しておくこともできます。そうすれば、害虫や病気に汚染されてしまったり、万一枯れてしまった場合にも、新たに栽培することが容易です。
タイリンエイザンスミレの歴史
タイリンエイザンスミレは、日本の本州から九州にかけて、山地の落葉樹林に生えている多年草です。名前の由来は、「叡山の」となっています。余談ですが、カクレミノという別名もあるとのことです。茎は、太めの円筒状で、花の形はカマキリの頭のような、逆三角形です。大輪で、ふわっとした印象の花を咲かせます。昔から存在しており、散策すれば誰でも見つけられます。
急斜面にも生息することがあり、山中の植物なので、強くたくましい花と言えるでしょう。変わりやすい山の天気や、気温差などに負けず、毎年美しい花を咲かせています。日本人の美徳感覚にも通ずるところがありそうです。花は春に咲きますが、秋に一度つぼみをつけます。これは花を咲かせるものではなく、種を飛ばすためです。
つぼみが大きくなると、自然にはじけ、新たに芽吹いて、春にまた花を咲かせます。山中で見かける花は、往々にして大きく、多彩な色を持っていません。しかしタイリンエイザンスミレは比較的小さく、色も多彩で、可愛らしい印象です。山の中の環境は厳しく、美しい花を咲かせるには決して良い条件とは言えませんが、
過酷な環境の中でもこのスミレは生き残り、子孫を増やしてきました。このように可憐でありながらもたくましいスミレの花には、ぜひ出会ってみたいですね。葉に特徴がありますので、葉だけで見分けることもできますが、とても美しい花なので、少し努力して、春に実物を見てみましょう。
タイリンエイザンスミレの特徴
葉の特徴としては、深い切れ込みがあり、ギザギザとしています。葉が細く裂けていて、印象としては、例えるならイタリアンパセリの葉のようです。ギザギザの葉がたくさんに枝分かれしています。茎の高さも低く、多少太めです。全体の佇まいは、タンポポの印象にも通づるところがあります。
タイリンエイザンスミレは日本が原産で、生息地は主に本州、九州、四国の、主に山岳地帯です。多年草で、すみれ科すみれ属に分類されています。日本海側には生息数が少ないので、主に太平洋側の山岳地帯のほうが見つけやすいでしょう。比較的小さな花ですが、様々な色のものが存在します。
薄い白色から、色の濃いものまで、実にバラエティ豊かですので、ひとつ見つけても、また違う種類を見つけたくなります。そういった点で飽きがこないので、収集好きの方にはもってこいのお花かもしれません。また、花自体は可憐で、とても可愛らしいです。林の中で見つけると、きっと心がホッとさせられることでしょう。
多くは日陰の林の中や、斜面に多く生息していますが、林の縁の向陽で見かけることもあります。また、崩壊地のような急斜面に生息する場合もある、とても強い花です。4から5月に咲く花なので、お好きな方は春の良い時期に山にくり出してみましょう。
山登りなどしながらゆっくり観察してみると、出会うことができるかもしれません。山中の林の中に存在しますので、さっさと歩いていたら見つける確率は低くなります。心に余裕を持って散策してください。
-

-
サンダーソニアの育て方
サンダーソニアは南アフリカのナタール地方で発見された花で、1851年に発見されたイヌサフラン科の多年生植物として伝えられ...
-

-
エスキナンサスの育て方
エスキナンサスとは、イワタバコ科の観葉植物です。半つる性で赤い花をつけるこの植物は、レイアウトをすることで、南国風のエキ...
-

-
アイノカンザシの育て方
アイノカンザシはユキノシタ科の植物ですが、別名をエリカモドキともいいます。植物の中でも呼び名がとても印象深く、イメージも...
-

-
グラプトペタラムの育て方
グラプトペタラムは様々な品種があり日本ではアロエやサボテンの仲間として扱われることが多く、多肉植物の愛好家の間でとても人...
-

-
アルケミラ・モリスの育て方
アルケミラ・モリスは、ハゴロモグサ属でバラ科の植物です。アラビア語のAlkemelych、錬金術に由来しています。アルケ...
-

-
ナスタチウムの育て方
ナスタチウムはノウゼンハレン科ノウゼンハレン属の一年草です。ブラジルやペルー、コロンビアなどが生息地となり、葉と花と種に...
-

-
ダボエシアの育て方
ダボエシアは学名でDaboeciacantabrica’bicolor’といいますが、分類で言うとツツジ科ダボエシカ属に...
-

-
セリンセ・マヨールの育て方
セリンセ・マヨールは、セリンセの園芸品種です。セリンセはムラサキ科キバナルリソウ属の一年生です。「黄花瑠璃草」という和名...
-

-
レティクラツム・オウァリウムの育て方
この花についてはキツネノマゴ科、プセウデランテムム属となります。園芸上の分類としては熱帯植物です。また暖かいところに生息...
-

-
アストランティアの育て方
アストランティアは原産が中央や西部ヨーロッパのセリ科の宿根草で、生息地はヨーロッパだけではなく西アジアのほうにまで広がっ...




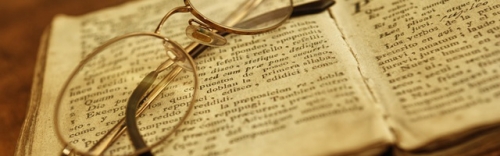





多年草で、すみれ科すみれ属に分類されています。日本海側には生息数が少ないので、主に太平洋側の山岳地帯のほうが見つけやすいでしょう。比較的小さな花ですが、様々な色のものが存在します。薄い白色から、色の濃いものまで、実にバラエティ豊かですので、ひとつ見つけても、また違う種類を見つけたくなります。