ヒアシンスの育て方

育てる環境について
日当たりの良い場所で育てることが望ましい花です。室内でも鑑賞用の花として人気の高い花ですが、できるだけ明るい場所に置くことで、花の開きが綺麗です。しかし、ヒアシンスは一定の低い温度に一度あててから育てないと花芽がつきにくく、
花芽がついても茎が伸びずに根本に近い所で花が咲いてしまう場合もあります。寒さの目安としては10度以下になるような暗い場所に保管しておき、芽が伸びてきたら窓際の日当たりの良い場所に置いて植える時期を待つのが良いでしょう。
外の寒さに十分当ててから暖かい室内に置いてやることで、温かい室内でも、長期間花を観賞することができます。積雪の多い地域では庭などでも栽培できるので、全国で気軽に育てられる花です。気温が高いと花はすぐに開くのですが、伸びきって開花時期が短くなってしまうので、
温度管理にも注意が必要です。寒さには霜が当たっても大丈夫なほど、強いので、鉢植えの場合であっても、室内に取り込んだり、日当たりが良いところを探して置く必要はありません。ヒアシンスが枯れてしまう原因の多くは気温が高すぎるのが問題です。
花が枯れてしまったら、茎は根本から切り落として処理します。しかし、1つの球根から複数本の花が咲くことがあるヒアシンスは外や窓際の日当たりの良い場所において、様子をみていると、茎がまた出てくることがあるので、その時はまた、1本目と同様の育て方をすれば花を咲かせてくれます。
種付けや水やり、肥料について
球根を植え付けは10月に行います。庭植えで、寄せ植えをするのであれば、球根と球根の間隔は球根1.5個分ほどあけ、土から球根の下までが10cmほどになるように植えます。鉢植えの場合、1つの球根につき、5号鉢程度が目安です。しかし、鉢植えでも寄せ植えをしたいのであれば、
球根同士が当たってしまうのではないか、というぐらいに詰めて植えることで花が咲いたときに見栄えのする鉢植えになるのですが、その場合、基本的に来年咲くことはありません。また、庭植えとは違い、球根の頭が少し出るぐらいの浅いところで植えることで、
鉢植えでも根のはるスペースが十分にできるので正常に育つことができます。水やりは植えつけてから枯れるまでの間は土の表面が乾いたらたっぷりと水をあげるようにしましょう。その後は花や葉は枯れ、休眠期に徐々に入っていくので、水やりの回数は減らし、
完全に枯れてしまう6月頃には水やりの必要はありません。水栽培の場合は、一週間に一度水を取り換えるだけで十分ですが、根が伸びてきたら、根が呼吸するためのスペースを確保するため、水を少なくしていきましょう。肥料はあらかじめ水はけの良い赤玉土6、
腐葉土3、パーライト1の割合で混ぜ込んだ土を使用する際に緩効性の粒状化成肥料と苦土石灰を一緒に混ぜ込んでおきます。その後は、芽が伸び、花が咲くまでの間は一週間から10日に1回ほどのペースで液体肥料を追肥として施します。もし、固形の有機質肥料を、
使う際は球根を植えた場所から離したところに埋めるようにしなければ、栄養がそこまで必要のない花なので、咲いた際にバランスが悪い見栄えになってしまうことがあります。来年も咲かせたい場合は、球根を太らせるために、開花時期が終わる頃に追肥として、固形の有機質肥料などを使うようにします。
増やし方や害虫について
一般的に日本でよく栽培されているダッチヒアシンスの球根は、分球しにくいので、増やしたい場合は球根に意図的に傷をつけて増やすことになります。彫り上げた球根を7月頃にそこから半分ほどの深さになるべく深く、十字をかくように切れ目を入れていきます。
浅く切り込みを入れることで、切り込みを入れる球根がそのあと咲かなくなる事態を防ぐことができますが、深く切り込まなかった分、生まれる小球の数も少なくなります。秋の植える時期になるまで、風通しの良い涼しいところにおいておくことで切れ目に小さな球根がつくので、
それをそのまま土に入れて育てることで2~3年の年月をかけて花を咲かせることができる大きな球根に成長させることができます。病気としては軟腐病や、黄腐病や白腐病といった、球根の内部から黄色く腐っていったり、球根の外側から白く腐っていったりします。
いずれも細菌が原因の病気なので、薬剤で防ぐことはできないのですが、水はけをよくして、梅雨前の早めの時期に彫り上げることで予防することができます。予防することはできますが、発病すればどんどんと腐っていくだけなので、被害にあってしまった際には、
非常にもったいないですが、球根ごと処分します。害虫はつきにくい花なのですが、ヒアシンスは匂いが強い種類の花なので、その匂いにつられてハチが寄ってくることがあります。外で栽培する際にもハチには注意が必要ですが、屋内で栽培するにしても窓の開け閉めなどに注意してください。
ヒアシンスの歴史
ヒアシンスは16世紀前半にヨーロッパにもたされ、イタリアで栽培されていた歴史がありますが、ヨーロッパにも伝わった16世紀前半よりも前に生息地であるオスマン帝国のスルタンムラト3世が非常に好んでおり、1583年に山地からたくさんのヒアシンスをイスタンブールへ集めたという歴史があります。
16世紀末にはイギリスへ渡り、園芸愛好家の中で注目が集まり、年月が経った18世紀から19世紀にかけては盛んに園芸用の花として栽培する人が多くなりました。それに伴い、その間だけで数百種類の品種が作られ、現在でもヒアシンスの種類は多種多様にわたります。
しかし、イギリス系のヒアシンスは20世紀初頭に衰退してしまったので、品種が残っていないものも多いです。現在出回っているヒヤシンスのは地中海東部沿岸が原産であるダッチヒアシンスで、18世紀にオランダで改良されたものの1つで、1本の茎に青色や紅色、白や黄色などの多数の花をつけるのが特徴です。
そんなヒアシンスの名前の由来は、ギリシャ神話に出てくるヒュアキントスに由来します。同性愛者であった彼は、医学の神アポロンと共に円盤投げをしていたとき、楽しそうな様子に嫉妬した西風の神ゼピュロスが風を起こした結果、アポロンの投げた円盤がヒュアキントスの額に直撃しました。
アポロンが医学の力を持って治そうとするも、力及ばず、ヒュアキントスは大量の血を流して死んでしまいました。その大量の血から生まれたのがヒアシンスとされているのです。この神話からヒアシンスの花言葉は「悲しみを超えた愛」「遊戯」となっています。
ヒアシンスの特徴
ヒアシンスは防寒性秋植え球根として扱われており、鉢植えや花壇での栽培はもちろんですが、水栽培という栽培方法で鑑賞用の花として大変人気の高いポピュラーな花です。ヒアシンスの色は様々あり、紅色や黄色などの暖色系はもちろんですが、
自然界ではあまりないと言われている青色も濃い色から水色のような薄いもの、紫に近い深いものなどあり、黒に近いような色のものまで様々あります。しかし元々のヒアシンスは紫のものしかなかったと言われているので長年の品種改良の功績が多種多様な色のバリエーションからうかがえます。
花は花びらが外側へとグンと伸びた小花がすべて外側を向き密集し、縦に長細い丸の形をつくります。葉も肉厚で、放射状に広がるので、葉と花のバランスがよいとされ、強い香りもあるので、目で楽しむだけではなく、鼻でも楽しめるのが特徴です。
主に日本でよく栽培されているダッチヒアシンスは球根の色と花の色が同じような色をしているので、球根を見るとどのような色の花が咲くのかの想像が大体できるので、植える前からも楽しい花です。基本的に1つの球根から1本の花が咲くようにできているのですが、大きな球根であれば2本咲くこともあり、
最近ではマルチフローラタイプという品種で1つの球根から何本かの花が咲くように改良されたものも販売されています。球根の中では水栽培をしても、正常に成長してくれる花であり、まっすぐに伸びた白い根や、高めの草丈が水から伸びる様子は愛好家の中でもファンは多いです。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ヒオウギの育て方
タイトル:ヒアシンソイデスの育て方
-

-
ハベナリアの育て方
ハベナリアはラン科の植物で、草丈は15cmから60cmほどになります。洋ランの中でもその品種が非常に多い植物でもあります...
-

-
ビギナー向けの育てやすい植物
カラフルな花を観賞するだけではなく、現在では多くの方が育て方・栽培法を専門誌やサイトなどから得て植物を育てていらっしゃい...
-

-
グレープフルーツの育て方
グレープフルーツの生息地は亜熱帯地方になります。ミカン科・ミカン属になり、原産地は西インド諸島になります。グレープフルー...
-

-
ベニジウムの育て方
ベニジウムは南アフリカ原産の一年草です。分類としてはキク科ペニジウム属で、そのVenidiumfastuosumです。英...
-

-
セロリの育て方
セロリはセリ科の食物でヨーロッパや中近東などが原産で、冷涼な湿原地域が生息地だとされています。古代ローマやギリシャなどで...
-

-
モミジカラマツの育て方
モミジカラマツの特徴について書いていきます。その名前の由来からして、葉っぱは紅葉のように切れ込む葉が特徴的です。実際に見...
-

-
フィクス・ウンベラタ(フィカス・ウンベラータ)(Ficus ...
フィクス・ウンベラタとは、フィカス・ウンベラータとも言われていますが、葉がとても美しいだけでなく、かわいいハートの形をし...
-

-
カトレアの育て方について
カトレアと言えば、バラと並んで花のクイーンとも言える存在になっています。ただし、カトレアとバラには大きな違いがあります。...
-

-
テコフィレアの育て方
南米にはたくさんの野生生物が生息しているとされています。そのなかでテコフィレアという植物があります。テコフィレアは、テコ...
-

-
カモミールの育て方について
カモミールはハーブの一種です。ハーブというのは、食用や薬用に用いられる植物の総称です。人の手が必要になる野菜とは異なり、...




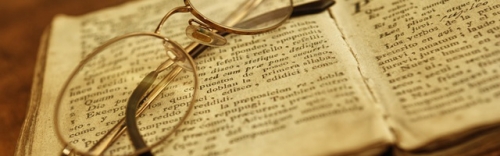





ヒアシンスは16世紀前半にヨーロッパにもたされ、イタリアで栽培されていた歴史がありますが、ヨーロッパにも伝わった16世紀前半よりも前に生息地であるオスマン帝国のスルタンムラト3世が非常に好んでおり、1583年に山地からたくさんのヒアシンスをイスタンブールへ集めたという歴史があります。