ヤブジラミの育て方

育てる環境について
またこの植物の実は、漢方薬の蛇床子という薬になり、食べるのではなく塗り薬として皮膚の痒み止めに効果があるということだそうです。精油、クマリン誘導体などが含まれているそうで、抗菌、抗ウイルス作用等があるということだそうです。また抗トリコモナス、抗真菌作用、性ホルモン作用などもあるようで、
昔から特に女性用として用いられたということでした。そのように日常生活でも利用できる植物ということで、身近な植物でもあったということになります。今でも漢方薬として通販などでも販売されているので、普通に手に入る漢方薬でもあります。また白い花がレースのカーテンのように見えるのでホワイトレースフラワーの仲間にも入っているということです。
花の花弁は5枚で、枝分かれした先端に小さな白い花がまとまって咲きますので、白いカーテンのように見えるのでしょう。花は大体10個ぐらいまとまって咲いています。実が薬草になるということですが、植物全体でも葉も、そのような漢方薬のような感じのする植物でもあります。一般的な野草という感じの植物です。葉の形も面白くて、
緑の槍のような感じで細く鋭い葉に一枚の大きな葉が分かれているような感じで、大きな緑の葉を切り絵にしたような感じの葉になっています。木の葉だけを見ても面白いですが、観賞用にしてもは面白いのではないかという感じの植物です。そのように全体的にもいろいろな特徴のある植物ということになります。
種付けや水やり、肥料について
しかしやはりヤブジラミという名前は合っていないようにも感じますので、名前に関しては少々残念な感じもする植物です。またこの植物ではオヤブジラミという近縁種がありますが、こちらも花が美しく白いのですが先端が、ほのかにピンクになるそうで、観賞用としてはこちらのほうが美しくなるようにも感じます。
また育て方ということでは野草なので日本の環境では強いということですが、セリ科なのでセリ科の植物で日本で根付いている植物も調べてみると参考になるかもしれません。セリ科では有名なところでは人参やパセリなどがあり、多くのセリ科の植物は、ハーブや野菜、香辛料などにも使われているということです。その仲間ということでもあります。
またセリ科で似ているのがシャクという植物で、葉などは素人には判別できないほど似ていますが花が咲けばすぐに分かります。また育つ環境としては、低地や山地の半日陰のような所や、まばらな光のあるところなどですから、育て方や栽培ということでも参考にできるのではないかということです。また面白いところでは花言葉も変わっていて、
ジキルとハイドというそうで、名前のヤブジラミも含めて、非常に損をしている植物で、その花の美しさからは想像ができない感じですが、これほど名前などや花言葉で損をしている植物も珍しいのではないかという感じもします。気の毒な植物ということですが、そのような花もあるということでは非常に面白い興味深い植物でもあります。
増やし方や害虫について
ガーデニングで育てるということでは、面白いですし、中国などでは有名な漢方薬でもあるということですので、そのような興味からも育ててみるのも面白いかもしれません。またホワイトレースフラワーの仲間ということでも興味を持たれるかもしれませんが、ひっつき虫ということもあるので、その点は減点という感じもします。
また野草ということですので、それらを鉢植えなどで試しに育ててみるのも面白いかもしれません。また漢方薬ということでは、果実を煎じて服用すると陰萎、悪瘡、関節痛に効果があり、強壮、強精になるということもありましたが、痺痛を除き、関節を動きやすくするということの効果もあるということでした。
また長く服用すれば身体を軽くし、顔色を良くするともあり、そのように利用されている地域もあるのでしょう。また若芽や根は食用になるともありますが、その点は定かではありません。漢方薬として使う場合には、専門家に相談をして利用したほうが無難ですが、付け薬や煎じて飲む飲み薬としては利用されてきたということでしょう。
しかし最近では、そのように利用しなくても良い薬はたくさんあるので、やはり観賞用として楽しむということが主な目的になります。そのようにこの植物はいろいろな特徴もあるので非常に面白いのではないかということですが、そのようなことも含めて、興味をそそられる植物ということは間違いないようです。関心を持ってみるのも面白い植物のひとつです。
ヤブジラミの歴史
自然の中では昔から人々に注目されながら、その植物自体は知られていないという植物も多くあります。雑草として扱われているということなので、そのために問題にもされないということなのでしょうが、そのような植物の中に、ヤブジラミという植物があります。これは田舎の方に住んでいた人には経験があるかもしれませんが、
ひっつき虫ということで迷惑がられていた植物で、実などが衣類などにくっついて取るのが大変になる植物群です。その中のひとつがこのヤブジラミですが、動物などの体毛について種が移動することにより繁殖していくという植物としては非常に進化しているような仕組みを持った植物です。実際にはひとつではなく十数種類存在していて、
植物では珍しいというほどでもない仕組みのようです。多分この植物も、種がひっつき虫になるのですが、それがシラミに似ているので、そのような名前がついたのではないかとも考えられますが、単に人間にくっつくのでシラミということで名前がついたのかもしれません。実のまわりに繊毛のようなものがたくさんついていて、
それが衣類などや動物の毛にくっつきやすくなっています。この仲間は2種類あります。また花は小さな白い花で見過ごしてしまいますが、よく見るととても美しい花です。また花言葉も面白くて、逃がさないという言葉だそうですが、植物そのままのイメージで面白いです。また日本では一般的な野草で、平安時代の植物の書物などにも見られるので、古くから知られていた植物ということになります。
ヤブジラミの特徴
分類はセリ科でヤブジラミ属ですが、原産地及び生息地ということでは中国から朝鮮半島、台湾、日本言うことで東アジア一帯に生息している植物ということになります。またこのヤブジラミ属は世界的には、カナリア諸島や地中海から東アジアにかけて約15種が知られているそうで日本では2種が分布し、2種が帰化しているということだそうです。
日本でも自生しているということですので、栽培ということでも育てやすい植物ということになります。日本では全国の道端に生えている植物ということで、名前は知らなくても花は見たことがあるのではないかという植物ですが、このひっつき虫の部分は、花の花序の部分で白いかわいい花が咲いている元の部分が、花が落ちた後ひっつき虫になるようです。
またとてもヤブジラミというイメージとは違う美しい花が咲きますが、名前でだいぶ損をしている花のひとつではないかという感じもする植物でもあります。もう少しロマンチックな名前をつけてあげると良かったという感じもしますが、よほどよくくっつくので、それでイライラしたのではないかということも予想出来て面白い感じもします。
そのようにユーモラスは植物ということでもあります。特徴としては、高さが30センチから70センチぐらいで、夏に花が咲く植物ですが、5月から7月ぐらいが開花期になります。花は3ミリぐらいの小さな白い花ですが、それらがまとまって咲くのでわかりやすい花でもあります。
-

-
イベリス・センパーヴィレンスの育て方
イベリスには2種類があり、1年草と多年草になります。イベリス・センパーヴィレンスは多年草にあたります。アブラナ科で別名は...
-

-
ピラカンサの育て方
ピラカンサは英名でファイアーソーンといいます。バラ科トキワサンザシ科です。ラテン語のままでピラカンサとされている場合もあ...
-

-
セッコクの育て方
セッコクは単子葉植物ラン科の植物で日本の中部以南に分布しています。主な生息地は岩の上や大木で、土壌に根を下ろさず、他の木...
-

-
家庭菜園の栽培、野菜の育て方、野菜の種まき
家庭菜園ではプチトマトやゴーヤなど育てやすい野菜を育てるのが人気です。ですが、冬野菜でもある大根の栽培でも、手軽にするこ...
-

-
クンシランの育て方
クンシランはヒガンバナ科クンシラン属で、属名はAmaryllidaceae Clivia miniata Regelとい...
-

-
ホトケノザの育て方
一概にホトケノザと言っても、キク科とシソ科のものがあります。春の七草で良く知られている雑草は、キク科であり、シソ科のもの...
-

-
ガーベラの育て方について
ガーベラは、キク科の花であり、毎年花を咲かせる多年草です。園芸では、鉢花や切り花などに広く利用され、多数の園芸品種が存在...
-

-
ツルハナナスの育て方
ツルハナナスの名前の由来は、つる性の植物であるために「ツル」と、またナス科の仲間であるためその花は紫の綺麗な色をしている...
-

-
ナスタチウム(キンレンカ、金蓮花)の栽培
ナスタチウム(キンレンカ、金蓮花)は、南米原産のノウゼンハレン科のつる性の一年生です。開花時期は5月から10月過ぎる頃ま...
-

-
ナンブイヌナズナの育て方
ナンブイヌナズナは日本の固有種です。つまり、日本にしか自生していない植物です。古くは大陸から入ってきたと考えられますが、...




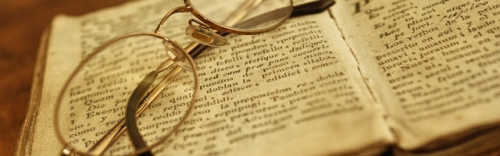





分類はセリ科でヤブジラミ属ですが、原産地及び生息地ということでは中国から朝鮮半島、台湾、日本言うことで東アジア一帯に生息している植物ということになります。またこのヤブジラミ属は世界的には、カナリア諸島や地中海から東アジアにかけて約15種が知られているそうで日本では2種が分布し、2種が帰化しているということだそうです。