アルストロメリアの育て方

アルストロメリアの育てる環境について
品種によって異なることがありますが、一般的には日当りがよく、温暖な気候を好みます。日当りがよいところ以外にもやや日陰といった場所でもよく育ち、どちらも水はけの良い土壌であることが条件となります。水はけをよくするために、腐葉土や赤玉土、川砂などを入れて適した土壌にしてください。
というのも暑さと多湿に弱いことがあり、高温多湿の環境下では根腐れしやすく、また株が凍結すると枯れる特性を持っています。地中深いところに根茎があり、生育に適さない時期は、地上部が枯れて休眠するので水はけをよくすることで深く根を張れるようにしてあげるのがよいです。
アルストロメリアのもともとの品種は、暑さに弱い特性を持っています。鉢であれば、春と秋の成長期は日なたで管理し、夏は日陰、冬は凍らない場所に置くというのが基本です。夏の高温といったものには弱いので、鉢であれば夏場は風通しのよい日陰に移動するようにしてあげてください。
また夏の時期には梅雨が来るので、土の水分多くなり多湿気味になります。梅雨期は軒下などの雨の当たらないところで乾燥気味にしておくのが安全対策といえます。鉢植えでは移動が可能なので、こういった管理がしやすいですが、地植えといった場合は困難なこともあります。
たとえ、夏場の高温や冬の寒さで葉が枯れてしまっても地中部にある球根は生きています。地植えなどでは、日当りと風通しがよい場所をポイントに置いて植えつけるようにします。冬には腐葉土などを敷いて凍結しないように防寒するなどの工夫をしてみてください。
種付けや水やり、肥料について
アルストロメリアは水はけの良い土壌に植え付けるのがよく、多湿にしないように育てるのがポイントです。多湿が苦手なのもあり、地植えの場合は、降ってくる雨の水だけで十分といえ、基本的には入りません。ただ鉢植えは、生育期といった時期にはとくに乾きやすいので注意します。
春の伸長や開花期には、茎葉が元気に伸びてくるので土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。鉢が水切れしないように、土の表面が乾いたらあげるようにしてください。地植えも開花期になるまでは土が乾くようでしたら、たっぷりと水を与えるようにし、花が咲いたら乾かし気味に育てます。
葉などの様子をみながら水を加減して与えます。真夏に葉が枯れてしまうことがあった場合は、休眠に入ることから水やりはストップし、与えないようにします。休眠時期に水をやり続ければ根が腐ってしまうことがあるからです。茎葉の様子を見るというのがアルストロメリアの栽培には重要になってくる点とし、
夏場や冬場には葉が枯れてしまうこともあります。そういった場合は休眠したと考え、水やりや肥料などは与えません。葉が枯れてないときの育成法としては、基本的に土は乾燥気味にし、枯れない程度に水をあげるというのがよいです。成長が鈍いと感じた場合にも水やりは控え様子をみるようにしてください。
肥料は庭植えではほとんど不要ですが、生育期にときどき薄めの液体肥料を与えてもよいです。鉢植えでは、春の芽だしから開花時期まで月に1回の置き肥か、月に3回から4回の液体肥料を与えてください。どちらも休眠期や生育が鈍い時期は与えないようにしてください。
増やし方や害虫について
アルストロメリアは、株分けや種まきで増やすことができます。株分けは植え替え時に同時に行うのが基本とされ、9月または3月ごろに芽をよくみながら株分けします。3年から4年目になるとアルストロメリアは花数が少なくなるので、花壇では3年に1度ぐらいを目安に株分けをしてあげるのがおすすめです。
小さな鉢植えなら1年から2年に1回、大きめの鉢なら2年から3年に1回、一回り大きな鉢に植え替えてあげるのがよく、そのときに株分けしてあげてください。どちらも根を傷つけないように堀上げ、掘り上げた球根は2芽から3芽が1株になるようにして、球根が乾かないうちに手早く土に植えます。
球根は折れやすいので注意して扱うようにしてください。春までにやると多くの花を見ることができます。種での栽培は自家採取といった方法が多く、種は市場ではあまり出回っていません。原種やリグツ・ハイブリッドなどはタネで増やすことができ、種が熟して2か月ぐらいのときにまくと一番よく発芽します。
種まきは重ならないように土に蒔き、6mmから7mmくらい土をかぶせます。湿度の低い場所で水きれしないように管理します。病害虫については、湿度が高くて気温が低い時期に灰色カビ病が発生することがあります。花びらや葉に斑点が現れひどくなると株が腐ってしまうことがあり、
風通しを良くして湿気を溜めないような環境を作って予防してください。害虫では、アブラムシやオンシツコナジラミ、ハダニ類が付きます。被害がひどいようでしたら薬剤散布などの対策をとるようにしてください。
アルストロメリアの歴史
アルストロメリアは、南米原産の単子葉植物の属の一つで、アルストロメリア属、または別名をユリズイセン属とします。チリを中心にブラジル、ペルー、アルゼンチンなどの南米に60種から100種の野生種が分布するとされ、生息地によって特性なども違い様々なものがあります。
たとえば、砂漠や砂丘に自生するものもあれば、森林に育つものもあります。多くのものはチリタイプとブラジルタイプに大別され、種によって高地から低地、乾燥地から湿地と、生育環境はいろいろです。原産地とその花姿から「ペールのユリ」「インカ帝国のユリ」などの異名があり、
世界でも花束やフラワーアレンジに使われるなど人気です。アルストロメリアの名前の由来ですが、スウェーデンの植物学者リンネの友人の「アルストロメール男爵」にちなんで付けられたそうです。日本へは1926年(大正15年)に渡来し、和名は「百合水仙(ユリズイセン)」などと呼ばれていました。
1926年頃の当時は親しまれなかったのか、なぜかあまり普及することがありませんでした。本格的に栽培されはじめたのは1980年代以降です。アルストロメリアはオランダで品種改良が盛んに行われ、そういったものが日本にも多く入って来ました。
また、オランダやイギリスを中心に交配選抜が進められ、カラフルでしかも四季咲き性がある作りやすい品種などがたくさん育成されています。近年では日本でも改良が行われ、暑さに強いなどの特性を持った品種も生まれているようです。
アルストロメリアの特徴
アルストロメリアは、花色が豊富で、色鮮やかなものからパステル調やシックな感じのものまで多数あります。多彩でエキゾチックな姿は世界中で愛され、花持ちの良さから切り花などによく利用されています。地下茎を伸ばして地中に白くてやや細長い球根を作り、高さは30cmから100cmくらいに成長します。
一般的な花の最盛期は5月から6月とされ、長くて7月頃まで咲いていますが、四季咲き性の品種は春から晩秋まで花を咲かせるなどより長く花期を楽しめます。花色は白、オレンジ、ピンク、赤などカラフルなものが多くあり、アルストロメリアの花の特徴というと花びらには条斑(じょうはん)というすじ状の模様が入ることです。
ほとんどのものにこの条斑が入るのですが、ないものもあり、これを「スポットレス」といい条斑が入っていない品種もあります。こういった品種は改良タイプが多く、たくさんの品種が存在します。バラエティーに富んでいるので、選ぶ楽しみがあるというのもアルストロメリアの魅力の一つだといえます。
品種や系統が多い花とされ、暑さに強いものとしては、「カリオフィレア・ハイブリッド系」があります。また、逆にバタフライ系は四季咲き性で草丈が低いですが、耐寒性が強く凍らせなければ耐えるといった特性を持っているなど、こういったものを選べばいろんな地域での栽培が可能です。
花以外の特徴としては、茎はやや太めでまっすぐ立ち上がり、葉といえば180度くるりとねじれて裏側が上を向いてしまうといったことがあります。多年草で植えておけば毎年花を咲かせるものなので、環境さえ合えば育て方は簡単です。いろいろな色のアルストロメリアを花壇や鉢などに植えてみてください。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:エキザカムの育て方
-

-
ハナニラの育て方
ハナニラは別名セイヨウアマナやアイフェイオンといいます。原産地はアルゼンチンで、生息地は南米メキシコからアルゼンチンの辺...
-

-
ディフェンバキアの育て方
ディフェンバキアはサトイモ科ディフェンバキア属で原産地や生息地は熱帯アメリカです。和名にはハブタエソウやシロガスリソウと...
-

-
トリカブトの仲間の育て方
トリカブトとはキンポウゲ科トリカブト属の植物の総称で、その多くは多年草の植物です。強い毒性があることで知られており、危険...
-

-
ハギの育て方
ハギの花は、日本人には古くから愛されており、万葉集に最もたくさん読まれている落葉性の低木です。生息地は、温帯、亜熱帯など...
-

-
クレマチス(四季咲き)の育て方
クレマチスは、キンポウゲ科センニンソウ属(クレマチス属)のこといい、このセンニンソウ属というのは野生種である原種が約30...
-

-
タイサンボクの育て方
タイサンボクはモクレン科モクレン属の常緑高木で、北米中南部が原産です。タイサンボクの木は大山木や泰山木という字も使用され...
-

-
グロッバの育て方
グロッバ/学名・Globba/ショウガ科・グロッバ属です。グロッパは、東南アジアやインドが原産地・生息地とされ、70種ほ...
-

-
モモ(桃)の育て方
桃はよく庭などに園芸用やガーデニングとして植えられていたりしますし、商業用としても栽培されている植物ですので、とても馴染...
-

-
リクニス・コロナリアの育て方
花の特徴として葉、ナデシコ科、センノウ属となっています。いくつかの花の名前が知られていて、スイセンノウの他にはフランネル...
-

-
小かぶの育て方
原産地を示す説はアジア系とヨーロッパ系に分かれており定かにはなっておりません。諸説ある中でも地中海沿岸と西アジアのアフガ...




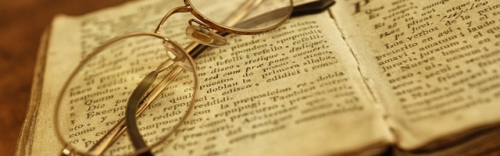





アルストロメリアは、南米原産の単子葉植物の属の一つで、アルストロメリア属、または別名をユリズイセン属とします。