プルモナリアの育て方

プルモナリアの育て方
プルモナリアは高温と乾燥には弱いですから開花するまでは日当たりが良く、その後は日陰になるような場所が向いています。ただし日陰になるとはいっても水はけは良くないと根腐れを起こしやすくなってしまいます。土は山野草用の用土が使いやすいですから腐葉土と混ぜて使うといいでしょう。
小粒の赤玉土を2、鹿沼土を3、軽石を2、腐葉土を3の割合で混ぜ合わせた土を使うのも良いです。この配合の土はよくクリスマスローズの育て方の時にも使われるものです。水はけをよくしておく必要はありますが、プルモナリアの苗や株を乾燥させないように土の表面が乾いてきているようであれば水をたっぷりと与えます。
肥料は秋に気温が下がってから施すのが栽培する上でのポイントです。3月から4月の成長期は特に肥料を必要とするので、育て方のポイントは10日置きくらいに液体肥料をプルモナリアに与えるか2回から3回置き肥料をしておくのがベストです。ただ6月以降であれば土の中に肥料が残ってしまわないように気をつけます。
マルチングの補充をしておくことは大切なので、忘れないようにしましょう。マルチングは土の表面にプラスチックフィルムやバークチップなどで覆っておくことです。こうすることでプルモナリアの栽培している土の温度が上昇し過ぎないようにすることができます。
プルモナリアを栽培する上での注意
栽培している時に特に注意したほうがいいのは病気ですとうどんこ病です。うどんこ病は梅雨から夏にかけて葉に白い小麦粉がかかったようなカビがついてしまう病気です。予防するには育て方のコツでもありますが、風通しをよくしておくことが大切です。そして花がらや枯れ葉などは見つけたらすぐに取り除くようにしておきましょう。
害虫ではネコブセンチュウが発生する恐れがあるので気をつけます。発生しやすいのは水はけが悪い時です。ネコブセンチュウは寄生されてしまうと根の細胞組織がコブ状になってしまいます。寄生しているネコブセンチュウが多いと根がコブだらけになってしまい、植物の生育が妨げられてしまいます。
またナメクジの発生にも気をつけるほうがいいです。ビールトラップを仕掛けるか薬剤の散布で退治してしまいます。ビールトラップといっても難しいものではありません。ナメクジの大好物であるビールを牛乳パックなどを使って仕掛けておくだけです。
数日放置しておけば、匂いにつられたナメクジがひっかかっています。ひっかかったナメクジを捨てる時は中に入っているナメクジを触らないように気をつけます。ナメクジは人間の体内に入って悪さをする線虫を媒介するといわれていますからすぐに袋に入れるなどして廃棄し、こぼしたりしないようにするのが良いです。
種付けをして育てることはできる?
プルモナリアは基本的には株分けをして増やしていきます。種付けをすることはもちろんできますが、種から育てることが少し難しいといわれています。種付け自体は花が咲き終わった後にそのまま花茎をカットしないで置いておくと自然と種付けされます。
熟したら種を採取しますが、種を地面に落としてしまわないように慎重に採取します。苗になるまでは新しい清潔な土を使って育てるようにします。苗になってしっかりしてきたら鉢植えや庭などに植え替えするといいです。一度植えつけてしまえばほとんど手はかかりませんし、いくつかの株を植えることで群生して美しい姿を見せてくれます。
プルモナリアには園芸品種を含めるといくつかの品種があります。例えばプルモナリアといえばこの品種といわれるほど人気が高いのがルイス・パルマーです。花は青紫色をしていて葉は白い斑点が入っています。薄い桃色の花が徐々に明るい青紫色に変化していくのを楽しめるのがダイアナ・クレア、淡いサンゴ色の花が咲き、白覆輪の葉が特徴的なデイビッド・ワードです。
同じようにピンク色の花が明るい青紫色の花に変化しているものにはコットンクールという品種があります。コットンクールはシルバー模様の美しい葉を持っているのが特徴です。葉のほとんどの部分が白い斑入りになっていて緑色が少しだけ残っているもので、花はピンク色から青紫色に変化していくのがシルベラード、やや小さい青い花が咲き、銀白色の美しい葉をつけるのはマジェステです。
また斑のない葉を持ち、濃くて青い大輪の花を咲かせるのがブルーエンサインという品種です。シェードガーデンにオススメされるのがサムライです。葉の全面に銀白色のオーバーレイがのっており、ほとんど銀色の葉に見えます。青紫色の花は葉の色と非常にマッチしています。
プルモナリアの中でもとても丈夫な性質をしており、花が咲き終わったとしても葉の状態だけでその美しさを楽しむことができるのがメリットです。いくつかの日陰でも育つような植物と組み合わせてガーデンを盛り上げてくれます。
プルモナリアの歴史
プルモナリアはムラサキ科プルモナリア属に属し、多年草です。園芸ではプルモナリアと呼ばれていますが、ハーブティーなどにも使われていて、ハーブの世界ではラングワートという名前で知られています。原産はヨーロッパから西アジアまでで、薬用ヒメムラサキやエルサレムカウスリップなどという別名もあります。
プルモナリアという言葉は肺の草という意味があります。ラテン語の肺という意味があるpulmonarisからきていて、白い斑点が入っている葉が肺を想像させることからこういう名がつけられたといいます。昔からプルモナリアが肺病の治療に使われてきたことが由来となっています。
薬用効果としては収れんや利尿、皮膚軟化薬、去痰薬、気管支炎、胃腸障害などがあるといわれています。原種が14種類ほどあります。日本へ渡来した時期については詳しくわかっていません。しかし日本へ入ってきてからも品種改良が行なわれており、たくさんの園芸品種ができてきています。
花だけではなく、日陰などのたいていの植物が育ちにくい場所を彩る葉ものとしても人気が高いのがプルモナリアの良いところだといえます。また薬用としてもよく利用されるようになっています。
プルモナリアの特徴
生息地は原産地と同じくヨーロッパから西アジアにかけての地域です。霜や凍結にも強く、ほとんど傷んでしまうことがありません。花が咲いていても成長して葉も大きくひろがっていきます。
鮮やかな青色の花がよく知られていますが、他にもピンク、白、咲き始めがピンク色だけど徐々に青色に変化していくという品種もあって花色の変化を楽しむことができます。開花は2月中旬から5月中旬あたりまでです。草丈は10cmから40cmほどあります。
寒さには非常に強いですが、暑さには少し弱いです。カラーリーフとして利用できるだけではなく、グランドカバーとしてもよく利用されています。クリスマスローズや球根系の花などと一緒に植えておくことも良いです。草丈の低さを利用して素敵なガーデン作りに大いに役立ってくれるのがメリットです。
植える時は落葉樹の陰などもオススメです。早春に花が咲くような山野草類がよく育つ場所を選ぶのがラングワートを植える場所を見つけるポイントになります。もちろん庭だけではなく、鉢植えにして栽培することもできますので育てておいしいハーブティーの材料として使われることもよくあります。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:セリンセ・マヨールの育て方
タイトル:ティアレアの育て方
-

-
オジギソウの育て方
オジギソウは非常に昔から日本人に好かれてきた植物です。そもそものオジギソウの名前の由来を見ると、触ると葉を閉じてしまって...
-

-
カラミンサの育て方
カラミンサはシソ科のハーブで白やピンク、淡い紫色の小さな花をたくさんつけることで人気となっている宿根植物で葉の部分はハー...
-

-
マスタード(カラシナ)の育て方
特徴として、フウチョウソウ目、アブラナ科、アブラナ属となっています。確かに葉っぱを見るとアブラナ、菜の花と同じような形を...
-

-
ファイウスの育て方
花においては、ラン目、ラン科、カンゼキラン属とされています。園芸上はランになり、多年草として育てることができます。花の高...
-

-
キュウリを種から育てる方法
花と野菜の土をポットに準備します。ポットにキュウリの種まきをします。キュウリの種は扁平な中央部がやや膨らんだ長円形です。...
-

-
ゴールデンクラッカーの育て方
この花についての特徴としてはキク科、ユリオプス属になります。花が咲いている状態を見るとキクのようには見えませんが、黄色い...
-

-
エゾギク(アスター)の育て方
中国や朝鮮が原産の”アスター”。和名で「エゾギク(蝦夷菊)」と呼ばれている花になります。半耐寒性一年草で、草の高さは3c...
-

-
マツムシソウの育て方
マツムシソウは科名をマツムシソウ科と呼ばれており、原産地はヨーロッパを中心にアジア、アフリカもカバーしています。草丈は幅...
-

-
サクラの育て方
原産地はヒマラヤの近郊ではないかといわれています。現在サクラの生息地はヨーロッパや西シベリア、日本、中国、米国、カナダな...
-

-
ラズベリーの育て方
ラズベリーとは、バラ科キイチゴ属に属する果樹のことです。分類上は亜属に属する種類で、フランス語読みでフランボワーズとも呼...




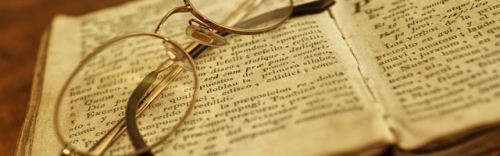





プルモナリアはムラサキ科プルモナリア属に属し、多年草です。園芸ではプルモナリアと呼ばれていますが、ハーブティーなどにも使われていて、ハーブの世界ではラングワートという名前で知られています。原産はヨーロッパから西アジアまでで、薬用ヒメムラサキやエルサレムカウスリップなどという別名もあります。