ミヤマキンポウゲの育て方

育てる環境について
栽培をするにあたってはどのような環境を用意するのが良いかですが、生息地は日当たりのよい草原です。それを考えると日当たりの良い所が咲くところとしては好まれるようです。1年中日当たりがよく、風通しも良い所が良さそうです。この花においては耐暑性がやや劣るとされています。そのことから日本でも南部ではあまり育てられないことがあります。
高温多湿になる場合には気をつけないといけない場合があります。北海道には梅雨がないとされますが、その他の地域においては当然ながら梅雨があります。空梅雨と言われることもありますが、一般的にはジメジメとした日が続き常に雨の対応をしないといけなくなります。この花にとっては過湿状態になるので良くなくなります。
梅雨の時期から夏の間に関しては、雨が当たらないようにするなどの管理ができるところになります。あまり庭などに直接植えられないかもしれません。日差しが強いと起こるのが葉焼けです。ある程度の日光においては対応できますが、葉が傷んであまり見た目が良くなくない状態になるなら寒冷紗を用いて遮光します。
30パーセントから50パーセントほどしておくようにします。冬の管理はそれほど難しくありません。この時期は落葉して休眠状態に入ります。寒くても特に問題はありません。庭植えをするときにおいてはロックガーデンタイプにします。夏には少し心配になることがありますが、どんどん増やしていける環境になります。
種付けや水やり、肥料について
育て方としては鉢植えを考慮した用土の配合を決めます。水はけと水持ちの良い土を使うようにします。まず5割に鹿沼土を利用します。日光砂を4割加え、後の1割は軽石の砂タイプのものを使います。砂タイプは2ミリから5ミリぐらいの大きさの軽石になります。水はけも水持ちも両方兼ね備えるためには少し難しさもありますが、
植木鉢においてはどうしても庭土よりも水はけが良くなりすぎることがあります。乾きやすくないことも必要になります。水やりをする場合においては、毎日1回の水やりを習慣づけて行います。時期によって水やりのタイミングを変えたほうがいいとされています。よく言われているのは春と秋冬については朝方が良く、夏には夕方以降が良いとされます。
夏に朝方にまいてしまうと、水が下の方に行く前に蒸発してしまうことがります。夜であれば、気温が暑くても日差しがない分蒸発も抑えられます。しっかり染み込んだ状態で朝を迎えることができるので、水も十分ある状態になります。土の下の方まで日差しで蒸発する事は少なくなります。夏眠性の根の太いタイプがあります。
こちらについては成長期に水を与える必要があります。休眠後においては、用土に少し水を与える程度で十分です。水のやり方を変えていきます。肥料はできれば与えるようにします。与えすぎると姿がおかしくなることがあるので注意しないといけません。生育が旺盛になる4月から6月、秋に液体を与えます。
増やし方や害虫について
増やし方であるのは種まきです。花の後に金平糖のような実がなるようになりますから、ここから種を取るようにします。この種においては、培養土にまくようにします。発芽自体は翌年になります。花が咲くのは発芽から1年から2年ぐらいかかることがあります。多年草ですから植え替えをすることがあります。
その時において株分けをすることが出来るチャンスがあり、それによって増やすことが可能になります。根茎が絡まっているので解くようにして分ける必要があります。この時にはいくつかの芽をつけた状態でわけるようにします。そうすることで成長を早めることができます。植え替えは増やさない場合でも必要な作業になります。
この植物は根が旺盛で絡みやすくなっています。あまり絡みすぎるとよくありません。植え替えの時に絡み具合を見て対応するようにします。根をほぐすと脱水しやすくなりますから、それまでと同じ水やりではいけません。少し多めの水やりを心がけるようにしておきます。植え替えの頻度は2年に1回程度で問題ありません。
古い土については全て落として、新しい土に変えるようにしたほうがよいでしょう。病気としては、芽出しの時期においては炭疽病になることがあります。葉に色ムラが出てくるウイルス病にかかることもあります。用土がベタベタしてきた時は多湿による軟腐病のことがあります。害虫はアブラムシなどが多いです。用土が傷むことによって出てくる虫の対応をしましょう。
ミヤマキンポウゲの歴史
大きい花と小さい花のどちらが好きかがあるでしょう。花束などであれば大きな花のほうがいいことがあります。花瓶などに生けるのであれば大きい花の方が豪華になるかもしれません。そもそも花瓶は深いタイプもありますから、それだけの茎などがないと生けることができない場合もあります。
花においてはそれだけでなく非常に小さい花がこじんまりと咲いていることもあります。道端などでひっそりと咲いているために気づかないようなこともあります。でもそういったところにも特徴的な花が咲くこともあります。ミヤマキンポウゲに関しては、小さい花の部類になるでしょう。道端にひっそりと生えている花と言えます。
原産地に関しては細かいことはわかっていません。世界的に見られるかもしれませんが、今のところは日本における情報がメインになっています。本州の中部地方から北海道にかけて咲くとされています。ですからあまり西日本など暖かい地域では見ることができない花になるかもしれません。
日本固有種とされているので海外では見つかっていないようですが、よく似ている種類などはありますからもしかするとそれらの花が影響していることもあるでしょう。この花についてはある本において高山に咲く花として掲載されたようです。秋田県といいますと日本の北部ですから佐久地域となりますが、今はレッドリストに指定して絶滅危惧二類に指定しています。その他の山などでも減少しているとされています。
ミヤマキンポウゲの特徴
この花の種類はキンポウゲ目、キンポウゲ科、キンポウゲ属です。漢字で記載すると深山金鳳花となります。高山に主に生えることが多い山野草になります。多年草で、環境が良ければ枯れずにそのまま咲き続ける事ができます。草丈としては低いものがほとんどで、10センチぐらいです。でも成長を進ませるようにすると40センチぐらいになることもあるようです。
花の色は黄色がメインになるでしょう。金色に輝くように咲く花が印象的です。開花期間としては4月下旬から7月上旬です。自生している花に関しては7月くらいから8月くらいとされます。耐寒性があるので寒いところでも冬を越せます。しかし耐暑性が少ないです。生息地は日本でも中部より北なので涼しいところ、寒いところになります。
湿り気のあるゆるやかな斜面などで大群落を作ることがあります。芽出しとしては雪解け頃に始まります。そして葉が展開していきます。葉はどんどん分裂して、もみじの葉っぱのような形になります。夏になってようやく花が咲く準備に入ります。花芽が伸ばされるようになり、黄色い5枚の花びらを開くようにして咲き始めます。
花びらは扇状のもので、特に柄などが入っているわけではありません。中心部分も黄色で花びらも黄色ですから、まさに黄色一色の花になります。花の大きさとしては2センチほどです。丸みを帯びた花びらが5つ付きます。花の後には実ができます。これはそう果のタイプで、中に種子が入っています。
-

-
ペピーノの育て方
日本的な野菜の一つとしてナスがあります。他の野菜に比べると決して美味しそうな色ではありません。紫色をしています。でも中は...
-

-
ハゴロモジャスミンの育て方
ハゴロモジャスミンの原産地は中国雲南省ですが、現在では外来種としてニュージーランドやアーストラリアなども生息地となってい...
-

-
イキシアの育て方
イキシアはアヤメ科の植物で、原産地は南アフリカになります。また、別名として「ヤリズイセン(槍水仙)」、「コーン・リリー」...
-

-
コデマリの育て方
コデマリは中国中部原産の落葉低木で、「コデマリ(小手毬)」の名はその漢字が示す通り、小さな手毬のように見える花の姿に由来...
-

-
アサリナの育て方
アサリナは、つる性植物です。小さな花を付け、その色も白、ピンク色、黄、紫、青といった複数の色があります。また、つる性植物...
-

-
ケールの育て方
ケールはベータカロテンやルテイン、ビタミンCやカルシウム、食物繊維と言った非常に多種多様な栄養素を含むことから緑黄色野菜...
-

-
バイカカラマツの育て方
バイカカラマツとはキンポウゲ科の植物で、和風な見た目やその名前から、日本の植物のように考えている人も少なくありませんが、...
-

-
ニシキウツギの育て方
ここでは、「ニシギウツギ」の特徴について、いくつかピックアップして書いていきます。ご参考程度にご覧いただけますと幸いでご...
-

-
セイヨウイワナンテンの育て方
セイヨウイワナンテンはツツジ科の常緑低木で北アメリカが主な原産地です。バーニジア州、ジョージア州、テネシー州などに分布し...
-

-
シキミの育て方
シキミはシキビ、ハナノキ、コウノキなどとも呼ばれる常緑の小喬木です。以前はモクレン科でしたが、現在ではシキミ科という独立...




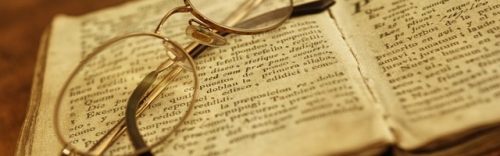





この花の種類はキンポウゲ目、キンポウゲ科、キンポウゲ属です。漢字で記載すると深山金鳳花となります。高山に主に生えることが多い山野草になります。多年草で、環境が良ければ枯れずにそのまま咲き続ける事ができます。