ヒメノカリスの育て方

育てる環境について
元々の生息地が中国であることを考えると育て方は一年中ある程度の湿気を含んだ土地であることが推測されていて、日本で自生しているヒガンバナ科の植物に関しては直射日光が殆ど当たらない墓場や田畑の周辺などに多く自生しています。
ヒメノカリスを育てるために必要なことは美しい花を毎年咲かせるために枯れてきた花を摘み取るという作業で、それによって栄養が球根などに適切に配分されるので、状態が良い球根を作ることができます。真夏の太陽の日差しが苦手な植物なので、
夏の暑い時期にはあまり日の当たらない場所で栽培する必要があるのですが、地面に直接植えている場合は日除けネットを設置したりするなどの工夫が必要になります。強い日差しが当たると葉の部分が傷んでしまうので、球根が十分に育たないまま寒い時期を向かえることになって、
翌年の生育に影響を及ぼす可能性があります。球根に関しては寒さに弱いので暖かい地方でない場合には土から出して貯蔵する方法が取られています。しかし霜が降りるなどの心配のない地域の場合にはそのままの状態で保存することも可能となっています。
球根を植え付ける時期は3月の半ばから5月の半ばまでで、開花期は初夏の時期となっています。基本的には寒さに弱い性質を持っているので、日当たりの良い環境で育てることが重要なのですが、あまりに暑いと葉の部分が茶色く変色してしまうので、それを防ぐために強い日差しが当たらないようにしておくことが重要です。
種付けや水やり、肥料について
過剰な湿気を嫌う性質を持っている植物なのでヒメノカリスに関しては必要以上に水分を与える必要はありませんが、土の表面が完全に乾いてしまっている場合にはたっぷりと水分を土に吸い込ませる必要があります。とくに開花している期間には水を多く必要としているので、
水分をこまめに与えて水分不足になることを防ぐことが必要です。水分が不足してしまうと花がしおれてしまうので、注意が必要で、その場合には水を与える回数を増やすなどして対処をしていきます。肥料に関してはゆっくりと吸収されるものが適しているとされていて、
即効性の有る液体肥料を月に1回の割合で与えると球根が大きく生育するので翌年も美しい花を咲かせるようになるとされています。肥料に関してはあまり与えすぎると球根が腐ってしまうことがあるので、適度に与えることが重要です。
土に関しては水はけの良い物を好んでいるので粘土質のものよりも赤土や腐葉土を含んでいる土で栽培することで生育環境を良くすることができます。球根を掘り上げないで栽培している場合は5年に1度を目安にして植え替えを行うようにする必要があるとされていて、
球根を植え付ける場合には気温が比較的高い時期の4月の下旬などに行うのが良いとされています。球根に枯れている根の部分や干からびた皮などが付着している場合にはそれらを取り除いて、植え付けの深さは球根の頭の部分が地面に少し出ているくらいが丁度良いとされています。
増やし方や害虫について
増やし方に関しては球根の周りに小さな球根が自然発生するのでそれを大きく育つまで待ってから収穫するとヒメノカリスの球根を増やすことができます。親球から取り外した小さな球根は翌年に植え付けを行うとヒメノカリスとして美しい花をつけることができます。
害虫に関してはダニなどが心配されているのですが、猫などに掘り返されることなどもあります。しかしヒメノカリスをはじめとするヒガンバナの仲間の球根には猫などが嫌がるニオイ成分や毒が含まれているので、犬や猫などに掘り返される心配はほとんどありません。
しかしダニに関しては根の部分の細胞を破壊してしまうので栄養分や水分の吸収の妨げになることがあるので、対処する必要があります。ネダニは乳白色で体長が1ミリにも満たない小さな害虫なので、根が食べられてなくなるまえに取り除いてしまう必要があります。
またネダニに対する薬剤は現在使用が認められていないので、球根を植え付ける場合には肉眼でしっかりと確認をしてネダニがいる場合には植える前に除去することが重要です。ネダニがいる場合には生育が遅くなるだけではなく茶色く変色することがあるので、
その場合には除去する以外の方法はありません。また茎の部分にまでネダニが付いてしまうと葉が茶色く変色をしてしまうので、ひどい場合には枯れてしまうことがあります。対策としてはネダニが発生した土地には植え付けを行わないことや、事前に清潔な環境で球根を貯蔵しておく方法などがあります。
ヒメノカリスの歴史
ヒメノカリスはヒガンバナ科の植物で原産地は北アメリカ南部や南アメリカで、日本では一般的には球根を春に植えると夏には白く美しい花が見られるので人気となっています。この種類の植物の歴史は非常に長く、元々は西インド諸島が原産であると考えられています。
それが植民地時代を経てアメリカ全土でも栽培されるようになり、現在では約30種類のヒメノカリスが栽培されています。ヒガンバナ科の植物は日本産のものも多いのですが、中には日本に渡来してきた年代が古すぎるので現在でも帰化種として扱われているものも数多くあります。
大半の種類がネギ属に属しているのですが、硫化アリルなどを多く含んでいるので独特の臭気が漂っていることがあります。しかし花の部分が美しいことから世界中で栽培がされていて、たくさんの観賞価値の高い種類が作られています。
また南極大陸となどを除いた地域に広く分布しているヒガンバナ亜科の場合にはリコリンという有毒な物質を含んでいるのですが、花が美しいことから世界中で園芸品種として改良が重ねられていて、園芸の歴史を知る上で非常に重要な植物となっています。
日本においてもヒガンバナは球根部分に有毒な物質を含んでいることが知られているので、咲いていても栽培することがあまりありませんが、世界的にはアマリリスのように園芸品種として大切に扱われているものも多いので、世界的な園芸品種として考えた場合には毒性よりもむしろ美しさが優先されています。
ヒメノカリスの特徴
ヒメノカリスの特徴は球根植物であることで、もともと熱帯で自生している植物なので寒さに弱いので冬の時期にはほとんど休眠しています。花は白や淡い黄色のものが多く、品種によっては良い香りがするものもあるので、観賞用の植物として世界的に人気があります。
種類としては西インド諸島原産のスペキオサが一番ポピュラーとされていて、花びらが細長く伸びることからスパイダー・リリーとも呼ばれています。この花には独特のつよい臭気があり、これがとてもよい香りであることから人気となっています。
花の色は薄い白色で球根部分が他の品種と比べると大きく出来ていて、葉の部分は長さが60センチ以上にもなります。この他にも様々な品種が作られていてラッパ水仙のような形状の花をつけるものもあります。ヒメノカリスのようなヒガンバナ科の植物は人気が高いことから様々な品種ができているのですが、
日本で一般的に見られているものはリコリスや曼珠沙華などとも呼ばれていて、赤い美しい花が放射状に咲くことが特徴となっています。球根には有毒な成分を含んでいるので日本ではヒメノカリスなどのヒガンバナ科の植物は敬遠されることが多いのですが、
欧米などでは園芸品種として多くの種類が開発されていて、赤い花をつけるものだけではなく白いヒガンバナなどもあります。日本国内では北海道から琉球列島まで見られているヒガンバナ科の植物ですが基本的にはヒメノカリスを含めて中国から帰化した品種であると考えられています。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:キルタンサスの育て方
タイトル:プルメリアの育て方
-

-
ゴーヤーともよばれている健康野菜ニガウリの育て方
ゴーヤーは東南アジア原産の、特有の苦味があるつる性の野菜です。沖縄では古くから利用されており郷土料理”ゴーヤーチャンプル...
-

-
キュウリの育て方について
キュウリは、夏を代表する野菜であり、カリウム・ビタミンC・カロチンなどの栄養素が豊富に含まれた野菜です。浅漬けにしたり、...
-

-
ウメ(花ウメ)の育て方
ウメの系統をたどっていくと、サクラやモモと同じように、もともとトルコやイランなど、中東の地域を原産とする植物だと考えられ...
-

-
トウワタの育て方
トウワタ(唐綿)とは海外から来た開花後にタンポポのような綿を作るため、この名前が付けられました。ただし、唐といっても中国...
-

-
シスタスの育て方
シスタスは、ロックローズとも呼ばれる花になります。大変小さくて可愛らしい事から、ガーデニングをする人に大変人気があります...
-

-
リパリスの育て方
特徴としては、被子植物になります。ラン目、ラン科、クモキリソウ属に該当します。ランの種類の一つとされ、多年草としても人気...
-

-
プランターで栽培できるほうれん草
ほうれん草の生育適温は15~20°Cで、低温には強く0°C以下でも育成できますが、育ちが悪くなってしまうので注意が必要で...
-

-
はじめての家庭菜園で役立つ基本的な野菜の育て方
家庭菜園をやっている人が増えています。また、これからはじめてみたいと思っている人も多いと思います。しかし実際は、なにから...
-

-
スモモの育て方
スモモにはいくつかの種類があり、日本、ヨーロッパ、アメリカの3つに分類されます。ヨーロッパではカスピ海沿岸が生息地だった...
-

-
サクラの育て方
原産地はヒマラヤの近郊ではないかといわれています。現在サクラの生息地はヨーロッパや西シベリア、日本、中国、米国、カナダな...




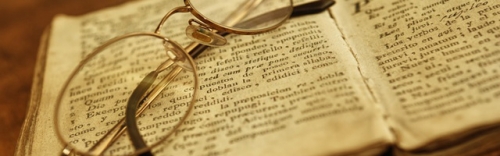





ヒメノカリスはヒガンバナ科の植物で原産地は北アメリカ南部や南アメリカで、日本では一般的には球根を春に植えると夏には白く美しい花が見られるので人気となっています。この種類の植物の歴史は非常に長く、元々は西インド諸島が原産であると考えられています。