みつばの育て方

育てる環境について
みつばにおいてはどのようなところで栽培されるかです。育て方としては、水耕栽培をした様子が江戸時代においてあったとされます。特に日本においてはどこで育てるかを気にする必要はないとされています。北から南まで幅広く育てられていることが知られています。光を好むことがあるので、日光のよく当たるところを利用すると良いとされます。
土地としては水分を適度に含んでいる所が良いようです。あまり乾燥したところは好まれないとされています。寒い時期においてはハウスを用いることがあると言われるくらいなので、決して育ちやすいわけではありません。あまり寒いところで育てるときには、温度調整が必要になってきそうです。暖かい環境に関しては問題としては少なくなりそうです。
時期としては、春頃から行って、収穫に関しては4月頃から始められるケースがあります。1年に一度しか収穫できないわけでなく、幾つかに分けて行うことができます。1月から始めた場合は4月頃に収穫、3月頃であれば7月頃まで収穫が可能になります。6月から始めることによって9月まで、
9月からのものは11月頃に収穫できるようになっています。このように見ていくと真冬に関してはさすがに収穫が難しくなることがありますが、それ以外の季節においては問題なく行うことが出来ると言ってもよいでしょう。自宅においてハウスのような設備を用意することが出来るのであれば、1年を通してできることもあります。
種付けや水やり、肥料について
みつばのためにはまず畑の準備をする必要があります。畑に関してはすぐに出来るわけではなくじっくりと作る必要があります。それによってやっと栽培可能な状態に持って行くことができます。栽培を開始する時期を逆算し、1箇月ぐらい前から行い始めます。まこうとする土地において、石灰、堆肥をよく巻きます。そして耕すようにします。
1平方メートル当たり石灰に関しては大さじ3杯ぐらい、堆肥については小さいバケツに1杯ぐらいで十分かもしれません。耕し方としては、土となじませるようにしながら行います。事前に何かを作っていたり、以前に作っていたのであればそちらを利用するようにします。そうすることで作業も簡単になるでしょう。
少しずつ準備を始めたから今度は原肥をいれます。深さとしては10センチほどの溝を掘ります。そこに化成肥料と油かすをいれます。溝の長さが1メートルに対して化成肥料は大さじ3杯程度、油かすに関しては5杯程度入れるとよいでしょう。溝を平行して作る場合にはそれぞれの溝に関しては50センチぐらい離すようにします。
あまり近づけ過ぎると互いの溝に入り込んでしまうことがあります。その次に行うこととしてはまき溝を作ります。種をまくための溝です。元肥を入れた後に土をかぶせていきます。この時には溝の底が平らになって、種を巻いた時に均等に育てられるようにしなければいけません。凸凹になっていると、生育の方もバラバラに成ってしまうことがあります。
増やし方や害虫について
増やすためには種まきをしなければいけません。どのように種まきをしていくかですが、適当にバラバラに行うのはよくありません。まき溝を予め作っておき、その全面にまいていくようにします。1.5センチから2センチの間隔を守るようにします。この間隔をキープするのも大事なことの一つです。
それはバラバラにまいてしまうとあるところでは密集していて、あるところでは空白が開く状態になります。水であったり肥料は均一にしていても、生えているところがバラバラだと均一に吸収できなくなってしまいます。そのようなことがないようにしておく必要があります。
巻き終わったら土をかぶせて軽く抑えるようにして種まきを完了させるようにします。たくさん収穫するときに必要なこととしては間引きと除草になります。除草剤を使いたいところですが、せっかく自然の状態で栽培をしているのですから、あまりそういった薬を使いたくありません。ですからまめに除草をするようにします。除草の他にすることとしては間引きです。
たくさん生えすぎてしまうと栄養分を取り合って成長がされにくくなることがあります。そのようなことがないように適度に間引きを行い、均等に成長できるようにしておきます。追肥をするのは草丈がある程度伸びた頃です。5センチぐらいに伸びたとき、そして15センチぐらいの時などに行うようにします。時期を決めるのではなく、草の伸び具合を基準に行うと調度良いようです。
みつばの歴史
料理においては野菜を色々使います。野菜には多くは緑色のタイプがいいおいですが、根菜類などは根の色をしています。またトマトやナスなどにおいてはそれぞれ果実の色をしています。カラフルな色のものが多いです。野菜においても、その主体が葉っぱになっているもの、葉やさいのタイプのものは緑色になります。
野菜においては常に主役になるような野菜もあれば、常に脇役のような野菜もあります。脇役の野菜に関しては味よりも香りなどを楽しむためのものになることが多くなります。脇役になることが多い野菜の一つとしてミツバがあります。料理において、完成した上に生のままのものを直接おいて飾ることが多いかもしれません。
原産としては比較的多くの土地において知られていて、日本においても古くからあったとされています。北海道から沖縄まで見ることができます。日本以外においては外国にもあるようです。北であれば生息地にサハリンであったり千島列島の一部においても見ることが出来るようです。中国や朝鮮半島にも見ることができます。
そのことから歴史において何処かから伝わったよりも、この付近においては自然に生えていたものと考えることができそうです。昔においては栽培までされたかどうかはわかりませんが、自然において多く見つけることができたのであれば、わざわざ作る必要はないこともあります。メインの食材としてではないですから、自然に生えているものだけで使われてきたのかもしれません。
みつばの特徴
みつばの特徴としてはセリ科に該当します。せりといいますとやはり香りの良い野菜として知られていますから、その系統になっているかもしれません。キキョウ類、セリ目、セリ科として分類されています。名前において3つの葉であることが言われていますが、実際に3つに分かれています。シロツメクサの葉っぱが3つの葉にわかれていることで知られています。
変異形として四つ葉や五つ葉があると知られています。見た目に関してはこの葉にも少し似ています。高さに関しては40センチほどで、6月から8月頃にかけて小さな花を咲かせます。葉っぱのほうがよく知られているのであまり花の方は知られないかもしれませんが、非常にきれいな花が咲きます。真っ白の花が咲きます。
葉の形もよく知られているとおりに特徴的になっています。楕円形のような形ですが、先のほうが尖っています。そして葉にはギザギザが刻まれたようになっています。これらの葉は3枚ですが、少し重なった状態になっています。真ん中の葉が最も上についていて、横につく葉についてはその下につくように付けられています。
香りが高いとされていますが、そのままで香りがあるわけではありません。香りを強くしようとするときは手で挟んで叩いたりするといい香りがするようになります。後は料理の上に乗せたり添えたりするだけです。チョットした葉っぱを乗せるだけですが、これだけでもかなり料理の質を変えることができます。
-

-
小カブの育て方
カブは煮物、サラダ、漬物など色々な食べ方が出来る野菜であり、煮込む事で甘みが増すため、日本料理には欠かせない食材となって...
-

-
ペトレアの育て方
ペトレア属はクマツヅラ科の植物で、一口にペトレアといっても様々な種類があります。およそ30種類ほどあり、その中でも日本で...
-

-
グーズベリーの育て方
グーズベリーという植物をご存知ですか、日本ではもしかしたらセイヨウスグリの名前の方が有名かもしれませんが、スグリ科スグリ...
-

-
ロペジアの育て方
分類はアカバナ科です。別名はロペジアともいわれています。学名はLopeziacordata、英名はMosquitoflo...
-

-
桃の育て方
桃の歴史は紀元前にまで遡り、明確な時期は明かされておりませんが、中国北西部の黄河上流が原産地とされています。当時の果実は...
-

-
タニウツギの育て方
タニウツギはスイカズラ科タニウツギ属の落葉小高木です。スイカズラ科の多くは木本で一部はつる性や草本です。タニウツギは田植...
-

-
オヒルギの育て方
オヒルギはマングローブを構成する植物の種類のうちの一つです。仲間の種類として、ヤエヤマヒルギやメヒルギなどがあります。自...
-

-
レウカデンドロンの育て方
「レウカデンドロン」は、南アフリカ原産の常緑低木で熱帯地域を中心に広く自生しています。科目はヤマモガシ科レウカデンドロン...
-

-
ダチュラの育て方
ダチュラといえば、ナス科チョウセンアサガオ属、あるいはキダチチョウセンアサガオ属の植物のことです。しかし、この区別に関し...
-

-
ピーマンの栽培やピーマンの育て方やその種まきについて
家庭菜園を行う人が多くなっていますが、それは比較的簡単に育てることができる野菜がたくさんあるということが背景にあります。...




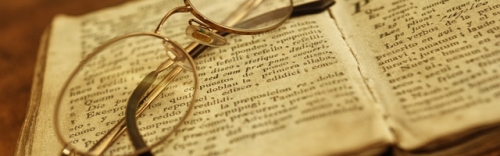





みつばの特徴としてはセリ科に該当します。せりといいますとやはり香りの良い野菜として知られていますから、その系統になっているかもしれません。キキョウ類、セリ目、セリ科として分類されています。名前において3つの葉であることが言われていますが、実際に3つに分かれています。