モモバギキョウの育て方

育てる環境について
育て方としてはどういったところが適しているのかです。環境を知っておく必要があるでしょう。まずは発芽に関する適温としては15度から20度ぐらいとされています。日本であれば春ぐらいにおいてこのくらいの気温になるでしょう。寒さに関してはそれなりに強いですが、暑さであったり多湿には少し弱いところがあります。
生育の適温としても13度から20度と日本の春から夏の気温からするとやや低めの環境を好むことがあります。寒さが苦手なら室内に入れる方法がありますが、暑さが苦手な場合にクーラーを当てるわけにはいきません。方法としては風通しを良くしたり、日当たりを調節することになるでしょう。全く日当たりを避けてしまうと涼しいですが発育に影響します。
ある程度の日当たりと風通しを重視した環境を作るようにします。土の度合いとしては中性の土壌を好むとされています。ペーハーで言えば6.5から7.5ぐらいです。酸性でもアルカリ性でもあまり良くありません。水はけについても気をつける必要があります。よく使っているところになると酸性に傾いている土壌があります。
このようなときに中性に向けるのであれば石化を施すと良いとされています。この辺りについては適度な量が必要です。あまりいれすぎれば今度はアルカリ性が強くなってしまいます。どのくらい入れればよいかについては案内書などがあるでしょうからそれを見ながら酸度の調整をするようにします。
種付けや水やり、肥料について
用土の準備としては、硬質の鹿沼土か日向土、桐生砂か赤玉土、軽石を使います。軽石は2割でその他は4割ずつ似します。土を利用する場合においてはいずれもしっかりと水でよく洗うようにします。赤玉土を使うときにもふるいをつかってふるうようにします。根と茎の境界においては少し土の構成を変化させたりします。
花崗岩質の荒いタイプの砂利を使ってそれで覆うようにします。このような配合をすることによって水はけなどに対応することができます。寒冷地においてはどのようにするかですが、草花用の培養土を使うことで育てることが可能になります。水やりを行うとき、鉢植えにおいては表土の乾きを目安にします。
庭植えにおいては最初の植え付けの時はきちんと与えますが、その後については雨水で対応します。雨の量が少ないようであればその都度水やりをしなければいけなくなります。夏の間の対策としては二重鉢を利用することがあります。こうすることで水分をある程度確保することが出来るようになります。
乾燥を防ぐ目的にも対応できますし、植木鉢の中の温度について上昇させるのを抑制する効果もあるとされています。肥料については元肥として一定量を与えるようにしておきます。リン酸とカリウムが含まれたタイプが良いとされています。すぐに効くタイプではなく、ゆっくり、じわじわ効くタイプをいれておきます。量としては3号鉢で二つまみ程度の量になります。3月から9月にかけては月に1回から2回の頻度で液体肥料を与えます。
増やし方や害虫について
増やす方法としては種まきが可能になります。花が咲いて種ができた後、種を冷蔵庫に保管しておきます。まく時期としては翌年の2月から3月くらいです。少し寒いと感じるかもしれませんが、この頃に行っていきます。この植物に関しては発芽率が比較的良いとされています。そのため注意としてはあまりたくさんまきすぎないことです。
発芽率が良くないものの場合、発芽しないことを想定して多めにまくことがあります。たくさんまいてもそれでちょうどよかったりします。でもこの花はたくさん芽が出てしまって結局そのうちの幾つかを処分しないといけなくなります。それなら最初からまく量を調節すればいいことになります。まいた種についてはすぐに花をつけるわけではありません。
1年目は難しく2年目につけてくれる事が多いです。株分けをすることができます。植替えと同じ時期に庭植えなら3年に1回ぐらい行うことがあります。行い方としては、古くなった根茎を見て行います。すると自然に分かれそうなところがわかるでしょう。その部分でわけるようにします。
分けた根についてはそれぞれにきちんと芽がついていることを確認しなければいけません。芽がなければ発芽してくれません。自然についていれば手で取れますが、そうでない場合はナイフで切り分けることも可能です。切り口はきちんと消毒をします。害虫としてはヨトウムシ、ハダニなどが出てくる可能性があります。季節によって出ることがあります。
モモバギキョウの歴史
植物は花に特徴がある場合、葉っぱに特徴がある、実に特徴がある場合があります。その他根っこなど目に見えない部分に特徴を持っていることもあります。それぞれにおいて何らかの違いがあるのであれば別の種類にしなければいけません。見た目は全く同じでも、掘り返してみると根っこの部分が異なるから
別の種類として認識しないといけないことも出てくるとされています。きれいな花を咲かせる植物にモモバギキョウと呼ばれるものがあります。この植物の名前においてはモモバとついています。この花は葉っぱに少し特徴があることからそれが花の名前に影響したようです。その他の名前としてもモモノハギキョウになるので同じような意味合いになるのでしょう。
この花の原産、生息地としてはヨーロッパからロシア、トルコなどとされています。トルコキキョウなどが知られていますから、そのあたりがよく生息しやすいところになるのでしょう。日本に入ってきたのは1930年頃とされています。時代としては戦争等があって大変な時期ですが、ヨーロッパなどとの交流も進んでいる時期に
このような美しい花が渡来していたのは非常に嬉しい事の一つになります。しかし日本での普及となるとあまり進んでいないとされています。花は美しく葉も特徴的ではありますが、他のキキョウなどとの区別があまりされにくいところがあるのかもしれません。実際に自分で栽培などをしてみると、その良さを知ることが出来るかもしれません。
モモバギキョウの特徴
この花の特徴としては、キキョウ科、ホタルブクロ属となっています。園芸においては山野草、草花としての利用が多くなります。形態としては多年草として扱われています。草の高さとしては30センチぐらいから90センチぐらいになります。花が咲くのは春と夏の中間あたりで、5月くらいに花がついていきます。花の色としては印象的なのは白色ですが、
その他にピンク色であったり、紫色の花をつけることもあります。紫色の花についてはかなり濃い色がつくことがあります。こういった花の場合は比較的薄い紫などが多いですが、この花ははっきりした紫色になっています。ですから白い花と紫の花を一緒に咲かせたりするとそのコントラストを楽しむことが出来るかもしれません。
白ばかり、紫ばかりで栽培するのもいいでしょうが、別々の色どうしで作ってみるのもいいかもしれません。花の花びらに関しては5枚から6枚ついています。花びらは全て開ききるのではなく、途中までになります。ですから小さいラッパのような、コップのような形になります。
中央部分に関しては白い花でも紫の花でも黄色になります。茎に関しては直立した株立になります。茎の先端部分に花をつけます。多いものになると10輪近くつけるものもありますから結構一つの株で楽しむことが出来るかもしれません。葉っぱに関しては花の豪華さに比べると地味に細いタイプになっています。少し控えめに表現をしているのかもしれません。
-

-
バンダの育て方
原産地は赤道を挟んだ北緯南緯とも30度の間の国々で主に熱帯アジア、インド、オーストラリア北部、台湾などがあります。また標...
-

-
モッコウバラの育て方
花の中でも王様と呼ばれるほどバラに魅了される人は多いです。そのためガーデニングをはじめる際にバラを育ててみたいと思う人は...
-

-
ヒメシャガの育て方
ヒメシャガはアヤメ科アヤメ属の多年草でシャガよりも小型になります。シャガとよく似ており絶滅危惧植物に指定されている耐寒性...
-

-
パパイヤの育て方
パパイヤはメキシコ南部から西インド諸島などが原産と言われており、日本国内においても熱帯地方が主な生息地になっており、南国...
-

-
クヌギの育て方
クヌギは広葉樹の一つあり、かつてはツルバミとも呼ばれていた樹です。またコナラとともにカブトムシ、クワガタムシといった昆虫...
-

-
レプトシフォンの育て方
この花についてはハナシノブ科、リムナンツス属になります。属に関しては少しずつ変化しています。園芸における分類としては草花...
-

-
植物の栽培に必要な土と水と光
植物の栽培に必要なのは、土と水と光です。一部の水の中や乾燥している場所で育つ植物以外は、基本的にこれらによって育っていき...
-

-
アボカドの育て方・楽しみ方
栄養価も高く、ねっとりとした口当たりが人気のアボカド。森のバターとしてもよく知られています。美容効果もあり、女性にとって...
-

-
シネンシス・エピソードの育て方
シネンシス・エピソードがきんぽうげ科ヒエンソウ属ということです。シネンシス・エピソードという淡い紫色の花があり、とても美...
-

-
パンジーの育てかたについて
スミレ科のパンジーは、寒さには強いのですが、暑さに弱く、5月前後に枯れてしまいます。ガーデニング初心者の方には、向いてい...




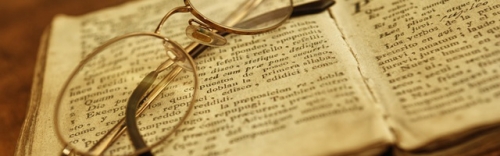





この花の特徴としては、キキョウ科、ホタルブクロ属となっています。園芸においては山野草、草花としての利用が多くなります。形態としては多年草として扱われています。草の高さとしては30センチぐらいから90センチぐらいになります。