シロバナタンポポの育て方

育てる環境について
シロバナタンポポの生息地は関東地方以西ですが、最近は関東地方でも見かけるようになっています。住宅の近所の空き地などに自生しており、生命力が強い植物ですので、比較的簡単に育てることができます。最近はセイヨウタンポポに押されて個体数を減らしていますが、これはセイヨウタンポポの繁殖力があまりにも強く、
シロバナタンポポの繁殖力が相対的に劣るためです。鉢植えで育てる場合には、日当たりの良いベランダなどに置くことが適しています。鉢植えの際には、タンポポの根の太さは5センチほどになるため、比較的大きめの植木鉢が必要になります。タンポポ類は乾燥に弱いので、植木鉢は湿気がある場所に置くことが必要です。
屋内でも育てることができますが、乾燥と日照不足には十分に注意します。生息地は関東以西ですので、関東以西の地域では温度の管理は神経質になることはありませんが、関東以北の寒冷地での栽培はあまり適していません。どうしても育てたい場合には、温暖な場所に鉢を置いて育てることが必要です。
関東以北の地域では、カントウタンポポやエゾタンポポの栽培の方が簡単にできます。シロバナタンポポを住宅の庭などに地植えする場合の育て方は、根の大きさは1メートルを超える場合があるため、他の植物と一緒に栽培する場合には、根が大きくなることに十分に留意することが必要です。地植えの場合も、日当たりが良くて適度な湿気がある場所で育てることが大切です。
種付けや水やり、肥料について
種付けは春に行います。4月の上旬が種付けには最適な時期です。綿毛が付いている状態のまま鉢に蒔くと2週間程度で発芽します。種付けの際には、とても小さな種ですので、あまり深く埋めてしまうと発芽できない場合があるので注意が必要です。土を軽く覆う程度で十分です。シロバナタンポポは乾燥が大敵ですので、種付けを行ってからしばらくは、乾燥させないように十分に注意します。
鉢全体にビニール袋を被せると乾燥を防ぐことができます。庭に地植えする場合には、発芽するまでの間は、水やりには特に注意をします。発芽の温度は23度前後ですので、4月の上旬に種を蒔いた時には、4月の中旬から下旬にかけて発芽します。芽はとても小さな双葉の芽ですので、うっかり見逃してしまう場合があります。
発芽してから5月の上旬になると、徐々に本葉が出てきます。本葉はだんだんと大きくなり、5月の中旬になるとロゼット状になります。5月の下旬にはロゼット状の葉っぱはギザギザになり、タンポポらしい形状になります。成長期の水やりは、土が乾燥する前に水やりを行うようにします。
日頃から土の状態を観察しておき、乾燥にはくれぐれも注意することが必要です。シロバナタンポポは生命力が強い野生の植物ですので、特に肥料を与える必要はありません。肥料を与えると成長しすぎて巨大化する場合があります。鉢植えで成長しすぎた場合には、大きめの植木鉢に交換することが必要です。
増やし方や害虫について
自生のものを植木鉢で育てる時には、自生していた土地の土を使用すると増やしやすくなります。市販の培養土を購入する場合には、自生している土地と土質が似ている土を選ぶようにします。肥料を与えなくても増やすことはできますので、肥料には気を配らなくても大丈夫です。どうしても肥料を与えたい場合には、できるだけ少量にしておきます。
タンポポの栽培で最も大事なことは、乾燥に注意をすることです。土の表面が乾燥した時には、必ず水やりをすることが大切です。害虫については、成長期になると茎や葉にアブラムシが付くことがあります。薬剤を使って駆除することができますが、牛乳やカキ殻石灰を使って駆除をすることもできます。薬剤を使用すると確実に駆除することができますが、
天然由来の成分を配合している殺虫剤を使用すると安心です。木酢液には有機合成化合物が含まれているため、できる限り使用しない方が賢明です。開花の時期は春になりますので、種は飛散する前に収穫しておきます。収穫した種をそのまま鉢植えをすると増やすことができます。植木鉢はなるべく深めの鉢を選ぶようにします。
ランの栽培に使用するような深めの植木鉢が最適です。駄温鉢で栽培することも可能ですが、根がぐるぐるに巻きついてしまいますので、生育上はあまり好ましくありません。自宅の庭に地植えする場合には、種を適当に飛散させるだけで十分です。種を飛散してから2週間程度で発芽します。
シロバナタンポポの歴史
シロバナタンポポの原産国は日本で、1904年に外来種のセイヨウタンポポが侵入してくるまでは、関東地方より西の地域で自生していました。シロバナタンポポは、万葉集や古今和歌集などには登場していませんが、平安時代の初期に書かれた日本最古の植物辞典の本草和名に記載されています。
その当時はタンポポとは記載されておらず、蒲公草という名称で記載されていました。タンポポという名称で呼ばれるようになったのは、室町時代の頃です。タンポポと呼ばれるようになった由来については諸説があり、定かではありません。漢字では蒲公英と表記されるようになり、生薬の原料としても使用されるようになりました。
食用としても利用されるようになり、他の野菜と同じような方法で調理されていました。江戸時代になると、大本草学者の小野蘭山が記した本草綱目啓蒙の中に登場し、シロバナタンポポという名称で記載されています。江戸時代から明治時代にかけては、関東地方より東の地域に自生するエゾタンポポと共に、日本原産のタンポポとして、
関東地方以西の地域ではあちこちに自生していました。外来種のセイヨウタンポポが日本に侵入して帰化種となってからは、その数が減少しました。現在ではタンポポといえば黄色の花弁のセイヨウタンポポが主流になっていますが、シロバナタンポポも住宅の近くなどに自生しています。自然交雑種が多いため、在来種のタンポポと勘違いされることも多いです。
シロバナタンポポの特徴
シロバナタンポポの特徴は、花の色が白色であることです。舌状花の数は他のタンポポと比べると少なく、1つの頭花に100個程度の舌状花が付きます。白色の花で舌状花であることがシロバナタンポポの大きな特徴になり、他のタンポポと容易に見分けることができます。花の大きさは4センチ程度で、花茎の高さは10センチから20センチ程度です。
綿毛の種子が付くと、20センチから30センチ程度の高さになります。高くなることによって、綿毛の種子を遠くまで飛散させることが可能になります。タンポポといえば黄色のイメージがありますが、街中などでよく見かける黄色のタンポポは、セイヨウタンポポと呼ばれる外来種です。セイヨウタンポポは春から秋にかけて花を付けますが、シロバナタンポポが開花するのは春だけです。
最近では秋にも開花する事例が報告されていますが、どのような理由で秋に開花するかについては、まだ解明されていません。秋に開花するのは在来種ではなく、自然交雑種ではないかとも言われています。シロバナタンポポは、カンサイタンポポと間違われることがありますが、
カンサイタンポポの花の大きさは3センチ程度で、シロバナタンポポよりも一回り小さいので、花の大きさを観察することによって見分けることができます。シロバナタンポポは生薬の原料や食用にすることができ、花弁をてんぷらにして食べることができます。根はタンポポコーヒーにすることができます。
-

-
ワーレンベルギアの育て方
特徴としては、被子植物、真正双子葉類、コア真正双子葉類、キク類、真正キク類2、キク目、キキョウ科、キキョウ亜科となってい...
-

-
クラッスラの育て方
クラッスラはベンケイソウ科のクラッスラ属に属する南アフリカ、東アフリカ、マダガスカルなどが原産の植物です。クラッスラ属は...
-

-
ベッセラ・エレガンスの育て方
この花については、ユリ科のベッセラ属に属します。花としては球根植物になります。メキシコが生息地になっていますから、暑さに...
-

-
サヤエンドウの育て方
サヤエンドウの歴史は大変古く、古代ギリシャ、ローマ時代にまでさかのぼります。生息地や原産は中央アジアから中近東、地中海沿...
-

-
メセンの仲間(夏型)の育て方
この植物の特徴としては、まずはハマミズナ科に属する植物で多肉植物であることです。ですから茎などがかなり太くなっています。...
-

-
ヒアシンスの育て方
ヒアシンスは16世紀前半にヨーロッパにもたされ、イタリアで栽培されていた歴史がありますが、ヨーロッパにも伝わった16世紀...
-

-
ワサビの育て方
ワザビの色は緑色をしており、香りは大変爽やかになっています。しかし何と言っても最大の特徴はあの抜けるような辛みでしょう。...
-

-
つい捨てちゃう、アボカドの育て方
最近では、サラダやグラタン、パスタなどに使われることもなりスーパーでもよく見かけるようになったアボカド。「森のバター」や...
-

-
ダンピエラの育て方
世界分布の区分における熱帯から亜熱帯地域に多く発見されてきたクサトベラ科、そのうちの一種類として認識されています。学術名...
-

-
シカクマメの育て方
シカクマメは日本でも食されるようになってきましたが、どちらかというと熱帯を原産とする植物です。元々の生息地は東南アジアや...




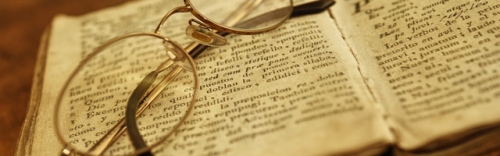





シロバナタンポポの特徴は、花の色が白色であることです。舌状花の数は他のタンポポと比べると少なく、1つの頭花に100個程度の舌状花が付きます。白色の花で舌状花であることがシロバナタンポポの大きな特徴になり、他のタンポポと容易に見分けることができます。花の大きさは4センチ程度で、花茎の高さは10センチから20センチ程度です。