ほうれん草の育て方

ほうれん草の育て方及び下準備
ほうれん草は畑に種を直播をして栽培する野菜でですが、プランターなどでも栽培できます。育て方としては簡単な部類の葉野菜になります。少しコツを覚えれば誰にでもほうれん草の栽培が出来ます。また、庭に少しのスペースがあれば面倒な植え替えなどをする必要もなく気軽に栽培できます。
まず土の準備ですが、畑であれば水はけのよい日当たりのよい場所を選びます。ほうれん草は酸性の土壌を嫌うので、pH5.5以下ですと成長が悪くなってしまいます。ですので種付けの前に苦土石灰を散布してpH6.2~6.5程度に調整をする必要があります。土の状態を整えたら土を良く砕いて畝立をします。
畝の幅が1mあれば2条のまき溝に条まきにすることになります。またほうれん草は連作が出来ない品種ですので最低でも1年間は同じ畑には作らないようにしましょう。プランターの場合は45~60㎝程のものに市販の培養土を使うと簡単です。
これに石灰を土10?当たり10~20gの割合で混ぜ、化成肥料を同じく10?につき10~20gほど混ぜて土づくりをし、プランターに2~3㎝程のウォータースペースを作った状態で土をいれます。これを植え付けの3週間前に準備をします。その後植え付け1週間前程になったら元肥を施しておきます。
ほうれん草の種付け
ほうれん草は、春まきか秋まきが出来ますが、品種によってそれぞれの時期を選ぶものもありますのでよく調べておく必要があります。ほうれん草の種は、ホームセンターや町の園芸店でも簡単に入手することが出来ます。品種も豊富ですので植え付ける時期などをよく検討して育てやすいものを選びます。
種付けの準備として水に一晩つけておくと発芽しやすくなります。この時水に浮いたものはよけておきましょう。あとは水切りしてすぐに蒔くことが出来ます。また、発芽効率を上げたもので、ネイキッド種といったプライマー種子なども販売されていますのでこれも利用することが出来ます。
種の準備が出来たら、畝に鍬などで幅5㎝程のまき溝を浅く作り、厚まきにならないように種付けします。その上から1㎝程の土をかぶせて水やりをしておきます。プランターの場合も条まきを行いますが、スペースが限られますので間隔は狭くなります。
しかし、ほうれん草は株間が狭くても十分育つので心配はいりません。また、後に間引きをすることで大きさはある程度調整することが可能です。この時にプランターの底から水が流れるぐらいたっぷりと水やりをします。
種付け後3日~1週間ほどで発芽となりますが、この時の茎はとても弱いので雨などに当たると倒れてしまいます。ですのでしばらくは雨に当たらないようにする工夫が必要です。
ほうれん草の育て方、管理
春うえのほうれん草を育てるときには高温に注意します。生育期が高温の季節と重なる場合は遮光ネットなどを利用して光と熱の管理をする必要があります。乾燥を嫌いますので、晴れの日にはまず忘れずに水やりをする必要があります。この時10日に一度は液肥を混ぜてやると生育の助けになります。
水やりの時間は晴天の日の午前中に一回だけとし、日が沈むころには土が乾いている状態のほうが病気の予防になります。この後本葉が出始めた頃、間引きを行います。特に込み入ってきたと思われる個所を選んで、本?4~5枚ある場合に5㎝ぐらいの株間に調整します。
追肥は列の脇に肥料溝を作り肥料をまき、土をかぶせておきます。2回目の間引きや追肥の時に畝の手入れをして除草しておきます。プランターの場合の間引きは、1回からそれより大きくしたい場合は2回の間引きをします。本葉が2~3枚程度になったら株間が3㎝程になるように間引きします。
また、更に大きくしたい場合は2回目の間引きをしますが、タイミングは本葉が4~6枚になった時に5~7㎝程度の株間に調整します。その他発生しやすい病気として「べと病」が挙げられます。育成経験の少ないうちは最初からこのような病気にかかりにくい品種を選ぶことが必要です。
その他には、多湿を避ける育て方をすることと、畝を高くするなどして水はけを良くすることが病気の発生を防ぐことになります。また、発生しやすい害虫はアブラムシ類、ヤガ、メイガなどが挙げられます。発生したら早い時期に食品成分を利用した殺虫剤などを利用して駆除しておきましょう
ほうれん草の収穫
草丈が15~16㎝程あるいは20~25㎝になったものから収穫していきます。秋まきの場合種付けから30日~50日程度が目安で、春まきの場合は種付け後30日~40日が目安となります。
この時注意が必要なのは、ほうれん草の葉は非常に折れやすく痛めてしまわないようにしなければなりませんので、株元の土を抑えるようにして株全体を持つようにして引き抜くとよいでしょう。
ほうれん草はアクの強いものとして知られていますがそれだけに栄養価も高いものがあります。何よりもその鮮やかな緑色は、料理の引き立て役としてだけでも価値の大きい野菜といえるでしょう。
ほうれん草の歴史
中央アジアから西アジアの地域を原産地とするほうれん草が、初めて栽培されたのはアジア地方だと言われています。中世紀末にはアラブからヨーロッパに伝わり葉物野菜としては良く普及して一般化しました。
一方東アジアの方にはシルクロードを使って広まることとなり、その後中国に7世紀ごろ伝わったとされています。日本には、江戸時代の初期に伝わり、一説によると伊達政宗もこのほうれん草を食べたとされています。
名前の由来は「ペルシャの草」という意味のバウリンからなると言われ、ホウレンは中国語でペルシャという意味といわれています。この時中国方面に伝わったものが「東洋種」といわれヨーロッパに伝わったものが「西洋種」といわれるようになりました。
それぞれの品種がそれぞれの生息地で長い年月をかけて改良され現在の「西洋種」と「東洋種」として確立しました。西洋種は、11世紀ごろにスペインで栽培され16世紀にはヨーロッパ全土に広まったとされています。
中国に伝わった東洋種も日本へ16世紀ごろには伝えられました。日本へ最初に伝わった東洋種は葉に切れ込みをもちアクが少なく食べやすかったのですが、後の明治以降に伝わった西洋種は、?の形状も丸く肉厚でアクが強いものでした。しかし大戦後のアニメ「ポパイ」の影響と栄養価の高さから一気に需要が急増しました。
ほうれん草の特徴
西洋種と東洋種に分かれていたほうれん草ですが西洋種のほうはアクが強くあまり好まれず現在では両者を掛け合わせたものが主流となっています。この野菜にはカロテンやビタミンA・B1・B2・C・葉酸といったビタミンが豊富でその他鉄分や食物繊維を多く含んでいます。
ビタミン類は体の調子を整え他の栄養素を取り込むために補助的な役割を果たします。このため同時に含まれる鉄分などの吸収を高める相乗効果があります。鉄分の補給は貧血の症状に有効で、食物繊維は腸内環境を整え抵抗力のある体作りを助けます。
血液と腸内環境の改善は根本的な健康の基礎を作ることが出来ますので疲れやすい人や体力の衰えた方には最適の野菜といえます。ただ、ほうれん草にはシュウ酸といわれるものが含まれており、カルシウムや鉄分の吸収にマイナスであるといわれる面もあります。
また、シュウ酸は、結石の原因でもあり大量の摂取は体に悪い影響を与えることもあります。しかしながらシュウ酸は、水に溶けやすく水にさらしたり、米のとぎ汁米ぬかで容易に除去することが可能ですから調理方法でカバーすることが出来ます。
下記の記事も詳しく書いてありますので凄く参考になります♪
タイトル:チンゲンサイの育て方
タイトル:オカノリの育て方
-

-
初心者でも栽培しやすいえんどう豆の育て方について説明します。
えんどう豆の栽培は、マメ科なので前回マメを育てた場所での栽培は避けた方が無難です。しかし、えんどう豆は日当たりが良く水は...
-

-
コノテガシワの育て方
コノテガシワは中国の全域を生息地とする常緑樹で、中国では古くから寺院に植えられる樹木として利用されていました。一年を通し...
-

-
ラムズイヤーの育て方
この植物は被子植物になります。双子葉植物綱になります。キク亜綱、シソ目、シソ科、イヌゴマ属となります。園芸上の分類として...
-

-
長ねぎの育て方
長ねぎの他、一般的なねぎの原産地は中国西部あるいはシベリア南部のアルタイル地方を生息地にしていたのではないかといわれてい...
-

-
そら豆の育て方
そら豆は祖先種ももともとの生息地も、まだはっきりしていません。 原産地についてはエジプト説、ペルシャ説、カスピ海南部説な...
-

-
ハナモモの育て方
ハナモモというのは、中国が原産地で鑑賞をするために改良がなされたモモですが、庭木などにも広く利用されいます。日本へ入って...
-

-
ワックスフラワーの育て方
花についてはフトモモ科、チャメラウキウム属になります。園芸上の分類としては庭木であったり花木としてになります。草丈に関し...
-

-
ワトソニアの育て方
ワトソニアは草丈が1m程になる植物です。庭植え、鉢植えにも適しています。花の色は、白やピンク、赤やサーモンピンクなどの種...
-

-
ヒイラギナンテンの育て方
ヒイラギナンテンの原産地は中国や台湾で、東アジアや東南アジアを主な生息地としています。北アメリカや中央アメリカに自生する...
-

-
シャクヤクの育て方
シャクヤクの最も古い記述については、中国で紀元前五世紀には栽培されていたという記録が残っており、宋の時代には品種改良が行...





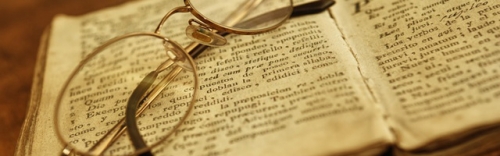





中央アジアから西アジアの地域を原産地とするほうれん草が、初めて栽培されたのはアジア地方だと言われています。中世紀末にはアラブからヨーロッパに伝わり葉物野菜としては良く普及して一般化しました。