ゲラニウム(高山性)の育て方

育てる環境について
ゲラニウムの育て方としては日当りのよい場所や半日陰で水はけのよい肥沃な土壌に植えることがポイントです。高温多湿な場所にはあまり強くありませんので、夏などの日射しが強く気温も高くなるシーズンには西日があたらないようにするために半日陰に植えるようにしましょう。
少し湿ったような場所に植えることがおすすめで、落葉樹などの下辺りは最適です。鉢植えで育てていく場合は、日なたに置いておき日中は半日陰の場所に移動するなどしてください。6月頃から9月上旬くらいまでは特に直射日光があたり続けないように注意してあげてください。
直射日光を浴び続けてしまうと日焼けをして高温傷害を起こしてしまうことがあります。夏場に冷涼となる場所が適し、植え付けをする場所には軽石や鹿沼土、腐葉土をよく混ぜておくことで水はけがよい土壌を作ることができます。
蒸れてしまうと株が弱ってしまうことがありますので、開花後で梅雨のシーズンに入ってしまう前に二分の一くらいに刈り込んでおくことがおすすめされています。鉢植え栽培をしている場合は生育が旺盛で株が広がっていきますので、
いつまでも小さな鉢で育てていると成長が悪くなってしまいます。毎年一回り大きな鉢へと植え替えをしていくように注意しましょう。庭植えをして育てているような場言いでも、3年くらい経った頃に株分けをおこなってください。株分けのタイミングとしては、4月頃か10月頃が適しています。
種付けや水やり、肥料について
苗の植え付けをおこなう場合は、春頃から夏の初め頃までにポット苗を有機質肥料や緩効性化成肥料を施した用土に植え付けていきます。水はけのよい軽めの用土が適していますので、赤玉土5、腐葉土3、川砂化か桐生砂2を混ぜたような用土がおすすめされています。
鉢植えで育てている場合は、土の表面部分が乾いてきたと感じたらたっぷりと水やりをおこなってください。鉢植えは、二重鉢にしておくとよく育ちます。庭植えをしている場合でも自然の雨だけでは乾燥が続いてしまいますので水やりをおこなってあげてください。
夏場は暑さで傷みやすいですので、10センチメートルから20センチメートルほど土を盛ったレイズドベッドや腐葉土などを利用した水はけのよい土に植え付けることがおすすめです。傾斜になっている場所に石で土留めをするように植栽をすると水はけがよくなります。
この時株の間隔を15センチメートルから20センチメートルほど空けるようにしてください。肥料はあげ過ぎてしまうことに注意が必要です。窒素分が多いような肥料は花つきが悪くなってしまうことがあります。葉は問題なく元気な状態で花のつきが悪いという場合は可能性が高いです。
春頃と秋頃には追肥をしますが、活動活発になり始める3月頃に粒状肥料などを施していくとよいでしょう。草花用の液体肥料を1500~2000倍くらいに薄めて施す方法もあります。真夏に使用する場合はさらに薄めた方がよいとされています。
増やし方や害虫について
ゲラニウムの増やし方には株分けと種まきとがあります。株分けをおこなう場合は、植え替えをおこなう時期におこないます。地下茎から不定芽を出して子株をつくるアケボノフウロなどは、古株になると中心部分が枯れてきてしまいますので3年くらいを目安に株分けをすることがおすすめです。
根を切ってしまわないように掘り上げて土を軽くはらあってから自然に分かれている部分で分けていきます。根茎がつながっている場合でも、それぞれの芽に根がついているのであればナイフなどでカットして分けていくこともできます。
株分けをおこなう場合は、1株に3から5芽がつくようにしてカットするようにしてください。根茎というのは、根のように地中をはって根の節から根や芽を出す部分のことを言います。種まきをする場合は、採種したものを保管しておいて3月上旬頃にまいていきます。
皮が厚いためそのままの状態では発芽率が悪いため、種の一部を白い部分が見えるくらいに剥皮処理しておくことがおすすめです。順調にいけば2年目くらいに開花します。主な病気として軟腐病、うどんこ病が挙げられます。水はけのよい用土に替えたり、
茎の付け根部分から上部を粗目の砂利で覆うことで予防することができます。うどんこ病が発生してしまった場合は、できるだけ早目に葉を取り除いていきましょう。害虫はヨトウムシ、アブラムシ、ハダニが発生することがあります。夏場にハダニが発生してしまうと重症化してしまいますので注意しましょう。
ゲラニウム(高山性)の歴史
高山性ゲラニウムの学名は、ゲラニウム・ロザンネイです。別名でフクロウソウとも呼ばれている宿根草で、世界にはおよそ400種類ほどもあるとされています。ゲラニウムは英語の発音でゼラニウムと呼ばれることがあります。ゲラニウムという学名は、もとはギリシャ語の鶴という言葉に由来しています。
長いくちばし状の果実を鶴のくちばしに例えられたとされています。種小名は、草原の、草原に育つの意味があります。原産地にはヒマラヤから中国南西部やヨーロッパなどが挙げられます。生息地として日本も挙げられ、古くから山野草として栽培されてきました。
日本で自生している原種には、アサマフウロ、エゾフウロ、イヨフウロ、グンナイフウロ、チシマフウロ、ビッチュウフウロなどが挙げられます。外国の原種で育てやすいとされているのがアケボノフウロやクロバナフウロ、シボリザキフウロ、ダルマティクム、シネレウムなどがあります。
耐暑性が強い種類にはアケボノフウロやクロバナフウロ、カンタブリギエンセ、シネレウムなどさまざまなものがありますが、アケボノフウロは特に性質が強いとされています。園芸ショップなどではヨーロッパやアメリカなど、
外国で改良された品種も多く販売され取り扱われています。ゲラニウムジョンズブルーと呼ばれている種類は、ゲラニウムヒマライエンセ種とノハラフウロ種との交雑によって作り出されたものです。色鮮やかなブルーの花が美しいです。
ゲラニウム(高山性)の特徴
ゲラニウムにはさまざまな種類がありますが、栽培されている大部分が株立ちになり茎を伸ばしていきます。ブッシュ状に株が茂りますので花壇の手前に配置することが好ましいです。ブッシュ状というのは、地際から何本か枝を出して高さが2メートルを超えない樹木のことを言います。
草丈は20センチメートルから80センチメートルほどになります。ゲラニウム・パトリシアという種類は、鮮やかなピンクに黒い花芯が美しいのが特徴です。ゲラニウム・ブラッシング タートルは、ピンクに濃筋の大輪花が開花します。開花時期が長く春頃から秋頃まで咲き続けるとされています。
ゲラニウム・ジョンソンズ ブルーは、美しい青花で秋の葉の紅葉も美しく人気があります。雨風で倒れやすいため、まとまりのある株にはなりにくいです。ゲラニウム・サンギネウムは、ヨーロッパ原産の原種で、乾燥や暑さにも強いとされています。
濃い赤紫色の花が、初夏頃になると株を覆うようにして開花します。まめに花柄を摘んでいくことによって、その後も花を咲かせます。ゲラニウム・サマースカイは、ヨーロッパ原産で晩春に細い花茎が長く伸びて先端部分に小さな花をたくさん咲かせます。
茎が分岐しやすく秋頃まで花を咲かせ続けます。花の色は紫ピンクで小さい花ではありますが、株は大きくて存在感があります。ゲラニウム・ヒマライエンセは、春の終わり頃に花茎の先に青紫色の花を咲かせます。花付きがよいですので満開の際はとても見事です。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:パンジーゼラニウムの育て方
タイトル:ゲンペイカズラの育て方
-

-
タイムの育て方
学名はThyme、分類はシソ科イブキジャコウソウ属に当たります。高さおよそ15センチメートルから40センチメートルほどに...
-

-
ミニヒマワリの育て方について
一言で「ミニヒマワリ」といっても、品種改良が行なわれ、中小輪の矯性品種まで、数多くのミニヒマワリが存在しています。大きな...
-

-
ひまわりの育て方
ひまわりはきく科に属し、日輪草(ニチリンソウ)や日車(ヒグルマ)と言う別名を持ちこれは、ひまわりが日輪のように見えること...
-

-
レモンの育て方
レモンの原産地や生息地はインドのヒマラヤ地方とされ、先祖とされている果物は中国の南部やインダス文明周辺が起源です。そして...
-

-
クロガネモチの育て方
クロガネモチの原産地は、日本の本州中部から沖縄、朝鮮半島南部、台湾、中国中南部、ベトナムなどです。もともと日本に自生して...
-

-
植物や果物を育ててみませんか
仕事や行事などで毎日が忙しく、たまに休みがあったとしてもやりたい趣味活動がなかなかないという人も最近ではよく見かけること...
-

-
ソレイロリアの育て方
特徴としては、イラクサ科の植物とされています。常緑多年性の草になります。草の高さとしてはそれ程高くなりません。5センチぐ...
-

-
カラスウリの育て方
被子植物に該当して、双子葉植物綱になります。スミレ目、ウリ科となっています。つる性の植物で、木などにどんどん巻き付いて成...
-

-
ヒヨドリジョウゴの育て方
ヒヨドリジョウゴの特徴は外観と有毒性が挙げられます。外観に関して、白い毛が生えています。現物を見た人や写真を見た人の中に...
-

-
金のなる木の育て方
金のなる木は和名をフチベニベンケイ(縁紅弁慶)といいますが、一般にはカネノナルキ、カゲツ(花月)、成金草、クラッスラなど...




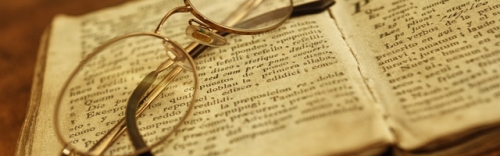





高山性ゲラニウムの学名は、ゲラニウム・ロザンネイです。別名でフクロウソウとも呼ばれている宿根草で、世界にはおよそ400種類ほどもあるとされています。ゲラニウムは英語の発音でゼラニウムと呼ばれることがあります。