カタクリの育て方

カタクリの育てる環境について
日本におけるカタクリの生息地は、北海道から九州の各地であり、朝鮮から中国などの地域にも多く分布する多年生の植物です。片栗粉の原料でも有名ですが、原料としての植物の量が少ない事からも貴重価値が高いと言われています。
また、綺麗な色の花を咲かせることからも観賞用として栽培する人も多く人気の植物の一つになります。尚、育てる環境については日当たりが良い環境を好むと同時に、落葉広葉樹林の林床に偶成している事からも、育てる環境はこれらを踏まえた場所を選ぶ事がポイントとなります。
また、発芽1年目のカタクリは、細い糸状の葉をつけ、2年目から7、8年までの間は卵状をした楕円形の一枚の葉だけで成長をし、鱗茎が大きくなることや、二枚目の葉が出てから花が咲くなどの特徴が有ります。更に、初夏に入ると葉を落ちて夏眠の状態になるのも特徴で、1年を通して春の数ヶ月のみと言う特徴も有ります。
育て方のポイントは、鉢植えの場合は10号くらいのサイズの深い鉢を利用したり、通気性の良い山草鉢を利用すると成長を促すことが出来ます。また、夏場は日陰で栽培をし、温度が上昇しないように管理を要します。自然環境の中で自生するものは、落葉樹などの下草として自生しているため、
直射日光の当たるような環境を嫌いますので、夏場の暑い時期などは出来る限り日陰での栽培がお勧めです。理想な環境としては、葉が開いている時期は、半日ほど日陰の場所で栽培をし、葉が枯れてしまって球根だけの時は日陰になるような場所だと言われています。
カタクリの種付けや水やり、肥料について
植え付けを行う時期は、8月頃から9月頃が最適であり、この時期に植え付けを行う事で新しい根が成長を促すことが出来るからです。また、鉢植えの場合の鉢の置き場所と言うのは季節により変える事が大切で、その都度管理を徹底する事が重要です。
暑さがやや収まる9月から翌年の5月の中旬頃までは太陽の光が当たる場所に置いておいて、鉢の中の土の乾燥を見ながら適量の水を与えます。また、これ以外の時は常に日陰に置くことを心がけることが大切で、真夏に太陽の真下などにおいておくと枯れてしまうので注意が必要です。
但し、地上部分は枯れた場合については日当たりが良い場所に出しても平気なので、枯れたら日当たりの良い場所にと考えておけばよいのです。しかしながら、暑さには滅法弱いと言う特徴が有りますが、寒さについてもそれほど強いわけではありません。
特に真冬の寒い時期などは、地植えを行っている時など、地面を落ち葉などを利用して覆ってあげるなど、自然環境で自生をしているものと同じような環境を作り出してあげる事が大切で、これにより綺麗な花が咲くことになります。また、鉢植えの場合などはそのまま外に放置するのではなく、軒下などにおいてあげて管理をします。
そのため、鉢植えは生育サイクルを考えてその都度置き場所を変えてあげて、なるべく自然環境に近い状態で栽培をしてあげる事が大切です。春先になると葉が開き、夏には葉が茂り、そして冬に落葉すると言った樹木の下などに地植えを行うと良いと言われています。
カタクリの増やし方や害虫について
植え付けを行う場所に、腐葉土と言った有機質が含まれている土を入れて耕しますが、鉢植えの場合では赤玉土を4、荒砂や軽石の小粒のものを4、腐葉土を2の割合で混ぜた用土を作り鉢の中にいれて植えつけます。また、水はけはとても重要な要素であり、どのような土を使う場合でも水はけを持つ土を選ぶ事が大切です。
尚、カタクリは湿り気を持つ土を好みますが、これは自生している環境が落葉樹の葉の中に自生するからであり、適度な湿気を与えるためにも水やりは大切です。3月から5月にかけては1日に1回、6月から10月にかけては3日に1回ほど水を与え、これ以外の時期は1週間に1回ほど水を与えてあげて自然環境に近い状態にします。
因みに、湿気が起きる事でナメクジが寄り付きますので、これを防除する事が大切です。また、常にじめじめした状態にしてしまうと、ナメクジが寄り付くだけではなく、球根が腐る事も在るため過湿には注意が必要です。これは、球根部分は表面に皮が殆ど無く裸の状態になっているからで、乾いたら水を与えると言う形で水やりを行うようにします。
更に、花は繊細であり、傷みやすい部分です。そのため、開花している時期の水やりと言うのは株元に水を与える事が大切です。肥料については、冬から春の開花の際に、根が一番旺盛に生長するため、このタイミングで追肥を施します。尚、種が出来る事も在りますので、この場合は種を採取してから種まきをすることで増やすことが出来ます。
カタクリの歴史
カタクリは従来片栗粉の原料として利用されていた植物であり、現在でも片栗粉の原料として利用されていますが、希少性が高い事や一度に採れる量が少ない事からも、現在市販されている片栗粉と言うのは、ジャガイモやサツマイモと言った野菜から抽出されるデンプンを利用して製造が行われており、
カタクリを利用した片栗粉は貴重な物と言われています。カタクリは、ユリ科カタクリ属に属する多年草であり、国内においては北海道から九州など幅広い地域が生息地になっており、中国や朝鮮などにも生息しています。因みに、古語の中では「堅香子」と呼ばれていると言います。
以前は、日本各地にある落葉広葉樹林の在る場所で見られたと言いますが、乱獲、盗堀、土地の開発などにより生育地が減ったなどの理由からも減少傾向にあると言います。ユリ科に属すると言うカタクリ属は、ユーラシア大陸の中の大陸温帯域地域に4種類、
北米大陸地域に20種類が生息していると言います。そのため、片栗の花と言うのは種類に応じて黄色の花、ピンク色の花、白い色の花、赤い色の花などが有ると言われており、鑑賞用としても人気が高いとされます。また、日本や朝鮮半島、中国などが原産だと言われていますが、
歴史の中では万葉集の歌にも登場しており、古い時代から存在している植物だと言う事が解ります。尚、万葉集の歌に登場するのは「かたかご」と呼ばれるもので、「かたかご」と言うのがカタクリに相当するのだと言います。
カタクリの特徴
球根部分の形状が栗を半分にしたような形になっているのが特徴と言えますが、花後に出来る果実が栗の実の一つに似ている事からもカタクリと言う呼び名がついたのではないかと言われています。また、日本を生息するカタクリは中央アジアからシベリアにかけて分布するものと似ていると言われています。
尚、カタクリは日本全国に分布すると同時に、世界各国にも分布しているのが特徴ですが、近年、その量は減少傾向にあり、人工的に増殖を行って山林や野原などに植林させる試みが行われていると言います。また、春を告げるスプリング・エフェメラルの人である事、
春先には斑の入った葉をつくりだし、薄紫色、ピンク色、赤色、黄色など様々な色の花を下向きの状態で咲かせるなどの特徴が有りますが、花の色と言うのは種類により様々であり、この色を楽しみたい人の中には観賞用として栽培を行う人が多いのです。
3月頃から4月にかけて地上部分を展開して、5月の上旬頃には葉や茎部分は枯れてしまうのも特徴です。しかし、枯れた場合でも植物は生きており、翌年には再び芽を出して綺麗な花を咲かせると言う多年草です。
因みに、多年草と言うのは1つの個体が複数年にわたり生存する植物であり、一度植え付けを行う事で毎年綺麗な花を咲かせることが出来るものであり、鑑賞用として利用する場合には毎年綺麗な花を観賞できると言うメリットが有ることからも、カタクリを栽培したいと言う人が多くいるのです。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ジョウロウホトトギスの育て方
タイトル:シバザクラ(芝桜)の育て方
-

-
グリーンカーテンの栽培方法。
地球は温暖化の一途を辿っています。日本では、温暖化対策の1つとして、グリーンカーテンを導入している家庭や市区町村が増えて...
-

-
ギンバイカ(マートル)の育て方
ギンバイカはフトモモ科ギンバイカ属の低木常緑樹です。ギンバイカは和名になり、漢字では「銀梅花」と書きます。これは開ききる...
-

-
カラテア(Calathea ssp.)の育て方
カラテアの名前はギリシャ語のかごという意味があるカラトスが由来となっています。これは南アメリカの先住民達がカラテアの葉を...
-

-
シモバシラの育て方
学名はKeiskeaJaponicaであり、シソ科シモバシラ属に分類される宿根草がシモバシラと呼ばれる山野草であり、別名...
-

-
トウガラシの育て方
トウガラシの原産地や生息地は中南米で、メキシコでは数千年前から食用として栽培や利用されていたのです。このことから中南米や...
-

-
イチリンソウの育て方
イチリンソウは日本の山などに自生している多年生の野草でキンポウゲ科イチリンソウ属の植物です。元々日本でも自生している植物...
-

-
ピラカンサの育て方
ピラカンサは英名でファイアーソーンといいます。バラ科トキワサンザシ科です。ラテン語のままでピラカンサとされている場合もあ...
-

-
ネコノヒゲの育て方
このネコノヒゲの特徴は、何と言ってもピンと上を向いた猫の髭の様な雄しべと雌しべではないでしょうか。髭の様な雄しべと雌しべ...
-

-
ハーデンベルギアの育て方
ハーデンベルギアはオーストラリア東部に位置するタスマニアが原産のツル性の常緑樹で、コマチフジ・ヒトツバマメ・ハーデンベル...
-

-
ニホンズイセンの育て方
特徴において、種類はクサスギカズラ目、ヒガンバナ科、ヒガンバナ亜科になっています。多年草ですから、一度避けばそのままにし...




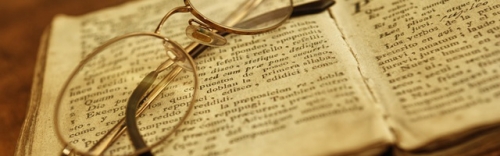





カタクリは従来片栗粉の原料として利用されていた植物であり、現在でも片栗粉の原料として利用されていますが、希少性が高い事や一度に採れる量が少ない事からも、現在市販されている片栗粉と言うのは、ジャガイモやサツマイモと言った野菜から抽出されるデンプンを利用して製造が行われており、カタクリを利用した片栗粉は貴重な物と言われています。