ナズナの育て方

育てる環境について
ナズナは、ユーラシア原産の越年生雑草で、その生息地は日本全土・北半球に分布しています。種子の伝播は主な理由として風雨、動物や人間などによるとされています。元々はムギ栽培の伝来と共に、日本に渡来した史前帰化植物と考えられています。その種子は結実落下後、約数ヶ月で発芽が可能な状態になります。
発芽適温はおおよそ10から25℃で、一般に秋に発生します。ただし条件さえ合えばそれ以外の季節でも発芽する場合があります。発生深度は比較的浅く、土壌中での種子の寿命は比較的長い植物です。茎は直立して高さ10から50センチに生長します。また茎葉部分は披針型で基部が茎を抱き、ロゼットは一般に有柄で葉が羽状に深く切れ込みが入ります。
また茎につく果実がハート型をしているのも特徴す。基本的に土壌の種類は選びません。日当たりが良い肥沃地を好みますが、日陰や冷涼な気候、やせた土地にも耐えることができます。日本中の畑や水田、道端、荒れ地などに普通に見ることができます。またゴルフコース等ではフェアウェイやラフに発生しやすいです。
その性質の頑強さ故、「ぺんぺん草が生える」というような表現もある程です。これはナズナが荒廃した土壌であっても生育することから、その土地が荒れ果てた様子を指す言葉です。逆に「ぺんぺん草も生えない」という言い回しもあって、これは荒廃した場所で育つナズナでさえ、生育しない様子から、何も残っていない状態を揶揄した表現で、例えば「○○が通った後はぺんぺん草も生えない」のように使われます。
種付けや水やり、肥料について
種まきと挿し芽で増やす事ができます。土は2ミリ程度と薄くかけ乾燥しないように適宜水をやります。一ヶ月くらいで発芽するようです。室内におけるナズナの発芽では、種を採取した直後の休眠状態の種子を、戸外畑土中に1~3ヵ月間貯蔵することで休眠が覚醒されるようになります。
こうすることで低温湿潤土中に貯蔵した種子よりも高い発芽率が期待できるようになります。種の採取時期によって、この休眠覚醒の時期が異なってきますが、温度条件については10℃から25℃が最も発芽率が高いと言われています。屋外の場合、採取直後の種は、雨の多い時期に出芽率が高くなる傾向が見られます。
種まき後に人為的な土壌を攪乱すると、出芽率が高くなると言われています。ロゼットと呼ばれる根生葉で越冬します。生育期間は一般に11月から6月で、秋頃に発生して冬を越し、翌年の春の早い時期からから生長を再開します。その後2月から6月頃に花柄を伸ばし茎の先に花を多数つけます。開花後6月頃には生育を終え枯死します。なお冬の極寒期でも条件によっては開花することがあります。
ベランダや室内で育てる場合には、日当たりと水はけのよい環境を作ってあげるようにします。基本的に頑強な植物ですが、あえて言えば高温多湿に弱いので、花壇に植える場合は夏は半日陰になるところを選びます。鉢植えも、夏は風通しのよい半日陰で管理します。肥料は植え付けをする時に緩効性肥料を与える程度でよいでしょう。与えなくても問題はありません。
増やし方や害虫について
育て方がとしては、挿し芽や水耕栽培で増やす事ができます。挿し芽の場合、花が終わってから、先端部分をハサミで切って、バーミキュライトに挿しておきます。夏場に挿し芽をすると、暑さのせいかぐったりしてほとんど根がでないことがあるので、9月頃まで待って一旦気温が落ち着いてからするのが良いでそう。
水耕栽培の場合、水耕栽培液を用いたロックウール上での栽培法が良いでしょう。最初に水でぬらした濾紙上で種子に亀裂が走り、根の先端が見えるまで待って発芽させます。その後に、水耕栽培液に浸したロックウールに移し、生育に合わせて大きな容器に移して行くようにします。
発芽してから双葉が展開するまでに普通より少し時間がかかりますが、根がしっかりとロックウールに食い込み、成長するようになってきます。基本的に病害虫についてはあまり心配する必要はありません。強いて言えば、うどんこ病に注意するようにします。症状としては、最初は地際部の下位葉の表面に小さな白い粉がみえ、次第広がっていくようになります。
発病は下位葉から、次第に上位葉に広がり、激しく発病した葉は黄変し、最終的に枯死してしまいます。このような場合には、発病初期を見逃さずに、薬剤散布することで対処することができます。害虫としてはアブラムシが発生することがあるので、これも早めに取り除くか薬剤散布によって対処するようにしましょう。予防のための方法としては、窒素肥料の多用をさけ、風通しをよくしておくことが大切です。
ナズナの歴史
ナズナは春の七草の一つとして広く知られている植物です。春の七草のひとつで、秋頃に芽が生え、早春に咲き始めます。漢字では「薺」と書きますが、これは「撫菜」(なでな)が段々と変化してきたものであると言われています。撫菜は、撫でたいほどかわいい植物という意味です。
また他にも夏に枯れて無くなることから「夏無(なつな)」が変化したものだとも言われています。他にも風で揺れたり、手で振って揺らしたりすると音がすることから「ペンペン草」とか、実が三味線の撥(ばち)に似ているから「三味線草」と呼ばれることもあります。春の七草の一つで、若苗を食用にします。昔は冬の貴重な野菜でもありました。
また薬草としても世界各地で知られており、幅広く利用されている植物の一つになります。中国においては止血剤として、ヨーロッパでは通風、赤痢として利用されてきました。日本における薬草の古典を著した貝原益軒は『大和本草』で、「天は世を捨て暮らしている人の為にナズナを生じた」とまで書いています。
特にサラダとしての利用は世界的にもよく知られているものとなっています。七草粥をはじめサラダ、浸し物や和え物、お吸い物、炒め物などに使われています。日本において昔から人々に愛されてきた植物でもあり、多くの俳句や和歌などにも登場してきます。有名どころでは松尾芭蕉が「よく見ればなづな花咲く垣根かな」、与謝蕪村が「妹(いも)が垣根三味線草の花咲きぬ」と詠んでいます。
ナズナの特徴
植物分類としては、アブラナ科のナズナ属となります。高さは20から40センチで、花の時期は2月から6月にかけて。ロゼッタ状の葉の中心から茎を伸ばしてその先に沢山の花をつけます。4枚の白い花弁を持つ直径3ミリほどの小さな花を多数、花穂に付けます。次々に花を咲かせる無限花序で、下の方で花が終わり、新たに種子が形成される間も、
既に先端部では次々とつぼみを形成して開花していきます。果実は特徴のある軍配型になっています。これはだんだんと膨らんで2室に割れて種子を散布します。こぼれ落ちた種子は、秋頃になると芽生えはじめ、ロゼットで冬を越すようになります。越年草、または一年草です。
民間薬として陰干ししたのちに煎じたり、煮詰めたり、黒焼きにしたりすることによって、薬用に利用されることがあります。血圧降下作用のあるコリン・アセチルコリンや、血管壁を強化する働きのあるルチン・フラボノイドの他、フマル酸・バニリン酸・スウェルチシン等の栄養成分が豊富に含まれています。
薬効としては、高血圧の予防や動脈硬化の予防・利尿作用・便秘解消・止血作用・胃潰瘍の予防・十二指腸潰瘍の予防等が知られています。昔から、春の七草として、七草粥に利用されることが多いですが、料理方法やレシピとしては、
青臭さが少なくタンパクながら甘みの強いナズナは、サラダ等にも簡単に利用することができます。基本的には全体を細かく刻んで料理に使うようにすると良いでしょう。葉や茎は湯がいておひたしや和え物や味噌汁に使えます。
-

-
クヌギの育て方
クヌギは広葉樹の一つあり、かつてはツルバミとも呼ばれていた樹です。またコナラとともにカブトムシ、クワガタムシといった昆虫...
-

-
ロウバイの育て方
強い香りをあたりに漂わせ、どの樹木よりもいち早く春の訪れを告げる花ですが、江戸時代の終わり頃に、中国から朝鮮半島を経て伝...
-

-
ハーブを種から巻いて大きくしよう
ハーブは日本語で香草といい、ハーブの種類によって香りの高いものなど様々あります。料理やハーブティーに使えてとても利用効果...
-

-
家で植物を育ててみましょう
植物はそこにあるだけで人を癒してくれます。緑は安らぎ、穏やか、やさしさなどを想像させ、またマイナスイオンによる空気浄化効...
-

-
上手な植物の栽培方法
私たちが普段生活している場所では、意識しないうちに何か殺風景だなとか、ごちゃごちゃ物がちらかっているなとかいう、いわゆる...
-

-
ライスフラワーの育て方
ライスフラワーの特徴として、種類としてはキク科、ヘリクリサム属になります。常緑低木です。草丈としては30センチぐらいから...
-

-
ホオズキの育て方
ホオズキは、ナス科ホオズキ属の植物です。葉の脇に花径1~2センチ程度の白い五弁花を下向きにつけるのが特徴です。同じナス科...
-

-
ヒトリシズカの育て方
ヒトリシズカは原産地や生息地が日本を含め、中国や朝鮮半島です。栽培するのは5段階中でいえば4で、かなり難しいといえるでし...
-

-
ニンジンの育て方
ニンジンはセリ科の一種であり、この名前の由来は朝鮮人参に形が似ていることからつけられたものですが、朝鮮人参はウコギ科の植...
-

-
トウワタの育て方
トウワタ(唐綿)とは海外から来た開花後にタンポポのような綿を作るため、この名前が付けられました。ただし、唐といっても中国...




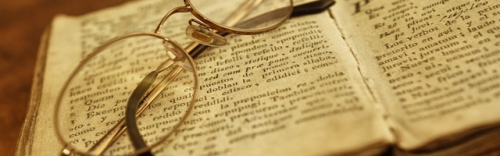





植物分類としては、アブラナ科のナズナ属となります。高さは20から40センチで、花の時期は2月から6月にかけて。ロゼッタ状の葉の中心から茎を伸ばしてその先に沢山の花をつけます。4枚の白い花弁を持つ直径3ミリほどの小さな花を多数、花穂に付けます。