カリフラワーの育て方

カリフラワーの種付けと苗の植え付け
カリフラワーの種付けは春まきと夏まきがあり、春まきなら2月中旬から3月中旬、夏まきなら7月中旬から8月中旬の間に行います。育苗ポットを利用し、土を詰めて一か所当たり5、6粒ほど種をまきます。
種付け後は十分水を与え、乾燥を防ぐために発芽するまでは新聞紙などで覆っておくとよいでしょう。種が発芽したら新聞紙を取り除きます。本葉が2枚になれば、苗が2本になるように一回目の間引きをします。
次に本葉が3、4枚になればもう一度間引きをして苗を1本にします。本葉が5、6枚になれば畑やプランターに植え付けをします。苗を植え付ける場合にはまず土つくりから始めます。植え付けの2週間前までに苦土石灰を1㎡当たり100gから150g散布してよく混ぜておきます。
畝幅は約60cm、畝の中心に深さ20cmの溝を掘って、そこに1㎡当たり2kgの堆肥と1㎡当たり100gの化成肥料を入れて土を戻しておきます。土を盛り上げて10cmくらいの高さの畝を作ります。
プランターなら60cmくらいの深さのものを選びます。土は市販の培養土を使用してもよいでしょう。苗はポットからそっと出し、20cmから30cm程度の間隔をあけて土に定植をします。その時に子葉が地上に出る程度に浅く植えることがポイントです。
カリフラワーの栽培中の注意点
定植後は水をたっぷり与え、苗が成長する間は土の表面が乾いてきたころにたっぷりと水を上げるようにします。カリフラワーは乾燥に弱いので、夏の気温が高いときに種付けした時には乾燥しないように十分に水やりを行うようにします。
乾燥を防ぐためにわらなどを敷く方法もあります。また寒冷紗をかぶせることによって害虫や夏場の暑さから防ぐこともできます。カリフラワーはアブラナ科で青虫が付きやすいので、隙間から入ってこられないようにかぶせることもうまく栽培していくためのコツになります。
そして育て方のポイントとして肥料の与え方があります。カリフラワーは多肥性の野菜なので、肥料を切らすことがないように栽培することが大切です。一回目の追肥は本葉が10枚くらいになったころに行います。一つの苗に3gほどの化成肥料を与えます。
苗と苗の間にも肥料をまいて軽く土と混ぜ、苗に土寄せをしておきます。それ以降も3週間おきくらいに同じような追肥を行います。栽培期間を経て花蕾が大きくなり始めたら黄色く変色しないように遮光をするようにします。遮光の方法は外葉でくるむことです。
そうすることで日光を遮るだけでなく雨などによる汚れや傷も防いでくれきれいなカリフラワーができるのです。収穫時期は花蕾ができて早生なら15日程度、中生なら30日程度となります。花蕾が15cmくらいの大きさになったころが収穫のタイミングです。収穫するときには外葉を5、6枚つけたまま根元を切り取るようにします。
カリフラワーの育て方のポイントとまとめ
カリフラワーは花蕾ができるまでに外葉を大きく成長させることにポイントがあります。葉が大きいと花蕾も大きく成長するからです。そのためには定植をするときに間隔をしっかり開けておくこと、水をしっかりあげて乾燥をしないように注意すること、肥料を絶やさないこと、花蕾ができてきたら寒冷紗を利用し遮光をし、害虫から守ることが大きくてずっしりとしたカリフラワーの育て方のポイントです。
カリフラワーの発芽の適温は20度から25度、生育の適温18度から20度で、花蕾の適温は15度から18度となっています。そして平均気温が25度以上になると花蕾の生育状態が悪くなるので、初心者の場合は春まきより夏まきのほうが、種付けの時に気温が高く生育時には気温が下がってくるので良いでしょう。
もともとカリフラワーは低温に弱く、暖かい地方や夏に栽培されていましたが、耐寒性に強いキャベツとの交配によって冷涼なところでも栽培が可能な品種が改良されてきました。またブロッコリーとは違って結球が密集し白雪を思わせるような姿がブロッコリーよりも珍重されブロッコリーよりは高い値段で市場では売られています。
カリフラワーにもいろいろな品種があり、定番の白いものでは「スノークラウン」「ホワイトパレス」「バロック」「ミニカリフラワー」などがあり、種を購入するときに初心者向けや中級者向けなどといった目安も記してあるので、自分に合ったもの、または栽培する時期に合ったものを購入し栽培を始めてみるとよいでしょう。
ゆでてそのまま塩コショウやマヨネーズ、ドレッシングなどで食べたり、甘酢で和えたり、グラタンやカレー、シチューに入れたり、炒めものにしたりと料理でも利用法もたくさんあります。
ブロッコリーに比べて市場には出回りにくいカリフラワーですが、これらのように上手な育て方のポイントを押さえて家庭菜園で挑戦してみると、ブロッコリーとは違った食感と味がするカリフラワーを使った料理がいろいろと楽しめます。
カリフラワーの歴史
カリフラワーはブロッコリーが突然変異で白くなったもので、原産地は地中海沿岸です。ブロッコリーと同様野生のカンランから派生したといわれています。15、16世紀には南ヨーロッパで重要な野菜となり、18世紀にはヨーロッパの北部にも普及し、19世紀にはアメリカやアジアにも伝えられ、日本には明治時代の初期に伝えられました。
しかしあまり普及はせず、第二次世界大戦後に洋風文化の広まり、白いアスパラガスとセロリとともに「洋菜の三白」といわれて洋食に上るようになってきました。しかし1980年以降健康志向となるにつれ、緑黄色野菜の栄養価の高さが認識されるようになりカリフラワーよりもブロッコリーが好まれるようになり、最近では生産量もブロッコリーがカリフラワーの約8倍にも上るようになりました。
こちらのセロリの育て方も詳しく書いてあり、凄く参考になります♪
それでもカリフラワーのさくっとした歯ごたえと独特のやさしい甘みが好まれ、旬の時期には市場でもよく出回っています。
カリフラワーの特徴
ブロッコリーと同じでアブラナ科のキャベツの仲間です。花野菜で花のつぼみの部分を食用にしているのです。栄養素もブロッコリーと同じビタミンCを含んでいてその含有量はブロッコリーのほうが多いものの、ゆでれば壊れてしまうのですが、カリフラワーはゆでてもビタミンCの成分が壊れないので、「畑のレモン」といわれるほどです。
日本では白が主流ですが、オレンジ色や紫色のものもあり、紫色のものはゆでると薄緑色になります。オレンジ色のものは「オレンジブーケ」、紫色のものは「バイオレットクイーン」などの名前が付けられていてこのようなカラーのものも人気が高まっています。
現代の日本の生息地で一番収穫量が多いのが徳島県で、全国の10.8%です。次いで、愛知県、茨城県となっています。旬は11月から3月ごろで、選ぶときにはつぼみの部分が白く、こんもりしていてずしりと重みのあるもの、そして周りの葉が青々としているものを選ぶとよいでしょう。
ゆでるためのコツもあります。柔らかくゆでたいときには塩を少し入れてゆで、形を崩さずにゆでたいときにはゆで汁に酢かレモン汁を「入れるとよいでしょう。またビタミンCの損失を少なくし、甘みを生かし、ゆで時間を短縮するために小麦粉を入れtゆでることもあります。
カリフラワーは民間療法の薬用としてもつかわれることがあります。風邪を引いたときにはレンコンと一緒にすりおろしたものをガーゼや付近に包んで絞り、はちみつを入れて飲んだり、レタスと一緒に煎じて飲むことで整腸作用もあるのです。
下記の記事も凄く参考になりますので、見て下さい♪
キャベツの育て方
白菜の育て方
-

-
ルバープの育て方と注意点とは。
ルバープは和名をショクヨウダイオウといい、シベリア南部地方原産のタデ科の多年草です。大型の植物で高さは1メートル以上にな...
-

-
マツムシソウの育て方
マツムシソウは科名をマツムシソウ科と呼ばれており、原産地はヨーロッパを中心にアジア、アフリカもカバーしています。草丈は幅...
-

-
キウイフルーツの育て方
キウイフルーツは、中国にある長江中流地域の山岳地帯から揚子江流域を原産地とする植物です。1904年に中国からニュージーラ...
-

-
カリブラコアの育て方
カリブラコアは南米原産です。1825年にメキシコの植物学者であるセルバンテスとヴィンセンテによりナス科カリブラコア属が新...
-

-
カシワバアジサイの育て方
カシワバアジサイは古くからアジサイ類の仲間として広く親しまれてきました。日本でも奈良時代後期の万葉集にアジサイのことが詠...
-

-
ミナ・ロバータの育て方
花の種類としては、ヒルガオ科、サツマイモ属、イポメア属とされることもあります。さつまいもの仲間であるようです。園芸上の分...
-

-
ウスベニヒゴスミレの育て方
ウスベニヒゴスミレはガーデニングでも適した植物と言われていて、専門家も性質も強く園芸的にも優れていると太鼓判を押している...
-

-
マツカゼソウの育て方
松風草は、一般的には、マツカゼソウと表記され、ミカン科マツカゼソウ属に属しており、東アジアに生息するマツカゼソウの品種と...
-

-
リパリスの育て方
特徴としては、被子植物になります。ラン目、ラン科、クモキリソウ属に該当します。ランの種類の一つとされ、多年草としても人気...
-

-
トウワタの育て方
トウワタ(唐綿)とは海外から来た開花後にタンポポのような綿を作るため、この名前が付けられました。ただし、唐といっても中国...




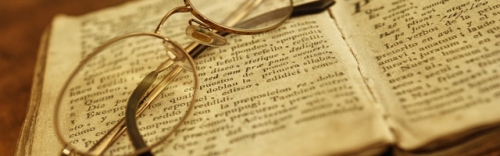





カリフラワーはブロッコリーが突然変異で白くなったもので、原産地は地中海沿岸です。ブロッコリーと同様野生のカンランから派生したといわれています。15、16世紀には南ヨーロッパで重要な野菜となり、18世紀にはヨーロッパの北部にも普及し、19世紀にはアメリカやアジアにも伝えられ、日本には明治時代の初期に伝えられました。