さやいんげんの育て方

さやいんげんの育て方のポイント
さやいんげんの育て方でポイントとなるのは、1つ目に栽培に適した温度です。適温とされているのは15度~25度で、25度を超えてしまうと、せっかく花が咲いても落ちてしまうことがあります。
さやいんげんには暑すぎない温度で花を開花させることが重要となります。2つ目に長期間収穫をするので、根群を深く張らせなければなりません。よって、土を深く耕して柔らかい土づくりをしましょう。マメ科の作物の根には、根粒菌という菌が共生して根粒を形成します。
この菌は、さやいんげんから栄養をもらう代わりに、チッソを与えてくれます。そのため、痩せている土でも長期にわたり収穫が出来るというわけです。3つ目にマメ科の作物は、非常の多くの肥料を必要とするので、肥料を切らさないことが育て方のポイントになります。では、さやいんげんを実際に栽培方法を確認していきましょう。
基本的なポイントと種付け
まずは畑を作りましょう。種付けを行う1週間~2週間前を目安に、土を中和させる作用がある苦土石灰を1㎡当たり100g程度まいてよく耕しておきます。そして1週間後に堆肥を1㎡当たり2kg、化成肥料(野菜専用などもあります)を1㎡当たり120gまいてしっかり混ぜ込みます。
そして、高さが10cm程度の平らな畝を作ります。その後種付けをしていきます。種を蒔く時期は4月中旬~6月中旬が最適なので、種付け時期から逆算して土作りを始めましょう。つるあり品種は、1条植えでの育て方が良いでしょう。株の間隔はおよそ40cmにします。
種は、1か所に付き3粒ずつ蒔いていきましょう。つるなし品種は、2条植えで育て方ができます。株の間隔はおよそ30cmにします。種は、1か所に付き4粒ずつ蒔きましょう。どちらも蒔き終えたら、2cm程度の土を軽く被せてたっぷり水を与えましょう。種付け直後は、鳥の食害を受けやすいので、不織布などで覆ってあげると良いでしょう。
土が乾いたら水を与えるようにして発芽を待ちます。発芽して本葉が2枚になったころに、生育の良い株を、1か所に付き2株残して間引きを行い、土を株元へ寄せておきます。この時、つるあり品種は株と株の間に支柱を立て、ネットを張ります。つるなし品種も、倒れるのを防ぐと共に枝を広げやすくするため、低めの支柱を畝の両端と中間にたて、ネットを表土と平行に張ります。
花が咲いてきたら、2週間に1回のペースで即効性のある液肥を与えましょう。水で500倍に薄め、水やりの代わりとして与えます。この頃は梅雨の時期にもなるので、泥はねを防止するのと乾燥を防ぐため、わらを敷くと良いでしょう。
さやいんげんの収穫と病害虫について
種まきから2か月~3か月ごとに、化成肥料を1㎡当たり120g程度株元へまいて追肥を行います。開花して、およそ10日~15日経つと、さやが10cm以上に成長してきます。長さが12cm~13cm程度になったら収穫します。
この長さで収穫すると、さやもやわらかく、味にも甘みがありとても美味しいです。収穫時期を過ぎたさやいんげんは、中の種子が大きくなりすぎてさやが凸凹してきます。また、味も若い時期と比べて落ちてしまいます。花が開花すると次々と実ってくるので、肥料を切らさないようにしましょう。
病気と害虫にも気を付ける必要があります。病気は、特に雨の多い梅雨時期に発生することがあり、炭疽菌や菌核病には注意が必要です。日が株元や葉の全体に当たるようにすることと、風通しを良くして蒸れを防ぐために、枝の管理をしっかりしましょう。
害虫には、アブラムシ類・ハダニ類・ハモグリバエ類・フキノメイガなどが発生しやすいです。アブラムシはよく新芽に付くことがあり、確認して発生していたら早めにたいじしましょう。
殺虫剤には、食品成分から作られた環境に優しい「ベニカマイルドスプレー」や、天然のヤシ油を使用した「アーリーセーフ」というものがあります。また、しっかり退治するには「マラソン乳剤」という殺虫剤もあり、これはさまざまな種類の害虫に効果的です。
どの病気・害虫にも、早期発見・早期防除対策が重要です。このようにさやいんげんは栽培していきます。長期間の収穫が見込めるので、挑戦してみてはいかがでしょうか。
さやいんげんの歴史
中南米が最初の生息地であり、中央アメリカが原産といわれています。16世紀末にコロンブスが新大陸を発見した時に、さやいんげんも一緒に発見され、ヨーロッパへと伝わっていきました。その後、ヨーロッパから中国へと伝わり、日本には17世紀(江戸時代)に伝わりました。
1654年に、当時の中国に当たる明から日本へ帰化した、僧侶の隠元隆琦禅師によって伝えられたことから、「いんげん」という名が付いたとされています。この説ともう1つ説があり、隠元禅師が伝えたのは実際には藤豆(ふじまめ)という説もあり、関西では藤豆をいんげん豆とも呼んでいます。
また、関西ではいんげん豆が1年に3回収穫ができることから、三度豆とも呼ばれています。このさやいんげんが日本に伝わった江戸時代には、さやの部分は食べず、中の豆だけを食べていたとのことです。
さやいんげんの特徴
さやいんげんの品種には大きく分けて2つに分類できます。1つは「つるなしいんげん」、もう1つは「つるありいんげん」です。
つるなし品種は、種付けから収穫までの期間がおよそ55日と、いんげん栽培の中では比較的短く、またつるが伸びないため支柱を立てる必要も無いので、初めていんげんを育てるという方や、畑が無くコンテナなどで栽培される方などに適した品種です。
つるなし品種には、「さつきみどり2号」や「アーロン」といった品種があります。つるあり品種は、収穫期間が長い「ケンタッキー101」や「プロップキング」という種類があります。また、柔らかくて美味の品種である、平さやいんげんもつるあり品種になり、種類には「モロッコ」や「あきしまササゲ」などが比較的作りやすい品種です。
さやいんげんは、いんげん豆の若い時期に収穫したもので、中の豆がまだ柔らかい時期のものをいいます。これが完熟したものがいんげんとなります。さやいんげんの特徴には、まず豊富な栄養素が含まれている点が挙げられます。
低脂肪・高タンパクであり、ビタミンB群・食物繊維・βカロテン・カルシウム・鉄・ミネラルが含まれている緑黄色野菜です。βカロテンは、体内に入るとビタミンAに変化し、粘膜や皮膚の抵抗力を高めると共に、生活習慣病やがんを予防する効果が期待されている物質です。
βカロテンは、油と一緒に摂取すると効率良く体内に吸収されるので、炒め物や揚げ物で摂取すると良いでしょう。また、完熟したいんげんまめには、血糖値を抑制する効果のあるα-グルコシターゼという物質や、赤ワインに含まれていて抗酸化作用があることで知られている、ポリフェノールも含まれていることが分かっています。
種類には、どじょういんげん・サーベルいんげん・平いんげん・モロッコいんげんが、主な種類となっています。最も一般的などじょういんげんは、長さおよそ20センチ強の丸さやのいんげんで、独特な風味をもった品種です。またサーベルいんげんは、丸さやですが、どじょういんげんよりも長さが短いのが特徴です。
平さやいんげんは、他のいんげんに比べ筋が少なく味も濃いので、サッとゆでて食べると非常に美味しいです。また調理もしやすい品種です。モロッコいんげんは、大きくて平らな形が特徴で、熱を通すと甘みが増しとても美味しいので、サッとゆでてサラダ感覚で食べのも、天ぷらにしても非常に美味しくいただけます。
下記の記事も詳しく書いてありますので、凄く参考になります♪
つるありいんげんの育て方
エンドウの育て方
-

-
にんにくの育て方
にんにくは、紀元前3000から4000年以上前から古代エジプトで栽培されていたもので、主生息地はロシアと国境を接している...
-

-
エゾエンゴサクの育て方
エゾエンゴサクとは北海道や本州の北部の日本海側の比較的湿った原野や山地に古くから生息してきたという歴史があります。生息地...
-

-
イチジクの育て方
イチジクのもともとの生息地はアラビア半島南部、メソポタミアと呼ばれたあたりです。文明発祥とともに身近な食物として6000...
-

-
ニシキギの育て方
ニシキギは和名で錦木と書きます。その名前の由来は秋の紅葉が錦に例えられたことでした。モミジやスズランノキと共に世界三大紅...
-

-
シザンサスの育て方
シザンサスはチリが原産の植物です。もとの生息地では一年草、あるいは二年草の草本として生育します。日本にもたらされてからは...
-

-
レモン類の育て方
レモンと言えば黄色くて酸っぱいフルーツです。レモン類には、ライムやシトロンなどがあります。ミカン科、ミカン属になっており...
-

-
温州みかんの育て方
みかんは、もともとインドやタイ、ミャンマーなどが原産だと考えられています。生息地は、現在では世界各国に広がっていますが、...
-

-
大ギクの育て方
花色や花の形、品種が大変豊富な秋の代表花である大ギク。菊の中では大変大きな花を咲かせとてもきれいな花になります。大きく分...
-

-
ガルトニアの育て方
ガルトニアは南アフリカを生息地とする植物で、原産はこの地域になります。ガルトニアはツリガネオモトとも言われる植物で、原産...
-

-
植物や果物を育ててみませんか
仕事や行事などで毎日が忙しく、たまに休みがあったとしてもやりたい趣味活動がなかなかないという人も最近ではよく見かけること...




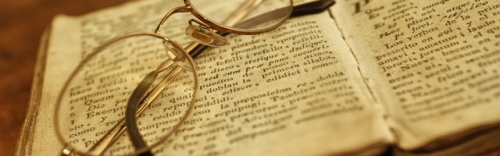





中南米が最初の生息地であり、中央アメリカが原産といわれています。16世紀末にコロンブスが新大陸を発見した時に、さやいんげんも一緒に発見され、ヨーロッパへと伝わっていきました。その後、ヨーロッパから中国へと伝わり、日本には17世紀(江戸時代)に伝わりました。