コマツナの育て方

コマツナの育てる環境について
コマツナは初心者でも比較的簡単に育てられます。厳冬期を除けば、1年中育てられます。発芽適温は15℃~35、生育適温は20℃~25℃くらいです。低温を好み、間引きしながら育てます。-3℃くらいまでは耐えられます。肥料はできればたっぷりあげます。
できればプランターで育てることが好ましいですが、少数の株なら、適応力の高いコマツナは植木鉢でも十分に育ちます。その際は株は少なめにする方が良いです。土は市販の培養土を利用するのが、簡単で便利ですが、自分で作るなら、赤玉土7、腐葉土2、バーミキュライト1、
石灰用土10ℓに10~20gの化学肥料を混ぜたものを準備します。鉢8分目くらいまで土を入れます。種の選び方ですが、ホームセンターなどで簡単に手に入ります。インターネットでもたくさんの種類の種から選んで入手することができます。
種のまき方は条まき(すじまき)です。条まきとは、土に直線をつけて、溝をつけてその溝に沿って種をまく方法です。その際は支柱を使うと便利です。条間は10cm~15cmくらいが理想です。その後の間引き、追肥を考えるとそのくらいが理想ですが、
小さめのプランターの場合は5cmくらいでも良いと思います。条まきは浅めにまきましょう。あまり深くまくと発芽率が下がります。種をまいた後は、土と種を良く密着させて、発芽するまではこまめに水をあげることが大事です。水の量はたっぷりです。発芽の準備を丁寧に整えて待ちます。
コマツナの種付けや水やり、肥料について
種付けや水やり、肥料については色んな方法があると思いますが、種付けは害虫の少ない秋~冬場が好ましいでしょう。-3℃まで耐えられるので適応力に強いコマツナは育て方としては、種が発芽するまでです。発芽まではこまめに水やりをして間引きをします。
プランターに種付けをする場合、コマツナの種の種類は豊富ですが、とても強く育てやすい野菜なので、種の選び方で失敗することはまずありません。水やりはこまめにたっぷりとします。種を浅めに植えるので、種が流されないように、慎重に水やりをします。
肥料は市販品、ホームセンターなどで売っているものでよいでしょう。土作りの方が大事なので、土を作る場合は赤玉7、腐葉土2、バーミキュライト1、石灰用土10ℓに10~20gの化学肥料を混ぜます。土を丁寧に作って発芽を待つまでが大事です。
短期間で収穫ができて、あまり肥料が効かなかったとしても、よく育つので家庭菜園では人気です。間引きを丁寧にし続けることで、長い間収穫ができます。品種や地域によって収穫時期が異なるので、その時期を調べることも大切です。害虫が心配なら、防虫ネットをかぶせると安心です。
秋まきのコマツナは、冬に収穫を迎えることが多く、冬に収穫したコマツナは甘みが増して美味しいのが特徴です。追肥をし過ぎると食味が悪くなることがあるので、追肥は控えめにすることが重要です。手間は適度にかけることで満足できる収穫となるでしょう。
コマツナの増やし方や害虫について
春にまいた種のコマツナには28種類以上の害虫が付きやすいので注意します。害虫の種類としては、ニセダイコンアブラムシ、キスジノミハムシ、ダイコンハムシ、ヤサイゾウムシ等があります。プランター栽培の場合は害虫ネット、手で簡単で払うことで害虫から守ることができます。
プランター栽培の場合はこまめにコマツナの様子を見てあげることで、簡単に防げるトラブルが多いです。アブラムシ、コナガの幼虫は春と秋に多く発生します。コマツナが病気にかかりやすい時期は春と秋、雨の多い時期です。畑で育てる場合、害虫を防ぐために、
寒冷紗をかけてあげるとよいでしょう。発生時期に薬剤散布するという手段もあります。しかしコマツナはとても強い種類の野菜なのであまり神経質になる必要はなさそうです。人間もそうですが、あまり過保護にし過ぎるほど良いことはありません。適度に水やり、
追肥、防虫対策をすることで楽しく収穫できます。プランターで手軽に育てることのできる野菜なので、プランター栽培がお勧めです。初心者からも人気があるのは、手軽でとても育て易いからです。葉物なので、プランター栽培の場合は必要なだけ収穫して、
また葉が伸びるのを待って次の収穫まで待つのも楽しみです。小さなプランター栽培から始めて、新しく次の野菜を作ることも挑戦してみましょう。コマツナは初心者向きなので、比較的簡単なので、自信につながります。収穫と種まきの時期を間違わないことが大事です。
コマツナの歴史
コマツナの歴史は国内では江戸時代まで遡ります。東京の江戸川区の小松川で栽培されていたことが、小松菜という名前になった由来です。徳川吉宗が鷹狩の際に、香取神社に立ち寄り、小松川で栽培されていると聞き、命名したという説が有力です。
いまでも香取神社に小松菜命名の記念碑が残されています。そして江戸川区小松川町では特産野菜になっています。コマツナには別称があります。雪菜、冬菜、うぐいす菜、等です。収穫の時期に因んでつけられましたが、品種改良が進んで、1年中食べられるようになりました。
コマツナは根菜類の仲間であるクキタチナという根菜類の品種改良されたものだとされています。クキタチナな茎立菜と書きます。茎立菜の仲間には、ブロッコリー、ホウレンソウ、キャベツなどが有名です。コマツナは関東地方から全国各地に広がっています。
根菜類と違うのは茎が地表に出ているのが特徴です。原産地はヨーロッパ地中海岸で中国と経てきていますが、日本で人気となっているのは耐冬性に強く初心者でも栽培しやすいのが特徴です。近年ではベランダ栽培を始める人が多いのでコマツナを育てている人も多いでしょう。
プランター1つで育てることができるのでお勧めの野菜です。新潟県の大崎菜、大阪府の黒菜、福島県の信夫菜はコマツナの仲間です。育てやすいことから、関東圏から全国に広がったのでしょう。いまでは親しみ深い野菜のひとつです。料理方法も焼く、煮る、など方法も豊富です。
コマツナの特徴
コマツナの特徴はバランス良く栄養素が含まれていることです。タンパク質、脂肪、無機物、ビタミン等です。緑黄色野菜の中では群を抜いて栄養素たっぷりのおすすめの野菜です。貧血予防、骨祖ショウ症、肌荒れ、便秘改善、女性にとって大変メリットがあって親しみやすいです。
茹でると鮮やかな緑色になり、焼いても柔らかく食べやすく、調理方法もたくさんあります。冷蔵庫の中で余れば、ホウレンソウと同じように煮て水分を絞って小分けにしてラップに包んだり、小分け容器に入れて冷凍しておけば、忙しい朝でも卵と炒めれば、
もう1品立派な朝ご飯の1品になります。生息地に関係なくプランターで育つので、調理し終わった根っこの部分だけを残して、プランターに植えてあげると葉がまたすぐ伸びてくるので、便利で扱い易い野菜です。コマツナの選び方としては葉の大きさが大きく、
元気があって伸び方のバランスが整っているものが好ましいです。ホウレンソウよりは日持ちが悪いのでなるべく早く使い切るか、やはり冷凍保存が良いでしょう。冷蔵保存の方法としては、立てた状態が好ましいので、濡れた新聞紙で包んだり、根っこに水分に与えるようにするとより良いです。
調理する前に水に浸けてあげると元気になります。関東では正月のお雑煮に入れる家庭が多く、冬場は特に甘みが増します。艶のある野菜なので、艶を損ねないようにしましょう。ホウレンソウと同じ使い方ができるので食卓に欠かせません。
野菜の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:シシトウの育て方
-

-
ブルーベリーの育て方
歴史の始まりはヨーロッパ大陸からアメリカに移住してきた人がネイティブアメリカの人たちにブルーベリーを分けてもらい、乾燥し...
-

-
バイカオウレンの育て方
バイカオウレンは日本原産の多年草の山野草です。生息地としては、本州の東北地方南部から近畿、中国地方西部などであり、深山の...
-

-
モチノキの育て方
モチノキは樹皮から鳥や昆虫を捕まえるのに使う粘着性のあるトリモチを作ることができるため、この名前がついたといわれています...
-

-
クルミの育て方
クルミは美味しい半面高カロリーである食材としても知られています。しかし一日の摂取量にさえ注意すれば決して悪いものではなく...
-

-
パンジーの育て方について
冬の花壇を美しく彩ってくれる植物の代表格は、なんといってもパンジーです。真冬の街にキレイな彩りを与えてくれる植物としては...
-

-
大ギクの育て方
花色や花の形、品種が大変豊富な秋の代表花である大ギク。菊の中では大変大きな花を咲かせとてもきれいな花になります。大きく分...
-

-
ダチュラの育て方
ダチュラといえば、ナス科チョウセンアサガオ属、あるいはキダチチョウセンアサガオ属の植物のことです。しかし、この区別に関し...
-

-
サンセベリア(Sansevieria)の育て方
サンセベリアの原産地は、アフリカ、南アジア、マダガスカルなどです。熱帯の乾燥した地域を好んで生息地としており、約60種類...
-

-
ペピーノの育て方
日本的な野菜の一つとしてナスがあります。他の野菜に比べると決して美味しそうな色ではありません。紫色をしています。でも中は...
-

-
ボケの育て方
ボケはもともと中国原産の落葉低木です。梅と比べてもかなり木の丈が低く、コンパクトな印象で春の花木として人気があります。 ...




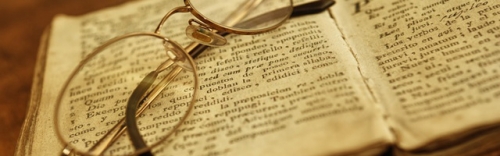




コマツナの歴史は国内では江戸時代まで遡ります。東京の江戸川区の小松川で栽培されていたことが、小松菜という名前になった由来です。徳川吉宗が鷹狩の際に、香取神社に立ち寄り、小松川で栽培されていると聞き、命名したという説が有力です。