タカナ類の育て方

タカナ類の育てる環境について
発芽温度は15度から25度生育温度は15度から20度で気候区分としては温暖な土地を好みます。幼苗時期は熱さ、寒さに強い方ですが成長してくると寒さに弱くなります。タカナ類は中性に近い弱酸性の土壌を好みます。土が酸性に傾いている場合は石灰を混ぜてよく耕ます。
育て方は畝の真ん中に20センチ程の溝をつくり堆肥や油かす化成肥料をまき、埋め戻し幅50センチから60センチ高さ10センチの畝を作ります。間引きをした後最終的には苗と苗の間隔は15センチから20センチ位になるようにします。
また、間引いたものはまだ柔らかいのでサラダかそのまま食べる事も出来ます。プランターで育てる場合は根が大きく張る為深鉢を用意します。種まきは秋ごろ収穫は11月頃から始められるようで12月から1月まで収穫できる地域もあります。
7週間程したら収穫可能になりますので草丈20センチ以上になったら株ごと引き抜きます。タカナ類は寒さに当たると味が凝縮すると言われています。すぐに全部食べるより、外の葉から必要な分だけ株の下から一本ずつ葉を切り取って収穫する方法もあります。
九州などの暖かい地方では収穫は3月中旬まで続ける事が可能です。なお、苗を定植はなるべく浅植えで根が大きく下に伸びる様にします。その後水やりや施肥で土が下がってしまった場合は、畝の溝から土を高く盛って上げます。プランターの場合は苗の回りに土を足してください。
タカナ類の種付けや水やり、肥料について
種まきは秋8月の終わりか9月ごろに行います。元肥を用意します。化成肥料かもしくは有機肥料、堆肥や牛ふんなどでもいいでしょう。プランター植えの場合は鉢底石を敷き詰め培養土の後元肥を敷き込み更に培養土入れてならし水をかけ土を濡らします。
土中のゴミが全て水と一緒にプランターの外へ出る様にタップリかけます。種をすじまきする溝を指か棒で1センチ深さで作り種をまきますその上から浅く土を掛け水をかけます。育苗用のポットに最初から種をまいてもいいです。2週間程して本葉が2枚ほど出てきたら最初の間引きを行います。
まず立て込んでいる場所を間引く事と元気がないものも間引きます。ポット苗の場合本葉3枚になる頃にはポットに1株になるようにします。本葉が6枚位でプランターかもしくは畝に定植します。プランター植え、畝も双方定植後万遍なく水を与えます。
その後しばらくは水やりを控えます。地中で根を沢山出させるためです。追肥は2回目の間引き後から2週1回化成肥料を与えるか週1回液肥を与えます。畝の場合は月に一回株の間に施肥を施します。また、時期が10月を過ぎてくると気温が下がり生育に影響がでるので、
畝かプランターへも穴のあいたビニールで覆いを作ります。プランターの場合はアーチ型の支柱を3本さしてビニールをかぶせ、畝はトンネルのように支柱を刺しすようにします。穴をあける事で水やりや施肥なども便利です。プランターの場合は土を足してください。水やりは土が乾いてきたらタップリ与えます。
タカナ類の増やし方や害虫について
アブラムシなどの虫対策が必要になります。苗が小さい時に虫の食害に合うと枯れてしまうか生育が遅れます。またアブラムシを餌にするテントウムシなども沢山つく事があります。アブラムシ対策には市販の殺虫剤を散布します。オルトランを使う場合もありますが、
土に溶けて作用するので効き目が出るころには葉の栄養分が取られて元気がなくなってしまいます。また、蝶などが卵を産み付けて幼虫に孵った場合も葉が食害にあいますし他にも野鳥などの食害の心配があります。対策として寒冷紗などのネットを回りに張る方法があります。
また幼虫を見つけたら補殺する方法が一番です。苗が成長してある程度大きくなればネットを取り外します。連作障害を起こしやすい植物なのでこれも注意が必要です。連作障害を起こすと植物が病気にかかりやすくなったり生育状態が思わしくない事があります。
地中の中のミネラルが不足する事が原因だと考えられています。現在は土のリサイクル材など再利用しやすい薬が市販されていますが、野菜などを栽培する場合は同じ種類の食物を同じ場所で育てない事が一番です。畑などは場所のローテーションを行ったて、全開アブラナ科以外の植物を育てた場所で栽培します。
プランター植えは同じ土を使わず前に使った土を再利用したいのであれば同様にアブラナ科でない植物を育てたものを使います。タカナ類も春が来れば花は咲き鞘が出来ます。茶色くなって乾燥してきたらつまんで袋に入れ中で鞘を開き種をとります。
タカナ類の歴史
アブラナ科アブラナ属のタカナ類はからし菜の変種で原産、生息地は東南アジアと言われています。シルクロードを渡ってきたという説もありますが、日本では平安時代には食用として存在していたので歴史の古い植物です。中国から日本へ渡った場所は九州とされその後西日本全体に広まりました。
以前は西日本で栽培されていましたが、温暖な気候を好む事とその歴史のせいか現在は九州地方での栽培が盛んで地方タカナ類が数種類あります。 タカナ類類には葉の色が緑の青タカナ類で三池タカナ類、葉が紫タカナ類で赤大葉タカナ類、株元にコブがある雲仙こぶタカナ類、
長崎タカナ類、筑後タカナ類などがあり漬物として使われる事で有名です。特につけ菜としての漬物は有名で優良発行食品として九州のタカナ類は野沢菜、広島菜と並んで日本三大漬け菜の一つです。九州では乳酸発酵が進んだ古漬けがよく食べられているようです。
タカナ類は特徴的な辛味がある為その他の用途でも広く使われており、その圧倒的な収穫高にはかないませんが近年近畿和歌山地区でも栽培が進むなど栽培農家が増えてきています。九州地区の漬物は全国に広まりその食べ方も漬物自体を、
料理に活用する他色々な調理法が工夫紹介され関東のスーパーや小売店でも見かける事が多くなりました。今後東日本でも生産栽培の量が増えればより身近な食材として庶民の食卓に浸透いていく事でしょう。また、福岡にカツオナという在来種があり煮物に使われています。
タカナ類の特徴
見た目はからし菜とよく似ています。からし菜に比べると葉は幅広で丸みを帯びてふっくらしています。淵はギザギザしていなく葉面は縮れ幾分葉脈は根本に近づくにしたがって太目で白菜に似ています。外葉は硬く食用に向きませんが内葉は柔らかくつけ菜に向いていると言われています。
株は20センチほどから大きなものになると1メートル位に育つものもあります。タカナ類の葉は食べるとピリッと辛味を感じこれが特徴で、辛味成分の元であるイソチオシアン酸アリルはマスタードの成分と同じものです。タカナ類の収穫時期は一年を通して行われています。
これは発芽した後立て込んで着た芽を摘む作業や間引きをした後つみ菜として出荷され市場に出回るためです。漬物用として収穫されるのは株が大きく成長した12月から3月までとなります。寒さに強い葉物野菜の一つであることは間違いありません。
栄養面からみるとビタミンK、B、Cなどが豊富に含まれ、食物繊維、鉄分や緑黄色野菜なのでカロテンも多い万能野菜とも言えます。ビタミン類は加熱すると壊れて水分と一緒に溶け出てしまいますが、タカナ類の漬物であれば生食が出来栄養を体に取り込む事が出来ます。
タカナ類はそのまま食べても美味しくたべられますが、炒め物として他の葉野菜同様に使う事ができます。タカナ類は間引きなどして早めに摘んだものは柔らかいのでそのまま生で食べる事に向いていますが長期保存するには塩漬けにしておくとよいです。
野菜の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:プチヴェールの育て方
タイトル:トウミョウの育て方
-

-
ゆりの育て方
ゆりは日本国であれば古代の時期から存在していました。有名な古事記には神武天皇がゆりを摘んでいた娘に一目惚れして妻にしたと...
-

-
リンゴの育て方
リンゴの特徴として、種類はバラ目、バラ科、サクラ亜科になります。確かに花を見るとサクラとよく似ています。可愛らしい小さい...
-

-
マンデビラの育て方について
マンデビラはキョウチクトウ科マンデビラ属で、原産地や生息地は北米や中南米です。チリソケイやディプラデニアという別名もあり...
-

-
ヤマハギの育て方
植物の中には生息地が限られている物も珍しくありません。しかしヤマハギはそういった事がなく、日本全土の野山に自生しています...
-

-
シシリンチウムの育て方
シシリンチウムは原産地が北アメリカの常緑多年草となっています。この名前ではピンとこない人でも、庭石菖(ニワゼキショウ)と...
-

-
ディオスコレアの育て方
観葉植物として栽培され、日本でも人気を集めているのがディオスコレアであり、特に普及しているのがディオスコレアエレファンテ...
-

-
オレアリアの育て方
意外と感じますがキク科の植物になるので、日本にも適用するイメージが強くあります。そして大きさは高さというのは25~60c...
-

-
クレオメの育て方
通常クレオメというとセイヨウフウチョウソウの種のことを言います。フウチョウソウ属とはフウチョウソウ科の属の1つで主な原産...
-

-
家庭菜園で甘くておいしいトマトを作る方法
家庭菜園を始める際、どんな野菜を作りたいかと聞けば、トマトと答える人は多いようです。トマトは見た目もかわいく、野菜なのに...
-

-
ポトス(Epipremnum aureum)の育て方
ポトスの原産地はソロモン諸島だといわれています。原産地のソロモン諸島は南太平洋の島国で常夏の国です。一年を通じて最高気温...




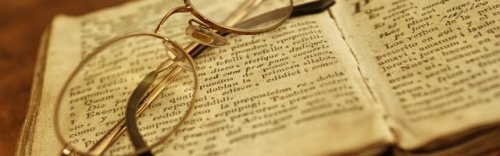





アブラナ科アブラナ属のタカナはからし菜の変種で原産、生息地は東南アジアと言われています。シルクロードを渡ってきたという説もありますが、日本では平安時代には食用として存在していたので歴史の古い植物です。