ボタンの育て方

花に対する手入れ
ボタンは美しい花を咲かせますが、花が終わりかけの頃に、根元からばっさりと切ってしまいます。植物は花を咲かせるためにエネルギーを使いますが、それよりも種子を作るのに大きなエネルギーを使います。
もしも花をそのままにしておくと、受粉して種子を作るようになり、そして実ができるわけですが、そこまでには大きなエネルギーを消費してしまい、株の勢いが衰えてしまうことがあります。すぐに枯れることはないでしょうが、翌年の育ちがあまり良くないこともありますから、そうならないように気をつけましょう。
そのためには、花が咲いたのならそのままにしておくのではなくて、花が終わりかけの頃に切ってしまうのが良いです。花弁だけをはらうのではなくて、花の茎の根元からばっさりといったほうが良いです。美しい花を咲かせるためにはこれが必要です。
美しい花を咲かせるためには、花芽があまり多すぎるのは良くありません。エネルギーが分散されるからです。6月下旬くらいになれば、葉の根元の部分に花芽が形成されます。この花芽の育て方によって美しい花が咲くかどうかが決まるのですが、うまく栽培するためには芽を間引いていくことが必要です。
上の方についている芽を2つくらい残して、後はすべてかき取りましょう。このときに、すべての芽をかき取るとその枝には栄養が行き届かずに花が咲かなかったり、あるいは咲いても小さいものしか咲かないと言ったことになることもありますから注意が必要です。全体の形を考えながら剪定をしていくことで、良い形のボタンになります。
ボタンの環境と育て方
ボタンの育て方で最も大事なものは栽培環境です。どのような場所で栽培するのかによって花の美しさは変わってきます。鉢植えでも地植えでも良いのですが、暑さに弱いと言うことも頭に入れておかなければなりません。たとえば、西日本なら夏はかなり暑くなるでしょう。
地植えをすると場所を動かすことができず、暑さに弱いボタンはダメージを受けてしまうこともありますから注意が必要です。地植えする場合には、日当たりを確保しつつ、風通しの良い場所や涼しい場所に植えることが必要です。
日当たりについては、半日以上は日の当たるところにおいた方が良いです。日当たりが悪すぎると生育が悪くなります。1日中日が当たっているほうが良いですが、半日くらいしか当たらないところでも生育はします。
水やりは定期的に行わなければなりません。これが美しいボタンの育て方の大事なことの一つです。表面が乾いてくればたっぷりの水をやります。地植えの場合には根が十分に張ってくれば過度な水やりは必要ありません。普段は水やりをせず、炎天下の続くような真夏にのみ水やりをすれば良いです。
肥料を好む花ですが、多くやれば良いというものでもありません。その時期は5月と9月で、この時期に適当な量の肥料をやります。置き肥すれば良くて、化成肥料を用いれば良いです。
増やし方について
ボタンは種付けといった作業を行うことは希です。というのも、種から育てると、どのようなものが育つのかが分からないからです。好みの品種があれば、その苗木を育てるというのが基本です。気に入った品種の苗木が成長し、花を咲かせて種ができた場合、それを種付けに用いると、元の品種とは違うものができることが多いです。
販売されている苗木は、偶然できた美しいものを接ぎ木によって増やしていることが多く、種から育てると美しいものができない場合もあります。そのために、種付けは行わないことが多いのです。ただ、種付けから育てていくことができないわけではありません。
種から植えていけばきれいな花を咲かせることもあります。この方法は品種改良の時に行う栽培方法で、品種改良と言っても基本的には偶然にできることに期待して行うわけですから、種から育てたものが美しい花を咲かせればそれを接ぎ木によって増やしていくという形をとります。
接ぎ木によって増やしたものの場合、元のものと遺伝子が全く同じになりますから、そだてかたが全く同じであれば全く同じ花を咲かせることができるのです。種を取ってそれで増やしていくことによって、元の花とは異なるものができる可能性があります。これを楽しみにしている人もいて、たくさん育てていれば新しいものを育てられる可能性はあります。
全く新しいものを作ってみようと思うのなら、たくさんのボタンを植えて受粉させ、そしてできた種を植えてみるのも良い方法です。新しい品種を作るときにはやはりこのようにしています。時間がかかることもありますが、良いものができるかも知れませんし、それも楽しみの一つです。
接ぎ木で増やす場合、シャクヤクを用いることが多いです。シャクヤクのゴボウ根に接ぎ木をします。その年に後場新しい枝を10センチくらいに切って接ぎ木をします。接ぎ木が成功すれば、元と同じ花を咲かせるでしょう。
ボタンの歴史
牡丹の原産は中国の西北部だと考えられています。この地域では、もともとは観賞用ではなくて、薬として用いられていたそうです。中国の唐の時代には、花が美しいと言うことから「花の王」と言われるようになりました。
この頃の経緯は詳しくは分かっていないのですが、隋の時代に則天武后が気に入っていたと言われることもありますから、さらに歴史が古い可能性はあります。その後は、清の国の花として認められていました。生息地を中国として愛されたボタンは、聖武天皇の時代に日本へもたらされたと考えられています。
平安時代には宮廷や寺院で観賞用として用いられるようになります。その後、江戸時代には流行を呼び、いろいろな品種が作られるようになります。他の植物が江戸時代に園芸用として品種改良されたのと同じように、ボタンもやはり江戸時代にいろいろな品種が生み出されて、一気に人気を集めるようになるのです。
ボタンの特徴
ボタンの開花時期は種類によって異なります。一般的な品種は春ボタンと呼ばれ、4月から5月に開花します。寒ボタンは、通常は11月から1月が開花の時期となります。品種によっては冬に咲くものもあります。花の色は様々で、基本的には赤と白のものが好まれているようですが、黄色い花を持つものも販売されるようになりました。
地植えにも鉢植えにも用いることができます。鉢植えの場合にはもちろん水やりが必要ですが、地植えの場合には夏の暑い時期にのみ水やりをします。極端な感想がなければ徳の問題はありませんから、高温になる夏の時期だけで良いです。手入れとしては特に必要ありませんが、他の植物と比べると肥料を好むという特徴はあります。きれいな花を咲かせるためには適当な肥料をやることが必要です。
多くの場合には接ぎ木によって増やします。接ぎ木でないと同じ花が咲かないと言うこともあって、接ぎ木が好まれているようです。シャクヤクの苗の根に接ぎ木する方法が一般的に用いられていて、接ぎ木されたものが販売されていることが多いです。8月の下旬から9月中旬頃に接ぎ木するのが一般的です。
元々低木ですから、大きくなりすぎることはありませんが、美しい花を咲かせるためには適度な剪定も必要です。芽をすべて取ってしまうくらいの強剪定は良くありませんが、そこそこ強めに剪定をしても新たに花を咲かせるようになりますから、管理は難しくはありません。剪定と肥料がきれいな花には大事なことです。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:シャクヤクの育て方
タイトル:リナム・グランディフロムルの育て方
タイトル:マツバボタンの育て方
タイトル:ハボタンの育て方
タイトル:シコンノボタンの育て方
-

-
シノブ、トキワシノブの育て方
これはシダ植物と言われる植物になります。一般的な種子植物とは異なり種を作って増えるタイプではありません。胞子があり、それ...
-

-
エボルブルスの育て方
エボルブルスは原産地が北アメリカや南アメリカ、東南アジアでヒルガオ科です。約100種類ほどがあり、ほとんどがアメリカ大陸...
-

-
キンギョソウの育て方
キンギョソウはもともとは多年草ですが、暑さで株が弱り多くが一年で枯れてしまうので、園芸的には一年草として取り扱われていま...
-

-
クロッカスの育て方
地中海沿岸から西アジアを生息地とする多年草の球根植物であるクロッカスは、世界に約80種類の園芸品種があるとされ、チューリ...
-

-
植物の育て方について
今年はガーデニングで野菜を育ててみようと思っている初心者の方におすすめな野菜の1つがプチトマトです。今まで植物を育てたこ...
-

-
ラバテラの育て方
ラバテラは原産地が南ヨーロッパ、北アフリカの植物です。アオイ科ラバテラ属の総称になります。一年草になり、日本には明治に渡...
-

-
キンシバイの育て方
初夏から本格的な夏を迎える時期に、黄金色をした花を咲かせるキンシバイは中国原産の半落葉性の低木です。半日陰でも育つ丈夫な...
-

-
玉レタスの育て方
サラダの食材に欠かせないレタスには幾つかの種類が在りますが、お店に行くとレタスと名の付く物が沢山店先に並んでおり、どれに...
-

-
ブルンネラの育て方
ブルンネラはユーラシア西部を原産とするムラサキ科の多年草です。ブルンネラという名前は、スイスの植物博士であるブルナーから...
-

-
植物の育て方で考えるべき要素や種類の選択について
植物の栽培を考える上で考えるべき事は、栽培する植物に合わせた環境を作るという事に尽きると言えます。特に重視したいのは肥料...




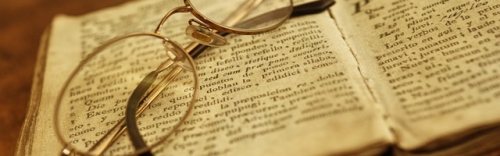





牡丹の原産は中国の西北部だと考えられています。この地域では、もともとは観賞用ではなくて、薬として用いられていたそうです。中国の唐の時代には、花が美しいと言うことから「花の王」と言われるようになりました。