ゼラニウムの育て方

ゼラニウムの育て方
極端な暑さと寒さ以外には強く、初心者でも栽培しやすい植物です。乾燥が激しいヨーロッパなどの都市の窓辺に飾られることが多く、窓辺の花として人気があり人々の目を楽しませてくれます。環境さえよければ開花時期は長く、葉の模様を観賞することもできるため園芸初心者でも楽しんで栽培することができます。
乾燥に強いため、水やりを忘れてしまったというときでもそれほど慌てることがありません。土の表面が完全に乾いてから、鉢底からあふれ出るくらいたっぷりの水を与えることが基本です。鉢植えやプランターで栽培することができ、ベランダガーデニングでも重宝されることが多い傾向にあります。
雨が当たりにくく風が強いベランダは植物にとって劣悪な環境になりがちです。ゼラニウムは丈夫な性質を持っているため、少々の悪条件であっても育て方さえ間違えなければ枯れずらい植物であるといえます。霜にあたると枯れてしまいますが、軒下や屋内にとりこんでおけば地域によっては越冬が充分に可能です。
マイナス5度以下になる環境の場合は屋内にいれてあげましょう。摘心することでわき芽が増え、見栄えを美しく育てることができます。春から秋にかけての生育期に液体肥料を与えましょう。冬は生育が止まるため、肥料はやらず水も控えめに与えましょう。
真夏などの高温の季節には株が弱りやすくなっているため肥料はいったん中止します。石灰質の土壌を好むため、植え替えの時期には苦土石灰などを用土に混ぜ込むといいでしょう。植え替えに適した時期は春です。植え替えをすることで根詰まりが解消され丈夫に育ちます。
栽培中に注意したいこと
丈夫な性質を持った植物ですが、育て方によっては花が咲かなくなったりすることもあるため注意しましょう。暑さには強いですが、30度以上の高温が毎日続くような場合には日中の高温になる時間帯だけ庇の下にいれてやるなど工夫することが育て方のコツです。
暑さだけで枯れることはあまりないですが、日本の湿度の高い夏はゼラニウムにとって好ましい環境ではありません。もともとの性質が丈夫なため誤解されがちですが、高温多湿を好むわけではなく、日当たりと風通しの良い場所を好みます。水はけのよい用土を使い、やや乾き気味に栽培することをこころがけましょう。
草丈が高くなると、バランスが悪い姿になってしまう場合があります。葉が込み入ってくると、日が当たらない部分の生育が悪くなってしまうためバランスを見て剪定することが花付きをよくするためには必要です。栽培するうちに茎ばかりの姿になってしまうこともあるため、適宜切り戻すことで見栄えを整えましょう。
ゼラニウムは生育するうちに根本の部分がまるで木の枝のように太く育ってしまうことがあります。これを木質化といい、あまり見栄えがよくありませんが枯れてしまったわけではありません。節の部分で切断することで新しい芽がはえてきます。木質化を防ぐためにはいくつか方法があります。
植え替えの際に木質化してしまった部分を深く植える方法があります。植えた部分の根本から根が張ってきたら、掘り出して株分けすることも可能です。根の様子をしっかり観察する必要があるため、慣れないうちは挿し木などをして増やす方が安心だし簡単にできます。茎の節の上で切れば新しい芽がちょうど切った位置あたりから出てきます。
花は枯れた後、切ったり手で引っ張ったりしなくても自然に落ちてきますが、花をつけている茎の根本からはさみで切り取るか摘み取ると見栄えが美しいです。湿度が高い状態のまま風通しが悪くなると、灰色カビ病にかかりやすくなります。
枯れ落ちた葉は取り除き、多すぎる葉を取り除いて風通しを確保してあげましょう。春になって温かくなるとアブラムシがつきやすくなります。見つけてから駆除すると数が増えすぎていて大変な場合があるため、あらかじめ専用の薬剤を散布しておくと安心です。
ゼラニウムの増やし方
種付けに適した時期は5月頃です。種付けするために必要な温度は20度から23度です。種付け以外にも挿し木をすることができ、簡単に増やせます。種付けにこだわらなくても、剪定したときに出た茎を使って挿し穂に利用することができます。あまり伸びすぎているものはやめ、葉の色が良いものを使用するといいでしょう。
根元に近い部分の葉をすべて切り落としてから土にさします。土にさすときに残っている葉は3枚程度が好ましいです。葉が大きすぎる場合には水分が蒸発しすぎることを防ぐため、葉を半分に切る方法があります。切り口をななめに切るか、楔の形のなるように形を整えてから日陰で適度に乾かして土にさすようにすると発根しやすくなります。
切り口が湿りすぎているとそこから腐ってしまうことがあるため、注意しましょう。根付くまでは明るい日陰で管理するようにします。苗や鉢は一般的な園芸店で入手することが可能です。手にしたときにずっしりと重く、葉の色とつやが良いものを選びましょう。
ゼラニウムの歴史
ゼラニウムの主な原産地は南アフリカです。南アフリカを中心にオーストラリアや中東などの広い範囲を様々な種類が生息地としています。フクロソウ科の植物としてゼラニウム属とペラルゴニウム属の二種類に分類されていますが、現在ゼラニウムという名称で親しまれているものはペラルゴニウム属の方です。
ゼラニウム属として分類されている方は園芸の分野ではこの名称で呼ばれることはないといっていいでしょう。南アフリカの地で発見された野生種を元に様々な改良が行われ、愛されてきました。日本には江戸時代の終わりに渡来したとされています。大正時代には葉の模様や色彩を楽しむことを目的として盛んに品種改良が行われました。
昭和の初めころには珍しい葉を持つゼラニウムは高額で取引されたといわれています。現在では一部のマニアの間だけでなく、一般的な園芸店でも様々な種類の取扱いがあり、丈夫で育てやすいところから多くの人に愛されています。
ゼラニウムの特徴
品種にもよりますが比較的高温に強く、ベランダなどでの植物にとってあまり良い環境でないと思える場所でも花を楽しむことが可能です。全世界に広い範囲で約280種類が存在するといわれています。一年で花が咲いて終わる一年草、何年かにわたって楽しむことができる多年草、低木に分類されるものなどその特徴は種類によって様々です。
開花時期はそれぞれの種類によって違い、草丈などの姿形も違います。改良によって四季咲きのタイプも生まれました。野生種が親となって生まれた種類をゾナーレタイプといいます。ゾナーレタイプの中でもいくつかの種類にわけられ、最も広く愛好されている種類はホルトルムタイプとして分類されています。
花の色は赤、ピンク、白などがあります。花の形は一重咲きの他に八重咲きのものがあります。葉は丸みを帯びた形をしており、中心に黒っぽい輪のような模様があることが特徴です。茎は太く、独特のにおいがあります。好き嫌いが分かれるにおいかもしれませんが、ハーブとして利用されたり蚊を防ぐ効果が期待できる種類もあります。
まるでバラやカーネーションのようなユニークな花びらを持つものや、葉がもみじのようになるものなど様々な種類に改良されています。ペラルゴニウム系と呼ばれる種類は野生種を元に様々な品種とかけあわされた交雑種です。
葉の色は明るいグリーンで表面に産毛のような毛が生えており、花は大きくて花びらに模様が入ることが特徴です。大きな花を楽しみたいペラルゴニウム系は、春から初夏にかけて開花します。同じゼラニウムという名前がついたものでも、特徴が異なるということを覚えておきましょう。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:パンジーゼラニウムの育て方
タイトル:ゲラニウム(高山性)の育て方
タイトル:カーネーションの育て方
-

-
レンゲショウマの育て方
花の特徴として、キンポウゲ目、キンポウゲ科となっています。山野草として分類されています。咲き方としては多年草になります。...
-

-
ディネマ・ポリブルボンの育て方
ディネマ・ポリブルボンは、中南アメリカ原産の小型のランです。主な生息地は、メキシコやグアテマラ、キューバやジャマイカで、...
-

-
アーティチョークの育て方
アーティチョークの原産地や生息地は地中海沿岸部や北アフリカで、古代から栽培されているキク科のハーブです。紀元前から高級な...
-

-
コクリュウの育て方
コクリュウは日本や中国など東アジアに生息地がある植物で寒さにも非常に強く、冬の間も黒っぽい葉を落とすことがありません。似...
-

-
ツタ(ナツヅタ)の育て方
ツタはナタヅタともいい、ブドウ科ツタ属のツタ植物です。古くから存在していて、日本でもよく使われている植物の一つです。昔か...
-

-
モチノキの育て方
モチノキは樹皮から鳥や昆虫を捕まえるのに使う粘着性のあるトリモチを作ることができるため、この名前がついたといわれています...
-

-
セネシオ(多肉植物)の育て方
植物としては多年草に分類されます。キク科に属しており、つる植物という独特な分類になっています。これは種類が非常に豊富にあ...
-

-
ダイコンドラ(ディコンドラ)の育て方
ダイコンドラ(ディコンドラ)は、アオイゴケ(ダイコンドラ・ミクランサ)と言った別名を持ち、ヒルガオ科のダイコンドラ属(ア...
-

-
シネンシス・エピソードの育て方
シネンシス・エピソードがきんぽうげ科ヒエンソウ属ということです。シネンシス・エピソードという淡い紫色の花があり、とても美...
-

-
プランターで栽培できるほうれん草
ほうれん草の生育適温は15~20°Cで、低温には強く0°C以下でも育成できますが、育ちが悪くなってしまうので注意が必要で...




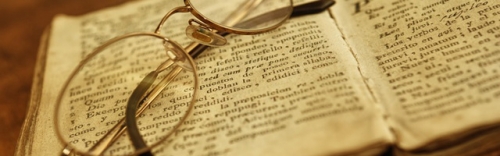





ゼラニウムの主な原産地は南アフリカです。南アフリカを中心にオーストラリアや中東などの広い範囲を様々な種類が生息地としています。フクロソウ科の植物としてゼラニウム属とペラルゴニウム属の二種類に分類されていますが、現在ゼラニウムという名称で親しまれているものはペラルゴニウム属の方です。