ヘチマの育て方

ヘチマの植え付け
4月中旬ごろに25~30℃を確保できる場所で、9cmのポリポットに3粒ほどタネをまきます。本葉1~2枚のころには1本に間引きましょう。本葉が4~6枚ほど出てきた頃を目安に定植します。または遅霜の心配がなくなってから4粒ずつほど直まきにします。タネから育てる他、ポット苗を用意するという方法もあります。
園芸店には4月ごろからヘチマの苗が並びます。寒の戻りに気をつけ、寒くなるようでしたら株元をビニールシートやわらなどでマルチングしたり、ビニールキャップをかぶせたりして保温しましょう。5月の上中旬ごろまでポット苗のまま暖かい場所で管理するのも良いでしょう。
ヘチマは日が短いと花つきが早くなり、日が長くなると遅くなります。日が長くなる6月になると、花つきが遅れてしまうので、なるべく5月中旬までには植え付けを終えるようにしましょう。庭植えの場合、植え付けの2週間ほど前までに苦土石灰や牛ふん、肥料を土にすきこんでおいて下さい。
直前に行うと石灰や肥料が醗酵する際に熱を出し、その熱で根を傷めることがあります。どうしても直前になってしまう場合は、有機石灰や完熟の牛ふんを選ぶと良いでしょう。株間は70~90cmで植えつけましょう。水分は好みますが、過湿には弱いので高畝にして植えつけると良いでしょう。
鉢植えの場合、野菜用の土を使うと便利です。肥料の含まれていない土の場合、植え付け前に肥料を混ぜ込んでおくと良いでしょう。65cmの深型プランターなら1株が目安です。狭いところに多くの苗を植えてしまうと生育が悪くなるので注意してください。深植えは禁物です。
ヘチマの育て方
日当たりと風通しの良いところで栽培しましょう。西日は嫌うので西側に日差しを避けるものがあるところが最適です。水は土の表面が乾いたらたっぷりと。鉢植えの場合、鉢底から流れ出るくらいに与えてください。メリハリの利いた水やりを心がけましょう。真夏の日中に与えると根が温まり生育が衰えてしまうことがあるので、涼しい朝方に与えると良いでしょう。
ヘチマは連作障害と呼ばれる、同じ科の植物を続けて栽培すると生育が悪くなり枯れやすくなると言う現象が起こりやすい植物です。前年にキュウリやメロンなど、ウリ科の植物を栽培していた場所は避けて栽培しましょう。植えつけてから2週間ほどしてから追肥を行います。ヘチマに用いる肥料に書いてある育て方、注意書きに基づいて与えてください。
ヘチマはツル性の植物です。ネットや支柱を使って育てるようにしましょう。カーテン状に仕立てる場合と、棚状に仕立てる場合が多いです。植え付けと同時に支柱とネットを立てておくと良いでしょう。ツルを伸ばし始めたら、ネットに絡みやすいようにひもなどでツルを固定するとよいでしょう。
仕立て方によって育て方が変わります。カーテン状に育てる場合、真ん中の茎の先端を摘み取り、脇芽を伸ばすと茎数が増え、密集したカーテンが作れます。棚状に育てる場合、真ん中の茎を伸ばしたまま、脇から出る芽を摘んでいくようにします。こうすると棚上に早く届き、仕立てやすくなります。棚上に届いたら真ん中の茎の先端は摘み取り、脇芽を伸ばすようにしましょう。
自然交配で果実は実りますが、確実に果実をつけるためには、人工受粉をするとよいでしょう。午前10時ごろまでに雄花をとり、花粉を雌花につけるようにしましょう。ヘチマは大きく実ると重くなります。果実の実の茎部分をひもでネットや支柱に固定すると良いでしょう。
ヘチマの収穫時期
果実を食用に用いる場合、着果してから10~14日が収穫の目安です。タワシにする場合は9月上旬、果実が黄ばみ、つるが茶色く変わってきた頃が収穫適期です。化粧水を取るときは、9月15日~20日ごろがよいでしょう。種付けをする場合、果実を茶色くなるまで収穫するのを待ちましょう。
茶色くなったら果実を割り、黒くてつやのあるタネを採取して乾燥保存しましょう。必要な分だけ種付け用に果実を残し、他は 摘み取ることで、栄養を効率よく残った種付け用果実にまわし、いいタネを得ることが出来ます。種付け用の果実以外は早めに収穫するとよいでしょう。1株当たり15個くらいが目安です。
ヘチマの病害虫
葉が粉をまぶしたように白くなるうどん粉病がウリ科の植物には良く見られます。また、葉に薄茶色の不規則な斑点が出るたんそ病やべと病も出る場合があります。適した薬を使用して、早めに対策を行いましょう。そのまま放っておくと生育が衰え、枯れてしまう場合があります。ツルに亀裂が入る、つる割れ病は薬剤では防除できません。
育て方で対応しましょう。つる割れ病が出た場合は、混み入ったツルを誘引して整理し、風通しをよくすると良いでしょう。アブラムシは爆発的に増殖します。見つけたらすぐに薬剤などで防除しましょう。ウリノメイガという芋虫がつく場合があります。見つけ次第捕殺するか、適した薬を散布しましょう。
ヘチマの歴史
熱帯アジアを生息地とするインド原産の植物です。日本には中国を通して江戸時代に伝わったと言われています。ヘチマは元々、果実を乾燥させたときに繊維状になるので「糸瓜(イトウリ)」と呼ばれていました。それが「トウリ」に縮まり、「トウリ」の「ト」はイロハ歌の「ヘ」と「チ」の間にあることから「ヘチ間」から「ヘチマ」と呼ばれるようになったそうです。
ウリ科の一年草で、ツル状に伸びて生育していきます。実が熟した頃に、根元から30cmほどの部分で茎を切って得た水分をヘチマ水と呼び、昔から化粧水として使ったり、飲み薬や塗り薬として使ったりしてきました。また、茶色くなった果実を一週間ほど水にさらして、軟らかい部分を腐らせて洗って取り除き、残った繊維質部分を乾燥させて、浴用や炊事用のスポンジとして使ってきました。
繊維の少ない品種は果実を食用としても扱います。沖縄ではヘチマをナーベラーと呼び、ゴーヤと共に夏の代表的な野菜として楽しまれています。ナーベラーは鍋を洗うことに用いていたことからついた呼び名とされています。暑さと強い日差しに強いため、近年では日よけを目的とした緑のカーテンとしても人気の植物です。
ヘチマの特徴
ウリ科の一年草でツルを伸ばして最大10メートルほどまで生長します。雌雄同株で花が雄花と雌花に分かれています。 雄花は花茎にいくつか均等につき、雌花は葉の脇に1つつきます。雌花は花の付け根が膨らんでいます。 花色は黄色で径は5cmくらい。葉には柄があり、互生と呼ばれる、茎から互い違いに生える性質を持ちます。
葉の表面はざらざらしますが、毛は生えていません。果実を食用として用いるほか、茎を切ったときに得られるへちま水は化粧水や飲み薬、塗り薬として用いられます。また、完熟して乾燥した果実を、1週間ほど水にさらして中身を腐らし、繊維質のみを残して乾燥させたものを浴用や炊事用のスポンジとして用います。色々な用途に利用できる実用的な植物です。
近年では緑のカーテンとしても人気が高まっています。ネットなどに這わせ、大きな葉で夏の日差しを遮ることで太陽から伝わる熱を和らげることに使われます。小学校の教材としても古くから用いられ、育てて利用することで植物への興味を育てることに効果を発揮しています。種苗会社からは主に食用に適した品種を選抜して育種し、「食用ヘチマ」として販売しているものもあります。
緑のカーテンを作れる植物や果実の育て方に興味がある方は下記も凄く参考になります♪
タイトル:ナーベラー(ヘチマ)の育て方
タイトル:スイカの育て方
タイトル:ツルムラサキの育て方
タイトル:ミニメロンの育て方
-

-
コマチリンドウの仲間の育て方
コマチリンドウの仲間は、30種ほどあります。もとはヨーロッパ産で、山野草として、自然の中で、そのかわいらしい小さな花を咲...
-

-
レモンの育て方
レモンの原産地や生息地はインドのヒマラヤ地方とされ、先祖とされている果物は中国の南部やインダス文明周辺が起源です。そして...
-

-
ペンツィアの育て方
特徴としては、種類はキク科のペンツィア属になります。1年草として知られています。花が咲いたあとに種をつけて枯れますから次...
-

-
フジの育て方
藤が歴史の中で最初に登場するのは有名な書物である古事記の中です。時は712年ごろ、男神が女神にきれいなフジの花を贈り、彼...
-

-
ミラクルフルーツの育て方
小さな赤い果実のミラクルフルーツは、あまり甘くなく、食した後、しばらくは、酸味のあるものを食べると、甘く感じ、とてもおい...
-

-
シェフレラの育て方
シェフレラは台湾や中国南部を原産としたウコギ科の常緑低木です。手の平を広げたような可愛らしい葉が密集して育ちます。ドイツ...
-

-
しだれ梅の育て方
しだれ梅は原産が中国であり、古くから観賞用として親しまれている木のひとつです。しだれ海の原産は中国ですが、現在では日本で...
-

-
ヤマシャクヤクの育て方
ヤマシャクヤクは、ボタン科、ボタン属になります。ボタン、シャクヤク、ユリといいますとどれも女性に例えられる事がある花です...
-

-
植物を栽培するに当たって注意しなければならない事。
何かの植物を栽培したり、種から育てたりするのはとても楽しい事です。それは娯楽や趣味にもなりますし、その結果できた物を収穫...
-

-
ナシの育て方
ナシの歴史は、中国の西部から南西部を中心として、世界中に広がりました。原産地となる中国から、東に伝わって品種改良が進んだ...





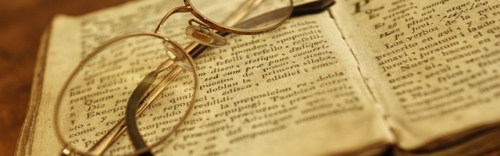





熱帯アジアを生息地とするインド原産の植物です。日本には中国を通して江戸時代に伝わったと言われています。ヘチマは元々、果実を乾燥させたときに繊維状になるので「糸瓜(イトウリ)」と呼ばれていました。それが「トウリ」に縮まり、「トウリ」の「ト」はイロハ歌の「ヘ」と「チ」の間にあることから「ヘチ間」から「ヘチマ」と呼ばれるようになったそうです。