ヒマラヤスギの仲間の育て方

育てる環境について
ヒマラヤスギの仲間の栽培は、非常に育てやすい部類に入ります。ただし、挿し木すると定着し難いきらいがあるので注意してください。植え込みに適した場所についてですが、日本の酷暑にも強く、ある程度耐寒性があるのでよほど寒い場所でなければ育ちます。
最低気温がマイナス6度を下回らなければだいたい大丈夫です。あと、日当たりは良いに越したことはありませんが、日陰でもそれなりに育ちます。土もそれほど気にしなくても大丈夫ですが、水はけが良いほうが好ましいです。土壌が湿潤だともともと浅い根がさらに浅く育ちます。
問題となるのは大きく育つ割に根の張り方が浅いことです。台風など強風で簡単に倒れてしまいます。土が湿潤であるとか関係なく、対策をしたほうが良いでしょう。まず風が吹き抜けるような場所はなるべくやめるべきです。できれば風の影響をまともに受ける場所も避けたいところです。
あとはしっかりとした支柱を用意しましょう。場所については大きく育つことも念頭においてください。特にほったらかしの状態で育てると高さが30m以上になりかねません。屋根などの下で育てることは無いと思いますが、横にも大きく育つのですぐ近くに建物がある場所は注意が必要です。
もしも十分なスペースがあるなら、手を加えず放任して雄大に育てるのも良いかもしれません。プランターで栽培するのなら、水はけを良くしてください。それ以外は特に気にする必要はありません。中粒の赤玉土2に対し、完熟腐葉土か樹皮堆肥を1の割合で混ぜた土を使用すればよいでしょう。
種付けや水やり、肥料について
植え付けの時期は2月から4月の中旬になります。移植する場合もこの時期に行います。種まきから始める場合は種を購入するのはもちろん、球果から得られる種を利用することもできます。種まきは3月に行います。1年したら鉢上げしてください。
苗を購入する場合は見た目を重視して選びましょう。たいていは観賞用として育てるはずなので、形の悪いものは買わないようにしましょう。植え替えする予定なら構いませんが、ヒマラヤスギはとても大きくなるので、しっかりと間隔をとって植えてください。
家の庭で育てるのなら、よほど広い庭でもない限り覚悟が必要です。おそらく自分では剪定できないでしょうから、業者に依頼することになるので費用がかかります。もし放っていたら隣家に迷惑をかけたり道路にはみ出たりと大変なことになります。安易な気持ちで栽培するのはお勧めできません。
広い敷地に植える場合は一本だけでも絵になります。日当たりの良い場所で育てて剪定しなければ、非常に大きく育つので雄大な姿を楽しむことが出来るでしょう。苗木を植える前に堆肥や腐葉土をすきこんでおきましょう。風に弱いと書きましたが苗木のうちは特に倒れやすいので、
必ず支柱を用意してください。水やりは植え込んだ時だけで大丈夫です。もし乾燥した状態が続くようなら水をやりましょう。肥料は3月頃に寒肥として、堆肥や油かすを株元のまわりに埋めましょう。プランター栽培なら化成肥料を追肥してください。他にはする必要はありません。
増やし方や害虫について
種は球果から採取することが出来ます。秋のうちに熟している球果から種を採取して、乾燥しないように保管しておいてください。球果は熟するのに2年ぐらいかかります。接ぎ木で苗を増やすのであれば、2月から3月の初めに種から育てておいた2、3年生苗を台木として使います。
前年に伸びた若い枝を使って穂木にします。穂木は真っすぐ伸びた枝の先を使うと形の良い苗になります。ヒマラヤスギの仲間の気をつけるべき病気は特にありませんが、毛虫が発生しやすく食害が起こります。例えばクロマツなどに発生しやすいマツカレハという大型の毛虫があげられます。
樹皮の隙間や樹の下で冬を越した幼虫が春になると葉を食べはじめます。夏に産卵を行い卵からかえった幼虫も葉を食べて11月ごろに木を降り始めます。この時にあらかじめ地上から1、2mの高さに菰(こも)を巻きつけておけば菰の中で越冬しようと幼虫が入り込みます。
翌年の2月までに菰を外して処分すればよいわけです。他にはハマキムシという口から糸を吐いて葉を束ねて巣を作る害虫がいます。この虫も葉を食べるので駆除してください。中には枝や幹を侵食する種類もいます。この虫は樹の上で越冬します。
枝に積もった古い葉に潜りこむので取り除いておくと良いです。これら毛虫は薬剤で駆除できます。ヒマラヤスギで他に気をつけるべきことは、やはり強風対策です。どうしても不安であればちらし玉という形で剪定することで風への抵抗が小さくなり倒れにくくなります。
ヒマラヤスギの仲間の歴史
ヒマラヤスギはヒンドゥー教では、古来から聖なる樹として崇拝の対象とされてきました。ヒマラヤスギの集まる森のことをDarukavanaといい、これは聖なる場所という意味を持ちます。例えばヒンドゥー教の神話では、インドの賢人がこういった森に住み、シヴァ神を崇め苦しい修行を重ねたと云われています。
このような逸話がいくつも存在します。聖書においてもレバノンの香柏と訳されるレバノンスギは、神の気高い樹とされ教会を建築すると植樹する習慣があります。レバノンスギは木材としてもメソポタミアや古代エジプトの時代から利用されてきました。
レバノンの住人であったフェニキア人は、レバノンスギを使ってガレー船を建造し木材を輸出することで地中海に進出しました。現在のレバノン共和国の国旗のデザインにも使われています。さてヨーロッパでも公園の樹として親しまれているヒマラヤスギですが、
日本に入ってきたのは明治になってからの西暦1879年、明治12年のことだといわれています。横浜に住んでいたイギリス人であるヘンリー・ブルックが、インドのカルカッタから取り寄せた種子を植えたのが始まりでした。今でも横浜の山手公園内で、
ブルック松といわれるヒマラヤスギたちが見られます。ただし、これにはもう一つ説があって、元アメリカ大統領であるグラント将軍が来日した時に、芝の増上寺に植樹したのが最初というものです。これは門前に植えられグラント松と呼ばれています。どちらにせよ明治時代の前半には伝わっていたということです。
ヒマラヤスギの仲間の特徴
ヒマラヤスギはマツ目マツ科ヒマラヤスギ属の常緑針葉樹です。名前にスギと有りますがマツの仲間です。スギはスギ科スギ属なので近縁でさえありません。葉がスギに似ているのでこのような名前になりました。冬になる頃、マツボックリができます。
日本では高さは20~30m、それ以上にもなります。その美しい姿からコウヤマキやナンヨウスギと共に世界三大公園木と称されています。ヒマラヤスギ属にはヒマラヤスギ、レバノンスギ、アトラススギ、キプロススギの4種があります。
ここではこれら4種をヒマラヤスギの仲間として育て方などを紹介させていただきます。ヒマラヤスギの原産地はヒマラヤ山脈西部の高地で、生息地は西ヨーロッパや地中海と黒海沿岸、中国中南部、北米と広く分布しています。レバノンスギの原産地はレバノン、シリアの高地で、
この他に生息地としてはトルコやモロッコなど地中海沿岸があげられます。アトラススギは北アフリカ地中海沿岸に分布、キプロススギはキプロス島の固有種となっています。さて、ヒマラヤスギは園芸植物として、特にヨーロッパの公園に植樹されることが多いのですが、建築資材としても昔から重宝されています。
耐久性や難腐敗性が高く、木目も美しいからです。レバノンスギも同様です。樹には芳香があるので香料としても利用されています。また、精油は虫除けやカビ防止に使えます。現在、レバノンスギは絶滅の危機に貧しており、保護林を設定して残したり植樹活動が行われています。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:ニオイヒバの育て方
タイトル:イトスギの仲間の育て方
タイトル:フトモモの育て方
タイトル:ヒメシャラの育て方
-

-
奇想天外(ウェルウィッチア)の育て方
ウェルウィッチアは生息地をアフリカのアンゴラ及びナミビアのナミブ砂漠にしている裸子植物の一つです。日本では2つの和名があ...
-

-
きつねのぼたんの育て方
きつねのぼたんはキンポウゲ科の多年草です。分布は幅広く北海道、本州、四国、九州、沖縄や朝鮮半島南部にも存在します。原産は...
-

-
パンジーの育て方
パンジーの原産はヨーロッパで、生息地は世界世界各国に広がっています。パンジーは交雑によって作られた植物です。その初めはイ...
-

-
ツニアの育て方
この花の特徴はラン科です。園芸分類としてもランになります。見た目もランらしい鮮やかで豪華な花になっています。多年草で、草...
-

-
アセビの育て方
アセビは日本や中国が原産で、古くから日本人の生活になじんでいた植物です。その証拠に枕草子や古今集のなかでその名がみられる...
-

-
パセリの育て方
その歴史は古く、紀元前にまでさかのぼります。特徴的な香りにより、薬用や香味野菜として使われてきました。日本には、鎖国時代...
-

-
ニンジンの上手な育て方について
ニンジンは、春まきと夏まきとがあるのですが、夏以降から育てるニンジンは、春に比べると害虫被害が少なく育てやすいので、初心...
-

-
レンゲツツジの育て方
この花の特徴は、ビワモドキ亜綱、ツツジ目、ツツジ科、ツツジ属になります。見た目を見てもツツジに非常に近い植物であることが...
-

-
ダーウィニアの育て方
ダーウィニアの特徴を挙げていきます。まずは、植物の分類ですが、ダーウィニアはダーウィニア属のフトモモ科に属します。このダ...
-

-
シュガーバインの育て方
シュガーバインは、ブドウのような葉をつけ、葉のつけ根からひげのような根(気根)が伸びて、他の植物に巻きつくことで広い面積...




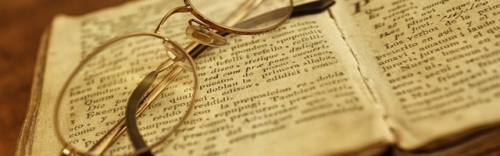





ヒマラヤスギはヒンドゥー教では、古来から聖なる樹として崇拝の対象とされてきました。ヒマラヤスギの集まる森のことをDarukavanaといい、これは聖なる場所という意味を持ちます。例えばヒンドゥー教の神話では、インドの賢人がこういった森に住み、シヴァ神を崇め苦しい修行を重ねたと云われています。