ハーデンベルギアの育て方

育てる環境について
ユーカリの林の中、石灰岩地帯の砂丘と言った生息地を持つことからも、水はけが良い環境を好みます。また、日光を好みますが、真夏の太陽や冬場の寒さは苦手な植物であり、春や秋は風通しが良く日当たりが良い環境で管理をし、夏場は午前中は太陽の光があたり、
午後は日陰になるような場所で管理をしていきます。冬場については室内に持ち込み、日当たりの良い窓際などで栽培をすると言った形で育ててると良いです。但し、鉢植えだけではなく、庭植えでも環境が整う事で栽培が可能になります。尚、庭植えを行う場合には、
夏場の暑さに注意が必要であり、コンクリートやアスファルトの照り返しが有る場所は避けてあげることが無難であり、この照り返しにより、花は傷んでしまうので注意が必要です。因みに、ハーデンベルキアと言う植物は日光を好みますが、日陰でも育つ性質でもある、
比較的耐陰性であり、日陰の時間帯が多い場所でも栽培は可能なケースもあり、日陰の時間が多くても水はけが良い場所であれば育てる事も出来ます。因みに、マンションなどのベランダで鉢植えでの栽培も可能になりますが、真夏の太陽でベランダの表面が高温になる場合など、
直接そこに鉢植えを置いてしまうと高温になりやすいため弱ってしまうので注意が必要です。そのため、ベランダなどで栽培を考えている場合は、棚などを設けて、棚の上で管理をしてあげることでコンクリートからの熱を与えずに栽培をすることが出来ます。
種付けや水やり、肥料について
育て方のポイントとしては置き場所に注意する事や、強い直射日光が当たる場所を避ける事などが挙げられます。尚、耐寒温度は2度から3度であり、暖地の場合や平地の場所であれば戸外での越冬も可能になりますが、霜が発生した時や寒風に当ててしまうと株が傷んでしまうので注意が必要です。
一年を通して比較的暖かい場所であれば庭植えも可能ですが、気温が著しく低くなる地域などでは鉢植えでの管理の方が安心ですし、鉢植えであれば自由に場所を移動させて管理が出来るのでお勧めです。植え付けは5月頃に行い、肥料は5月から7月にかけて施します。
開花時期は、植え付けた翌年の3月から5月にかけてとなりますが、種が熟す事で豆果から種が零れ落ちて発芽する事もありますが、基本的に種で増やすのではなく挿し木が一般的だと言います。植え付けを行う時の用土は水はけが良い物を選んであげるのコツで、
赤玉土の小粒を5、腐葉土を3、川砂を2の割合で混ぜ合わせて用土を作り植え付けを行います。因みに、根が鉢の底から出て来た時などは一回り大きな鉢に植え替えを行う必要が有りますが、植え替えを行うタイミングは花後が最適であり、6月頃までに行うのが良いとされます。
過湿や乾燥を嫌いますので、水やりは重要な要素となります。生育時期の場合は、土の表面が乾いた時にたっぷりと与え、冬場は休眠状態になるため、土の表面が乾燥して数日経過したら水を与える程度で良いでしょう。
増やし方や害虫について
ハーデンベルギアは、肥料は多くを必要としませんが、花後5月から7月の期間に、ゆっくりと効果を得られる粒状の肥料、固形の油かすなどを月に1度程株元に施してあげます。ハーデンベルギアなどのようなマメ科の植物は、窒素分が多く含まれている肥料を与えることで、
葉が茂り過ぎてしまい、花つきが悪くなるので注意が必要です。増やし方は種による増やし方も有りますが、一般的には挿し木を利用して増やす方法になります。枝を、先端部分から5cm程の場所で切り取り、それを赤玉土や川砂が入っている鉢の中に挿しておきます。
挿し木による適期は5月頃が最適であり、挿した後に乾燥しないように管理を行うのがコツであり、適量の水を与えて乾燥を防止する事で根が出て来ます。また、この状態でそのまま管理をして、秋ころになったら鉢に植え付けを行います。尚、1本だけではなく、
2本から3本ほどまとめて植えてあげる方が全体的なボリュームが出て来ますのでお勧めです。因みに、ハーデンベルギアはツル性の植物であり、ツルが良く伸びます。そのため、支柱を立ててあげてツルが絡まるようにしてあげる事も大切です。
園芸ショップなどでも購入できる朝顔などに利用するアンドン支柱を利用するとまとめやすくなり便利です。尚、ハーデンベルギアはかかりやすい病気や害虫というものは得に有りませんが、春先などにアブラムシなどが発生した時などは、殺虫剤を利用して防除してあげます。
ハーデンベルギアの歴史
ハーデンベルギアはオーストラリア東部に位置するタスマニアが原産のツル性の常緑樹で、コマチフジ・ヒトツバマメ・ハーデンベルギアと言う別名を持ちます。マメ科の植物で、ツル性であることからも草丈は50cmから3mなのですが、中には4メートルにまで成長するものも有ります。
尚、タスマニアには3種類が分布しており、そのうちの1種のハーデンベルギア・ヴィオラケアは日本国内で栽培が行われている品種になります。因みに、分類はマメ科のハーデンベルギア属、属名はHardenbergiaと表記され、この属名はドイツのハーデンベルグ伯爵夫人
(C. F. von Hardenberg)の名前から由来していると言います。尚、主な生息地と言うのはユーカリの林の中、石灰岩地帯の砂丘などであり、栽培する場合などでは生息地に近い環境にしてあげることで成長を促進させることが出来ますし、ツル科の植物であることからも大きく成長させることも出来ます。
また、日本で栽培が行われているハーデンベルギア・ヴィオラケアは、紫色の花が特徴の植物であり、ヴィオラケアと言うのは「すみれ色の」と言った意味を持っており、花の色から由来して付けられた名前だと言います。
因みに、マメ科の植物と言うのは、複数の小葉に分かれた「複葉」が一般的だと言われていますが、この植物についてはマメ科の植物でありながらも、小葉に分かれない1枚の単葉が特徴であり、別名として「ヒトツバマメ(一つ葉豆)」と言った和名が有ると言います。
ハーデンベルギアの特徴
オーストラリアの中でも東部に位置するタスマニア島を原産とするツル性の植物がハーデンベルギアであり、生息地はタスマニアのユーカリ林、石灰岩地帯の砂丘と言った場所が生息地になります。水はけの良い環境を好む植物であり、栽培する場合には水はけを考慮した環境づくりが大切です。
常緑低木で、枝はツル状になっており、小さな蝶の形の花が集まり穂状につくのが特徴です。尚、花の色には濃い紫色、桃色、白色などが有りますが、国内に流通しているヴィオラケアは紫色の花を咲かせる品種が一般的です。国内に流通されているヴィオラケアの花の特徴は、
花径が約1㎝ほどの紫いろをした蝶のような形をした花びらを茎に多数付けるのが特徴で、葉の特徴は3出複葉と呼ばれる、1枚の葉が3つの小さな葉に分かれた形になっています。また、これらは互い違いに生えると言う互生であり、小葉の形状は笹の葉のような形をした披針形になっています。
マメ科の植物と言う事からも花が咲き終えた後には豆果が出来ますが、莢の中には種子が入っており、この種を使えば増やすことが出来ると言います。因みに、ヴィオラケアは小町藤(コマチフジ)と呼ばれる流通名で知られているのですが、
近縁種にはコンプトニアナと呼ばれるオーストラリア原産のハーデンベルギアも有ります。コンプトニアナにおいても花の色は濃い紫色ですが、日本の中には白色やピンク色などの花を持つハーデンベルギアを栽培している人も少なくありません。
花の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:キングサリの育て方
-

-
ダイアンサスの育て方
ダイアンサスは、世界中に生息地が広がる常緑性植物です。品種によって、ヨーロッパ・アジア・北アメリカ・南アフリカなどが原産...
-

-
ディエラマの育て方
いろいろな名前がついている花ですが、アヤメ科になります。球根によって生育をしていく植物で、多年草として楽しむことができま...
-

-
カイランの育て方
カイランは、アブラナ科の緑黄色野菜です。別名チャイニーズブロッコリーともいい、キャベツやブロッコリーの仲間で、カイランサ...
-

-
ユーフォルビア(‘ダイアモンド・フロスト’など)の育て方
ユーフォルビア‘ダイアモンド・フロスト’などは小さな白い花のようなものが沢山付きます。だからきれいで寄せ植えなどに最適な...
-

-
アナカンプセロス、アボニアの育て方
種類としてはスベリヒユ科になります。多肉植物で、多年草となります。高さとしては3センチから10センチぐらいですから土から...
-

-
リョウブの育て方
両部の特徴においては、まずは種類があります。ツツジ目、リョウブ科になります。落葉小高木になります。若葉に関しては古くから...
-

-
キツリフネの育て方
特徴として、被子植物、双子葉植物綱、フウロソウ目、ツリフネソウ科、ツリフネソウ属になっています。属性までツリフネソウと同...
-

-
クレマチス(四季咲き)の育て方
クレマチスは、キンポウゲ科センニンソウ属(クレマチス属)のこといい、このセンニンソウ属というのは野生種である原種が約30...
-

-
フィットニアの育て方
フィットニアはキツネノマゴ科フィットニア属の植物です。南米、ペルー・コロンビアのアンデス山脈が原産の熱帯性の多年草の観葉...
-

-
グーズベリーの育て方
グーズベリーという植物をご存知ですか、日本ではもしかしたらセイヨウスグリの名前の方が有名かもしれませんが、スグリ科スグリ...




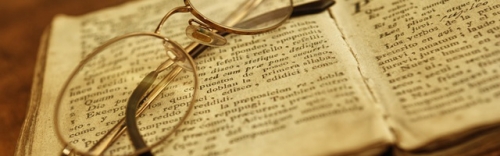





ハーデンベルギアはオーストラリア東部に位置するタスマニアが原産のツル性の常緑樹で、コマチフジ・ヒトツバマメ・ハーデンベルギアと言う別名を持ちます。マメ科の植物で、ツル性であることからも草丈は50cmから3mなのですが、中には4メートルにまで成長するものも有ります。