ルドベキアの育て方

ルドベキアの植えつけ
ルドベキアは、種でも苗でも流通しています。日当たりが良いところが大好きですので、植え付けの際は、花壇でも鉢でも日当たりの良い場所を選びましょう。種付けで植え付けるのが簡単です。ソメイヨシノが開花する時期から種まきができ、夏頃に開花します。
種まきが遅くなると開花は来年の夏になります。発芽率はとても良く、成長する力も強いです。大きく育ってから植え替えするのは難しくなるので、本葉が3~4枚程度までに育ったら、花壇や鉢に植え替えます。苗の場合も、大きくなりすぎないうちに、花壇や鉢など、お目当ての場所に植え替えましょう。
水はけが良く肥料持ちの良い土を好みます。花壇の場合は、土を良く耕し、堆肥や腐葉土を混ぜ込んでやり、緩効性化成肥料を施します。鉢の場合は、水はけの良い土を使いましょう。
赤玉土(中粒):腐葉土:酸度調整済みピートモスを5:3:2で配合し、緩効性化成肥料を施します。植え付けの際には肥料を施しますが、育ってきたら花壇の場合は特に肥料は必要ありません。鉢の場合は、4月~10月に緩効性化成肥料を施しましょう。
ルドベキアの育て方と管理
ルドベキアは日当たりを好みますので、育て方の第一条件としては、日の当たるところに植えてあげる、日の当たるところに鉢を置いてあげる、ということです。半日陰でも育たないことはありませんが、花付きが悪くなりますので、おすすめできません。
じめじめしたところが嫌いで、そこそこ乾燥に強く、真夏の直射日光にも耐えますので、そのようなところに植えてあげると、花付きも良くルドベキアの強みを生かせます。過湿には弱いので、水のやり過ぎには注意します。育て方にもよりますが、花壇で育てているなら、雨が降らず乾燥した時期が続かない限り、水やりは基本的に必要ありません。
鉢で育てているなら、土が乾いたら水をやるようにします。冬を越させる場合、北風にさらされないように保護してやり、乾かし気味に育てます。ただし、強い乾燥は葉が痛むので避けます。無理に冬を越させなくても、こぼれ種で翌年は必ずといっていいほど、また生えてくる繁殖力の非常に強い植物です。
そのため、花壇で育てる育て方の場合、植える場所には気をつける必要があります。ルドベキアは草丈もかなり高くなりますし、雑草として日本に根付いてしまうほど繁殖力の強い植物です。このため、植える場所によっては、一緒に植えている他の植物の成長を阻害してしまう可能性が高くなります。
花壇で育てるなら、他の植物を邪魔しない飛び地のような場所に植えるのが良いでしょう。毎年毎年こぼれ種で生えてくるのが嫌になったら、種ができる前に引き抜きます。春に生えてきたら抜いてしまいましょう。一度では無理かもしれませんが、何度か引き抜けば、繁殖力が強いとはいってもさすがに繁殖しなくなります。
育て方としては、野趣のある花ですので、整然とした花壇などにはあまり向かないかもしれません。繁殖力が強いことも考えて、ルドベキアのみ鉢で育てたり、イングリッシュガーデンのような自然風の花壇に少し陽気な雰囲気をプラスするという感じなら合わせやすいでしょう。
ルドベキアには色々な種類がありますので、ルドベキア・タカオ以外は混同されがちです。同じルドベキアでも、花色も形も色々ですので、初めてルドベキアを植えるなら、花が確認できてから購入する方が確実でしょう。
ルドベキアの種付け、栽培
ルドベキアは種でも苗でも流通していますので、増やす場合には、種付けでも株分けでもできます。簡単なのは種付けです。水はけが良く肥料持ちの良い土に、土をかぶせずに種をまきます。発芽する確率も高いです。種付けの時期は、花の終わる9月~10月、花の咲く前の3月が適しています。
9月~10月頃の種付けの場合は、凍ったりしないように冬を越させます。3月頃の種付けの場合は、発芽に必要な温度が不足することがあるので、発芽率が悪いようなら、ビニールで覆うなりして保温してあげるようにします。発芽したら、小さな鉢に鉢上げして栽培します。
本葉が3枚~4枚ほどになったら、花壇に植えるなり鉢植えなりにしてあげましょう。大きくなってからだと、移植が難しくなります。株分けの場合の栽培は、芽吹きの勢いが良くなる4月~5月に行います。茎葉に必ず根が付くようにして分け、株分けしたものを植え付けて栽培します。
この栽培方法の場合、大きく育ってからの植え付けになるので、植え付けてからしばらくは成長が悪くなることがあります。株分けでの栽培方法は、種付けより少し手間がかかりますが、数年に一回のペースでやって上げると、たくさん増やすことができます。
ルドベキアの病害虫
寒暖の差が大きいと、うどんこ病が発生することがあります。風通しの良いところで管理して、枯れ葉や花がらはきちんと摘み取り、予防するようにします。
害虫は、3月~10月にハモグリバエが付くことがあります。葉に落書きのような白い色が抜けたような模様があったら、ハモグリバエの幼虫が葉の中を食べた跡ですので、葉ごと指でつまんでつぶします。
ルドベキアの歴史
ルドベキアは北米を生息地としており、15種類ほどの自生種がある、アメリカを原産とする植物です。和名ではオオハンゴウソウ属、または花の名前から取ったルドベキア属のキク科です。名付け親は18世紀のスウェーデンの植物学者であるカール・フォン・リンネです。
彼が通ったウプサラ大学での植物学の師であるオロフ・ルドベックと同名の父親を讃えて、この名となりました。日本には、戦前に観賞用として入ってきた歴史があります。和名でオオハンゴウソウ属と名付けられたのは、日本にもともと自生するハンゴウソウに葉の様子が似ており、ハンゴウソウよりも背が高いことから名が付けられました。
導入当初は切り花用でしたが、現在は花壇用にシフトしています。もともとは草丈も花もかなり大きくなるのですが、90年代からは品種改良で小型の矮性種が多く栽培されるようになりました。とても繁殖力の強い植物で、丈夫でもあるため、外来種ではありますが日本に根付き、帰化植物となっています。
現在では中部山岳地帯や北関東以北では邪魔者扱いになるほど繁殖しているところもあります。ルドベキアには色々な種類がありますが、その中のルドベキア・ラシニアタはオオハンゴウソウと呼ばれ、特定外来生物に指定されて、駆除対象となっています。
ルドベキアの特徴
一口にルドベキアと言っても、色々な種類があり、1年草タイプと多年草タイプがあります。花色も色々で、黄色やオレンジ、赤などの花色の他に、あまり出回りませんがピンク、緑、白などの花色もあります。中心部も黒色や緑色のものがあり、様々な顔を見せてくれます。その中でもポピュラーなのは花色が黄色のものでしょう。
開花時期が6月中旬~10月中旬くらいで、夏を含むので、ヒマワリの代わりのように咲き乱れる様子を見ることができます。背丈は1~1.5メートルくらいになり、花は大きいもので20センチくらいになりますので、まさにヒマワリのようです。背丈が40~50センチくらいの、和名でアラゲハンゴンソウと呼ばれる矮性種もあります。
色々な種類がありますが、市場によく出回っているのは、アラゲハンゴウソウや1メートルくらいの背丈で小さな黄色い花をたくさん咲かせるルドベキア・タカオ等です。多年草として冬を越すこともありますが、冬に枯れてしまってもこぼれ種で翌年もきちんと育ちます。そのため、1年草の扱いで育てることもできます。丈夫で繁殖力旺盛な植物なので、初心者でも育てやすい植物です。
花に興味ある方は下記の記事も詳しく書いてあるので、凄く参考になります♪
ムスカリの育て方
マリーゴールドの育て方
ナスタチュームの育て方
ニチニチソウの育て方
-

-
スターアップルの育て方
スターアップルは熱帯果樹で、原産地は西インド諸島および中南米です。アカテツ科のカイニット属の常緑高木です。カイニット属と...
-

-
セラスチウムの育て方
セラスチウムは、20センチ前後の、あまり大きくない花になります。ですが、上へと伸びるのではなく、どんどんと横に伸びていき...
-

-
シーマニアの育て方
シーマニアは、南アメリカのアンデス山脈の森林が原産の植物であり、その生息地は、アルゼンチンやペルー、ボリビア等の森林です...
-

-
ニンニクの育て方
ニンニクの原産地は中央アジアと推定されていますが、すでに紀元前3200年頃には古代エジプトなどで栽培・利用されていたよう...
-

-
温州みかんの育て方
みかんは、もともとインドやタイ、ミャンマーなどが原産だと考えられています。生息地は、現在では世界各国に広がっていますが、...
-

-
シロダモの育て方
現在に至るまでに木材としても広く利用されています。クスノキ科のシロダモ属に分類されています。原産や分布地は本州や四国や九...
-

-
レプトシフォンの育て方
この花についてはハナシノブ科、リムナンツス属になります。属に関しては少しずつ変化しています。園芸における分類としては草花...
-

-
ヤマブキソウの育て方
特徴としては多年草であることが挙げられます。根がついていて毎年花を咲かせてくれるようになっています。色はなんといっても鮮...
-

-
レナンキュラスの育て方
レナンキュラスはキンポウゲ科・キンポウゲ属に分類され、Ranunculusasiaticsの学名を持ち、ヨーロッパを原産...
-

-
ナンブイヌナズナの育て方
ナンブイヌナズナは日本の固有種です。つまり、日本にしか自生していない植物です。古くは大陸から入ってきたと考えられますが、...





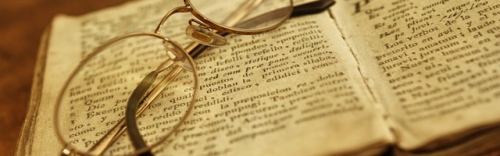





ルドベキアは北米を生息地としており、15種類ほどの自生種がある、アメリカを原産とする植物です。和名ではオオハンゴウソウ属、または花の名前から取ったルドベキア属のキク科です。名付け親は18世紀のスウェーデンの植物学者であるカール・フォン・リンネです。