ツルバキアの育て方

育てる環境について
ツルバキアの育て方のポイントは、日当りの良い場所、及び水はけのよいところで栽培することです。日当りと水はけを注意すれば、場所を特別に選ばずに育てることができます。日陰で育てた場合には、花の付きが悪くなる可能性も高くなりますので注意しましょう。
やせ地や乾燥地での栽培も可能です。また、耐寒性にもすぐれている特徴があり、南関東以南では、屋外でも冬越しすることができます。軽めの凍結や霜には耐えることができますが、マイナス5度以下になるような環境になる場合は、防寒をしてあげることがおすすめです。
一時的に掘り下げをすることで、乾燥貯蔵をすることも可能です。また、一般的には、宿根草と同様に育てることができます。植え付ける際には、日当りのよいところに腐葉土を良くまぜて植えます。鉢植えにすると、冬の寒い時期に室内に入れられるのでおすすめです。
寒冷地で栽培する際には気をつけましょう。それ以外の地域では、数年間は植えっぱなしでも管理ができるため、初心者の方でも比較的育てやすい植物です。冬の寒い時期の株の凍結の対処法としては、株もとに落ち葉やバークチップなどを敷いておくことがポイントです。
また、酸性土ではよく育ちませんので、植える前には、石灰などを巻き、中和してあげることをおすすめします。斑入りの種は、シルバーレースと呼ばれており、一般的に成長が遅い性質をもっているため、鉢植えをしたり、寄せ植えをするのも良いでしょう。
種付けや水やり、肥料について
ツルバキアを庭植えする場合には、水やりはほとんど必要がない性質をもっています。鉢植えで育てる場合には、用土が乾いた際にたっぷりあげましょう。低温期で成長が止まっている場合には、乾燥させても問題はありません。肥料は、花つきをよくする目的や、
生育の促進目的で使用します。春と秋に置き肥をします。緩効性の肥料を選びましょう。また、液体肥料を使用する際には、春頃から秋頃まで、月に一度与えてあげましょう。鉢植えで土を作る際には、赤玉土を7、腐葉土を3の配合しましょう。
一般的に花草用の培養土でも十分に育てることが可能です。水はけがよいものを選ぶのがポイントで、土の質はこだわらなくても可能です。肥沃な重い土ではかえって育ちが悪くなる場合もありますので通気性のよいものを選びましょう。窒素が多く含まれている肥料を与えすぎてしまった場合は、
葉っぱばかりがよく茂る傾向にあります。その分、花が咲きにくくなる傾向にありますので注意しましょう。白い縁取りがある斑入りのものは、花が咲かない時期でもさわやかなイメージを与えてくれると人気となっています。バエリガータなどがあります。植え付ける場合には、
1株で植えるよりも数株ずつまとめて植え付ける方が見栄えがよいためおすすめです。球根を植え付ける場合には、3月から4月ころはまだ球根が小さい場合が多くあるため、大きく育つまでには時間がかかります。葉っぱを収穫する際には3月下旬から11月中旬にハサミで切り取って収穫しましょう。
増やし方や害虫について
増やし方は、株分けと種まきの二種類があります。株分けをして増やす場合には、4月から5月にかけて、もしくは9月から10月に掘り上げます。年を重ねるにつれて芽数が増えるため、大株に育ちます。大株に育ったら行ないましょう。3から10芽ほどのかたまりに分けてから植え付けましょう。
芽数が多い大株に育った場合にも、混み過ぎによる生育の悪さを確認することはまれです。ですが、球根が増えて窮屈になってしまった場合には、数年に一度ほど掘りあげてあげましょう。それ以外の場合には、増やす目的やスペースなどに応じて株分けと植え直しの作業は行ないましょう。
また、種まきで増やす場合には、個体差がでますが、種をまいてから二年から三年目で開花します。種の特徴は径が2ミリメートルから3ミリメートルほどで、黒色をしているのが特徴です。種をとりたい場合には、花茎切りを行ないます。花が咲き終わったものを順番に切り取り、
種をとりたい部分のみ花を残しておくことで種を収穫することができます。大きく育てたい場合には、鉢植えではなく、花壇植えにし、株を大きく育てることをおすすめします。また、害虫はほとんどつかないのがツルバキアの性質です。
特にソサエティガーリックを植えた場合には、その強い香りを嫌う害虫も存在しているため、コンパニオンプランツとしても利用するのも良いでしょう。ソサエティガーリックは、24種類ほどあり、南アフリカが原産となっています。
ツルバキアの歴史
ツルバキアは、原産、生息地共に南アフリカのものが多くあり、主に24種類が自生しています。ユリ科のツルバキア属に属しています。属名であるツルバキアは、南アフリカのケープ植民地時代に由来がさかのぼります。18世紀、喜望峰の総督として存在していたオランダのツルバグの名前にちなんでいます。
日本明はルリフタモジと呼ばれ、ニラのことを古い時代では二文字と呼んでいたからという説もあります。また、イギリスではソサエティーガーリックという英名をつけています。甘い香りがすることから、スイートガーリックとも呼ばれています。足湯に加えることもできます。
身体を芯からあたためることができます。関節痛の緩和や、冷え性の改善などに効果があります。日本で普及しているのは、ツルバキア・フラグランスと、ツルバキア・ビオラケアの二種類です。副花冠の形が異なっています。フラグランスは、濃藤色の花を咲かせたり、
白やピンクなどの花を咲かせます。花からは甘い香りがしますが、茎を切った場合には、かすかににんにくのにおいがする性質があります。荒れ地でも育つツルバキアは、暖地ではグラウンドカバーとして人気があります。
また、年数が経った成球からは、花が何本も咲くため、切り花としても利用されています。花言葉には、落ち着きある魅力、小さな背信、残り香などが存在しています。また、日本では沖縄で帰化が報告されている帰化植物としても知られています。
ツルバキアの特徴
ツルバキアは、立ち姿が美しいのが特徴です。多年草の形態をもち、草丈は30センチメートルから60センチメートルほどです。アガパンサスを小型にした草姿をしています。花は六弁で、副花冠があるのも特徴です。副花冠は、スイセンに見られるようなものと似ています。
花の色は白色や紫色、ピンク色など、個体によって差があります。花のひとつひとつは、直径1センチメートルほどです。細長い茎の咲きに10数燐が密集して咲きます。花茎の長さはおおよそ40センチメートルから50センチメートル、その咲きに放射状に筒状の花が咲きます。
また、ネギ類やニラなどにみられる独特のにおいが葉と茎からします。葉っぱはおよそ長さ40センチメートルほどで、やや肉厚な性質をもっています。球根植物として扱われることが多いのが特徴です。白の斑入りの種も存在しており、株はロゼットです。
ポット苗状態で販売されていることが多くあります。暑さや乾燥にも強い性質を持っているため、ナチュラルガーデンやコンテナなどの寄せ植えにも向いています。アガパンサスと同様に利用をすることができ、長雨などにも耐えることができる性質を持っています。
宿根草と、球根の療法の性質を合わせ持っている特徴があります。主に栽培されているのは、ツルバキア・フラグランスという甘い芳香があるもので、切り花としても利用されています。また、四季咲き性が強いビオラセアは、春から冬の始まり前まで咲き続けるため、人気があります。
-

-
カンナの育て方
原産地は熱帯アメリカで日本には江戸時代前期にカンナ・インディアカという種類のものが入ってきて、現在では川原などで自生して...
-

-
ティアレ・タヒチの育て方
ティアレ・タヒチのティアレとはタヒチ語で花という意味があります。つまりティアレ・タヒチはそのままタヒチの花という意味の名...
-

-
コマツナギの育て方
この植物は背丈が高く40センチから80センチまであり、マメ科コマツナギ属の落葉小低木に分類されています。同じマメ科に属す...
-

-
ミヤマハナシノブの育て方
この花はナス目に該当する花になります。ハナシノブ科、ハナシノブ属に属します。高山などをメインに咲く山野草で、多年草です。...
-

-
ベニジウムの育て方
ベニジウムは南アフリカ原産の一年草です。分類としてはキク科ペニジウム属で、そのVenidiumfastuosumです。英...
-

-
根茎性ベゴニアの育て方
ベゴニアはシュウカイドウ科シュウカイドウ属の植物です。ベゴニアには他種を交配して作られた様々な品種がありますが、それらを...
-

-
ベンケイソウの育て方
ベンケイソウは北半球の温帯や亜熱帯が原産の植物です。ベンケイソウ科の植物の種類は大変多く、またその種類によって育て方は多...
-

-
ペトレアの育て方
ペトレア属はクマツヅラ科の植物で、一口にペトレアといっても様々な種類があります。およそ30種類ほどあり、その中でも日本で...
-

-
カトレアの育て方について
カトレアと言えば、バラと並んで花のクイーンとも言える存在になっています。ただし、カトレアとバラには大きな違いがあります。...
-

-
アガスターシェの育て方
アガスターシェは、初心者でも簡単に育てる事のできる、シソ科の花になります。別名が沢山ありまして、カワミドリやアガスタケ、...




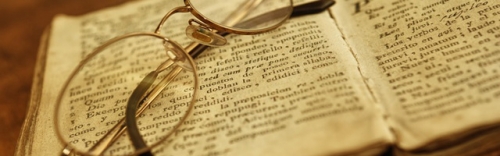





ツルバキアは、原産、生息地共に南アフリカのものが多くあり、主に24種類が自生しています。ユリ科のツルバキア属に属しています。属名であるツルバキアは、南アフリカのケープ植民地時代に由来がさかのぼります。