ヒイラギナンテンの育て方

ヒイラギナンテンの育て方
ヒイラギナンテンは庭木として植えたり、生垣に利用することが一般的です。日当たりと水はけがよければとくに気を遣わなくても育ってくれるところが魅力的で、園芸初心者でも育てやすいとされています。育て方というより、植える場所によって美しく育てられるかどうかほとんど決まってしまうといっても過言ではありません。
ヒイラギナンテンは日陰でも育つといわれています。確かに日陰でも枯れることはありませんが、徒長しがちになったり花が咲きづらくなることがあるため半日陰や日向に植えることをおすすめします。理想的なことをいえば、西日や強風にさらされない場所に植えるといいでしょう。
強烈な光にさらされると、葉焼けをおこさないまでもつやのある緑色が黄色くくすんだような色になってしまうため、注意が必要です。美しい紅葉を楽しむためには一日中日陰になってしまうようなところで育てることはさけましょう。最低でも半日は日照がないと、紅葉を楽しむことはできません。
植えつけに適した季節は春と秋です。植えつける場所の用土が痩せており乾燥しやすい場合には、腐葉土などを利用して土壌の改善を行ってから植えつけましょう。寒冷地では秋が深まってから植え付けると寒さで株が弱りやすいため、注意が必要です。
ヒイラギナンテンの魅力はなんといっても一年中美しい葉の色を楽しむことができるところです。紅葉し、花が咲き、実をつける、楽しみの多いところがヒイラギナンテンを栽培する魅力だと考えられます。できれば理想的な植え場所を作って、美しく育てたいものです。
水やりに関してですが、庭植えの場合でも真夏などに雨が降らない日が続いたときなどは水やりをしましょう。また、開花時期は土が乾きやすいことがあるため土の様子に気を配ることをおすすめします。
肥料は、春に花を咲かせる品種には2月頃、冬に花を咲かせる品種には4月頃、それぞれ油かすと骨粉を与えましょう。冬に開花する品種の場合は、肥料を与えるタイミングがずれると花芽がつかなくことがありますので時期に注意して与えます。
栽培中に注意したいこと
ヒイラギナンテンを栽培する際、花が咲き終わった後はそのままにせず根本から花茎を切り取りましょう。そのまま花をつけておくと美観をそこねるばかりか、実を作るために栄養を使ってしまい枝や葉の生長のさまたげとなってしまいます。
ヒイラギナンテンは放置しておくと縦方向には伸びますが、枝分かれしにくい性質があるためバランスの悪い樹形になってしまう場合があります。成長が緩慢なため、剪定をしなければならないほど枝がしげってしまうような状態にはふつうはならないのですが、長く伸びすぎた枝を切りとると見た目がすっきりとコンパクトに整います。
剪定の時期は花が終わった後の季節が適しており、大きくしたくないという場合には枝先から1節下を目安にして切ります。背が高く育ちすぎてしまったという場合には、好みの高さまで切断するといいでしょう。切断した場所から複数の枝が伸びてきて、形が整います。
コンパクトに形よく育てたい場合には毎年花後に剪定を行うことをおすすめします。ヒイラギナンテンを栽培中に注意したい病気にうどんこ病や立ち枯れ病があります。うどんこ病は春から秋にかけて発生する確率が高い病気です。葉に小麦粉をまぶしたような状態になって、見た目も悪いですし葉の栄養がすべて失われてしまい、植物を弱らせて最悪の場合には枯れてしまうこともあります。
症状を確認次第迅速に専用の薬剤を使用して治療する必要があります。立ち枯れ病は主に苗木のときに発生しやすく、土壌に住んでいる色々な種類の病原菌が原因となって植物を枯らしてしまう病気です。清潔な用土を使用し、水はけをよくすることで予防することができる場合もあります。
ヒイラギナンテンの増やし方
種付けの他にも挿し木で増やすことが可能です。種付けをするためには種を採取する必要があります。ヒイラギナンテンの種は、秋頃に黒みがかったブドウ色になって完全に熟した実から採取します。果肉をすべて取り除き、きれいに洗い流しましょう。
採取した種はすぐに植えないと発芽する確率が減りますが、種の採取が冬頃になってしまった場合は乾燥させないように保管しておき、3月か4月の温かい季節になってから植えます。乾燥しないように保管するためには、植木鉢に川砂などを入れて植木鉢ごと土の中に植える方法があります。
挿し木をする場合は6月か7月頃に充分に成熟した枝を10cmから15cmの長さで切断し、根本側の枝についた葉を取り除きます。ヒイラギナンテンは複葉で葉が多いため、先端に葉が数枚残っている状態になるまで取り除いてしまいましょう。枝を水を入れたコップに1時間程度さしておき、水揚げをします。
切り口に成長調整剤をまぶしておくとより発根しやすいです。挿し木用の土や小粒の赤玉土を入れた植木鉢にさして、たっぷりと水やりをして日陰で管理します。2か月から3か月くらいたった秋ごろに充分な大きさになったら鉢上げをします。庭に植えて楽しむことが多いヒイラギナンテンですが、挿し木で増やして盆栽仕立てに挑戦してみてはいかがでしょう。
ヒイラギナンテンの歴史
ヒイラギナンテンの原産地は中国や台湾で、東アジアや東南アジアを主な生息地としています。北アメリカや中央アメリカに自生する種類と合わせて、約100種類もの種類が存在します。ヒイラギナンテンは学名をMahonia japonica(マホニア・ヤポニカ)といいます。
マホニアはアメリカの植物学者バーナード・マホニアの名前にちなんだもので、ヤポニカには日本原産という意味がありますが、もとから日本に存在していたというわけではなく江戸時代に中国から渡来しました。漢字では柊南天と書き、葉が南天のように複葉で果実のつきかたが似ていることと、柊のようなとげを持っていることに由来しています。
別名はトウナンテンで、漢字で書くと唐南天です。日本では古くから生垣として利用されたり、立ち入り禁止の場所を示すために植えられたりしてきました。常緑性のため主に葉を楽しむために植えますが、葉だけでなく花と実を楽しむことのできる庭木として幅広く愛されています。
秋には紅葉し和風の庭にも、洋風の庭にもマッチするところが愛される所以かもしれません。実をつけた状態の枝を切り、フラワーアレンジメントや生け花として楽しむこともできます。ヒイラギナンテンの葉は柊と同じようにとげがあるため、魔除けとして鬼門に植えている家もあります。
ヒイラギナンテンの特徴
ヒイラギナンテンはメギ科の常緑低木です。開花時期は冬から春にかけてで、小さめの黄色い花を多く咲かせます。厚みと光沢があるギザギザした葉の先端は固い針状になっており、刺すと痛いです。花が終わった後には、青みがかったブドウ色の丸い果実をつけます。
果実は黒みがかったブドウ色に熟し、表面が粉をふいたように白っぽくなります。柊という名前がついているため誤解されがちですが、花は柊に似ていません。園芸種としてポピュラーなヒイラギナンテンの仲間に、葉が細長くなるホソバヒイラギナンテンや、非常に細くて繊細な葉をもつナリヒラヒイラギナンテンや、芳香のある花を穂のように咲かせるメディウムという種類があります。
木の高さは1.5メートルから3メートルほどになりますが、剪定によってコンパクトにまとめることが可能です。成長が比較的遅いため、狭い場所でも植えることができるところが特徴の一つといえます。枝先に柄のある花が均等について咲き、花弁は6枚です。
萼片は9枚で、おしべは6本、めしべが1本あります。開花時にめしべに触ると、めしべの外側にあるおしべがめしべの方へ動く変わった性質があります。これは昆虫の体に花粉を付着しやすくさせるためだといわれています。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:クロガネモチの育て方
タイトル:ナンテンの育て方
タイトル:セイヨウヒイラギの育て方
タイトル:メギの育て方
タイトル:ガマズミの育て方
タイトル:ブッドレアの育て方
タイトル:ギンヨウアカシアの育て方
-

-
タッカ・シャントリエリの育て方
原産地はインドや東南アジアで、タシロイモ科タシロイモ属の植物です。和名はクロバナタシロイモで漢字では黒花田代芋と書きます...
-

-
ツワブキの育て方
ツワブキは海沿いの草原や崖、林の縁などを生息地としている常緑の多年草です。原産は日本・中国・台湾・朝鮮半島で、日本国内で...
-

-
タカナ類の育て方
アブラナ科アブラナ属のタカナはからし菜の変種で原産、生息地は東南アジアと言われています。シルクロードを渡ってきたという説...
-

-
花壇や水耕栽培でも楽しめるヒヤシンスの育て方
ユリ科の植物であるヒヤシンスは、花壇や鉢、プランターで何球かをまとめて植えると華やかになり、室内では根の成長の様子も鑑賞...
-

-
コバイケイソウの育て方
この植物は日本の固有種ということですので、原産地も生息地も日本ということになります。わたぼうしのような、まとまった小さな...
-

-
バイカウツギの育て方
バイカウツギは本州から九州、四国を生息地とする日本原産の植物になり、品種はおよそ30~70種存在し、東アジアやヨーロッパ...
-

-
ウラシマソウの育て方
ウラシマソウ(浦島草)は、サトイモ科テンナンショウ属の多年草で、日本原産の植物です。苞の中に伸びた付属体の先端部が細く糸...
-

-
キョウチクトウの育て方
キョウチクトウとご存知すか、漢字では夾竹桃、学名はNerium oleander var. indicumといって、キョ...
-

-
マンゴーの育て方
マンゴーは、ウルシ科のマンゴー属になります。マンゴーの利用ということでは、熟した果実を切って生のまま食べるということで、...
-

-
シクノチェスの育て方
シクノチェスはラン科の植物で独特の花を咲かせることから世界中で人気となっている品種で、15000種以上の品種があるとされ...




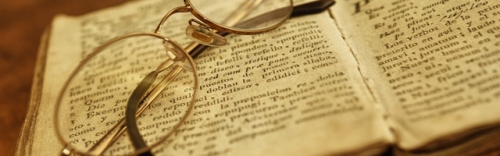





ヒイラギナンテンの原産地は中国や台湾で、東アジアや東南アジアを主な生息地としています。北アメリカや中央アメリカに自生する種類と合わせて、約100種類もの種類が存在します。ヒイラギナンテンは学名をMahonia japonica(マホニア・ヤポニカ)といいます。