ムラサキカタバミの育て方

育てる環境について
またこのカタバミ科カタバミ属は、世界中に500種類ほどあるそうで、共通するのは雑草化しやすいということだそうです。それでその中の100種類ぐらいが観賞用として育てられているということですが、その点からも非常に繁殖力の強い植物ということがわかります。しかし植物自体はきれいなものが多くて、ムラサキカタバミは名前の通り紫ですが、
カタバミなどの黄色の花の種類や、白い美しい花を咲かせているカタバミもあり、雑草としておくにはもったいない植物でもあります。繁殖力が強いという長所があるのですから、初心者としても育てやすくなるということですので、やはり鉢植えなどで限定的に育てるということがよい植物でしょう。どうしても庭に植えてみたいという人でないかぎり、
庭への地植えは、よしたほうがよい植物ということになります。最終的には手に負えなくなり、駆除をする時に苦労するということになるからですが、ムラサキカタバミだけを楽しみたいということでは、美しい庭を見ることができるということかもしれませんが、庭に咲かせるという花としては、なかなか勇気がいる植物でもあります。
あくまでも雑草化しないように注意しながら、管理するということが重要になります。しかし植物の中にも、このような強い植物もいれば、絶滅寸前の植物もいるということで、人間と同じで個性ということや植物自体の種の寿命というものもあるのかもしれないという感じも抱いてしまいます。
種付けや水やり、肥料について
ムラサキカタバミは、人間に有益な働きもするので、評価も色々ですが、例えば石垣などの隙間でも繁殖するということですが、雨などの侵食を葉が防いでくれるということで、その点では重宝がられているということもあるようです。また雑草ということですが、背丈も小さいので、あまり関心は持たれず、そのまま無関心に無視される雑草でもあるということです。
またわざとそのままにしておいて、畑を耕すときの肥料にするという方法もあり、そのような利用方法だと人間の役に立っているということになりますし、カタバミ類が繁殖しているところでは、他の雑草が生えにくいので、その点もメリットかもしれません。肥料として使うということでも、有益な雑草と言えます。またこれらの種類は、
どの花もとても美しいのですが、今では雑草としてどこでも見られるので、特に購入してまで育てるというほどの植物でもないということもあるようです。しかし新しい種類のものは、今でも輸入されたりして、育てられているので、そのような種類のものを鉢植えで育てるのは、初心者の練習用としても観賞用にもなるので面白い使い方ではないかということになります。
いずれにしろ非常に面白い植物であることは間違いないので、色々な色の花のカタバミを楽しむのもひとつの楽しみ方です。その中でもムラサキカタバミは花もきれいなので試してみると良い植物です。また葉も面白くて3枚大きな葉が育ちますが、それらの葉と紫の花のコントラストも楽しみ方のひとつになります。
増やし方や害虫について
また花も1輪ではなく葉が茂るように幾つもの花が咲くので、その姿も面白い形状になります。見れば見るほど魅力的な紫色をしていますが、日本の場合には紫色は高貴な色ということでしたので、その点でも身分の高い人たちに好まれたのかもしれませんが、確かに美しい清楚な感じを与える花になります。
育て方ということでは栽培にも適していますが、雑草化するということで庭がある場合には、そのことに注意しないと、いつのまにか庭に広がってしまうということになりかねない植物です。その意味でも鉢植えでも注意する必要があります。環境としては日当たりを好むので、日の当たるところに植えるか、置くかするということが基本になります。
水はたっぷり与えますが、鉢植えでは土は乾き気味がよいということです。また庭の場合でも、日本の冬にも耐える種類もあるので、そのような種類を植えると良いということになります。また鉢植えが根詰まりを起こした場合には、もう一回り大きな鉢植えに植え替えます。球根の場合には、7月か8月頃植え付けると良いということです。
また4月から9月の生育中は、肥料を与えながら育てるということが良いとのことでした。肥料の種類では、液肥の1000倍液を月2回ぐらい与えると良いということです。このように非常に強い植物なので、初心者には向いている植物ということが言えますが、あまりにも強すぎてコントロールが難しいようにも感じますので、あくまでも限定的な範囲で育てるということがポイントのようです。
ムラサキカタバミの歴史
日本人は昔から自然を楽しむことで生活を豊かにしてきたという特徴がありますが、文化的にも自然を好み、利用が上手いということがありました。理由としては、やはり四季が豊かということで、昔から海外の人たちが日本に来た時に感嘆するのが、自然の美しさということでしたので、
その日本に住んでいた先祖たちもそのような感性を育てられたのではないかと考えられます。今も円安で海外の観光客が非常に多くなり、また人気もある日本ですが、自然の美しさも話題になっていて、それも観光の目的のひとつになっています。そのような日本であり日本人ですので、今まで海外の植物なども多く輸入したりしていました。
カタバミの仲間のムラサキカタバミもそのひとつで、江戸時代に輸入された植物ですが、とてもきれいな花を咲かせるので、栽培を楽しむということで、昔のガーデニングとしても楽しまれたのでしょう。しかし日本の気候や土壌にあっていたのでしょうが、野草として繁殖してしまい、今では駆除の対象にもなるほどになってしまいました。
しかし、その美しさは魅力があり、痛し痒しという感じの植物でもあります。また非常に繁殖力が旺盛なので、抜いても抜いてもまた出てくるということで、その花自体は良いのですが、他の植物の邪魔になるということが問題で、駆除の対象になってしまっているということのようです。一面にムラサキカタバミの咲いている様子は、壮観で美しいのですが、少しは遠慮して育ってくれないと困るということでしょう。その意味でも興味深い植物ではあります。
ムラサキカタバミの特徴
また広く日本に帰化してしまった植物ということで、日本の環境省からも要注意外来生物に指定されてしまっているという植物でもあります。原産地は南アメリカですが、今では世界中で生息地があるという、繁殖力のある植物ということが言えます。オーストラリアや熱帯アジアなどでも生息しているというほどの植物になっています。
これほど繁殖力や適応能力が強いと感心してしまうほどですが、その分鉢植えなどやプランターで育てて花を楽しむ分には初心者向きですし、花も紫のかわいい花を咲かせるので、ベランダなどでのガーデニングでも、初心者に最適ということになります。またそのような育て方でしたら、繁殖しすぎて困るということもないですので、
楽しめるのではないかということになります。この植物は、カタバミ科カタバミ属の植物で、日本にもカタバミという植物がありますが180種以上あるということです。また最近では同じカタバミの外来種であるオッタチカタバミも繁殖しすぎているということで、カタバミ自体がそのような生命力がある植物なのでしょう。またこれらの植物の花は黄色いのでムラサキカタバミとは花で違いがわかります。
またカタバミは種子で繁殖しますが、このムラサキカタバミは、種子はなく地下の鱗茎で繁殖するので、駆除も大変ということになります。植物としては上手い戦略で繁殖しているということになりますが、そのように色々と面白い特色がある植物ということになります。雑草にしないように楽しむということがポイントになるということのようです。
-

-
クリサンセマム・パルドーサムの育て方
クリサンセマム・パルドーサム(ノースポール)は、キク科フランスギク属に分類される半耐寒性多年草です。ただし、高温多湿に極...
-

-
ガーデンシクラメンの育て方
シクラメンの原産はトルコからイスラエルのあたりです。現在でも原種の生息地となっていて、受粉後に花がらせん状になることから...
-

-
芝生の育て方
芝生には様々な特徴があります。原産地によって育つ時期や草丈などにも差があり、どれを選ぶかは自分の住んでいるところどで決め...
-

-
様々な植物の育て方の違いを知る
生き物を育てる事は、人間にとって大切な時間をもつ事でもあり、自然と癒しの時間になっている場合もあります。
-

-
サツマイモの育て方
サツマイモは薩摩芋と書き、生息地は薩摩と言うイメージが強いのですが、現在国内における生息地は全国となっています。また、サ...
-

-
アザレアの育て方
アザレアは名前の由来がラテン語のアザロスつまり乾燥という意味の言葉です。アザレアは乾燥した地域に咲くことからこう名付けら...
-

-
アサギリソウの育て方
アサギリソウは、ロシアのサハラン・日本が原産国とされ、生息地は北陸から北の日本海沿岸から北海等、南千島などの高山や海岸で...
-

-
つるありいんげんの育て方
インゲンは17000種に及ぶ植物、多くの渡り鳥の生息地で知られる中米原産です。スペイン人によりヨーロッパに持ち帰られたの...
-

-
フィゲリウスの育て方
フィゲリウスはゴマノハグサ科に属している植物です。また別名をケープフクシアといいますが、花の形は他の植物と少し変わってお...
-

-
ムラサキゴテンの育て方
この植物については、サトイモ目、ツユクサ科、ムラサキツユクサ属となっています。観葉植物として育てられることが多いです。多...




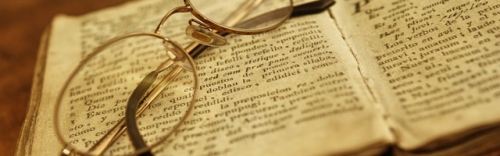





この植物は、カタバミ科カタバミ属の植物で、日本にもカタバミという植物がありますが180種以上あるということです。また広く日本に帰化してしまった植物ということで、日本の環境省からも要注意外来生物に指定されてしまっているという植物でもあります。原産地は南アメリカですが、今では世界中で生息地があるという、繁殖力のある植物ということが言えます。