ハボタンの育て方

ハボタンの種付けと植え替え
スイセンは、主に球根を分球させることによる種付け(繁殖)がメインの植物です。ヒヤシンスなどの球根植物同様、花が咲き、実がなり、種が出来ることはありますが、球根による栽培がメインです。また、実の膨らみはあっても種が出来ない品種もあります。ですからスイセンの繁殖に関しては、種付けという表現は、適していないかもしれませんね。
スイセンは、秋(10月ごろ)に球根を植えると、翌年の冬から春先にかけて、花を咲かせます。これは、地方の気候によって多少変わってきますが、1月~2月が、だいたい花の見ごろといわれます。しかし、早いものは12月には咲きますし、遅いものでは3月に開花を迎えるものもあります。
球根の植え付けにあたって、おさえておきたいポイントは「霜が降りる前に」ということです。霜が降りる前に、根をある程度張らせてあげておくと、生育が良くなるので、気候を見ながら、植え付けの時期を早めることも必要です。
小さな鉢で栽培する場合、ギリギリ球根の上部が土から顔を出すくらいの深さで植えます。大きな鉢で栽培するなら、土の表面と球根上部の間が、球根1個分の深さになるくらいが目安です。地植えでの栽培ならば、この深さが球根2個分、といったところです。以上が、植え付けや種付けのポイントです。
ハボタンの栽培法、日ごろの手入れ
苗の時期には半日陰におくようにし、生育していくにつれ徐々に日向に当てていくようにします。ハボタンは鑑賞期の葉が色づいてきたころにはあまり日光に当てない方がきれいに色づくのでそのころは日陰の方が良いのですが、冬のそのころになるとどこもあまり日が当たらないので、栽培を始める段階ではその点はあまり気にせずに、成長過程で日に当てるようにできるとよいでしょう。
水やりは土の表面が乾いてきたら与えますが、やや乾燥気味にするためあまりたくさん上げないようにします。肥料は10月以降は与えないようにします。生育していくにつれ下の方の葉が大きくなりだしてきます。するとどんどん形が悪くなっていくので、大きくなりすぎた葉や霜などで傷んできた葉は取り除くようにします。キャベツ科の植物なので、青虫やヨトウムシに食べられる恐れがあるので、見つけたら手で取り除くか殺虫剤を使用します。
ハボタンの上手な育て方のまとめ
鑑賞用としてハボタンを栽培するなら7月か8月に種付けをし、発芽するまでは日陰においておくようにします。水は植え替え時に根がつくまではしっかりと与えますが、その後はやや乾燥気味にすることが上手な育て方のポイントです。水をやりすぎないことが根腐れ予防になります。
苗の状態になればしっかりと日の当たるところで管理します。ただキャベツ科で虫がつきやすいので、虫を見た時に手で取り除くか殺虫剤で予防をします。中心部の花の色は低温になってくるとついてくるので、あまり高温の状態にさせないようにするとよいでしょう。このように上手な育て方をマスターしてハボタンを栽培すれば翌年のお正月には自作のハボタンを飾ることができるようになります。
お正月に飾られたハボタンはそのままにしていくと茎がどんどん伸びてきて春になると菜の花のような黄色い花が咲き、その後種ができます。その種をまた夏にまいて栽培することもできるのです。菜の花のような花が咲いた後4月ごろに開花した花茎を切り取ると、下部から新芽が出てきます。
その新芽は晩秋になると色づき始め、分かれていった枝が、人が踊っているように見える「踊りハボタン」を楽しむこともできます。ただきり口が濡れたままだと腐りやすいので、雨を避けるようにアルミホイルでふたをしておくなどの工夫が必要になってきますが、完済地方では特にこのような「踊りハボタン」を仕立てて鑑賞を楽しんできました。
お正月に紅白のものを飾ったり、寄せ植えでも楽しむことができます。花の色は紅白だけではなく紫色やピンク色、クリーム色、そして外葉は緑色でとても鮮やかなので、他の花と一緒に植えると美しいでしょう。高生種のものだと切り花にも利用することができます。最近人気の高いミニハボタンの育て方も同じ要領で、7、8月ごろ種付けをし発芽までは半日陰で管理します。
種をまいて2、3日で発芽をしますがそのあとは日当りの良いところで水切れに注意をしながら管理し、本葉が3、4枚になれば定植します。そしてこの場合もやや乾燥気味にし根腐れを防ぐように注意をしながら栽培をするのですが、ミニのタイプも可愛くて普通の花と同じように鑑賞したり寄せ植えをしたりすることができます。
育て方の難易度は低めで育てやすい植物とされていて初心者でも成功しやすいものなので、初心者でもぜひ挑戦してみるとよいでしょう。ただはじめのうちは苗を買ってきて苗から育てるほうが成功しやすいでしょう。そして次の春には種を収穫してその種で種付けをして毎冬にはハボタンを鑑賞できるようにできれば良いでしょう。冬の間は花や植物が少ないので、ハボタンのように色鮮やかな花が咲くととても重宝され、景色も美しく華やかになります。
ハボタンの歴史
ハボタンは日本で改良されて誕生したもので、海外から伝わってきたものではありません。江戸時代の前期に食用のケールがつたえられてきたのですが、そのケールや古い品種で葉が巻かないタイプのキャベツを鑑賞用として栽培しているうちに品種改良されたものなのです。江戸中期以降には斑入りの葉などが重宝され、紅白の2色が縁起のいいものとして好まれました。
明治時代以降、冬の園芸植物ということで海外にも紹介され、世界各地でも栽培されるようになりました。以前はお正月の縁起物として「寒牡丹」が飾られていましたが、現在では値段も安くて育てよく、見た目も牡丹のようなハボタンがお正月の縁起物としてよく飾られたり栽培されるようになっています。
ハボタンの特徴
もともと伝えられてきたキャベツの原産地は西ヨーロッパですが、観賞用に改良されたので原産地は日本です。キャベツは世界各国に伝えられると、各地で食用として様々なものに品種改良がされましたが、日本だけが観賞用の植物として品種改良をしたといわれています。食べてもおいしくなく、ハボタンを別名「鑑賞キャベツ」と言います。
発芽適温は20度から25度ですが、栽培の適温は10度から20度で少々の雪や霜など冬の低温にも耐える植物なので、寒い地方でも生息地として栽培できるでしょう。アブラナ科の植物で秋まきの一年草です。アブラナ科の植物は自分の花粉では受粉せず、他の株の花粉と受粉するという特徴があり、ハボタンも同じで他家受粉植物です。
中央部が赤や白に色がついているものや、葉の形が丸いものやちりめんの形をしたものなど種類があり、丸葉は東京系、縮緬は名古屋系、その中間の大阪系などがあります。現在はクジャク系やサンゴ系というものもあります。お正月に鑑賞するためには7月か8月に種をまきますが、そうでない場合は10月ごろに種をまいて11月に苗を植え付けます。
するとそれが育って3月か4月ごろには「とう」と言われている茎が伸びてきて菜の花のような黄色い花が咲きます。それが種を作ってそれらの種を周囲に飛ばした後、力尽きて枯れてしまう植物です。春に伸びてくる茎につぼみがつく前に数節を残して切り落としてしまうと、その残った節のわきから芽がでてハボタンに成長していくのです。
夏には日陰で涼しいところで管理をすれば夏を越すことができて大きく育っていき、低温になると中心部に赤や白の色がつき、お正月の縁起物として飾られるようになるのです。最近ではミニのハボタンもあり人気があり、冬枯れの景色を彩る冬の観葉植物です。
花の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:イベリス・センパーヴィレンスの育て方
タイトル:シコンノボタンの育て方
タイトル:ストックの育て方
-

-
スズメノエンドウの育て方
生息地は日本となっていますが、マメ科のソラマメ属に分類しています。後援などに雑草のようにその姿が見られ、古くから周りの草...
-

-
チャービルの育て方
チャービルはロシア南部から西アジアが原産で、特に、コーカサス地方原産のものがローマによってヨーロッパに広く伝えられたと言...
-

-
シュウカイドウの育て方
シュウカイドウは中国を自然の生息地とする植物で、多年生の植物です。中国名は「秋海棠」と書きます。これをそのまま日本語で音...
-

-
観葉植物の上手な育て方
観葉植物の上手な育て方とは、まず定番で簡単なものからチャレンジしてみると栽培しやすいです。場所を選ぶのが大切なポイントで...
-

-
トウミョウの育て方
エンドウ豆の歴史は古く、紀元前7000年の頃には南西アジアで作物としての栽培が始まっていました。その痕跡はツタンカーメン...
-

-
カンガルーポー(アニゴザントス)の育て方
ハエモドルム科の植物で、生息地はオーストラリア南西部です。別名「アニゴザントス」とも呼び、咲いた花の形状がオーストラリア...
-

-
植物を育てたことがない人でも簡単に収穫できる大葉の育て方
大葉は日本の風土でよく育つ植物です。育て方も簡単で家庭菜園初心者でも簡単に収穫を楽しむことができます。また、ベランダに置...
-

-
トマトの栽培は驚く事ばかりでした
今年こそは、立派なトマトを作ろうと思いながら数年が過ぎようとしていた時、テレビ番組を見た事がきっかけで、自分でトマトを作...
-

-
シロダモの育て方
現在に至るまでに木材としても広く利用されています。クスノキ科のシロダモ属に分類されています。原産や分布地は本州や四国や九...
-

-
シラサギカヤツリの育て方
シラサギカヤツリはカヤツリグサ科の多年草です。シラサギの名前からもわかるように、花を咲かせた姿が白鷺が舞っているようにも...




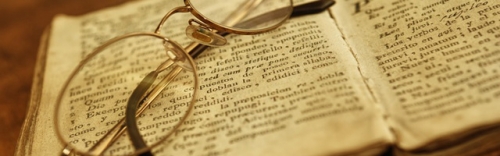





ハボタンは日本で改良されて誕生したもので、海外から伝わってきたものではありません。江戸時代の前期に食用のケールがつたえられてきたのですが、そのケールや古い品種で葉が巻かないタイプのキャベツを鑑賞用として栽培しているうちに品種改良されたものなのです。江戸中期以降には斑入りの葉などが重宝され、紅白の2色が縁起のいいものとして好まれました。