マムシグサの育て方

育てる環境について
野生に自生している生息地は、日本の場合、関東から西、九州と言われていますが、東北や北海道でも別名でその生息が確認されています。この東北や北海道にあるものが、サトイモ科テンナンショウ属マムシグサ種と同一であるかは、まだ研究により明らかにはなっていません。いずれにしても、関東以西の生育は、山林や若干の日が当たり、湿り気のある林床に自生します。
この生育条件が、育てる環境には適しています。耐寒性がありますので、一概に、関東以西の温かい環境を必ずしも必要とすることではないことが、性質からも見て取れます。ただし、冬の凍結は嫌います。一方で、非耐乾性はないため、少し湿った状態を好みます。山林などで生息していることから、木々の下で育つため、直射日光を嫌います。
若干の日が当たると表現したように、明るい場所自体は好むのか、林と一般道が隣接しているような場所でもよくみられます。そのため、山間部に住む小学生などが、マムシグサの身を食べてしまい、食中毒を引き起こすという事件が実際に起き、メディアでも取り上げられています。
もし、この種の有毒性のある野草を都市部など、普段は野草を見かけないような場所で栽培する際には、必ず、子どもから手が届かないところに育てなければなりません。近所の子どもにまで、マムシグサの毒性を説いて回るのは、困難なため、栽培者の責任で、触れさせないという環境が、植物の生息環境よりも重要であることを認識してください。
種付けや水やり、肥料について
乾燥を嫌う性質を持つため、たっぷりと水を与える必要があります。通常、多年草の場合、冬の時期にはあまり手間を掛けることはありませんが、冬の時期でも乾いたら、水を与えておきます。特異な形状が知られているように、茎から草頂まで、複雑な構成をしており、それぞれの部位について、さほど強さがあるわけではなく、折れやすい性質を持ちます。
そのため、水を与える場合に、真上から水やりを行うと、水圧や水の重さに耐え切れずに折れてしまう場合があるので、可能であれば、茎の部分に集中的に水を与えるようにします。支柱を立てて、折れを防ぐこともできますが、一部でも欠損させてくれない場合には、支柱よりも、茎の部分への水やりを選択するのがよいでしょう。
肥料を好みますので、11月から3月頃の植え付け、植え替え時に元肥を与えます。開花頃の晩春には、起き肥をし、開花後から冬眠前の可が枯れる頃を目安に、液体肥料を与えます。液体肥料を与えるサイクルは、月に2回程度、状態により月に3回与えます。土壌は特に好みはないのですが、乾燥を嫌うため、一定度の湿気を維持できるものを選びます。
ただし、多湿状態が続いてしまっても問題があるため、赤玉土と鹿沼土を半々程度で構成するのを目安として、栽培する土地で、多少の調整を行ってください。慣れない場合には、一般的な野草用の土を用いても問題ありません。一般的な野草用の土にも赤玉土をメインに構成されています。
増やし方や害虫について
雌雄異株のため、交配をさせる必要があります。交配のタイピングは、開花から3日から1週間以内に、仏炎苞の中から、肉穂花序を露出させます。雄株と雌株の見分け方は、雄株の場合、先端に花粉が出ていて、雌株の場合には、受粉用に先端が突起していて、つやつやしているのが特徴なので、これを確認します。花粉を、雌株に受粉させるため、綿棒などを用いて、
雄株から花粉をとり、先端の突起状の箇所に軽く、優しく叩くようにして花粉を付けます。その後、水やりを継続し、実がなれば、受粉は成功です。増やし方は、分球と種植があります。分球の場合には、親球根の近くにある、自然と離れた小球根を植え付けします。発芽率が高いわけではありません(または、発芽まで時間がかかる)ので、
発芽するような場合には、別途鉢植えなどに移して育てます。種から増やす場合には、秋ごろにかけて実が熟し、花茎が折れるタイミングで、種を採取し、水洗いをしてから、培養土に蒔き、発芽するまで待ちます。すぐに発芽しないことがありますので、2年程度待ちましょう。病害虫については、地下部に一般的に言うイモができるため、害虫のみならず、ネズミやもぐらにも気をつけます。
主に地下部にある球根を腐らせるような病害虫に注意を払う必要があるので、予防もさることながら、見つけた場合には適宜処理を施します。地上部でも、芽が出始める所に、イモムシやナメクジに気をつけます。病害虫については、薬剤を用いることもできますが、栽培に影響を与えます。育て方で一番難しいのは、この病害虫対応でしょう。
マムシグサの歴史
マムシグサは、その模様がマムシに似ていることから、蝮草と名付けられました。しかし、有毒性も併せて、名前に意味を込めたのではないかと言われています。マムシグサに限らず、有毒性を持ちわせる植物には、何かしら毒性を暗示するような名前が付けられていることが多いです。しかし、古来より、毒性のある植物というのは、薬用としても用いられることがあります。
蝮草の場合、茎の部分を、神経痛やリウマチなどに用いられることがありますが、当然、素人が簡単に薬用として用いることができるわけではないので、絶対に見つけても触ってはなりません。また、食用としても用いられてきました。古くは、アイヌ人にとって食用でしたし、高知県では、昭和初期まで即要として用いられていたという資料があります。
現在でも伊豆諸島の一部や八丈島などでも、毒性の部分を処理し、餅のようについて食べる方法が伝えられているといいます。特にアイヌ人にとり、自然のものは、伝統的に薬用として使えるものには、植物に限らず、動物の例えば胆嚢などを胃薬として用いたりと、自然と調和した生活を営んできました。
今でも、アイヌの血を引く人たちは、子どもに触ってはいけない植物として、マムシグサ(アイヌ名:ラウラウ)がありますが、一方として、有毒性のある箇所を取り除くことにより食用にもなると代々伝えられてきています。このように、マムシのような外見と印象が異なった形で、日本人の生活の一部に取り入れられていました。
マムシグサの特徴
マムシグサは、サトイモ科テンナンショウ属です。サトイモ科に属するので、毒性はあるものの、用途としては、毒を取り除いて食用にする、または一部を薬用として用いるなどなれてきました。サトイモと同じようにイモができるため、食用にする場合には、そのイモの部分を食べます。薬用にする場合には、主に茎の部分を利用します。
多年草ですので、冬にお休みをして、また春頃までに成長を再開し、晩春には開花します。晩春に咲く花は、茎の頂に、高さ約15cmの仏炎苞包まれた、非常に珍しい形の花を咲かせます。仏炎苞の色にも、それぞれ異なることが多く、これも特異性の一つですが、一般的には、緑から紫色、白い線(スジ)が入ります。偽茎があり、名前の由来にもなった紫褐色のまだらな模様があります。
複葉は2枚あり、小葉は枚9から15枚程度が、鳥足状に配列しています。秋ごろになると、実が熟し、赤くなり、トウモロコシのようになります。雌雄異株と言われていますが、性転換することでも知られています。栄養状態にもよりますが、基本的に雌株になります。雌雄異株ですから、外部の第三者による受粉の手伝いが必要です。
一般的には、訪花昆虫が受粉を行います。そのため、雄株では、訪花昆虫が抜け出しやすいように穴が空いている箇所があり、仏炎苞から抜け出し、受粉活動を促します。マムシグサの毒は、シュウ酸カルシウムで、日本では麻薬取締法などでも規制されている毒薬です。シュウ酸カルシウムの針状結晶は、葉や根にあります。なお、原産地は日本以外にも生育しているため不明です。
-

-
トロロアオイの育て方
トロロアオイは花オクラとも呼ばれるアオイ科の植物の事です。見た目はハイビスカスみたいなとても美しい花を咲かせます。この花...
-

-
シンゴニウムの育て方
シンゴニウムとは、中央アメリカ〜南アメリカが原産のサトイモ科のツル性植物です。現在では熱帯アメリカを主な生息地として約3...
-

-
ローズマリーの育て方
その歴史は古く、古代エジプト時代の墓からローズマリーの枝が発見されているように、人間との関わりは非常に古くからとされてい...
-

-
シンボルツリーとしても人気の植物「オリーブ」の育て方
オリーブは常緑性のモクセイ科の植物で、原産国は中近東・地中海沿岸・北アフリカと考えられています。樹高は10~15mで、最...
-

-
ニシキギの育て方
ニシキギは和名で錦木と書きます。その名前の由来は秋の紅葉が錦に例えられたことでした。モミジやスズランノキと共に世界三大紅...
-

-
クレソン(オランダガラシ)の育て方
クレソンは、日本では和蘭芥子(オランダガラシ)や西洋ぜりと呼ばれています。英語ではウォータークレスといいます。水中または...
-

-
グーズベリーの育て方
グーズベリーという植物をご存知ですか、日本ではもしかしたらセイヨウスグリの名前の方が有名かもしれませんが、スグリ科スグリ...
-

-
ネコノヒゲの育て方
このネコノヒゲの特徴は、何と言ってもピンと上を向いた猫の髭の様な雄しべと雌しべではないでしょうか。髭の様な雄しべと雌しべ...
-

-
クウシンサイの育て方
クウシンサイは中華料理やタイ料理などで使われる野菜で、主に炒め物やおひたし・天ぷらなどの料理として食べられています。その...
-

-
イチリンソウの育て方
イチリンソウは日本の山などに自生している多年生の野草でキンポウゲ科イチリンソウ属の植物です。元々日本でも自生している植物...




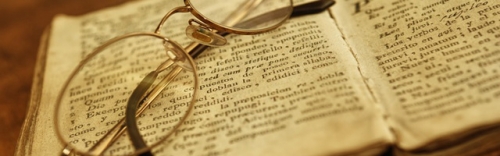





マムシグサは、サトイモ科テンナンショウ属です。サトイモ科に属するので、毒性はあるものの、用途としては、毒を取り除いて食用にする、または一部を薬用として用いるなどなれてきました。サトイモと同じようにイモができるため、食用にする場合には、そのイモの部分を食べます。