メギの育て方

メギの植えつけ方と増やし方
メギは種をまく方法でも、さし木をすることでも植えつけをすることができます。さし木をする場合は3月から4月の新芽が芽吹く前に行うか、10月から11月くらいの本格的な寒さが到来する前が最適な時期です。
鉢に入っていた根っこの部分の二倍くらいの深さと大きさの穴を植えたい場所に掘って置き、腐葉土に油かすやゆっくりと効くタイプの化成肥料を混ぜたものを穴の底に設置してから株の植えつけを行います。株を植えつけた直後は非常に乾燥しやすいため、
根の周囲は十分に水を注いで乾燥を防ぐととともに、鉢の形に固まっている根をよく解して土とよくなじませてあげましょう。メギはすぐに大きくなる植物ですから、庭植えでなく鉢に植える場合は毎年植え替えをしてやる必要があります。
種から育てる場合は、野生種のメギを使いましょう。9月から12月にかけて熟した果実を集めて果肉の部分を取り除いた後よく洗います。株植えの時と同じく種付けの時に乾燥させてしまうのが一番良くないので、すぐに赤玉土を施した場所に撒きます。
屋外に置いて、乾燥させないように適度に水をやりながら様子を見ていれば春には芽が出てきます。メギを増やしたい時も植えつけの時と手順や方法はあまり変わりませんが、さし木で増やす場合は6月から7月に伸びて硬くなっている枝を切りとって使います。
赤玉土を入れた箱などにさし木をして水やりを欠かさないようにし、根付くまではとにかく乾燥しないように注意深く管理することが必要です。
メギの基本的な育て方
水はけが悪い場所でなければ、置く場所や植える場所は日向でも日陰でもよく育ちます。紅葉を楽しむ植物なので、日のよく当たる場所で栽培すれば寒暖の差が激しくなるので、葉が色づく季節に一層鮮やかな葉色が楽しめるようになります。
元々野山に生えている植物ですから、鉢植えは基本的には屋外に置いておくようにしましょう。肥料に関してはあまり必要ありません。もし肥料をやるとすれば、花が咲いた後の5月頃にかけて行い剪定の時に形が整うようにします。
土質もあまり選ばずに生育しますが、極端な乾燥と水はけの悪い場所を嫌う傾向にあるので、バランスを考えれば小粒のタイプの赤玉土に腐葉土を全体の3割ほど混ぜたものが目安です。水やりは庭に植えている場合はあまり神経質になる必要なありませんが、
鉢植えにしている場合は春から秋にかけてはたっぷりとやるようにして下さい。メギは寒さには強いですが、乾燥にはやや弱い性質です。加えて鉢植えにすると土の面積が狭くなり生育期はすぐに水を吸い上げてしまうので、乾燥しないように気を配るようにします。
落葉する季節になると成長が鈍くなりますから、土を触って乾いているくらいでちょうど良い具合です。害虫はあまりつきませんが、カイガラムシがまれに発生しますので、見つけたら取り除いておくようにすれば問題ありません。
メギの剪定方法
庭植えの樹木でよく葉を伸ばすものは定期的に剪定をして姿を整え、葉で隠れてしまう部分の日当たりを考えてやる必要がありますが、これを透かし剪定と呼びます。メギは細かい枝にたくさんの葉をつけてよく芽吹くので、葉を刈ってやることによって好みの形に仕立てることができます。
これは刈込剪定といいます。育て方や鑑賞の目的によって剪定の仕方を変えるようにします。刈込剪定を行う時期は春から秋の季節にかけてが良いでしょう。この時期はメギの生育期にあたり、よく枝を伸ばして全体的に姿が乱れたものになりがちです。
そうした場合に、仕立てたい姿を保っておくために伸びてきて輪郭を乱している部分を切り落とし、遠目から見た樹形を確認しながらばっさりと刈り込んでやります。丸い形や角型に刈り込むのが一般的には人気のスタイルです。透かし剪定を行う時は、
混雑している小枝を間引いて姿を整えることを目的としますので、自然に生育しているようなナチュラルな姿にしたい時に向いたやり方です。古い枝や太くなり過ぎた枝をその根元から落とし、横に育ちすぎている枝や、重なって枝が陰を作ってしまうような部分を切り戻しします。
葉が生い茂りすぎていると日差しが通らず、遠目に重たそうな印象を与えてしまいますが、こうして伸びすぎた枝を間引いてやることで枝葉のあいだにほどよい間隔ができ、日の光が通って株元まで風や日光も通りやすくなりますし、軽やかな姿に仕立てることが出来ます。
剪定する時期は落葉の時期である1月から2月が適していますが、落葉木に剪定を行うと花や実に育つ部分も一緒に切り落としてしまいます。そうすると花や果実を楽しむことができなくなってしまいますので、メギが花実をつけるさまを楽しみたい場合は、
控えめに剪定を行って枝を落とし過ぎないようにすると良いでしょう。その他、樹高を高くしたい時は不必要な枝をその都度株元から落としていくようにします。枝のあまり伸びないオーレアという品種に関しては剪定はしなくても良いでしょう。
メギの歴史
メギはメギ科メギ属の仲間に入るもので、垣根によく利用される背の低い植物です。メギ属はアルカロイドという成分を含んだ種類が多く、有毒なものから薬理作用を認められたものまで数多くの品種に分かれています。
メギは日本を原産をする品種で、漢字にすると目木と書きます。これは目木が目に効く薬として使われてきた経緯によるもので、枝や幹、根を煎じたものを服用したり、うがい薬としての用法や、脱脂綿に煎じた液を浸して洗眼することなどが民間療法として行われています。
メギは関東以西、四国や九州に生育するものはオオバメギ、東海や近畿を生息地とするものはヘビノボラズ、日本全体や韓国、中国などに広く分布するヒロハヘビノボラズと呼ばれ、それぞれが薬用として使われてきた歴史を持っています。
メギは枝の部分に鋭いとげを持っており、鳥がそれを嫌って寄りつかないことからコトリトマラズ、ヨロイドオシなどという呼ばれ方をすることがあり、庭に害獣が入ってくるのを避けるために生垣としてよく用いられています。
メギは葉の色が明るく、秋には赤く色づく果実をつけ、見た目を楽しめる植物ですが園芸用として使われるというよりは、庭植え用の樹木としての利用が多いようです。
メギの特徴
メギは関東以西を広く生息地としており、野生種も見かけられます。成長後もあまり背が高くならず、1m~2mの間に収まります。秋には紅葉し、冬には葉を落とす落葉樹の一種です。メギは幹からたくさんの小さな枝を出して生い茂るためこんもりとした見た目が庭のアクセントには最適です。
季節によって色を変える葉、きれいに赤く色づく果実に小さな花と、全ての季節を通しての楽しみ方を持っています。メギの花は雄しべに触れると雌しべのほうに近づいていく様子が観察できますが、昆虫が蜜を吸いに訪れた時にその体に花粉を付け、
遠くに運ばせやすくするためにそうした機能を持っていると言われています。メギ属の植物は世界中に少しずつその品種や姿を変えながら分布しており、ユーラシア、アフリカ、南北アメリカなどの比較的温暖な地域によく生育しますが寒さや乾燥にも強い種類はヨーロッパや中東、ロシアでも見ることが出来ます。
赤く熟する果実は観賞用としても美しいですが、ロシアではボルシチに入れて食されることもあり、日本では果実をそのまま食べることはないものの果実酒としての利用が広くみられます。コムギ黒さび病を媒介することがあるため、栽培を禁止されている国もあります。
庭木の育て方や色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:マンサクの育て方
タイトル:ネズミモチの育て方
タイトル:カラタチバナの育て方
-

-
植物の上手な育て方は土にある
花・ハーブ・野菜などの様々な植物の育て方や栽培方法は種類によって様々で、土・肥料・水やり・置場所などによって育ち方にも影...
-

-
コルジリネの育て方
コルジリネはキジカクシ科のセンネンボク属に属します。原産地は東南アジア、オーストラリア、ニュージーランドなどでの熱帯から...
-

-
オキナワスズメウリの育て方
この植物は被子植物に該当します。バラ類、真正バラ類のウリ目、ウリ科になります。注意しないといけないのはスズメウリ属ではな...
-

-
サクラの育て方
原産地はヒマラヤの近郊ではないかといわれています。現在サクラの生息地はヨーロッパや西シベリア、日本、中国、米国、カナダな...
-

-
リビングストンデージーの育て方
リビングストンデージーの特徴として、まずは原産地となるのが南アフリカであり、科・属名はツルナ科・ドロテアンサスに属してい...
-

-
タンジーの育て方
タンジーはキク科の多年生草本で、和名はヨモギギクと言います。別名としてバチェラーズボタン・ジンジャープランツ・ビターボタ...
-

-
ムクゲの育て方
ムクゲはインドや中国原産とされる落葉樹です。生息地は広く、中近東になどにも分布しています。韓国の国花として知られています...
-

-
ルッコラの育て方
ガーデニングブームとともに人気になっているのが家庭菜園です。自宅に居ながらにして新鮮な野菜をたべられるというのも人気の秘...
-

-
ミカニアの育て方
こちらについては比較的身近な花と同じ種類になっています。キク科でミカニア属と呼ばれる属名になります。育てられるときの園芸...
-

-
レモンの育て方
レモンの原産地や生息地はインドのヒマラヤ地方とされ、先祖とされている果物は中国の南部やインダス文明周辺が起源です。そして...




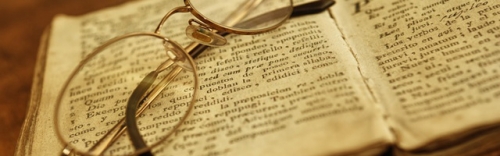





メギはメギ科メギ属の仲間に入るもので、垣根によく利用される背の低い植物です。メギ属はアルカロイドという成分を含んだ種類が多く、有毒なものから薬理作用を認められたものまで数多くの品種に分かれています。