コブシの育て方

コブシの育てる環境について
コブシは日本原産の植物ですので、庭木として育てる場合も特に問題が発生することはありません。耐寒性や耐暑性にも優れており、さらに強風や潮風にも強いことから非常に育てやすい品種であるといえます。また多少のやせ地に植えても十分生育しますので、
偏った育て方さえおこなわなければ、初心者でも比較的簡単に育てることができるでしょう。ただ生育が旺盛な樹木であるということは、それだけ大木になる可能性があるということにもなります。もちろん適切な管理ができるのであれば鉢植えも可能ですが、
大きくなることを考えれば庭木として用いるほうが初心者には適しているかもしれません。また庭に植える場合も木や葉が大ぶりになることを考慮して、適切なスペースが確保できるところに植えることが大切です。またいくら庭に植えるからといっても、
あまりに大きくなりすぎると困りますので、適切な時期に剪定をおこなうことが必要になります。自分で剪定ができるのであれば問題ありませんが、自信がない場合は業者に依頼しておこなってもらうことになりますので、育てる際はそのことも考慮しておいたほうがいいでしょう。
ただしこの品種は成長自体は遅いので、植えてからしばらくはそんなに手間がかかることはありません。種から育てると花が咲くまでに5年から7年はかかるとされているほど成長が遅いので、庭のシンボルツリーとして活用しようと考えているのであれば、このこともしっかりと考慮しておく必要があります。
コブシの種付けや水やり、肥料について
コブシを種から育てるのであれば、種まきの時期は9月から10月になります。植え付けは春です。基本的には2月から3月頃におこなうといいのですが、寒冷地では根が十分に張っていない状態で寒気にあたると枝枯れを起こしてしまう可能性がありますので、
気温が高くなる4月中旬以降に植え付けを行ったほうが無難です。また樹木は根が粗いので、一度植え付けてしまうと移植が難しくなります。ですから庭に植える場合は、植え付ける場所を十分考えたうえでおこなうことが大切です。ある程度日当たりがあり、湿潤な土地に植えている場合は、
水やりを頻繁に行わなくても大丈夫です。やせ地でもそれなりに育ちますが、あまりに栄養分がないと花つきに影響がでますので注意が必要です。土質が極端に悪い場合は、樹木を植える前に腐葉土などを用いて土壌を改善してから植え付けたほうがいいでしょう。
肥料については木が若い頃は生育も旺盛なため、1月、5月、9月頃に骨粉を混ぜた油粕やたい肥を置き肥します。ただしコブシは成長するにつれて根が広範囲にわたって広がりますので、そのぶん栄養素の吸収力も高まります。したがって気が十分に成長してしまったあとは、
それほど多くの肥料を必要としなくなりますので、5月や9月頃に追肥をおこなわなくてもかまいません。コブシは生命力が高く、日本の気候にマッチした樹木ですので、基本的には水やりや肥料に関して神経質にならなくてもいい植物です。
コブシの増やし方や害虫について
コブシを増やしたい場合は、種で増やすことができます。秋に採取した種をそのまま植えてもいいですし、乾燥しないように保存しておいて、気温の高くなった3月の中旬以降に種をまくのもいい方法です。ただこの樹木は非常に生育が遅いのが特徴で、
種を植えてから花が咲くまでに少なくとも5年から7年はかかるとされています。ですからコブシを増やす場合は長い期間をかけて取り組むことを覚悟しておく必要があります。生命力旺盛で丈夫な樹木ですが、栽培するからにはやはり病害虫への対処は欠かせません。
この木が罹患する病気の代表的なものはうどんこ病です。うどんこ病は葉が白い粉のようなものに覆われる病気です。この白い粉の正体はカビで、放置しておくと葉の光合成が妨げられ木が弱ってしまいます。この木は大木になることから、樹高を抑えるためには剪定が欠かせないのですが、
剪定の際に切り口を放っておくとそこから雑菌が侵入し、病気になる可能性が高くなります。そのため剪定により枝を切り落とした際には、切り口に癒合剤を塗って病気を予防することが必要です。害虫はカイガラムシやテッポウムシに気をつけなければいけません。
カイガラムシは枝の中で樹液を吸ってしまうのですが、成虫になると薬剤が効きにくくなりますので、早めに駆除を心がけることが大切です。カミキリムシの幼虫であるテッポウムシは、幹の内部を食い荒らしてしまいますので、こちらも見つけ次第に駆除しましょう。
コブシの歴史
早春に白い花を咲かせるコブシは日本原産です。野山に広く自生していたことから、古くから日本人の生活になじみ深い植物でもあります。コブシにはタウチザクラ、イモウエバナ、タネマキザクラなどの異名がありますが、これらは古代の人がコブシの花が咲いたのを合図にして、
農作業に取り掛かったことが由来となっています。このように農作業の合図となる樹木は日本全国にあり、タウチザクラなどと呼ばれる樹木も地域によって異なりますが、コブシをタウチザクラと呼ぶのは主に東北地域です。寒さの厳しい北の地域に住む人にとって、
春に咲くコブシの白い花は寒い冬の終わりを告げるとともに、その年の収穫に向けて農作業をはじめる合図でもあったのです。またコブシの蕾は漢方の世界では生薬として古くから使われていました。漢方薬の一つに辛夷というものがありますが、
これはコブシやタムシバを用いて作られます。コブシの蕾を日陰で干して乾燥させたこの辛夷は、鼻の通りを良くするのに効果があるとされ、蓄膿症や鼻炎による鼻づまりの解消はもちろん、頭痛や歯痛の症状にも用いられています。漢方薬としての歴史も古く、
約2000年ほど前に中国で記された神農本草経という本にもその名前が登場しています。ただし現在は原材料の流通が不安定になったことから、日本産の蕾でこの辛夷がつくられることは少なくなり、中国から輸入されたボウシュンカ、シモクレンなどのモクレン属の蕾を用いて生薬が生産されています。
コブシの特徴
コブシは日本の里山に春の訪れを告げる代表的な植物です。春を告げる樹木といえば桜をイメージする人も多いかもしれませんが、コブシも他の木々に先駆けて春に白い花を咲かせます。コブシの花は6枚の花弁をもち、中心の基部は淡い紅色をしています。花の下部に葉が一枚ついているのが特徴です。
またコブシといえば強い香りが特徴ですが、これは花から漂うだけではありません。じつは枝や葉にも香りがあり、これらを燃やすと強い香りを発します。コブシは葉が大きいのも特徴です。その大きな葉が日差しを遮るスペースを作ることから、街路樹など公共のスペースに植えられることも多くあります。
灰白色の樹皮も滑らかで美しいのですが、幹も柔軟かつきめ細やかな性質をしているので、茶室の床柱や軒の垂木、小物の器具材としても利用されています。早秋にできる実は長さ10センチほどの赤い実です。熟せば皮が裂けて、
なかから赤い種が白い糸につり下がって垂れ落ちてきます。このでこぼこした実の形が子どもの握りこぶしに似ていることが、この樹木の名前の由来とされていますが、蕾の形が拳に似ていることが由来だとする説もあります。原産地が日本いうこともあり、
北海道から本州、九州の広い一帯が生息地となっているため、公園の植栽や街路樹、庭木として広くコブシは利用されてきましたが、最近は園芸品種としてもさまざまな品種が開発されており、家庭のシンボルツリーとしての需要も高くなっています。
庭木の育て方など色々な植物の育て方に興味がある方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:スギ(杉)の育て方
タイトル:シマトネリコの育て方
-

-
カトレアの育て方
カトレアは、肉厚の葉とバルブと呼ばれるやや太った茎をもつ洋ランとされ、生息地は、熱帯、亜熱帯地域の南アメリカ周辺で中南米...
-

-
ヒトリシズカの育て方
ヒトリシズカは原産地や生息地が日本を含め、中国や朝鮮半島です。栽培するのは5段階中でいえば4で、かなり難しいといえるでし...
-

-
リーキ(無臭ニンニク)の育て方
ニンニクという名称がつけられる場合がありますが、ネギの仲間の野菜であるというのは記述済みです。焼きまんじゅうで知られてい...
-

-
アングレカムの育て方
アングレカムはマダガスカル原産のランの仲間です。マダガスカル島と熱帯アフリカを生息地とし、およそ200の種類があります。...
-

-
パセリの育て方
その歴史は古く、紀元前にまでさかのぼります。特徴的な香りにより、薬用や香味野菜として使われてきました。日本には、鎖国時代...
-

-
ガザニアの育て方
ガザニアはキク科ガザニア属で勲章菊という別名を持っています。ガザニアという名前はギリシャ人が語源とされており、ラテン語の...
-

-
グリフィニアの育て方
原産国がブラジル連邦共和国原産の”グリフィニア”はヒガンバナ科の植物です。和名”ミニブルーアマリリス”とも呼ばれており、...
-

-
ほうれん草の育て方について
ほうれん草は日常の食卓にもよく出てくる食材なので、家庭菜園などで自家製のほうれん草作りを楽しんでいる人も少なくありません...
-

-
コウリンカの育て方
コウリンカはキク科の山野草で、50センチくらいに成長し、7月から9月頃には、開花時期を迎えます。2007年に環境省のレッ...
-

-
アガスターシェの育て方
アガスターシェは、初心者でも簡単に育てる事のできる、シソ科の花になります。別名が沢山ありまして、カワミドリやアガスタケ、...




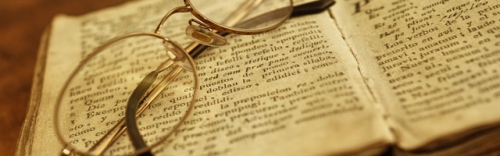





早春に白い花を咲かせるコブシは日本原産です。野山に広く自生していたことから、古くから日本人の生活になじみ深い植物でもあります。