ニチニチソウの育て方

ニチニチソウの育て方
まず苗を植え付けする前にどこに最終的に植えておきたいかを考えておきます。ニチニチソウは移植を嫌いますので根がまわってしまう前に咲かせたい場所に植え付けしてしまうのがベストなのです。そして植え付けのポイントはポットに入っていた時の形のまま植えるということです。基本的に日当たりの良い場所が良いのですが、西日が当たる場所や風あたりが強い場所は避けたほうが良いです。
水やりは土の表面が乾いていればたっぷりとあげる程度でOKです。ニチニチソウは土の乾きには非常に敏感な植物で1度水が切れてしまったがために枯れてしまったという場合も多いのです。花壇でもあまりに乾燥しているようであれば午前中に水をあげるといいです。植え付け時には元肥として粒状肥料を一緒に混ぜ込むと良いです。
もしくは液体肥料でも良いです。この場合は1000倍液を1週間に1度与えます。液体肥料以外の場合、肥料は追肥として1か月から2か月に1度置き肥すれば良いのですが、チッ素成分が多い肥料を与え過ぎると葉が多くなりすぎてしまい、花の付きが悪くなるので注意しましょう。
いくつかをまとめて植えたい時には15cmから20cmほどの間隔をあけて行ないます。土は水はけの良いものがいいですが、草花用培養土でもかまいません。植木鉢やプランターに植えるのであれば、小粒赤玉土6、腐葉土4を混ぜ合わせたものを使って植えます。庭に植える場合、水はけを良くするために腐葉土や川砂を混ぜておくと良いです。
ニチニチソウの栽培のポイントは何か?
栽培するにあたって気をつけておきたいのは苗の葉が8枚以上になった時に摘芯することです。芽をハサミで切ってしまうことで脇芽を出させるのが目的です。これは花の育て方のポイントの一つでニチニチソウ以外の花の育て方としても利用することができます。梅雨明け頃に摘芯するのはあまりに早い段階、例えば春の早い時期などにして茂ってくると蒸れてしまうからです。
ハサミを入れる場所は先から一節か二節ほどの位置が良いです。切った枝は土にさしておくことでまた殖やすこともできます。花は2、3日ほどでしぼんで落ちてしまい、種を作ろうとメシベに栄養が集中してしまいます。そうなるとよほど栄養の良い土であっても他のつぼみに栄養がまわらず大きく育ちませんから種を作りたいというわけでもない方はめしべを摘み取ってしまったほうが他の花がたくさんつきます。
また花が落ちてくると花びらが葉についてしまうことがあります。そこから病気にかかってしまうことも多いので、そういうものは毎日チェックして取ってしまいましょう。過去3年以内にニチニチソウを植えた場所には植えないようにしないと連作障害が起きてしまいます。プランターや鉢植えであっても土を新しくしてあげるのが良いです。冬越しをさせたい場合は13度以上の温度を保つようにします。
病気では立ち枯れ病、害虫はアブラムシに特に注意が必要です。立ち枯れ病というのは苗が水を吸収できなくなってしおれ、最後には枯れてしまう病気です。原因となる菌は土の中に潜んでいて茎から進入してきます。アブラムシはよく知られていますように新芽や茎、葉について汁を吸う虫です。
アブラムシを1匹でも見かけたら早い段階で薬をまいて退治してしまいましょう。アブラムシがするフンはアリを誘引する分泌物が混ざっていますのでさらに大変なことになってしまいます。葉を萎縮させたり、湾曲させたりするアブラムシもいて、種類によっては虫こぶを作ってしまいます。
鉢植えを外に置く時には病気の原因となる土はねを防ぐためにすのこや人工芝、一段高くするなどの工夫をしておくといいです。春から梅雨までや9月中旬以降は土も乾きにくくなりますから水を与えすぎないように気をつけましょう。苗は春から夏にかけて販売されますが、良い苗を選ぶには根元がしっかりしていて花やつぼみがたくさんついているものを選ぶと良いです。
ニチニチソウの種付けについて
ニチニチソウを種付けさせたいのであれば、花を摘まないでそのままにしておきましょう。すると種付けされて、その種から翌年芽が出て花が咲くこともあります。しかし市販されているニチニチソウには種付けしないように処理されてしまっていることも多いので購入時には確認してみるのが良いです。種から育てたい場合には発芽するのに20度から25度ほどの温度が必要になります。
気温が低い時に種まきしても発芽までに時間が長くかかってしまいますので、目安として八重桜が散る頃と考えておくのが良いです。種を植える時の注意としてしっかりと土をかけてあげることが大切です。ニチニチソウの種は光を感じると発芽しない性質なのです。このように栽培のポイントをおさえておくことで花を咲かせる楽しみが出てきます。
ニチニチソウの歴史
ニチニチソウに日本に渡来したのは1780年頃のことだといわれています。渡来してからの歴史が浅いので日本の文献などに出てくることはあまりありません。しかし原産地だとされる西インド諸島のマダガスカル島に住んでいる原住民はニチニチソウを糖尿病の民間薬として飲用しています。また中国では長春花と呼んで沈静や安神、平肝降圧、白血病、悪性腫瘍などに効果的だといわれています。
1958年には葉の部分から抽出したアルカロイドに抗白血病作用があることがわかりました。それによってガン細胞の増殖を抑制して患者の延命効果があることで話題になったほどでした。しかしこのアルカロイドというのは毒性が強いものでもありますので、素人の方がそのまま食するなどしてしまうと嘔吐や下痢など軽い症状ですまない場合がありますので絶対に気軽に食したりしないようにしましょう。
薬として利用されているのはニチニチソウに含まれる10種類以上あるアルカロイドのうちのビンクリスチンとビンブラスチンの2種類だけです。抗がん剤として使われる一方で、脱毛などの副作用や毒性も認められていますから病院で使われる以外では使うことはありません。
ニチニチソウの特徴
一年草でキョウチクトウ科ニチニチソウ属になりますが、野生種の場合は多年草です。日本国内は霜がおりる頃に寒さで枯れてしまうことが多いのです。初夏から晩秋までの開花時期には毎日花が咲き続けますのでこういう名前がつけられました。原種自体は小さくて低い木でふせたように生えてしまうことが多いのですが、改良されたものではそのようなことはなく、きちんと直立しているものが多いです。
葉は長楕円形で、花は直径3cmから4cmほどで白、ピンク、赤、赤紫などのカラーがあります。中央部だけ色が違うものもあります。生息地はマダガスカルからインドなどの熱帯地域です。鉢植えや露地植え、ハンギングなどで育てることができます。いろんなカラーのものをそろえて明るく可愛らしい雰囲気を楽しむのがオススメです。
比較的初心者でも育てやすいので挑戦してみるのも良いでしょう。茎の高さは直立していれば30cmから50cmほどになります。似たような名前のツルニチソウというのがありますが、そちらはニチニチソウとはまた別のものですから間違えないようにしましょう。生涯の友情や優しい追憶などの花言葉があります。
花に興味ある方は下記の記事も詳しく書いてあるので、凄く参考になります♪
タイトル:ムスカリの育て方
タイトル:マリーゴールドの育て方
タイトル:ナスタチュームの育て方
タイトル:キンギョソウの育て方
-

-
お洒落なハーブの育て方
お洒落なハーブを自分で育てることが素敵だと思いませんか?最近はお家でハーブを育てている人が多くなっています。ハーブと聞く...
-

-
センノウの育て方
センノウは鎌倉時代の末か室町時代の初めごろ、中国から渡来したと言われている多年草です。中国名は「剪紅紗花」と書き、センコ...
-

-
ポテンティラ・メガランタの育て方
ポテンティラ・メガランタは別名をハナイチゴや西洋キンバイといいます。葉がイチゴのものに似ていて愛らしい黄色の花を咲かせま...
-

-
じゃがいもの品種と育て方
じゃがいもは、寒さに強い植物です。人気は男爵やメークイン、キタアカリです。男爵は粉質が強いので、じゃがバター・ポテトフラ...
-

-
ネクタリンの育て方
ネクタリンの語源はギリシャ神話に出てくる神々の酒であるネクターに由来していると言われています。芳しい香りと柔らかくてみず...
-

-
ハベナリアの育て方
ハベナリアはラン科の植物で、草丈は15cmから60cmほどになります。洋ランの中でもその品種が非常に多い植物でもあります...
-

-
ビオラの育て方
ビオラの生息地は世界中に広がっており、温帯地帯に500種ほどが自生しているとされ、私たちにとってもっとも身近な植物の一つ...
-

-
ジャカランダの育て方
ジャカランダは世界三大花木の一つとして知られており、日本では数多くあるジャカランダの品種の内の一部が栽培されています。日...
-

-
イワタバコの育て方
イワタバコはイワタバコ科の多年草で、花が美しいことから山草として栽培されることもあります。イワタバコ科は、双子葉植物の科...
-

-
ベニバナの育て方
ベニバナに関しては見ると何の種類か想像しやすい花かも知れません。見た目には小さい菊のように見えます。実際にキクの仲間にな...




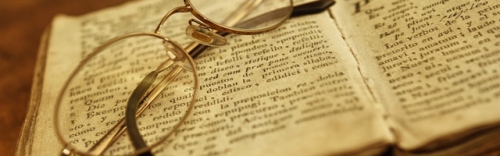





ニチニチソウに日本に渡来したのは1780年頃のことだといわれています。渡来してからの歴史が浅いので日本の文献などに出てくることはあまりありません。しかし原産地だとされる西インド諸島のマダガスカル島に住んでいる原住民はニチニチソウを糖尿病の民間薬として飲用しています。また中国では長春花と呼んで沈静や安神、平肝降圧、白血病、悪性腫瘍などに効果的だといわれています。