芝生の育て方

育てる環境について
芝生を育てるには、各芝に合った育て方をすることが一番のポイントといえます。もともと育っていた生息地を踏まえておく必要があります。暖地型の芝の場合には20度か35度くらいがよく、10度以下では生育は停止してしまいます。冬は葉が黄金色になり、寒さや風、乾燥で休眠状態になりますが、春になると新芽が出てきます。
一方寒地型は冬も美しい緑なので育てる環境に関してはあまり気にする必要はないです。日があまり当たらないところでも逞しく育つのもポイントです。こういった面からみてもわかるように、暖地型は関東より西の地域がよいです。色が四季とともに変わるので、そういった季節の変化を感じたい場合には、こちらが良いです。
一方で寒地型は北海道などでの寒い環境に暮らす場合に向いています。冬でも美しい緑をたもつことができるので、年中緑の美しい芝生が良い場合には寒地型のものにすべきです。一度枯れたようになってしまった場合にも次のシーズンになると自然と新しいものが生えてくれるので環境への変化などはそこまで気にする必要はないですが、
キチンとした手入れをし、芝にとってよりよい環境をつくってあげることによって、より美しく元気な芝を楽しむことができます。綺麗に育てたいという人にとっても、楽に庭の手入れをしたいという人にとってもよいものというのは、なかなかありませんが、その点芝ならばどちらでも可能なので迷った際には芝にするのがよいです。
種付けや水やり、肥料について
草木や花など、植物を育てる上で欠かすことができないのが水です。これは芝生にも、もちろん同じことが言えます。水分が不足すると緑色が失われていき、最後には枯れてしまいます。しかし、だからといって水をあげすぎるのもよくありません。鉢植えと同じくらいの頻度であげ、乾燥させないようにするのが一番です。
春ならば3日から4日に一度で、夏ならば毎日あげなくてはなりません。雨が降らない夏ならば1日2回目あげるのがベストです。日中の日差しが強い時間に水をあげると芝が蒸れて痛む可能性があるので、そういった時間帯は避けるべきです。種付けにも適した時期というのがあるので、いつでも良いというわけではありません。
芝は比較的丈夫なので肥料などがなくても育つと言われていますが、綺麗な芝にしたいのであれば肥料はきちんと与えたほうがよいです。芝によってあげるべき肥料も違うので注意が必要です。もちろん、あげすぎは逆効果になり枯れてしまうのでよくありません。水をあたえすぎるよりも数倍の注意が必要となります。
肥料を与えた後に水をやらなくてはならないと決まっているものもあるので、記載はしっかり読まなくてはなりません。肥料で一番の大事なのは、その成分です。もちろんそれだけではなく、即効性があるものとそうではないものがあるので、時期に合わせて使い分ける必要があります。時期を間違えると効果が十分に得ることができなくなってしまいます。
増やし方や害虫について
芝生を育てる上で気をつけなくてはならないことは、害虫の存在です。水不足でもないし、環境が悪くもないのに枯れてきたと言う場合には害虫がいる可能性が高いです。まだらに枯れてしまったり、一部に穴が空くということも害虫がいることが原因です。まずなによりも、害虫が寄りつきにくい環境をつくることが大切なポイントです。
虫にとって住みにくい環境を作ることが第一です。農薬を使うのも一つの手です。日光が十分にあたり元気に育った芝生は害虫の被害にあいにくいですが、もしそれでも被害に遭ってしまった際には、何か原因の元なのかをしっかりと見極める必要があります。こういったことをキチンとしておかないと、芝生を、増やすことも困難となってきてしまいます。
原因が分からない時には、プロに依頼するというのも一つの手です。鉢植えなどとは違い、芝生は大きな範囲にわたるので一度被害にあうとその全てがダメになってしまうので今まで育てた苦労が水の泡となってしまいかねません。芝生の栽培は、比較的難しいことではないですが、それも枯れてしまった後ではどうにもできません。
自分でできる範囲の手入れと無理な範囲をキチンと見極めることも大切なポイントとなります。インターネットなどで手入れの仕方や害虫駆除の仕方はたくさん書いてあるので、自分でできそうだと考えてしまいがちですが、実際に害虫のせいなのか病気なのかを見極めるのはそう容易なことではないということも知っておかなくてはなりません。
芝生の歴史
芝は、一種類もしくは数種類の芝草を人工的に増やして、刈るなどの手入れや管理をしたもので、イネ科の多年草の総称です。これが一面に敷き詰められたものを芝生と読んでいることが大半です。日本では大きくわけて、日本芝と西洋芝にわけられています。この二つも幾つかの種類に分けられます。日本では昔の和歌などでも芝の記述があるものがあり、芝の歴史の長さが伺えます。
明治時代には西洋芝が使われ出しました。昔からあるもので、今の時代もあるものというのはそれほどまでに日本人の生活には欠かせないものであり身近なものということになります。スポーツの面でもサッカーするところに敷かれていたりと、今や生活の一部としてなくてはならないものといっても良いです。
スポーツの時だけではなく、家の庭に芝を使用している家庭も多く見られます。昔からの歴史でも庭に芝を敷くのはよくあることだったので、昔ながらの文化といっても良いのではないでしょうか。歴史的には長いですが、そこまで注目を集める存在というわけでもなく、あまり気に留められることはありませんが、
日本だけではなく海外の歴史を見てもありとあらゆる面で芝は活用されています。こういった面をみると、芝が人々の生活の中でもいかに役立っていたのかがわかります。歴史の流れとともに芝もより強いものとなっていっていて、少しのことでは枯れないようになりつつあるのも特徴と言って良いのではないでしょうか。
芝生の特徴
芝生には様々な特徴があります。原産地によって育つ時期や草丈などにも差があり、どれを選ぶかは自分の住んでいるところどで決めるのが良いです。他の草花とは違い、毎年生えるし強いところがポイントです。伸びてきたら刈るなどの手入れは必要になりますが、育てるために特に苦労することはあまりないのも特徴といえます。
土やコンクリートの地面とは違い、転んだときに怪我をしにくいのも特徴です。小さな子供がいる家庭や学校、幼稚園、公園などでは芝生は安全性の面でも良いと言えます。それだけではなく夏はコンクリートではとても暑くなってしまいますが芝にすることにより、ヒートアイランド現象の緩和にもつながります。
ホコリなどがたたないので周りに迷惑をかけることも避けられます。目で見てもコンクリートに比べると自然にあふれていて緑があることによりリラックスできる環境となることも良いところと言えます。芝にすることによるメリットはとても多いです。ホームセンターなどでも大体のところでは販売されているので、
手軽に手に入り、自分で庭に芝をつくることもできます。初心者でも比較的簡単にできることや、手入れもホームセンターにある草刈機などでできるので業者に頼む必要がありません。手入れにかかる費用がかからないので、家の庭にも取り入れやすいのが特徴の一つと言えます。水たまりができにくいので、庭にはぴったりというのも頷けるところなのではないでしょうか。
-

-
コールラビの育て方
コールラビとは、学名をBrassica oleraceaと言い、英語名をKohlrabiと綴ります。その形は球根とキャベ...
-

-
チョコレートコスモスの育て方
チョコレートコスモスは、キク科 コスモス属の常緑多年草です。原産地はメキシコで、18世紀末にスペインマドリードの植物園に...
-

-
アリアケスミレの育て方
アリアケスミレは日本原産の本州から四国、九州に自生するスミレの仲間ですが、山野草としても扱われて盛んに栽培されています。...
-

-
シシウドの育て方
シシウドの原産地は日本になります。別名をウドタラシと言うのですが、猪独活ともいった名前が付いているのが特徴です。夏の暑い...
-

-
クラウンベッチの育て方
クラウンベッチはヨーロッパが原産であり、ツルの性質を持つ、マメ目マメ科の多年草です。また、日本におけるクラウンベッチの歴...
-

-
アズマギクの育て方
アズマギクは東北地方、関東地方、中部地方を原産とする日本固有の植物です。キク科ムカシヨモギ属の植物で、植物の中でも最も進...
-

-
マトリカリアの育て方
花の特徴は、キク科のヨモギギク属とされています。タナセツム属に入ることもあります。園芸分類としては草花に属します。形態と...
-

-
コヒルガオの育て方
コヒルガオの大きな特徴は、その花の咲き方です。アサガオやヒルガオと同じ様な咲き方をしています。またヒルガオと同様、昼ごろ...
-

-
チトニアの育て方
チトニアはキク科の植物になります。鮮やかなオレンジや黄色などのビタミンカラーが印象的で、美しい花を咲かせるでしょう。キク...
-

-
スカビオーサの育て方
別名を西洋マツムシソウといいます。英名ではピンクッションフラワーやエジプシャンローズ、スイートスカビオスなどあります。ス...




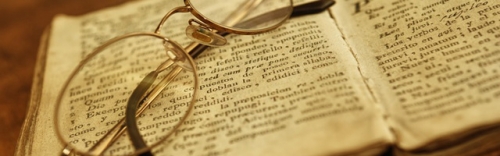





芝生には様々な特徴があります。原産地によって育つ時期や草丈などにも差があり、どれを選ぶかは自分の住んでいるところどで決めるのが良いです。他の草花とは違い、毎年生えるし強いところがポイントです。伸びてきたら刈るなどの手入れは必要になりますが、育てるために特に苦労することはあまりないのも特徴といえます。