ブロッコリーの育て方

ブロッコリーの種付け
育て方の1段階は種付けです。春まきの栽培では、2月中旬~3月中旬に種付けをして、6月頃に収穫をします。夏まき栽培では、7月中下旬に種付けをして、10月下旬頃から収穫になります。ブロッコリーは、1年に2回栽培できます。
まず9cmの大きさのポットに培養土を入れ、水をしっかり含ませておきます。そこへ種を、5粒~6粒程蒔いていきます。その上に薄く土を被せるか、指で軽く押して種付けをします。その後また水を十分に与えましょう。
発芽したら、丈夫な苗だけを3本程残して間引きをします。その後、本葉が2枚程生えてきたら苗を2本に間引きし、本葉が3枚~4枚になった時点で、丈夫な1本だけを残していきます。そして、本葉が5枚~6枚になった時点で、いよいよ植えつけをしていきます。ブロッコリーの育て方で重要な点の一つに、種付けで丈夫な苗を育てるかです。
ブロッコリーの植え付け
育て方の2段階として、植え付けになります。場所としては、日当たりと水はけのよい所を選び、堆肥を1㎡当たり2kg~3kg、土の酸性度を中和する働きのある苦土石灰を、1㎡当たり100g~120g施して粗起こしをしておきます。
その後、元肥として化成肥料を(チッソ:リン:カリウム=8:8:8の割合)1㎡当たり150gを、土全体に混ぜ込んで畝を作ります。本葉が6枚~7枚になった苗を、大きく開けた植え穴に30cm~40cm程度の株間隔で植え付けていきます。
ポットから苗を取り出す際、根鉢を崩さないように注意しましょう。前日にポットの苗に水やりをしておくと、根鉢を崩さなくて済みます。そして、植え付けたら十分に水やりをしておきましょう。この頃は、暑い時期になるので、こうした作業は夕方にすると、苗の植え傷みを防ぐことができます。
植え付けからおよそ1週間から10日程経った頃に、株と株の間に1回目の追肥を施します。肥料として、化成肥料を1㎡当たり70g~80gを混ぜ込みましょう。そして、1回目の追肥よりおよそ20日程度経過した時点で、2回目の追肥を施します。
2回目の追肥は、畝の肩部分に1回目と同量の肥料を混ぜ込んでいきます。この時に同時に中耕を行い、株元へ軽く土寄せしておくことで、今後成長していく株が重さで倒れることを防いでくれます。
害虫や病気について
ブロッコリーは、害虫が付きやすい野菜でもあるため、駆除はこまめに行うことが大切です。主な害虫には、アオムシ・ヨトウムシ・ネキリムシ・コガネムシの幼虫などがいます。これらに効果的な薬剤を散布して害虫からブロッコリーを守っていきましょう。
効果的な殺虫剤として、アオムシには天然成分を使用した殺虫剤である「STゼンターリ顆粒水和剤」や殺虫剤「マラソン乳剤」を、ヨトウムシには、「STゼンターリ顆粒水和剤」や「GFオルトラン粒剤」などが効果的です。
また、定植したばかりの苗が、根元から突然倒れてしまった場合には、土の中にネキリムシがいる可能性があるので、「サンケイダイアジノン粒剤3」を土に混ぜ込んで退治しましょう。この殺虫剤は、ネキリムシ同様に土の中にいて、根の部分を食べてしまうコガネムシの幼虫にも効果的です。
根ばかりでなく、葉にも害虫は付きます。代表的なのがアブラムシです。アブラムシに効果的な殺虫剤は多く市販されており、例えば食品成分を使用した殺虫殺菌剤である「ベニカマイルドいスプレー」や天然ヤシ油から作られている「アーリーセーフ」といったものもあります。その他にも、「マラソン乳剤」や「ベニカ水溶剤」が効果的です。
これらを散布して害虫を防ぎましょう。害虫の他に病気にも注意が必要です。代表的な病気として、根の部分に大小のこぶが出来ることによって生育不良を引き起こす「こぶ病」や、葉に黄色い斑点が現れ葉の全体に広がり、晴天が続くと葉がパリパリになり、雨天が続くと葉がベトベトになることから名付けられた「べと病」などがあります。
こぶ病の対策は、堆肥を多めに施して植え付け時に「STダコニール1000」を土に混ぜておくと予防できます。また、このSTダコニールはべと病にも効果があります。このように害虫を駆除していくことで、ブロッコリーは大きく成長し、やがて収穫を迎えます。
ブロッコリーの花蕾が大きく育ち、小さなつぼみたちがはっきりと見えて、固く締まってきたら収穫時期となります。収穫直後のブロッコリーのは、茎の部分もとても柔らかくて甘みが強く美味しいです。
ブロッコリーの歴史
サラダやスープ、炒めものにも使えて、非常に栄養価の高い万能野菜であるブロッコリーは、地中海沿岸が生息地といわれています。地中海沿岸のイタリアに栄えていた、古代ローマ時代からすでに食されており、ローマ人から「木の枝」を表すラテン語で呼ばれていました。
また、イタリア語でブロッコリーは 「茎や芽」を意味しています。その後15世紀~16世紀ころになって、本格的にブロッコリー栽培が始まったとされています。そして、イタリアからヨーロッパ各国に普及していったのは、17世紀に入ってからとされています。
ブロッコリーが日本に入ってきたのは明治時代初期といわれています。しかし、当初は人気がなくほとんど食べられることはありませんでした。そして、戦争が終結した後に徐々に需要が高まっていきました。
本格的に普及し始めたのは、日本食品標準成分表が改定された昭和57年(1982年)ころで、その成分表によってこの野菜の高い栄養価が人々に評価され、消費量が一気に伸びることとなりました。
ブロッコリーの特徴と品種
ブロッコリーは家庭菜園でも栽培が可能な野菜です。ここではブロッコリーの育て方を紹介していきます。この野菜の生育適温は20℃前後と、比較的冷涼な気候を好みます。また、苗の段階では高温に強いのですが、つぼみが大きくなり始めるころになると暑さに弱くなるという特徴があります。
従って、栽培に適した時期は、真夏を除いた春または秋となっています。初心者向けのブロッコリーの品種には、苗を植えつけしてからおよそ50日程で収穫できる、極早生種の「シャスター」や、植えつけしてからおよそ55日程で収穫できる早生種「エルデ」や「すばる」という品種があるので、それらを選んで栽培すると失敗が少ないでしょう。
この野菜の起源はケールとされており、同じくケールの起源を持つのがキャベツであり、このキャベツは、ケールの葉を結球させ栽培した野菜です。そして、ブロッコリーはその花の部分を摘み取ったものとなっています。
ブロッコリーには、非常に多くの栄養素が含まれており、必須アミノ酸を含むタンパク質・ビタミンA・ビタミンB群・ビタミンC・ビタミンD・ビタミンE・ビタミンk・カルシウムやマグネシウム、亜鉛などのミネラル類と、豊富な栄養が詰まっています。
そんなブロッコリーは、ヨーロッパ原産でありながら、肥満大国であるアメリカ合衆国において、「健康の象徴」として親しまれています。食用となっている緑の粒々の部分は、花蕾(からい)と呼ばれる花のつぼみ部分が集まったものです。
その独特な食感と、火を通すことで増す甘み、また灰汁がほとんどないため、小さなお子さんの食事やおやつとしても食べられています。この野菜の近縁種には、中国野菜であるサイシンと掛け合わせて改良された「はなっこりー」という種類が山口県で栽培されています。
また、この野菜に似たカリフラワーの変種に「ロマネスコ」という種類があります。これは、イタリアのローマで開発された野菜で、1990年代からヨーロッパを中心に流通しています。見た目はカリフラワーの形で、色は緑色をしたものと、多数の突起があり、フラクタル図形のような形の2種類があり、どちらも味はカリフラワーに近いです。
こちらのカリフラワーの育て方の記事も参考になります♪
-

-
ブラッシアの育て方
ブラッシアはメキシコからペルー、ブラジルなどの地域を生息地とするラン科の植物で、別名をスパイダー・オーキッドと言います。...
-

-
トキワサンザシの育て方
真赤な赤い実と濃い緑の葉を豊かに実らせるトキワサンザシは、バラ科の植物で、トキワサンザシ属です。学名をPyracanth...
-

-
小松菜の育て方
小松菜の原産地は、南ヨーロッパ地中海沿岸と言われています。中国などを経て江戸時代の頃から小松川周辺から栽培が始まり、以降...
-

-
観葉植物の上手な育て方
観葉植物の上手な育て方とは、まず定番で簡単なものからチャレンジしてみると栽培しやすいです。場所を選ぶのが大切なポイントで...
-

-
マツの育て方
マツ属はマツ科の属の一つで、原産はインドネシアから北側はロシアやカナダなどが挙げられます。大部分が生息地として北半球にあ...
-

-
ベラドンナリリーの育て方
特徴としては、クサスギカズラ目、ヒガンバナ科、ヒガンバナ亜科となっています。ヒッペアストルム連に属するともされています。...
-

-
ヌスビトハギの育て方
ヌスビトハギの仲間はいろいろ実在していて、種類ごとに持っている特質などに違いが見られ、また亜種も実在しています。例に出し...
-

-
ユーフォルビアの育て方
ユーフォルビア、別名、ユーフォルビアダイヤモンドフロストは、トウダイグサ科ユーフォルビア属の植物です。生息地は世界の熱帯...
-

-
家庭菜園でサヤのインゲンの育て方
サヤインゲンには、つるあり種とつるなし種があります。つるあり種は、つるが1.5m以上に伸びますし、側枝もよく発生するので...
-

-
アルケミラ・モリスの育て方
アルケミラ・モリスは、ハゴロモグサ属でバラ科の植物です。アラビア語のAlkemelych、錬金術に由来しています。アルケ...




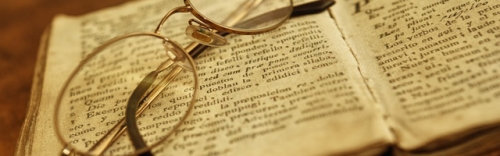





サラダやスープ、炒めものにも使えて、非常に栄養価の高い万能野菜であるブロッコリーは、地中海沿岸が生息地といわれています。地中海沿岸のイタリアに栄えていた、古代ローマ時代からすでに食されており、ローマ人から「木の枝」を表すラテン語で呼ばれていました。