マロウの育て方

育てる環境について
マロウとは毎年花を咲かせる多年草です。草丈は開花時で大きいものは1.5メートルほどにまで成長します。ここまで大きくなると風が強い場所では茎が横倒しになってしまうことがあります。ですから草丈が伸びてきたら支柱を立てると良いでしょう。直径3センチほどの花を咲かせます。沢山の花が咲くので、賑やかな見た目です。
薬効や野菜として以外にも園芸植物としても古代ローマ時代から栽培されてたようです。丈夫で植えっぱなしにできるので、手入れが苦手という方にも育てやすい植物といえるでしょう。具体的な育て方については、日当たりと風通し、水はけのよい場所が適しています。植えつけ場所や用土に、堆肥や腐葉土などの有機物を十分に加えて植えつけます。
神経質に水やりを気にするほどではありませんが、鉢土の表面が乾いた時にたっぷりと水やりをします。一株の寿命はあまり長くありません。5年に1回は、さし芽やタネで更新するほうが良いです。江戸時代に日本へと渡来したと言われているゼニアオイはこぼれた種でも増える事が多いです。
こぼれた種で増えた場合には、周囲に発芽した苗を鉢上げしてもよいでしょう。種で増やすならば春か秋にまきます。直根性で移植を嫌うので、直まきかポットまきにし、本葉が3~4枚になったら定植しましょう。咲き終わった花は随時摘み取ります。花がほぼ全部咲き終わったら、花茎の根元で切り戻します。花をハーブとして利用する場合には、咲いた日に1輪ずつ摘み取り乾燥させてからお湯を注ぎ楽しみます。
種付けや水やり、肥料について
手入れが大変という方でも育てやすい植物と言われているだけあり、乾燥にはある程度耐えられるそうです。冬は土の上では枯れてしまいますが、土の下ではきちんと根は生きています。生育期間ほど水を必要とはしないのでこまめに水をやらなくても大丈夫です。鉢植えは土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるように心がけておけば大丈夫でしょう。
地植えの場合には、植え付け直後はたっぷり水やりをします。根付いてしまえば、猛暑の日など暑い日以外は水やりをしなくても、自然の雨だけでも育つと言われているくらい生命力があります。種付けですが、春か秋にするのが良いです。具体的には春の場合には、3月上旬から5月上旬です。
もしくは秋の場合には、9月下旬から11月上旬ごろを目安に行います。苗を鉢植えにする場合は太い根を切らないように注意します。9~10号鉢に植えつけます。生育期に太い根を傷めてしまうと根付きにくいことがあるからです。一度植えたものは休眠期に株分けをするとき以外は植え替えをせずに育てます。庭植えでは株間を100cmくらいはとり、日当たりをよくする事で花が咲きやすくなります。
肥料は植え付ける際に土の中に即効性のものではなく、ゆっくりと効くタイプの肥料を混ぜ込みます。地植えの場合にはゆっくり効く肥料とともに堆肥を混ぜ込みます。地植えの場合には、根付いてしまえば自然と育つと言われているので、こまめに肥料を与える必要はありません。鉢植えで育てているものは花が咲いている期間は液体肥料を月に数回与えます。
増やし方や害虫について
増やし方には種まきと株分けがあります。株分けの場合には、大株になったら行います。少しずつ寒くなってくると地上部が枯れます。地上部が枯れる休眠期である10月から11月に株を掘り上げます。1株に5芽ほどつくように、ハサミで少し切れ目を入れてから手で裂いて、株を割り分けます。種まきよりも、初心者の方には株分けの方が簡単でしょう。
増えれば良いというわけではなく、葉が増えて混み合ってきた場合には間引く事で、それぞれの葉や花によく日が当たり綺麗に咲きます。植物を育てていて、1番の大敵とも言われる害虫にも気をつけなければなりません。主な害虫としてはハマキムシ、アブラムシ、ワタノメイガなどがいます。
ハマキムシはハマキガ類の幼虫のことで、葉を巻いたりして、その中潜んでいます。巻いた葉の上から押しつぶす方法もありますし、葉を開いて幼虫を捕殺して対応しても良いです。アブラムシは、温かくなってくる春頃からよく発生します。見つけしだい早急に駆除した方が良いでしょう。ワタノメイガは、幼虫が葉や枝を糸で繋げて巣をつくります。そして葉を食害しながら成長します。
葉の上で生活しているので、糞が落ちている場合があります。ワタノメイガのふんを見つけたら、幼虫を探して捕殺します。動きが幼虫の中でも早いので、取り逃がさないように素早く対応しましょう。何よりも、植物も生き物です。水や日当たり、害虫に気を付けていくのはもちろんですが、何よりも話しかけたりしながら愛情も注いでいく事で愛着心が強まり、日々の植物の世話も苦にはならないでしょう。
マロウの歴史
マロウはヨーロッパが原産地だと言われています。生息地としては、南ヨーロッパが代表的ではないでしょうか。細かくわけると沢山の種類がありますが、その中でもコモン・マロウとも呼ばれているウスベニアオイが代表的です。日本には江戸時代にマロウの変種が渡来したそうです。
日本に最初に来た変種と言われているのは、ゼニアオイというもので道端や畑でもよく目にします。ゼニアオイと言われるようになった由来としては、果実の見た目が真ん中が少しへこんでおり、ドーナツのような形をしています。そして、その見た目を当時の人達は銭に見立ててゼニアオイと言うようになったそうです。
マロウという言葉一つとっても、それぞれの外国語でも言葉に違う意味が含まれているようです。ギリシア語での呼び名には、柔らかくするという意味があるようです。ギリシア語の通りに、粘液が含まれ柔らかくする作用があります。またラテン語の由来は、この植物本来が持つ作用と葉の感触から名づけられています。
植物一つとっても、それぞれの国で作用や感触を人々がよく考えて、研究された結果に名づけられている事がよくわかります。植物一つとっても、原産地を調べてみたりそれぞれの国での呼ばれ方を調べるのは、とても興味深い事です。
国によって呼ばれ方が違い、その呼ばれ方にはきちんと意味が含まれているのですから、とても勉強になります。日本の花言葉としては複数ありますが、勇気や温厚、柔和な心などやさしさが溢れているような言葉ばかりです。
マロウの特徴
主に知られているのは、花はハーブティとして利用されています。ハーブと言えば、リラックス効果があったりと日本でもとても人気です。花にはほのかな香りもあります。乾燥した花をコップに入れてお湯を注ぐと、透きとおった青いお茶になります。レモンを浮かべると薄いピンク色に変色する事もあり、女性にとても人気です。
花自体に香りがありますので、色だけではなく淹れたお茶からほのかに匂う香りも楽しめる一つの要因です。細かくわけると沢山の種類があるわけですが、芳香をもつムスクマロウや、平たく広がるクリーピングマロウなどがあります。多くの成分が入っているので、薬としての効果も期待されています。咳に対して効果があるとされているようです。
しかし、だれでも飲めば良いというわけではなく、妊娠されている人や食べ物アレルギーがある人などは、医者に相談してからの飲んだ方が良いでしょう。ギリシア語でも粘液が含まれて柔らかくするという意味で呼ばれているマロウですが、その名のとおりに粘液質が含まれている他にも沢山の成分が入っています。
具体的には、タンニン、精油、ビタミンA,B1、B2、Cなどが豊富な成分が含まれています。咳以外にも消炎、炎症保護、緩下、利尿、気管支炎などにも効果を発揮するようです。芽や若い葉はゆがいて食べる事もできるそうです。硬くなる前の柔らかく未熟な実は、生のままサラダなどに入れて食べることがあります。食べたり飲んだりする以外にも、虫さされや腫れ物などにも効果があるとされ、使用される事があります。
-

-
ハゴロモジャスミンの育て方
ハゴロモジャスミンの原産地は中国雲南省ですが、現在では外来種としてニュージーランドやアーストラリアなども生息地となってい...
-

-
タンチョウソウの育て方
タンチョウソウは別名で岩八手といいます。中国東部から朝鮮半島が原産地です。生息地は低山から山地で、川岸の岩の上や川沿いの...
-

-
オオガハスの育て方
オオガハスは2000年以上も昔の種から発芽した古代のハスです。「世界最古の花」として知られ、世界各国に友好の証として贈ら...
-

-
ヤブミョウガの仲間の育て方
ヤブミョウガはツユクサ科の花です。したがって、ヤブミョウガの仲間はミョウガではなくツユクサです。ちなみに、ミョウガは歴史...
-

-
我が家で行っている家庭菜園のコツを紹介します
我が家では、猫の額ほどの庭ではありますが、自分たちの食べるものは自分たちで出来るだけ作ろうというモットーで家庭菜園を営ん...
-

-
キサントソーマの育て方
この植物の特徴としてはサトイモ科の常緑多年草になります。生息地の熱帯のアメリカにおいては40種類近く分布するとされていま...
-

-
ツルムラサキの育て方
ツルムラサキがどこに自生していたのかというのは、詳しくは分かっていないのですが、熱帯地域が原産だろうと考えられています。...
-

-
ディルの育て方
ディルは古代メソポタミアやエジプト時代から栽培されていたといわれて、薬用として古代から使われてきました。現在では薬味など...
-

-
マンサクの育て方
マンサクの名前がついた由来といわれるものは3つあります。1つは豊年満作というところからきたという説です。マンサクは樹木い...
-

-
センニンソウの育て方
センニンソウの特徴は、扁桃腺治療などに用いられる薬草としての役割も多いのですが、仙人の由来ともなった、仙人のヒゲのような...




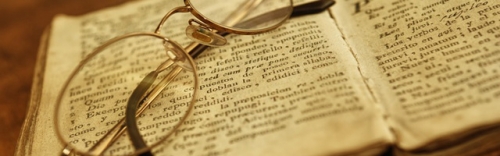





マロウは、アオイ科のゼニアオイ属になります。マロウはヨーロッパが原産地だと言われています。生息地としては、南ヨーロッパが代表的ではないでしょうか。細かくわけると沢山の種類がありますが、その中でもコモン・マロウとも呼ばれているウスベニアオイが代表的です。