ムスカリの育て方

ムスカリの育て方 「球根の植え付け」
ムスカリはヒヤシンス同様、園芸においては、球根栽培が一般的な植物です。秋植え、春咲きの球根植物です。まず、ムスカリに適した土ついてですが、前述の通り水はけがよく、弱アルカリの土壌を好みます。しかし、日本は酸性土壌が多く、庭植えや鉢植えなどの場合は、少し手を加えて、酸性を中和してあげるとよいでしょう。
これには石灰を土に巻いたり、土をブレンドする、などの方法がありますね。また、こうした土のpHについては、専用の液剤などを使って簡単にチェックできます。こうしたものは、園芸用品を取り扱う店で購入できます。さて、植え付けの時期ですが、これは10~11月が適していますが、地方の気候によっては前後するかもしれません。
早く植えすぎると葉が長く伸びすぎ、逆に植え付けが遅いと葉が伸びず花も見栄えのしない長さになってしまうことがありますので、この植える時期というのは、おさえておきたい重要なポイントでしょう。鉢植えなら、球根がギリギリ隠れるぐらいの深さで植えます。庭植えならば、球根上部から土表面までの深さが5cmほどになるように植えていきます。球根どうしの間隔は、5~15cmぐらいが目安です。
植え付け後は水をたっぷりとあげ、その後は土の表面が乾いたら水やりをする、という形になります。もともと湿気を嫌う性質ですので、過湿にならないように気を付けます。葉が枯れたら水やりをストップします。概ね6月頃には葉が枯れ、休眠期に入ります。
育て方のポイント
ムスカリの育て方の中でも、球根の管理というのは気になるところです。まず、ムスカリは植え付けから数年間は植えっぱなしで栽培しても、翌年に花を咲かせます。基本、丈夫な植物ですから、休眠期は放っておいて、水やりも自然の降雨に任せるような形で構わない部分はあります。しかし、やはり生育のことを考えると、球根を数年に一度掘り上げてあげる必要があります。
おおよそ、3~4年に一度、というところでしょうか。梅雨が来る前に、この掘り上げ作業を終えてしまいましょう。6月の梅雨前には、葉が黄色くなって枯れてきますから、これが掘り上げのタイミングです。小ぶりな球根を傷付けないように掘り上げ、陰干しします。これは、新聞紙などを敷いた上に土を取り除いた球根を並べて乾燥させるような形がよいでしょう。
球根の表面が乾いたら、風通しの良い場所で貯蔵します。冬場は凍らず、夏場は熱気がこもらない場所、というのは球根貯蔵の基本です。網袋などに入れ、吊るすようにして貯蔵すると、風通しが十分確保できますね。
ムスカリの育て方 「種付けやその他の手入れ」
ムスカリの種付け(繁殖)は、球根を分球させることで行なうのが一般的です。種を土に撒くところから始める栽培方法は、あまり行われていません。しかし、花が咲いて実がなり、それを放っておけば種が出来るので、その種が地に落ちて、新たな芽が出るということは十分にありえます。しかし、ムスカリは球根が分球して増えることにより、種付け(繁殖)が行われるのが通常です。
また、種からの栽培は、球根栽培に比べると、花が咲くまでに時間がかかります。掘り上げの際に、もともと植えた球根の回りに、小さな球根を見ることが出来ます。もともとの球根を母球、新たにできた小さい球根を子球といいます。このプロセスを分球と呼び、ムスカリの種付けは、ほぼこうして行われ、増えていくのです。
こうしたことから、球根の健康状態がとても大切であることが分かりますね。花が咲いて、種が付くということは、球根の養分を消耗してしまう要因になります。ですから、ムスカリは花が枯れてきたら、その花がらを摘んで、種が出来ないようにしてあげるのが手入れとして欠かせません。
ムスカリの園芸品種あれこれ
近年、様々な改良品種が流通するようになってきました。人気の一例を挙げてみましょう。まず、可愛らしいピンク色の花を咲かせるピンク・サンライズ。ブルー系が多いムスカリの中で、ひときわ目立つ存在です。それから、淡い水色をしたバレリーフィネスという品種。控えめな色ですが、香りを有しており、他のブルーの品種と合わせて栽培することで、ブルーのグラデーションを作ることもできますね。
次に、花穂の上部と下部で色の別れたラティフォリウム。濃いブルーと薄いブルーでセパレートになった、面白い姿です。白い花を付けることで知られた、ボトリオイデス・アルブムも可憐な姿で、見る者を楽しませてくれます。
その他、丸い粒状の花を咲かせるものが多い中で、細い羽毛状の花を咲かせるプルモーサムという品種もあり、これは羽根ムスカリなどと呼ばれて、そのユニークな姿が愛でられています。このように、様々な品種があるムスカリです。チューリップの引き立て役としてだけではなく、単品でも十分楽しめる植物であることは、疑いようもありません。
ムスカリの歴史
ムスカリは、ユリ科ムスカリ属の球根植物で、ヒヤシンスの近縁とも言える植物です。約30~50ほどの品種があるといわれ、その原産地を地中海沿岸とするものや、トルコやコーカサス地方を原産とするものなど、様々です。野生下では、水はけの良い肥沃な土地や弱アルカリ性土壌を好んで生息地とします。
ブドウの房を逆さにしたような花穂を、細い茎の上部に付けることから、グレープヒヤシンスなる異名もあるくらいです。色はブルー系を中心に、白や黄色、ピンクなど、近年は多様な改良品種が出回っています。特にチューリップとの寄せ植えに適した植物として重宝され、各国の植物園や公園など、または家庭の庭において、長く愛でられ続けています。
このムスカリ、ネアンデルタール人が埋葬されたと思われる場所から、花粉が発見され、この時代に死者に花を手向ける習慣が出来ていたのかもしれない、として話題になりました。それが本当ならば、この花と人類との関わりの歴史は、とても長いことになりますね。この花の名前、ムスカリは、麝香を意味するムスクから来ているとされます。
確かに、品種によっては甘い香りを持つものもあり、納得の由来といえるでしょう。しかし、実際の麝香(ムスク)の動物的な香りというよりは、甘い植物の香りです。また、ムスクほど強く香り立つものでもありません。
ムスカリの特徴
この植物の特徴としては、やはりその形状や色味、香りなどでしょう。一番ポピュラーな品種は、ムスカリ・アルメニアカムと呼ばれるものです。春に、小さく丸い粒状の濃い青色の花穂を付けます。この品種を群生させ、花の時期には、その青い色で川のように見える植え方は、ムスカリ・リバーと呼ばれとても有名です。
アルメニアカムは、甘さと清涼感のある香りがします。グレープヒヤシンスという別名のとおり、少しブドウっぽさもあります。黄色っぽく細長い花を付けるゴールデン・フレグランスという品種は、熟す前のバナナのような香りで有名です。いずれにしても、草丈が10~30cmと低いので、庭で花の匂いをしっかり嗅ぐには、しゃがみこんで鼻を近づける必要があるでしょう。
多くの植物の例にもれず、やはり原種や原種に近いものは丈夫です。耐寒性があり、病害虫もあまりなく、丈夫な植物です。庭植えの場合、植えっぱなしで、肥料をあまりあげなくても、それなりに育つものです。しかし、品種改良されたものは、この限りではありません。
花に興味ある方は、下記の記事も詳しく書かれているので、凄く参考になります♪
タイトル:ヒヤシンスの育て方
タイトル:ローズマリーの育て方
タイトル:クロッカスの育て方
タイトル:タッカ・シャントリエリの育て方
-

-
タバコの育て方
特徴として、意外な事実では、このタバコはナス科の植物ということで、タバコ属の多年草ということだそうです。どう見てもタバコ...
-

-
プランターで栽培できるほうれん草
ほうれん草の生育適温は15~20°Cで、低温には強く0°C以下でも育成できますが、育ちが悪くなってしまうので注意が必要で...
-

-
桃の育て方
桃の歴史は紀元前にまで遡り、明確な時期は明かされておりませんが、中国北西部の黄河上流が原産地とされています。当時の果実は...
-

-
アフェランドラの育て方
アフェランドラはキツネノゴマ科でアフェランドラ属に属します。ブラジル、ベネズエラ、エクアドルなどの熱帯、亜熱帯アメリカを...
-

-
ニガナの育て方
ニガナはキク科の多年草で、原産地及び生息地は日本や東アジア一帯ということで、広く分布している植物でもあります。日本でも道...
-

-
ヘリオフィラの育て方
ヘリオフィラはアブラナ科の植物で小さな青い花を咲かせてくれます。つぎつぎと花を楽しむことができる植物になっています。南ア...
-

-
ショウジョウバカマの育て方
ショウジョウバカマは日本から南千島、サハリン南部を原産地とするユリ科ショウジョウバカマ属の多年草です。北は北海道から南は...
-

-
リカステの育て方
この植物の特徴としては、キジカクシ目、ラン科、セッコク亜科になります。園芸の分類においてはランになります。種類としてもラ...
-

-
シロバナノヘビイチゴの育て方
シロバナノヘビイチゴの特徴は何と言っても、その花が白いことです。また、赤い果実を付けるのですが、どちらかと言うと普通の苺...
-

-
マツカゼソウの育て方
松風草は、一般的には、マツカゼソウと表記され、ミカン科マツカゼソウ属に属しており、東アジアに生息するマツカゼソウの品種と...





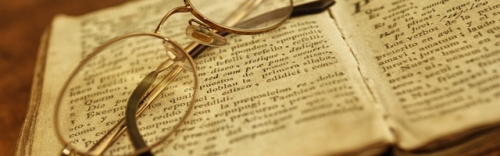





ムスカリは、ユリ科ムスカリ属の球根植物で、ヒヤシンスの近縁とも言える植物です。約30~50ほどの品種があるといわれ、その原産地を地中海沿岸とするものや、トルコやコーカサス地方を原産とするものなど、様々です。野生下では、水はけの良い肥沃な土地や弱アルカリ性土壌を好んで生息地とします。